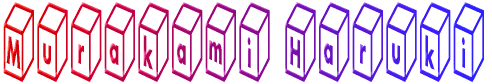
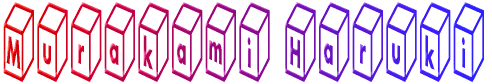
-村上春樹-
未完成ですが随時アップしています
注)
当欄では文庫本1冊程度に収まっている分量の作品を「中編小説」として扱っている。
本来なら長編小説とするべきだろうが、村上春樹の作品には、分冊にしなければならない量の作品が多く、
そちらを「長編小説」とさせていただくことにした。
| 騎士団長殺し (2017/02) |  |
|
| 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 (2013/04) |  |
|
タイトルとともに、登場人物の名前に驚いた。「多崎つくる」を主人公に、木元・赤松・青海・白根・黒埜・灰田・緑川、と具体的で現実的な名前のオンパレードである。そこには、アカ・アオ・シロ・クロという綽名を持つかつての親友たちの名の由来を、納得できる形で読者に差し出す必要性があったのかもしれない。だが、さらに主人公のフルネームを長編作品のタイトルに加えるその徹底ぶりに、やはり驚きを禁じ得ないのである。短編「ファミリー・アフェア」について、村上春樹は「ようやく登場人物に具体的なフルネームを与えることができてほっとした」という旨の発言をしていたが、ここで用いられた「ワタナベノボル」という名前は、「ワタナベトオル」(ノルウェイの森)・「ワタヤノボル」(ねじ巻き鳥クロニクル)という変奏を含め、何作品にも登場する。しかも、「渡辺昇」とは、村上春樹作品のイラストレーター、安西水丸の本名である。これほどまでにキャストへの命名を苦手としていた彼の「現在地」に、興奮せざるを得なかった。 現実的な名前に呼応するように、「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」はシンプルに完結した、推理小説にも似た文体を持ち合わせている(あるいはその逆で、この文体が現実的な名前を求めたのかもしれない)。そして、奇跡的なまでに緊密な関係を誇った親友グループから、つくるだけがある日突然放擲された理由を、16年の歳月を経て解明しようとするストーリーは、たしかに一種のミステリーを思わせる。しかし、村上春樹にその種の謎解き快感を求めると肩透かしを食う。実際、その謎は物語中盤でほとんど明かされてしまう。そのうえ、この小説では村上春樹特有の、明かされないまま回収されない謎の含有量がきわめて多い。もちろん彼のファンなら、その謎を自分なりに解釈してみようという思いに駆られるだろうが(僕もその一人だ)、村上春樹作品を苦手とする人々にとっては、妙に喉がつっかえたまま読了してしまう羽目になるだろう。 つくるはやや自意識の過剰な、自分の存在意義を見出せないことに振り回される人生を送っている独身男性である。この主人公設定は、村上春樹の定石ではあるが、当作ではその濃度が高い。中編というボリュームとも相俟って、読者をグイグイいざなうストーリー展開にはなっていないので、おのずとつくるの内省や独白が目立つ。タイトルに準えれば、この作品は色彩感が薄いのだ。そこで思い当たるのが、前述の名前と文体との関連性である。まず、冗長さを封じた簡潔な分の在り方は、モノローグ的な記述の多い、重く垂れ込めた内容のステップを軽やかにしている。また、登場人物の多彩さと彼ら・彼女らのユニークな個性が救いを用意してくれている(名古屋・東京・フィンランドと、舞台を変えていく展開も同様のはたらきをしている)。現実性の高い彼ら・彼女らの名前から、僕らは親しみを感じることもできる。もしこの作品から、現実味のある名を持つ多彩なキャストとソリッドな文体がなければ、主人公はやるかたない茫漠とした寂寥になんの光を見出すこともなかっただろう。 すべての「巡礼」を終え、最後の探訪で「あなたは空っぽな存在なんかじゃない」と断言されてもなお、自分を何者でもない虚ろな存在としか思えないつくるに、ほんのわずかな肯定の泉の水が湧き出る。そのかけがえのなさは声高に叫ばれたりはしない。その大団円からはかけ離れた現実世界のリアリティーに、「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」は命を吹き込まれている。純潔と汚されやすさを両刃の剣とする白色が崩壊と死をもたらし、すべてを飲み込む闇の黒色が再生と自立のシンボルとなる。そんな危うい地点に、あなただって僕だって立っている。 |
||
| 1Q84 (2009/05 〜 2010/04) |  |
|
| 東京奇譚集 (2005/09) |  |
|
| アフターダーク (2004/09) |  |
|
| 海辺のカフカ (2002/09) |  |
|
| アンダーグラウンド (1997/03) |  |
|
| 村上春樹、河合隼雄に会いにいく (1996/11) +河合隼雄 | ||
| スプートニクの恋人 (1999/04) |  |
|
| ねじまき鳥クロニクル (1994/04 〜 1995/08) |  |
|
短編集「TVピープル」から、村上春樹はオカルト的な要素を含んだ物語世界を紡ぎ始めたが、「ねじまき鳥クロニクル」からはさらに、暴力を取り扱うようになった。これまで、いくら悲劇的であったり沈鬱であったりするストーリー設定だったとしても、静謐な美しさを湛えた彼なりの小説世界へのいざないに慣れていたかつての僕には、激しい違和感があった。拷問として生きながら皮を剥がれる男。殴られ蹴られ血を流しながら笑っている男。シベリアの炭鉱で無慈悲に殺される人々。レイプよりひどい形にけがされる女性たち。どうして村上春樹がこんなものを書かなければならないのか。――しかし今となっては、現代世界に正面から対峙するためにも、小説家としての伸長を図るためにも、避けて通ることのできない作品だったのだと合点がいく。2年後にはオウム真理教事件を取材したノンフィクション「アンダーグラウンド」を上梓する彼の眼には、人間社会の有する混沌とした情念に切っ先を向けることの必然が横たわっていたはずだ。実際、彼は「デタッチメントからコミットメントへ」という自身の転換を語ってもいる。そしてそこには、全共闘世代の彼がその「落とし前」をつけるという過去に向けたベクトルから、いま・ここを物語るという姿勢の転換とも重なっているだろう(蛇足を加えれば、村上春樹は学生運動家ではなかったが、積極的であろうと消極的であろうと、その時代を生きた者として目を背けてはいけない物事として学生運動を捉えている)。 同時に、「ねじまき鳥クロニクル」では歴史を取り扱うようにもなった。ノモンハン事件に関するくだりは、とりわけ読者に強いインパクトを残したことだろう。新京での動物虐殺シーンも印象深い。にもかかわらず、前述のようにこれらのシーンは現在を物語る舞台装置として、欠かすことのできないポジションを担っている。このあたりは、現実世界と非現実世界の境界線を行き来するストーリーテリングを追いかけ続けている村上春樹の面目躍如である。ただし、非現実世界をそれとして描くために一定の抽象性が必要とされているのとは対照的に、歴史的史実を下地とした場面にはとことん具体性が要求される。もちろんそれらのセクションでは、村上春樹の念入りな描写によって、圧倒的な映像が展開されており、こうした筆致がのちの彼の作品に新たな息吹を吹き込む端緒となった。 ただし、何度かの再読を通じても、いまだにこの作品には腑に落ちない点がある。その最たるものは、笠原メイという16〜17歳の女性の存在である。村上春樹の作品には、本篇としてのストーリー以外に様々な文章が顔を覗かせる。当作で言えば、間宮中尉からの手紙や、「首吊り屋敷」に取材した週刊誌の記事などである。しかし、こうした文章での伏線は様々な形で本編に回収されている。それに対して、笠原メイはこの長編小説のほぼ全体を通じて登場するものの、その必然性をうまく飲み込むことができないでいる。たしかに、「路地」と「井戸」はこの作品の骨子を成す存在で、その導入に彼女が果たした役割は大きいのだが、その後、彼女が姿を消して主人公に送った手紙でしかほぼ姿を見せなくなって以降、物語を補完するにはごく小さな存在になってしまっている。 前作「国境の南、太陽の西」が、村上春樹の奥さんからの「多くの要素が盛り込まれすぎていて、物語のメインラインが乱される傾向がある」という指摘によって誕生したという経緯を持っているように、「ねじまき鳥クロニクル」は大きな版図を想定した野心作である。ある種混沌としたパワーが魅力だと思う。このタイプの作品にあっては、読者がそこから何を汲み取り、どんな想像を付与するのかに対する自由がより広く与えられている。そこに笠原メイの存在も位置づけられるのだろう。物語全体に垂れ込めた暗雲があまりに重く、殺伐とする点を、笠原メイが救ってくれるというバランサーの役目を果たしていることも理解できる。だが、「ノルウェイの森」で緑という、小動物のように生き生きとしながらもおかしみと揺るがない個性を与えられたキャラクターをすでに目撃した一読者として、笠原メイは彼女の年齢のようにまだ不安定で危うい。あるいは、加納マルタ・クレタ姉妹や本田さん・間宮中尉・赤坂ナツメグ・シナモン母子のように強烈な個性を放つ脇役を輩出する過程で、笠原メイのキャラクターの薄さがこちらでも中和剤としての役目を果たしているのかもしれない。また、完全に余計なお世話だが、彼女の水着や全裸のシーンが出てきたり、年の離れた主人公にキスする場面が出てくるたび、「ああ、こういう部分がアンチ村上春樹の人々を刺激してしまうのだろうな」とひやひやしてしまう(彼女の存在意義が薄いと感じているからなおさらだ)。その一方で、今後の読み返しで笠原メイの必然性を感じられるようになるのではないかという期待もある。 笠原メイを中心とする登場人物の多さやエピソードの数々を「意味づける」のではなく「手探る」ように読むことが、「ねじまき鳥クロニクル」を楽しめるかどうかの分岐点となるのだろう。村上春樹がそれぞれの作品のテーマに据えている事象は、簡単には語りようのないことばかりだ。簡単ではないからこそ、物語という形式を選択することに意義がある。本作は、その多面性の中に読者の想像力をうんと含ませることで完成する開かれた作品ではなかろうか。 |
||
| やがて哀しき外国語 (1994/02) | ||
| 国境の南、太陽の西 (1992/10) |  |
|
村上春樹といえば、現実と架空の行き来を大胆かつ精緻に描く長編作家であり、カットと演出の鋭い切れ味が小気味よい短編小説家である。もちろん、その範疇に収まらない作品も少なからず存在するが、おおむねそうである。だからだろうか、彼の手による中編小説は、実験的な作品が多いように映る。そんな中、中編小説「国境の南、太陽の西」は驚くほど一般的なスタイルで書かれている。まず主人公の生年月日から著述が始まり、名前が紹介され、父母のごく簡単なプロフィールが語られる。思わず誰か別の私小説作家の小説と間違えて手に取ったかと、表紙を確認すること請け合いだ。その後も時間軸に沿って話が展開してゆき、整然とした構成と冗長さを回避した文体が選択されている。もちろん、最後まで異空間も登場しなければ、シャープなエッジも意図的に封印されている。あまりにも既視感のあるそのありよう――そう、村上春樹は自分が禁じ手にしてきた「普遍的スタイル」を用いるという実験を、その場としてふさわしい中編に持ち込んだわけだ。 その手法を選択した理由は、のちに「村上春樹全作品 1990〜2000 第2巻」で彼自身が明かした「国境の南、太陽の西」誕生の経緯に求められそうだ。まず、「ねじまき鳥クロニクル」の原型を書き上げた彼は、そのあまりに様々なファクターを抱え込みすぎた野心的超大作に、各要素の関連性に対する不安を覚え、奥様に意見を求めた(蛇足ながら、彼の作品の最初の読者はほとんどの場合奥様であるそうだ)。その結果、「ねじまき鳥クロニクル」から3つの章が削除され、その3章を独立した一作品として練り上げた作品が「国境の南、太陽の西」として結実することとなった。そして、「ねじまき鳥クロニクル」を俯瞰的に眺め直すためにも、「国境の南、太陽の西」は先行してまとめられた。こういった背景から、村上春樹のシグネイチャー的な要素と新境地を我が物にせんとする野心の交差点である「ねじまき鳥クロニクル」とは対極的な立地に、「国境の南、太陽の西」はマッピングされたと考えられる。 さらにもう一つ、「国境の南、太陽の西」には珍しい点がある。村上春樹作品の男性主人公は基本的に、特筆すべき点のない人間、あるいは凡庸だと自己認識している人間として登場してくるが、この作品では冒頭の段階で「僕は事実あまやかされて、ひ弱で、おそろしくわがままな少年だったのだ」と独白している。しかも、主人公「始(ハジメ)」のこの傾向は物語の最後まで貫かれている。一見するとこれまでの彼の作品に登場する主人公と大差ないキャラクターとも重なるが、当作がハジメの二度の不倫によって他者も自身をも傷つけることになる顛末を中心に据えていることからも、一定のオブセッションを抱えた人物設定となっていることがわかる。この点からも、「国境の南、太陽の西」は私小説的アプローチに挑んだ作品だと感ぜられる。 この作品では、主人公以外の主要登場人物が全員、女性で占められている。安直な言い方をすれば「女性遍歴」ということになるのだろうが、それは早合点というものだ。ハジメにとっては、男女問わずほとんどの人物がただの脇役に過ぎないのに対して、一人っ子という言葉や環境を一種の呪詛と感じてきた彼が、同じ境遇にあって、精神の深いところで共鳴しあえる世の中でたった一人の少女=島野さんとの邂逅によって人生を決定づけられるところに、彼のオブセッションが存在するという構造を持っているからだ。ピンホールのように微小でありながら明確な範疇にしか、ハジメの心が震えることはない。そして彼の人生は、このピンホールの存在によって、自分ではそうしたくないと念じていても、倫理にもとる方向へとボブスレーのごとく急滑走してゆく。高校3年生のときに、同級生であり恋人でもあるイズミの従妹と出会ったハジメが、ねじ伏せられるほどの吸引力で肉体関係に耽溺してゆくエピソードもしかりである。 「ノルウェイの森」を執筆するにあたって、村上春樹はデビュー作「風の歌を聴け」とは真逆に、「セックスと死」を全面オープンにして描くことを念頭に置いていたという。改めて眺めれば、「国境の南、太陽の西」はまるっきりその系譜に属する作品である。しかも、前述のように私小説的タッチで現実的・同時代的な舞台装置が用いられている影響で、性的事項の扱いは「ノルウェイの森」よりも生々しい(逆に、「ノルウェイの森」では死の影が濃厚である)。ハジメ以外の主要登場人物が女性ばかりであることも含めて、「国境の南、太陽の西」は村上春樹の作品に欠かせなくなる「女性」の像を凝縮した作品だと見える。 |
||
| 雨天炎天 (1990/08) | ||
| 遠い太鼓 (1990/06) | ||
| TVピープル (1990/01) |  |
|
| 村上朝日堂はいほー! (1989/05) | ||
| ダンス・ダンス・ダンス (1988/10) |  |
|
「僕」を主人公とした作品が「羊をめぐる冒険」までの三部作として、一度完結したものであったことは、よく知られた話である。そして、現在に至るまでの村上長編の骨格を形作った「世界の終りとハードボイルドワンダーランド」と、あの一大ベストセラー作となった「ノルウェイの森」を挟んで、この「ダンス・ダンス・ダンス」は、ひょっこり現れた。 この四部作を貫いているのは、何といっても、若さを結晶化させたようなあの文体である。村上春樹と庄司薫との共通感を指摘する読者は、この一連の「僕」作品に同じにおいを嗅いでいるのではないだろうか。あるいは、かつてのアンチ村上派も、その毛嫌いの源をこの時期までの村上作品の文体に感じたのではなかろうか。 |
||
| ノルウェイの森 (1987/09) |  |
|
村上春樹の長編作品には、すでに発表された短編小説から発展したものが多い。彼はユリイカ誌のインタビューで、こうした短編の中には、先を続けられるものとそうでないものがあり、それは皮膚感覚で分かるというような発言をしていた。「ノルウェイの森」の原型となる「蛍」に、その先の「小説として書かれることを欲した世界」が広がっていることも、読者としては比較的理解しやすいケースだと思われる。「1973年のピンボール」に登場する「直子」のエピソードもまたしかり。 しかしそれでも、この作品は振り返ってみると驚きの連続である。改めて再読した「ノルウェイの森」は、これが村上春樹作品であることにかなり不思議な手触りをもっていた。もちろん、彼らしい比喩の妙に満ちてはいるし、主人公の「ワタナベ・トオル」の存在も、これまでの「僕」や「私」に似たポジションをとってはいる。また、異色作であるという感想にしても、「ノルウェイの森」がリアリズムを用いることを目的のひとつとして書かれていることは、著者自身の発言から知られている。だが、それでも他に何か、決定的に違うものがある。その糸口をほどいてみたい。 「ノルウェイの森」は言わすもがな、村上春樹の一大ベストセラー作で、実は僕もご多分にもれず、この作品が彼の世界に接触した最初だった。そして、多くの読者と同じく、僕もこの作品に激しく惹かれた。そこにはこの物語の意味するテーマに対する共振ももちろんあったが、残る半分ほどは、いくら喉を潤しても癒えない渇きのような若さの感傷に訴えられるものがあったはずだ。大学紛争の時代に遅れて生まれたことを悔いていた僕にとっては、この時代に対するオマージュもさらに甘い光を放っていたに違いない。その後、僕は彼の作品を後追いで手に取りながら、いわゆる「ハルキ・ワールド」に全身どっぷりと浸かってゆくのだが、そのゲート・ウェイトなったのが憧憬に値する時代背景を持ったこの作品でよかったと思っている。 ほぼ「蛍」の再収録となっている第2章は、この物語のスタート章となっている。第1章が37歳になった主人公の回想に充てられており、序章の役目を果たしているからだ。そして、この物語を貫く「直子」の透明な魅力と、その所以となる心の病、さらに彼女の死までもがこの1章ですでに語り終えられている(正確に言うなら、「1973年のピンボール」冒頭、つまり「ノルウェイの森」発刊以前に明かされてもいる)。直子について、そして主人公との関わりについては、そのイメージを降り積もる雪のように白く、そして次第に振り積もるだけの重みを加えるように物語は進んでいく。しかし、ここに生命の息吹を吹き込む「緑」が登場することで、「ノルウェイの森」はこれまでとまったく異なる作品となったことは、村上春樹の他の作品と本作を読み比べた読者なら誰でも気づくだろう。ユニークという意味では、「突撃隊」「永沢さん」といった得難いサブ・キャラクターも登場するものの、彼らは針の振れ切った異物として登場し、これまでの作品にもこうした珍奇な人物は常に見受けられた。彼らは他のほとんどの登場人物同様、著者によって与えられたレッテルを着ぐるみのごとく身につけたまま変容しようとしない、あるいは前進を受け容れられないままストーリーを脇から彩り続ける。村上春樹世界のストレンジャーの中では、ただ、「緑」だけが自身を鷹揚に発露し、生の世界にあまねく光をもたらす。第1章での種明かしといえば、「生は死と対局としてではなく、その一部として存在している」という作品全体のテーマも太字で紹介されているが、3章から姿を見せる「緑」は、生死の溝をポンと突き放したような態度で船の舳先となってゆく。この突き放し方が、旧来からの村上ワールドの代表者である主人公の「ワタナベ・トオル」とは大いに異なる。後者はあくまで諦念の上に立ち、他者のみならず、自身に対してもあくまで客観姿勢たることを崩さないのに対して、風変わりな自分の価値観を知りつつ肯定することで現実と照応し、生きることから死を眺めようとするのが「緑」である。 この明快なストーリー展開――つまり、テーマがあらかじめはっきりと掲げられて進む物語の構造と、「直子」と「緑」の鮮やかな対照――を基にしたリアリズム作品は、他の村上春樹のどんな小説よりも不特定多数の人々に迎え入れられる要素に満ちていたと言えるだろう。まさしく、僕にとってもそうだった。日本の純文学(改めて感じるが、なんと胡散臭い言葉なのだろう)の古典とでもいうべき作家を読む機会の多かった当時の僕は、私小説的リアリズムに慣れ親しんでいた。人物と風景と物語の推移を彩るための比喩表現は素直なあり方で理解しやすかったし、テーマの重苦しさに小粋な息吹を吹き込んでもいた。日本人の大好きなセンチメンタルな世界の描き方は、若かった僕の心象風景にもぴたりと当てはまった。それと同時に、「ノルウェイの森」はこの明快さゆえ、始めからほとんど種明かしされた、ストーリー重視の諸作とは対照的な、静物画のような作品でもある。絵画的要素といえば、初期の「風の歌を聴け」「1973年のピンボール」も同じ形容ができようが、この2作と「羊をめぐる冒険」の前半部分は啓示的な言葉を散りばめた連作絵画の趣で、一つのモチーフを丹念に描いた「ノルウェイの森」の印象とはずいぶん異なる。 こうしたことから、「ノルウェイの森」は短編に近い作品だといえる部分がある。生と死の綱引きで、「直子」も「緑」もしかるべき場所へと導かれ、その双方に自分の存在と喪失を重ね見る主人公、そして「直子」と主人公の狭間に、同様に揺れ動く「レイコさん」の位置づけを水彩画のように描くことで、この物語は完結している。短編のポイントはモチーフの採り方とその切り口であろうが、「ノルウェイの森」ははまさしくこの方法論で料理された短編的長編小説なのではないか。それゆえ、「緑」の存在がモノトーンになりがちな本作の世界に大きなインパクトを残すのだろう。「羊をめぐる冒険」での特殊な耳を持った女性、「世界の終りとハードボイルドワンダーランド」での太った女の子など、村上作品には独特の価値観と存在感を持った女性がしばしば登場するが、彼女らには及びもつかないくらいに「緑」が輝いたキャラクターとして記憶に残るのは、一つに、「ノルウェイの森」の完結的世界にあって唯一の風穴である彼女の立ち位置から来るものであろう。そもそも、村上春樹が短編「蛍」を用いてその続きを書こうとしたとき、「緑」の存在がなければどれだけこの作品が変容してしまうのかは自明である。そして、彼女の存在こそがこの作品を長編小説たらしめているのである。長編が長編である理由の一つとして、物語が動画となり、ストーリーの先行きを常に変動させ、読者を揺さぶってわくわくはらはらさせることがあるはずなのだから。こうした超越的存在が内在的暴力であったり、無意識の意識であったり、孤独で消耗的な都市生活であったり、村上作品には社会的で無形の存在として =続く= |
||
| 日出る国の工場冒険 (1987/03) | ||
| THE SCRAP 懐かしの1980年代 (1987/01) | ||
| ランゲルハンス島の午後 (1986/11) | ||
| 村上朝日堂の逆襲 (1986/06) | ||
| パン屋再襲撃 (1986/04) |  |
|
| 羊男のクリスマス (1985/11) | ||
| 回転木馬のデッド・ヒート (1985/10) |  |
|
| 世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド (1985/06) |  |
|
著者自身の手による「ノルウェイの森」あとがきで、この「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」が自伝的小説であると述べられているのは、よく知られた事実である。リアリズムを追求しながら、1960年代後半から70年に至るまでを舞台とした「ノルウェイの森」に関しても個人的な作品であると述べられてはいるが、どうしてこの徹底した寓話世界が自伝的なのか。それはずっと僕の喉元に引っかかってきた疑問だった。 この作品は静と動というべき二つのまったく異なる物語が交互に語られ、やがてそれが密接な相互関係になったことが徐々に明らかになり、息をつかせぬクライマックスへと導かれるという、村上春樹の見事なストーリー・テリングの妙を我々の前に披露してくれた初めての作品である。圧倒的な存在感を示す大きなテーマ、舞台装置の的確さ、めくるめくメタファー、それでいて確かな梁に支えられた娯楽性の高さなどは著者の他の作品にも共通しつつ、しかしこの作品でしか味わえない絶妙のブレンドを誇ってもいる。そして、そのブレンド具合がいわゆる「自伝的」な所以なのではないか、というのが僕の謎解きの入り口だった。 短編「ファミリー・アフェア」で「ワタナベ・ノボル」というユニークな主人公を登場させたことが、自身の創作にひとつの可能性を生みだし、それが「ノルウェイの森」のユニークな登場人物「緑」を作り出す原動力の大きな要因となったと、インタヴューで村上春樹は述べている。だが、そこに僕なりの蛇足を加えれば、彼はこの「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」でその可能性の一端をすでに掴んでいたのではないだろうか。僕が感じた「ブレンド」の要素に最も印象深かったのが、その部分だった。 ストーリー性の高さを前作長編「羊をめぐる冒険」で確立していた著者ではあるが、それまでの作品は基本的にモノトーンな色調に包まれている。著者は、スリルとサスペンスに満ちたハリウッド映画的といってもいい動画的な要素を発展させた「ハードボイルド・ワンダーランド」で、徹底して主人公を取り巻く状況に翻弄させ尽くす一方、「世界の終り」ではほとんど絵画のように静謐とした、時間軸を必要としない世界を描き、動きやゆらぎがないだけに主人公の目を通して一人称の印象画となっていることを強調する。これはどちらも、「羊をめぐる冒険」に内在したファクターの色づけを変え、双方向に意識的なデフォルメを施したものと考えられるが、その結果、ずいぶん毛色の違う作品が生まれたようだ。 ここから先は作品の種明かしになってしまうが、「羊をめぐる冒険」までの三部作では、「鼠」という名のもう一人の主人公が摩耗し、矛盾を抱え込み、そのたびに生命力を薄くして、最終的には大義のために自滅する。そして、狂言回し役である主人公はひたすらそれを眺め続け、「生きる」という名の殻に閉じ込められ(あるいは閉じこもり)続ける。主要な登場自分物の死をもってエンディングとするスタイルや、主人公が透明な語り部に徹することは小説のセオリーと言っていいだろう。この定石を破った「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」においては、「鼠」と「僕」のような生身の分身ではなく、ある一人の人間の内部と外部でのできごとが描かれており、現代日本の都市生活者なら少なからず受け持たなければならない自己分裂傾向を投影したものとも言えそうである。その帰着点は、「羊をめぐる冒険」まで「僕」というキャラクターが背負ってきた徹底的傍観者である「ハードボイルド・ワンダーランド」での「私」が終焉を引き受けている。そして、「私」はすべてが終わる直前に、この世の日常生活がいかに啓示に満ちているのかを知る。「鼠」を受け継ぐ「世界の終り」での「僕」の方は、最後に主体性を取り戻し、自らが運命を選び採っている。ここに僕は村上春樹自身を見る思いがする。彼が「TVピープル」以降に見せた世界観、「アンダーグラウンド」で取材したオウム真理教の実際に存在する日本という、孤独の軋む音が聞こえるような外部世界に翻弄されつつも、内部世界ではこの孤独から聴こえてくるかすかな鼓動を頼りに文を紡いでいこうとする彼の姿が重なって見えるのだ。 2011年、僕がこの文章を書いている現在、この本を読んだ経験のある人なら誰もが持つ感想のひとつに、この物語での「計算士」と「記号士」の設定は、ネットが完全に一般化した今日の状況にフィットしたものであるという驚きがあろう。「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」が発表された1985年は、パソコン関係でいえば、NECがPC-8801や9801の後継機を開発し、マイクロソフト社がMS-Windows1.0を発表した年であり、その前年にApple社(現マッキントッシュ社)のMacintosh初代機が出ていた時代である。記録媒体にオーディオ用のカセット・テープが用いられたそんな頃、彼は26年後の日本の質感を確実に捉えていたとしか言いようがない。共闘の時代が終わり、個人との苦闘がそんな舞台で繰り広げられる外的なポジションにあって、著者はこの作品に到達する以前まで「すり減る」という言葉を繰り返してきた。だが、彼はおそらくこの作品からその姿勢を、彼自身が用いている表現で言うなら、デタッチからコミットへと進めた。個々が生きるために背負い続け、その重さに喘ぐべき矛盾の代償を、「役割」という名のもとに他者に転嫁し、自身の心の喪失を選択することで自身を破綻から救おうとする現代社会の構図は、まさしく「世界の終り」で描写されているものと一致している。しかし、最終段階で著者は悩みに悩んだ末、同化も転化もさせない位置に主人公を着地させた。そのアンカー・ポイントこそ、この作品以降、村上春樹が世界へのコミットを始める最初のステップになったのではないだろうか。 ここまで来て、ようやく僕は村上春樹の「ブレンド」、つまり趣味性の部分でこの作品が自伝的だという仮説が、それこそ外部的な指摘だったことに気がついた。もとより、この作品が象徴的な意味での自伝的作品であることは自明だったはずだが、作中の「壁」が示す断絶をもっと積極的に考慮すれば、「ハードボイルド・ワンダーランド」の「ワンダーランド」という言葉が示すとおり、外部世界はデフォルメされた、趣味性に満ちたものでよいはずだ。舞台装置を娯楽性の高い物語で踊らせれば踊らせるだけ、中心核の空虚ぶりは浮き彫りになるだろう。その台風の目のような位置の寂寞に佇む村上春樹の内的な、まるである時期の、ある種のアンビエント・ミュージックが目指したような静寂の叫びが、村上春樹自身の生身の声なのだ。その二面的アプローチがいかに彼にとって重要なものであったかを、同じく二つのパラレル・ワールドが結び合わされた形式を有する「海辺のカフカ」(2002年)や「1Q84」(2009〜10年)に敷衍されていることが証明していることは言及するまでもないだろう。 |
||
| 蛍・納屋を焼く・その他の短編 (1984/07) |  |
|
| 村上朝日堂 (1984/01) | ||
| 中国行きのスロウ・ボート (1983/05) |  |
|
| 象工場のハッピーエンド (1983/01) | ||
| カンガルー日和 (1983/01) | ||
| 羊をめぐる冒険 (1982/10) |  |
|
| 夢で逢いましょう (1981/11) +糸井重里 | ||
| ウォーク・ドント・ラン (1981/07) +村上龍 | ||
| 1973年のピンボール (1980/01) |  |
|
ストーリー・テリングの妙は村上春樹作品の醍醐味であるが、この頃の彼は敢えて物語の起伏を薄くしたようにも見える作品を書いていた。確かに多くの人々が揶揄するように、悪く言えば「お洒落なカフェのマスターが書きそうな作品」ではある。しかし、彼の残した透明な喪失感には、夢とも現実ともつかない中に、読者にとって、ほかの誰でもない自分自身の問題を浮き彫りにする確かな質感があった。その陰の部分=現実を背負うものとして登場する、主人公の友達である「鼠」は、だからこそ非常に抽象的な描かれ方でしか登場しない。孤独を「孤独」と字面に直してみたところで、空虚な寂寞が待ち受けているだけである。 主人公としばらく居をともにする双子姉妹の登場は唐突で、その別れもあっけないものだった。そこには理由がない。それはとりもなおさず、理由など必要ないということである。物事が定めのように流転してゆく中で、人はただ抗えない何かをあきらめながら、それでも何かを目指そうとして明日を迎える。でも、それは空虚でも寂寞でもない。悲嘆すべきものもない。ただ渺々とした日々の連続があるばかりである。 =つづく= |
||
| 風の歌を聴け (1979/01) |  |
|
| |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
