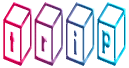
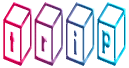
-旅行-
| 深夜特急 沢木耕太郎 新潮社(1986〜1992) | |
| とりあえず権威には反抗してみたくなる。僕がひとり旅をするようになった頃、「深夜特急」はすでにバック・パッカー必読の書といった位置に祭り上げられていたせいで、わざと距離を置いてしまった。それは本書の著者、沢木耕太郎自身が山口文憲とのとの対談で、地図を持たずに旅をすることを語ったのと似た気分も含んでいた。圧倒的な支持を得ている紀行文を読んでしまうと、旅が自分のものではなく、沢木の軌跡をなぞるものになりかねないという危惧がある。「深夜特急」を読んで旅に出る人にとって、それは立派な動機となっていい。一冊の本がある人の人生の方向づけを変えるようなファンタジーがあるから、書籍にはまだまだ他にはないリアルな命が脈々と流れているのだ。ただ、何気なく入国した台湾でこれまで感じたことのない高揚と自由を意識したことがひとり旅のスタートとなった僕には、他の旅行者と情報交換することよりも、現地の人々に交わり、できるだけ「日本」から遠いところに位置することが重要だった。 さて、初めて「深夜特急」に手を伸ばしたのはいつのことだったか。少なくとも、それは旅行者ではなく、バンコクで暮らし、挫折して、また再びバンコク生活を再開したのちのことであったことは確かだ。しかも、職場に置いてあったものを借りてきて読んだ。それがこの伝説の書に対する、僕なりに絶好のシチュエーションではないかと思いながら。 あっ、これは僕そのものではないか。著者はこの旅で徹底的に酔狂に身を投じ、歩き回ることで街の概要を掴み、思いがけない事態の渦に呑み込まれてゆくことを愉しみ、観光地を巡るより街の熱に浮かされ、やがて先へ先へと駒を進めることが快感となって、摩耗してゆく感性に、老成してゆく旅の終着を考えるようになる。そのストーリーは、僕自身と無理なくすっぽりと重なった。彼と僕とは似ているのだなと思いこみかけた。しかし、いや、そういうことではなく、沢木がここで著しているのは、バック・パッカーの多くが胸に抱く思いなのだ。それを鮮やかに汲みあげ、鮮やかに文字として織りなしたのが「深夜特急」だったのだ。 沢木と同じ深夜特急に乗れたことが、素直に嬉しい。たぶん、この本を読み終えて旅立った若者たちは、沢木と同じようなものを求めて深夜特急に乗り損ねた人が多かったのではないか。「同じようなもの」は、探し当てるものではなく、開け放った自分の中におのずと醸造される性質のものだからだ。その観点から言えば、この書物は罪作りな一面を持っている。玉手箱は、竜宮城に行く前や、その最中に開けるべきものではない。 そこから、さらに、長い長い露店街が続き、人はここにも溢れていた。 その人々の流れに身を委ねながら、私は激しく興奮していた。なぜ自分がこんなに熱くなっているのかわからない。しかし、とにかく、これが香港なのだ。今まで私がうろつきまわっていた場所などは、ここに比べれば葬儀場のようなものでしかなかった。これが香港なのだ、これが香港なのだ……。 そこが廟街という土地であることは、宿に帰って地図で確かめて知った。 |
 |
| 南の島へいこうよ 門田修 ちくまプリマーブックス(1991) |  |
| 誰にでも分かるやさしい言葉でシンプルな事柄を心に届くくらいにしっかりと書き上げるというのが、やっぱりもの書きの一つの夢だ。そのためには、語ろうとする物事に深く通じ、奥深く時間をかけて味わっていないといけない。モノを考えて論をひねり出すというのは、実はさほど難しいことではないだろう。AがいえるならB、Bが成り立つならC、と発想の連鎖を並べれば「それなりの主張」というのは見栄えよく並べておけるからだ。でも、ちゃんと時間をかけて自分の中に熟成された言葉はどんどん虚飾をはがして平易で簡潔な、誰にでもわかる言葉に置き換わってゆくものだ。 「南の島へ行こうよ」は、日本を出るときには鳥になった読者が、筆者の声に導かれながらサイパンやグアムのさらに南、カロリン諸島のサタワル島という地図にもほとんど載っていない島に降り立ち、そこで人間に戻って数週間を島の人々とともに過ごすという形になっている。定期的な船の便もなく自給自足で成り立っているサタワル島では、サンゴ礁の島であるために石がなかったり、女系社会でありながら女人禁制のカヌー小屋の前を歩くときには女性は腰を低くかがめないとならないとか、漁などいざというとき以外には男達は自然と向き合ってただボンヤリしていることが多いなど、それはほとんどの読者にとっては未知の世界で、非常に簡単な語り口調で筆を進める筆者の言葉は、まるで島を包む潮騒のようにごく自然に耳に入ってくる。 下には文章中でも啓蒙的な部分を挙げたが、この本の素晴らしいところは、よくある教示的な比較文化論に陥ったり「外界」をただ憧憬の念をもって描きあげる凡百のフィールド・ワークに成り下がっていないところだ。世界の海を眺め、深い時間を過ごし、醸造された言葉とそれを裏打ちする実体験を伴った知識で、読者である「君」をサタワル島での体験に連れていってくれる。文体が押し付けがましくないから、読者が自分の感想や想像や意見をはさみながらゆっくり読み進めていくこともできる。込み合った地下鉄に揺られながらでも、人の邪魔になりさえしなければ、僕はこの本を数行を拾い読みするだけで風を感じることができる。 肉は赤身で、ちょっと魚臭い牛肉のようだ。アオウミガメの料理なんて、フランスではかなり高級品だ。君も分け前として、両手にあまるほどの肉をもらったけど、さて、食べられるだろうか? 海のなかで、ゆうゆうと泳いでいる姿や、涙を流す黒い目を見ているから、かわいそうだと、カメに同情する気持ちになっていないだろうか? 目の前で大きな動物を殺して食べることなんて、日本では経験できないから、そんな気分になってもしかたがない。 でも、ちょっと想像力を働かせれば、冷凍パックになった肉だって、大好きなハンバーグだって、元をただせば、黒い目をした牛なんだけど。とにかく、どんなふうに思っても、「カメを殺すのはかわいそうだから止めろ!」と、島の人たちに叫ぶのはよそう。 君が心に何か痛みを感じるとすれば、それはきっと別のところに問題があると思う。 無人島での一週間は、完全に自然からの略奪だった。魚、鳥、ヤシガニ、アオウミガメと、てあたりしだいに捕って食べた。はたして、こんな豊かな自然がいつまでつづくのか、そして、自然のなかで生きる人びとの生活がいつまで変わらずにいられるか、それが問題じゃないだろうか。 捕っても、捕っても、捕りつくせないほどの豊かな自然があれば、そして、自然の回復力をよく知っていれば、人間の略奪なんてわずかなものなんだ。 しかし、これも人間の勝手な考え方かもしれない。人間だけが自然を略奪するのは公平ではない。自然のバランスが崩れるもととなる。だから、人間もときには、何者かにつかまり、食われなければいけない。ここまで考えると、そんな運命を受け入れる、豊かな精神正解が必要となる。現代の人間はそこまで賢くない。 |
|
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
