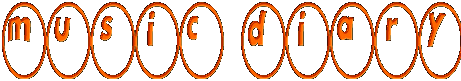
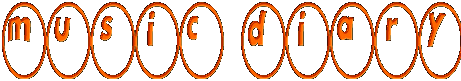
| �Q�O�P�V�N 12��14���i�j ���N���g�̓��L�ɏ����c���Ă��鎄�I�u���N�̃x�X�g10�ȁv��2017�N�x�ł��v���N�����Ă݂�ƁA�u���N�̃x�X�g����10�{�v�����I�ׂȂ����Ƃɂ͂��ƋC�Â��B ����Ȏ���̐�삯��1980�N��ɉ��o�����I���W���ł����}�C�P���E�W���N�\���ւ̃I�}�[�W���͍��܂������B �����A����80�N��A�ނ̓|�b�v�E�C�R���Ƃ��Ĉ����Ă������Ƃ�m���Ă���B �����́u���y���Ă�v���X�i�[�͕K���Ƃ����Ă����ق��v�����X�ɕ[�𓊂��A�W���N�\��5����ւ̕]���Ƃ͕ʂɁA�A���o���u�X�����[�v�ȍ~�̃}�C�P���E�W���N�\���̂��Ƃ��u�|�\�l�v�ƌ��Ă����B �ᓖ���̃v�����X�̊J���v�V�������ꂾ���ڂ���߂��M��������Ă����Ƃ�������� ����y���̂������ɘR���͂����Ȃ��A�}�C�P���E�W���N�\���̕]��������ɏオ�����B �ނ̎���2009�N6��25���B �����ē��{���㗤������iPhone3�̔������ق�1�N�O��2008�N6��9���B �l�b�g�̓����z�M�Ȃǂ�����̒��S�Ɉ�ʉ����Đ��E�I�Ɂu�ʔ������͖̂ʔ����v�ƌ����鎞�オ��������n�܂����B �A�j�\����{�J���A�A�C�h�����V�[���̒��S�ɖ��o�Ȃ���A�l�C�Ǝ������˔����A���ꂪ���Ƃ��ȒP�ɊC�O����̕]����������鎞��B �����N���}�C�P���E�W���N�\���̂��Ƃ��ǂ����ʼn��Ɍ���悤�ȕΌ��������悤�Șb�͂��Ȃ��Ȃ����B 9���特�y�G���^�[�e�C�������g�̂��߂ɐl����������ނ̂��Ƃ��A�l���܂�80�N��o�u���̓��{�ɏd�˂Čy�����Ă������Ƃ�\����Ȃ��v���Ă���B ����ɂ��Ă��ǂ����āA�l���90�N��܂ŁA����قǏ�M���X���ĉ��y��D��Ō�낤�Ƃ��Ă����̂��H �C���^�[�l�b�g����̓����B ���E�I�ȁu�V�F�A�v�͑��l�ȉ��l�ςݏo���A�V���Ȕ������e�ՂɊg�U���Ȃ���A���͂₻�̂ǂꂪ�㉺�ł��邩�Ƃ����₢���ɂ����B �����ʂ̌��t�ɒu��������A���y�ɂ����鎿�̏���͏I������A�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤���i�Ȃ�������`�̕���Ǝ���������������j�B �ł��A�u���̏���v�Ƃ������������̂��̂́A�Ȃ��Ȃ�ǂ��납�ߔN�����𑝂������Ă���B SNS�E����A�b�v�E�l���C�u�z�M�Ȃǂ�ʂ��Ėl�����l�l�̂ǂ����ɁA�u�����ˁv��{������J�E���^�[�ȂǁA������u�]���v�Ƒ��������Ȑ��������Ă܂��悤�ɂȂ����B �}�X�R�~���l�b�g���E�̂��Ƃ��L���ɂ���悤�ɁA�����ɉ���Ă��邻�̐�ɁA�u���[�h�o���h����̖l�����̔��M�͈ʒu���Ă���B ���y�̎���ɏ㉺���Ȃ��Ȃ����̂́A���Ȃ�ʎ����������u�z�M�ҁv�ɂȂ��Ă͂��߂āA�|�\�Ƃ�����̍�����A�m���x�l���Ƃ����ʂĂ��Ȃ���������������ł͂Ȃ��낤���B 90�N��܂ŁA�l�����͋Ȃ������̎苖�ɒu���Ă������߂Ƀ��R�[�h��CD���w�����Ă����B �u��i�v���Ƃ����ڂ��������Ă����B ���X�i�[�͍��z���͂��������̉��l�����҂��A����͂��̊��҂ɉ�����ׂ����������B �������A���R�[�f�B���O���ꂽ���y���Œ������Ƃ���̂ƂȂ������A�l�����̓e���r�`�����l���̂悤�ɃN���b�N��ʼn��y�T�[�t�����āA�A���o���ǂ��납1�Ȃ�ʂ��Ē������Ƃ����Ȃ��Ȃ����B �������Ėl�����͗]�ɐ����������Z�ɂ��Ă��܂����B �����āA�����҈ێ������L�[�v���邽�߂̎d�|�����Â炵���v���_�N�V�������o�����̂������ő������Ȃ��s���ǂɂȂ����B �����ȂƂ���A���a����̉��ÓI���n����u�̂͂悩�����v�ƌ��������C����������B �����A�l�̍ő�̊S�́A���炪���M���A���ȃv���f���[�X����������̐�ɉ�������̂��Ƃ������Ƃł���B �X�̃j�[�Y�ɉ�����R���e���c���p�ӂ���A���ꂪ�����ȃT�[�N���̓o��������炵�A���Ԉ�ʂɂ͒m���邱�Ƃ̂Ȃ����l���̏����ȃX�^�[�ݏo���A����ȃX�^�[�������{�����₢���˂��҂����@���njR�����ɂ���ē��X�l���鎞��́A���̐�́c�B ���R�ƕ����͖l���������̎Љ�ɋ��߂Ă�܂Ȃ����z�ł���B �����A����ȗ��z�ɋ߂Â����ƂɁA�l�����݂͂�݂�ǓƂɂȂ��Ă����B ����܂ŁA���ɂ͔�ꂽ�S��̂�����A�l�Ɋ��Y���Ă��ꂽ���y�B ���ꂩ������y�͂����������e�����t��������l��ɒ��Ă���邾�낤���B 2��8���i���j J-Pop�E��2000�N��ȗ��A�A�C�h���Ԑ����ł���B ���ɁA�n���A�C�h�����܂߂������A�C�h���̖u���͂���܂łɗނ����Ȃ��c���������Ă���B ���̒��O�A1990�N��͓��{�|�b�v�X�j��H�Ɍ���A�C�h���~�̎��ゾ�����B �����������ޔ��b�⏬���N��v���f���[�X�̏����V���K�[�����̂悤�Ɏ���̊�ƂȂ�₢���A�C�h�����ۂ������ʒu�̑��݂͐������������A���̒N��������܂ł̃A�C�h���̘g���͂ݏo���A�A�[�e�B�X�e�B�b�N�ȃt���O�����X��g�ɓZ���Ă����B �X���痢�₱�̎����̏����q���A�C�h���̕\���g�������Ɖ����L���A���j�R�[����`�F�b�J�[�Y���Ǝ��̑�����L���Ă����B ���w�����炢�̒j�����������R�ɂ��Ȃ�u�ʍD�݁v�ȃ`���C�X������A�����90�N�ゾ�����B ���ɂȂ��Ďv���A���Â��s�v�c�Ȏ��ゾ�B �����ɕ������J�����̂́A�����̐l���w�E���Ă���Ƃ���A���[�j���O���B�������B ����Ȕޏ������̕����p�ӂ����̂́ASMAP�������Ǝv���B ��q�̃A�C�h���X�͊����A���@���G�e�B�[�ԑg��h���}�Ȃlĵ����ƈȊO�̏ꏊ�ɐϋɓI�ɐi�o���邱�Ƃɂ���ăv���X�ɓ]���A�Ƃ��Ƃ����N�i2016�N�j�ɉ��U����SMAP�́A���[�j���O���B�̗����ʒu�ɑ傫�ȉe����^�����͂����B ����܂ʼnԌ`�����o�[�̌�o�ɉ���ł����A�e�p���̂����܈�̃����o�[�ɁA�u���@���G�e�B�[�ł̃L���������ɂ��K�v���v�Ƃ����I�����������A���̕������͍����܂ő����Ă���B ���[�j���O���B������q�b�g�𐋂��Ă����ߒ��ɂ́A�R���e�X�g�̃O�����v�����I�҂����ł���ޏ������Ƀv���f���[�T�[����^����ꂽ�`�����X�������Ƀf�r���[�ւƌ��т�����J�b����X�^�[�g����T�N�Z�X�E�X�g�[���[���傫������ł���B �܂��A�炢������o�Č��݂̎�������������Ƃ����X�^���X���P������ׂ��A�ޏ������͑����ɍ��x�ȃ_���X�E�p�t�H�[�}���X���I���邱�ƂɂȂ�B �ǂ�ǂ����Ď����̍����v���̎d�������Ă���Ǝ����Ύ����قǁA�݂��߂ȃX�^�[�g���C���ⓖ���̒�����Ƃ̗�����ῂ��������邩�炾�B �ޏ������̃f�r���[�������N�A�E�B���h�E�Y98�����\����A���̒����{�i�I�ɃC���^�[�l�b�g����ւƓ����Ă����܂��ɂ��̂Ƃ��A���[�j���O���B�q�X�g���[��p�t�H�[�}���X���悪���L���ꗬ�z����邱�ƂƂȂ����B ���̃p�^�[�����A���N�̉��ς݂���悤�₭�u���C�N���A����܂łɂȂ��_���X�E�X�^�C���ōJ��������Perfume�ȂǁA�l�X�ȂƂ���Ō��݂��J��Ԃ���Ă���B 2010�N��͂܂��������A90�N��ƃ[���N�オ�h���C�Ƀu�����h�������o�̂���A�C�h���Ɉ��̕]�����^������悤�ɂȂ�����������B �����ɂ��܂��A�l�b�g�������炵������̕ω��̉e�����[���e�𗎂Ƃ��Ă���B YouTube�ɑ�\����閳������T�C�g�̗��p���Z�����A�V���̎���̕ǂ���蕥��ꂽ���Ƃɉ����ACD������L���_�E�����[�h�������肷�邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ�A���������u�ڂ���ĉ��y�ɐZ��v���Ƃ����u����ƂƂ��ɉ��y���y���ނ��Ƃ��Z�b�g�ɂȂ��Ă���v�Ƃ�������ɓ������Ă���B �����ɁA�|�b�v���y�̊ӏ܂�傫�ȃr�W�l�X�Ɍ��т��邱�Ƃ�����Ȃ���鉹�y�ƊE�́A���R�[�f�B���O��i�����X�e�[�W�ɏd�_��u���悤�ɂȂ��Ă���B ����ŐV��PV�����ċȂ����߂悤�Ƃ������X�i�[�����A����������Ń��C���f�������Ă����Ɏ������Q���������Ɗ����鎋���҂���������͂邩�Ɍ����݂�����̂͊ԈႢ�Ȃ����낤�B �����������撆�S��`�̒��ɂ����āA90�N��`�[���N��̉��y�V�[���݂̍���́A���݂ɂ܂������q�����Ă���B Prefume�����̒[�����J�����B AKB�̐Ȋ��ȗ��A�H���N��80�N��f�l�H�����V�[�����X�N�G�A�ŃI�[���h�E�^�C�~�[�Ȃ��̂ւƃr�W�l�X�����Ă������APerfume�͂���ȃA�C�h���E�̃��C���X�g���[���ɁA�G�t�F�N�g�����������{�b�g�E���H�C�X�Ǝ��R�x�̍����\���͂��������_���X���������B �ޏ������Ɋy������Ă��钆�c���X�^�J�͂��̂̂��A�����[�ς݂�ς݂��Ƃ�����q�b�g������A�q�b�v�ƃ|�b�v�̐▭�ȍj�������y���ރ��X�i�[�w��n�o�����B �����āA�A�C�h���Ƃ����y�U���A�܂�ō�����������ꂽ�`�̂悤�Ɋ��C�ɖ��������ׂ̉Q�̃r�b�O�E�o�����N�����B ���^���ƃA�C�h���̗Z�����͂�����Babymetal�A�����_���X�ƈӏ����̍�������������N���[�o�[Z�A�����o�[�S�����I�^�N���ł�ϑginc�A�A�C�h���������X�^�[�g����BiS�A�h���}�u���܂�����v�Ɍ����邲���n�A�C�h���ȂǁA��ɂ͂܂��ɖ����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��B �����Ŗl�����͂悤�₭�C�Â����ƂɂȂ�B �A�C�h���Ƃ����W�������́A����܂Ŗ����Ǝv���Ă����e��̉��y�W�����������ݍ��ނ����̐e�a�͂̍����������Ă��邱�ƂɁB �|�b�v�E�X�^�[���X�^�[�ł��邽�߂ɂ́A���炩�̋P�����������邱�Ƃ���Ώ\�������ł���B ���ꂪ���Ƃ����Љ�I�ȃ��b�N�E�X�^�[��p���N�E�X�^�[�ł������Ƃ��Ă����B �������A2010�N��̍��A�u���[�X�E�X�v�����O�X�e�B�[���������юU�点�ăV���E�g���邱�Ƃ��A�V�h�E���B�V���X�������Ȃ�����f�r�����Ē��w�𗧂Ă邱�Ƃ��A�l�����̐S�����A���ȏꏊ�Ők�킹�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �|�b�v�E�A�C�R���̌������ɖ��͌���������ǁA�R�������P���ȑ��u����퐫���炠�܂�ɂ������ꂷ�����t�F�C�N�ł͔����Ă��܂��A���������C�����l�����̐��������Ă���C���ɉ�������Ă���B ����Ȍ��݂̃|�b�v�E�ɂ����āA�Ⴂ�A�C�h���������ɉH�������Ƃ���p�́A�L���w������x������ɒl����f��������Ă���B �Ⴂ����͂����Ɏ����̖����������A���N�w�͒ʂ�߂��Ă������X�̋L�����d�˂Č���B �u�ǂ������y�r�W�l�X�Ȃ�H�v�Ƃ������߂��₢�ɁA�A�C�h���͍ŏ����瓚����p�ӂ��Ă���B �u�������̓t�@�����y���܂��邽�߂̃A�g���N�V�����ł��v�ƁB ���̓����͂܂��Ƃ��Ő����ł���Ȃ���V�j�J���ŁA�����̋Ńu���[�Ȋ��o�����L���Ă��āA���Ȃ��Ƃ��l�ɂ͊����ɕ�������B �u�ǂ����Ȃ�Ⴍ�Ă��ꂢ�ȁi���邢�͂����������j�X�������L���r���A�e���_���g��Ō�t�ɑΉ����Ă��炦����b�L�[�v�Ƃ����A�����b�ł��炵���������邯��ǂ��g�Ɋo���̂��銴�o�������Ɖ����������2010�N��̃A�C�h��������B �T�[���B�X�ƂƂ��ẴA�C�h���́A���ꂪ������x�����Ƃ������Ƃ��Ă��A�Ď��Ō��C�őO�����łЂ��ނ����B ���ꂽ���N���猩�Ă��A���̐܂�ڐ������d���Ԃ�ɍD���������Ƃɂ�Ԃ����łȂ����낤�B ����A�R���r�j�X���̂����Ⴂ�X�������肵�����肵�Ă��đΉ��͂ɗD��A�l�ԓI�ȗD���݂��`����Ă��Ăق��Ƃ��邱�Ƃ�����B ����ȉ��y������Ă������A�Ɩl�͂����₩�Ȑ����𗧂Ă�̂������B �Q�O�P�U�N 11��18���i�j ����2���A�o���R�N�ő�̊y��X�X�������E�H���E�i�R�[���J�Z�[���Ƃ����n���т̗����ނ����N�����̂�m�����B �挎���R�[�f�B���O�̂��ƁA�e��X�e�B�b�N���P�[�X���ƃ^�N�V�[�ɒu���Y��Ă����l�ɂ́A���͂Ƃ�����܂����̕������挈�������B �X�e�B�b�N�̒��ɂ̓��b�Y��u���V��}���b�g������������A�����Ȃ�ƃE�H���E�i�R�[���J�Z�[���͋����B �X�\���������������̂́A���\�����̌��I�ȓX�����Ԃ̂ŁA�ǂ����ő������闦�����|�I�ɍ��������B �����ɂ̓}�����o������R���g���o�X������A�[���n�C�U�[���R���O���̔��X������B �Ԃ�茩�ĉ�����ŏo�����Ă��A��������w�����Ă��܂��ꏊ�A�ł��������B �x���A�o�C�N�ł̂�т�o�������l�́A���������ꏊ�ɁA��͓S��999�̂ǂ����̉w�̂��Ƃ����i�ɂЂ����爠�R�Ƃ��邵���Ȃ������B �S�[�X�g�^�E���\�\�ǂ̓X�����ׂăV���b�^�[������A���̗l�q������������Ƃ���݂Ȃ����ǂ��ł���B ���s���l������ɂ͂��邪�A�ǂ̊���I���̓��ɂ��܂�ɗn������ł��āA�����Ă���X�`�[����ɂ��������Ȃ��B �f��̃V�[���ɕ��ꍞ�悤�ȋC�����ŁA���炭�͔߂��݂�c�O�������v�������ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ������B �قƂ�ǂ̓X��̒��莆��n�}�Ɉړ]�悪������Ă���̂��A���߂Ă��̋~���ł���B ���������d�v�ȏ����A�^�C�ł͋ɒ[�ɓ����Ă��ɂ����B �C����蒼���Ēn�}��X�̗l�q�̎ʐ^���B���ĉ�����B ���ꂼ��̓X�́A�������������܂ł݂̍肵���̎p�̉�z�t�B�������b�V�����d�˂Ȃ���B ���̓��̂����ɁA�Ŋy��ɋ��������E�Z���E�~���[�W�J���̒n�}�𗊂�ɁA�`���I�v�����[����z���ĐV�X�܂Ɍ����������A�c�O�Ȃ���X���H���͎n�܂�������̂悤���B �J�X�\����ɂ��Ă��A�����ɂ�����ƈ��̐l�����́u�܂�������Ȃ��ˁ[�v�ƌ����Ă����B ���̓��̖�A�����E�Z���E�~���[�W�J���ƁA�X�e�B�b�N�̎�ނ����������C���^�[�~���[�W�b�N�̃t�F�C�X�u�b�N����₢���킹�����Ă݂��B �����A�ǂ���̓X������Ԏ�������A�^�C��IT�Љ�Ԃ�ɋ������B ���̋x���A�r���ŃX�R�[���ɑ����A�{�[�x�[�^���[�̋߂��ɂ���C���^�[�~���[�W�b�N�̈ړ]��Ń}���b�g�����B ���̎��̋x���͓��j�ŁA�ǂ�����c�Ƃ��Ă��Ȃ��̂�m���Ă��Ȃ���A�s���N���I���ʂɈڂ����E�H���E�i�R�[���J�Z�[���ň�Ԑl�C�������e�B�[���E�~���[�W�b�N�ƁA�����E�Z���̃��[���Œm�����X�N�T���b�g35�̑q�ɂɂ��o�C�N�ő����Ă݂��B ���������܂ŗ���Ƃ�������̂Ƃ���A�l�͂ƂĂ����a�ȓ��{�l�Ɖ����Ă���B ����͂��̓�_���J�X���Ă��鎞�Ԃɍs���Ă����B �����E�Z���q�ɂł͒��ɊɏՍ܂����������b�Y�ƁA�d���đ����i�C�����̃u���V�����B �r���A�E�H���E�B�G���E���C�t�߂Ɉڂ����^�C�����y��X�j���[�E�X�[�����[���̐V�X�u�x�[�E�q�[�v�E�^�C�v��T�������A������͂قƂ�lj��̏����Ȃ��菑���̒n�}����������ŁA���[�^�T�C�̌Z������ɐq�˂���x�ł͊ȒP�ɔ����ł��Ȃ������B �����A�ŏ��ɐq�˂��E�H���E�B�G���E���C�w�O�̃��[�^�T�C�̌Z����u�����ɕ`����Ă���̂͋��Ȃ̂��ȁH�v�Ƃ������t���q���g�ɂȂ�A2�{�ڂ̋��̋߂��ɑ��݂��Ă���̂��m�F�ł����i�[��5���X�������ŁA�����Ԃقǃf�B���C�j�B ����́A���߂ă��[�`���v�A�b�N�ʂ�𑖂��Ă݂��B �V�����čL���A�a���قƂ�ǂȂ����K�ȓ��������B �e�B�[���E�~���[�W�b�N�͈Е����X�Ƃ���4�K���Ăقǂ̐V�z�ɂȂ��Ă���A�����Ƒ���ۂށB �i�����X������̒m�������y���M���Ƃ��Ă̗͂��A�o���R�N�ő�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B ���̃o���R�N�ōł��r�����ƌ����Ă���W���Y�E�o���h���X���Ńf�����t�����Ă����̂����������A���T���j���A�[�����E�X�s�A�[�Y�i������3���قǑO��YouTube�Œm��������ŋ��k�̐��r�h���}�[�j�̃h�����E�N���j�b�N���G�J�}�C�ŊJ�����Ƃ�������X������ɋ����Ă�������̂ɂ��܂������������ɂȂ����B �����ł̓e�B���o���X�E�X�e�B�b�N�A�J�E�x���̃A�_�v�^�[�AXLR�i�L���m���j�P�[�u�������߂��B �X�e�B�b�N�ޕ����ƃ^�C�ő�̊y��X�X�����Ƃ����_�u���E�V���b�N����n�܂����y�퉮����́A�������x���̏��T���ɂȂ��Ă����B ����A�l�̓��R�[�f�B���O�ŃG���W�j�A����Ɂu�ŋ߁A���������y���D���Ȃ̂��y�킪�D���Ȃ̂�������Ȃ��Ȃ��Ă�����I�v�Ə�k���������A�G���W�j�A�����Ă��ꂽ�̂́A�ގ��g�A�l����������ł��邢���Ȋy��̎��^��ʔ��������Ă���Ă��邩�炾�Ǝv���Ă���B �o���R�N�ʼn��y�𑱂��Ă����̂́A���{�ł̑z���ȏ�ɓ�����A�����炱�����y��ʂ��Ă̐l�̂Ȃ���͉������B 9��11���i���j �p�[�J�b�V�����̓��R�[�f�B���O�ł��ɏd��B ���K���Ȃ��Ŋy��̓h�������܂߁A���Y�������ׂĂȂ̂ŁA���̊y��̎ז��ɂȂ����花���������肵�Ȃ��B ���Ƃ��Ɗw�����ォ��y��ł̓h��������Ԏ肪���Ă�������A���Y�������Ƃ����̂͏�肱�Ȃ��₷�����Ƃ��傫���B ���Ăɂ̓A�S�S��W�����E�u���b�N�Ȃǂ��C�P�x�Ŕ����Ă����B ���e���E���Y�����̂��̂ł��A�܂��A�����ƈ�������̂ɂł����p�������B ���ς�炸�̊y��M�A�Ȃ̂ł���B �Q�O�P�T�N 4�N�O�܂ŁA�l�͓�����I�ȉ��y���E�ł̉Y�����Y�������B �^�C�ɈڏZ���Ă�����K�X�^�W�I�ɓ��邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��������A����ɔ����ĉ��Ղ����߂�@����A1�N��1�x�̓��{�A�Ȃł����������}�X�^�[���ꂽ�����Ղ𐔖��A�Ƃ��������x�̂��̂������B ���̍��܂ł̖l�̔F���́u�|�s�����[���y��2000�N��ȍ~�傫�Ȓ�������邱�Ƃ����ł��Ȃ��Ȃ����v�ł������B �����A4th�V���O���̂��߂�1�ȁA�u�①�Ɂv�����������B ���̋Ȃ͖l���悤�₭�Y�����Y�𑲋Ƃ������Ƃ����������W�ł���B ����܂ł̓��L���e���܂߂āAFractal�Ɩ��Â���ꂽ�l�烆�j�b�g�̕ϑJ���A�Y���̌���ւ̕Y���ŊȒP�ɒ��߂Ă݂����B �܂��A�o���R�N�ŏ��߂Ẵ��R�[�f�B���O�o���ƂȂ���1st�V���O���u�T�J�i�v"Rainy, Cloudy"�́A�N���b�N�����Ƀ��R�[�f�B���O�����B �����90�N��̓��{�ŃA�}�`���A�����R�[�f�B���O��̌�����Ƃ��ɂ悭�p����ꂽ���@�������B �Z�ʂ̂Ȃ��v���C���[���N���b�N���Ȃ��烌�R�[�f�B���O����ƁA���X�ɂ��ă��Y���������B 10�N�ȏ�̃u�����N������l�ƁA���R�[�f�B���O�͏��߂Ăł��郁���o�[��A�Ɠ�l�����̃��R�[�f�B���O�́A90�N��ł����Ƃ���́u�f���E�e�[�v����v���x�̋C���������B ���������ʒu�Â����炢�ɂ��Ă����Ȃ��ƁA�l��͂��܂ł����Ă����R�[�f�B���O���I���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B 2nd�V���O���u���v�u�w��ɐ��E���n�܂�v�ł́A���Y���E�g���b�N��DAW�ŗp�ӂ�����A�V���Z�T�C�U�[�����̎������t�@�\���x�[�V�b�N�E�g���b�N�ɂ������ƂŁA�N���b�N�ɍ��킹��K�v�����o�Ă����B3rd�V���O��"Funk-168"�u�V�g�����������ꏊ�v�u�������v�ł͂���ɁA���H�[�J���ƃR�[���X�^���ȊO�͂��ׂ�DAW�ōs�������߁A���ׂĂ��O���b�h�Ɏx�z���ꂽ����ƂȂ����B �Ƃ��낪�A�l��͂����ŗ����~�܂炴��Ȃ��Ȃ����B A�̐g�����R�ɂȂ�Ȃ��v���C���F�[�g��������������A���͍ő�̏�Q�̓��R�[�f�B���O���̂��̂ɂ������B ����܂ŗ��p���Ă����X�^�W�I�ł́A�����̂������ɂȂ�Ȃ��ƋC�Â��Ă��܂������炾�B �ŏI�~�b�N�X�ł������܂���ԂŁA��ɒቹ�͒v���I�ɑ��Ȃ���B ������Ŕj���ׂ��A���g��������悤�ɂȂ����V�����{�i�I��DAW�Ń~�b�N�X�����݂��B ����ʼn��̕����͂悭�Ȃ������A�ቹ�̓X�^�W�I�ł̃~�b�N�X��肳��ɋ]���ɂȂ邱�ƂɂȂ����B �}�X�^�����O�Ɏ����ẮA�قƂ�ǒm�����Ȃ��B �C�Â��Ζl��͑��H�̐^���������ɘȂ�ł����B ���̂��ƁA�X�^�W�I���K����������́A�����������v���ǂ���ɉ��y�\�����ł���ꏊ�ɂȂ��Ă������B �K���Ȃ��ƂɁA�l��̓X�^�W�I���K���y�����Ďd���Ȃ����炢�ɂȂ��Ă䂭�B �O��̓��L�ɒԂ����Ƃ���A����܂ł̌o���ʼn��y�������R�ɂȂ������ƁA���ʼn�b���ł���悤�ɂȂ����̂͑傫�������B ����Ȃ�����AA�̒m�l�ł���M�^���X�g���烌�R�[�f�B���O�E�X�^�W�I���Љ�Ă�������B �v���E�f�r���[���Ă���o���h�̃����o�[����̏���Ɋ��ғx�������������A�C���[�W�ǂ���̃N�I���e�B�[�ł��邱�Ƃ������ɕ��������B ����́A�����Ƃ܂݂̕��R���\�[���̑傫��������A���b�N���G�t�F�N�^�[�̐�����������邱�Ƃ����A�����������������̂́A�g���b�N�ɘ^�����ꂽ�f�[�^���G�f�B�b�g���邻�̋Z�p�B ������Ƃ����^�C�~���O�≹���̕�A�G�t�F�N�g��~�L�V���O�ɑ���o�����X���o�́A�o���R�N�ł���܂Ŏg�p���Ă����X�^�W�I�̃����F���Ƃ͂܂�������r�ɂȂ�Ȃ��B DAW�Œ��ڑł�����L�[�{�[�h�ʼn��t������O���[���E�N���b�v��\������肵���f�[�^�Ɠ����悤�Ȋ��o�Ń��R�[�f�B���O�����g���b�N��ҏW�ł���Ƃ����̂́A�܂��ɖڂ���������B �����āA���ꂾ�����̍����X�^�W�I���g�p����ɂ������āA���������̉��t�͂��X�^�W�I���K�O�����������X�̂����ɏ����͒b�����Ă����̂�����t�����B �O���b�h�ɍ��킹�邱�Ƃɂ���āA�L�͂ȉ����G�f�B�b�g���\�ɂȂ������ƁA���ꂪ�l�̑�����2000�N�ȍ~�̉��y�̐i�����B �C���^�[�l�b�g�����Y�҂Ə���ҁE������Ɠǂݎ�������܂����킹�A�}���`���f�B�A������������悤�ɁA�|�s�����[���y���܂��A����܂Ń��X�i�[�ɂ����Ȃ蓾�Ȃ������w���g���b�N�E���C�J�[�ɉ�������ł����B �������ɍ��̃|�s�����[���y�͑傫�ȃ��[�������g����邱�Ƃ��ł��Ȃ��܂܂ł���B ����������̓��X�i�[�X�̎���ו�����A���y�ւ̐G����ɂ����Ă��\�l�\�F�ƂȂ����݂̂Ȃ炸�A��M�҂��������ɂł����M�҂ƂȂ邱�̎���̃A�N�e�B���Ȏp���ɂ��������낤�B �\�����L����Ƃ����Ӗ��ł́A����قǂ܂łɊJ���ꂽ������܂��Ȃ��B ���{�邩��A���Ă�����ԂŎn�܂���4�N�Ԃ́A1990�N�ォ��̉��y�I�^�C���E�g���x���ł�����A����ȏ�Ȃ��G�L�T�C�e�B���O�ŋM�d�ȑ̌��ł���B �Q�O�P�S�N �X�^�W�I���K���y�����B ���́A���������C�������������̂́A���߂ăo���h���n�߂����ȗ��̂��Ƃł���B �O��V���O��3�ȁi"Funk-168"�u�V�g�����������ꏊ�v�u�������v�j��DTM�Ƃ��āA�\����ԂłقƂ�ǂ�����ō�����B Fractal�̑����ł���A�������Ȃ��������������ƂƁA�ȑO���班������DAW�𗝉����n�߂Ă����Ƃ����킳�����`�ł̂��Ƃ������B �܂����߂Ă̂��Ƃ������̂ŁA�l�X�Ȗ��_������Ă��邪�A�����Ȃ�̎艞�����܂�������ꂽ�B �|�s�����[���y�̓e�N�m���W�[�̐i���Ɛ��Ă��藣���Ȃ����ڂȊW������A�V�����@�ށE�������y�ɗ^����C���X�s���[�V�����͂Ƃ�ł��Ȃ��傫���B �����āA����PC���Ƀ~�j���Ղ������Ă��炵�炭�́A�u��������������R�[�f�B���O�ɂȂ�I�v�Ǝ�Ɋ��������Ă����B �����A��͂�DAW�̎����Ƃ͌ǓƂȂ��̂ł���B ���ꂾ���������Ƒ����ĉ��y���������邱�Ƃ́A���̖l�ɂ͂ł������ɂȂ��Ƃ������Ƃ����������B ���傤�ǃV���O���Ȃ��܂Ƃ߂����ɁAA�̓s�������悤�ɂȂ�A�X�^�W�I���K���ĊJ���ꂽ�B ���̐���ڂ����肩��A��l�ŗ��K�X�^�W�I�̋��������ɓf���o���Ă�����̂��A����܂łƂ͈���Ă��邱�ƂɁA���݂��͂�����C�Â����B �Z�ʂ̂Ȃ��l��ɂ́A����܂Łu�����ɋȂ������Ƃ����邩�v���B��̃|�C���g���������A���̂Ƃ���̖l��́A���ɂ͏o���Ȃ��Ă��u�����ɉ��y���y���ނ��v���ɂ��Ă���̂���Ɏ��悤�ɂ킩��B ������m���Ō�荇���n�Ƃ�������B ����������K�Ђ��̓��X���n�܂����B ���͂̂قǂ͂܂��܂������A�r�O���ق�̏������サ�Ă��ꂪ�\�ɂȂ����Ƃ������Ƃ�����B ���ǁA������傫�������̂́A�`���ɏ������O��V���O���B DTM�̐����́A���肪�l�Ԃł͂Ȃ��̂ŁA�C�ɓ���܂ʼn��x�������Đ��E�^�����邱�Ƃ��ł������ƁB �������ŁA����3�Ȃɂ��Ă͂ǂ�ȃR�[�h���g���Ă���̂��ɔ���ꂸ�ɁA���������ʼn����d�˂Ă������ƂɏI�n�ł����B ���̃��U�C�N�I�ȉ��y���삩����C���X�p�C�A�͑傫�������B ����܂ł̃X�^�W�I���K�Ƃ����A����Y�����O���Ȃ�����S�z���Ȃ�����K���Ă������A���͉����o�����Ɓ�������\�����邱�ƁA�Ƃ����ӎ��ŗ��K��2���Ԃi���Ă���B ����Ȃ킯�ŁA���̃V���O���ɂ����҂��������A�ƌ����A���炭�y�����Ċy�����Ă��������Ȃ��X�^�W�I���K�ɂǂ��Ղ�ɂȂ肻���ȍ������̍��ł��B 4��5���i�y�j �M�y���������Ȃ��~���[�W�V�����������Ȃ��Ă���B ����͗���Ԃ��A1990�N�゠���肩��A�M�y�͓Ǝ��̈�背���F���ɒB���Ă����ؖ��ł�����B ���{�̎Y�ƑS�̂������ł������悤�ɁA�u�ǂ����A�ǂ��z���v�̊|�����́A���y�̐��E�ɂ��������B �����ɂ́u�ǂ��z���v�Ƃ��������A�m�y�͓��ۂ̑Ώۂ��������A���ꂾ����1990�N��ȍ~�A���g���m�y�ɂ��܂莨�������Ȃ��Ȃ��Ă��邱�̌���͋������B ����������ɂ��Ă�����Ȃ̂́A�M�y�����[���h�E�����F���̃N�I���e�B�[�ɓ��B�������ʁA�m�y���K�v�̂Ȃ��Ȃ������X�i�[�������M�y�Ɂu�����Ă�v���ʂƂȂ������Ƃł��낤�B �������ɁA�m�y���ǂ�ǂ�喡�ɂȂ��Ă����̂Ƃ͐����ɁA�M�y�̓R�[�h�i�s�ɂ��Ă����Y���ɂ��Ă��A�����W�ɂ��Ă��A���{�l�̊������y���Ƃ���ɂ���������L�����A�@�ׂȊ��������̂ɂ��Ă���B �����A�o�����Ȃ�ɉ؊X�ł͂Ȃ��ߏ��E���s�Ȃ�C�O�ł͂Ȃ������E��ނȂ�V�����l���ł͂Ȃ�����m������C���i�[�E�T�[�N���̃����o�[�Ƃ����}���ŕ��Ă���邱�̎���ɁA�M�y���������u�����Ȃ������́A�����ۂ�͂܂荞��ł��܂��Ă���悤�Ɍ�����B �C���^�[�l�b�g�ł�SNS���u���E���ƂȂ���v��������ɍL�����̂Ƃ͐����ɁA�A�W�A����"LINE"�͓d�b�ԍ���m���Ă��郁���o�[���m�̃N���[�Y�ȊW�ɃX�|�b�g�ĂĈꐢ���r���Ă���B �����āA���y�ƊE���������N�Ԃ�CD����グ��L�����AYou Tube�Ȃǂ̑䓪�ʼn��������ƈ��������Ɏ�ɓ����Ƃ����s�ׂ��̂��̂����n�߂Ă��錻�݁A���y�͏��X�Ɏ���������o�����p�g�����`���̈ʒu�Â��Ɉڍs���悤�Ƃ��Ă���B �~���[�W�V������p�g�������n�����̎��������߂悤�Ƃ������Ȃ�����o�����ł���A���ẴN���V�b�N��ȉƂ���������ɖ����c���悤�ɁA�L�������킹�ʍ�i���a�����Ă��邾�낤���A�u�M�y���������Ȃ��v�~���[�W�V�����Ƃ��̃t�@�������̊W���㐢�ɉe����^����悤�Ȃ��̂ݏo�����Ƃ��ł��邩�ǂ����́A�r���^��ł���B �u�̂͐��ɂ�A���͉̂ɂ��v�B 1990�N��܂ł́A���y���Y�Ɖ����悤�Ƃ���ƊE�Ƃ̌����₷���A������₷���Η��������āA���̋��ԂɐF�Ƃ�ǂ�̉Ԃ��炢���B 2000�N�ȍ~�A���̉��y�ƊE���̂�IT���̔g�ɂ����ۂ���܂�A���̂��܂�ɖڂ܂��邵���X�s�[�f�B�[�ɉ߂���IT�E�Ɠ����悤�ɁA���E�̊e��Y�Ǝ��̂��ȑO���͂邩�ɒZ���I�Ȕ���グ�����Ƃ��m�ۂ��Ȃ��ƁA�����ɑ傫�Ȋ�Ƃł����Ă��悪�Ȃ��Ƃ��������������ɏo�Ă��Ă��܂��悤�ɂȂ�A������y�Y�Ƃ������Ȃ����B �Ȃ̃N�I���e�B�[�⊴���ł͂Ȃ��A�����̃`�P�b�g�����߂�A�C�h���E�t�@��������CD�����܂��Ƃ��Ĉ����ASNS��u���O�ł̂Ђ�����Ȃ��������݂���`�Ƃ��Ċm�����A���݉Ԑ���ł���A�C�h�������͎��ہA����Ƃ����ɂ͂��܂�ɃT�[���B�X�Ƃł��邱�Ƃ����o�����������݂ɂȂ��Ă���B IT���ɂ��Ă��A�A�C�h���̔��M�����ɂ��Ă��A����͂ǂ�ǂ�l����ʉ��E�u�≻�̕����ւƉ��������Ă���B ����͂܂��A�l��̑������ʐ��E�u�����S�ŋ��߂Ă���؍����낤�B ����A�l�炪�ł�����ׂ��Ώۂ́A����Ȏ��{��`���E�ł�������~���ƍَ҂ł��Ȃ��B �����ۂ�������ǂ����������̂Ȃ��������g�Ȃ̂��B ���y�͂�͂肱�̂��т��A�����f���o�����ł���悤���B �|�s�����[�E�~���[�W�b�N�������Ă��Ă��܂��Ăǂ�����̂��A�Ɩ₢�����B �������A���̓����͑��ς�炸���ɐ�����Ă���B ���߂āA�l�͖l�̉̂��̂����Ǝv���B ���͂������ꂾ���ł���B �Q�O�P�R�N �����鍑���u�������v���ċC�Â����B �������������\�\�\�ɂ߂��o���h�́A�Ō�ɂ͂悭�����ꏊ�ɏo�Ă���B Beatles��"Across the Universe" Beach Boys��"Busy Doin' Nothin'" Sly & the Family Stone��"Family Affair" �͂��҂�����ǂ́u����Ȃ�A�����J�E����Ȃ�j�b�|���v ���j�R�[���́u�f���炵�����X�v �����āA�����鍑�́u�������v �V���v���ł��Ĕ����ȉA�e�̔������A�h�炬�̂���Ȑ��E�B �l�������A����Ȑ��E��`���Ă݂����B 9��12���i�j ���y�������Ă���\���̈�ɁA�������X�s�[�h������B �e���r����ƒ�̌�y�̉�����PC��o�C���ɖ����n�����錻�݂ł͂��邪�A����ł͂����������@���p���đ����̐l���������Ă��邩�Ƃ����ƁA���[����SNS�Ȃǂŕ����𑗂肠������A�l�b�g�L���ŏ���ǂ�A���y������A�J�����B�e������AYou Tube�œ����������Ƃ����A���ꂼ�ꕶ���E���y�E�ԑg�ϏܓI�Ȃ��̂ł����āA���������Ӗ��ł͎莆�����������āA�V����ǂ�ŁA�X�e���I�R���|�ʼn��y���āA�e���r��f������Ă���̂Ɠ����^�C�v�̂��Ƃ�����Ă���B �����A���̔w�i�ɂ�����ʂƃX�s�[�h���A�ȑO�Ƃ͈��|�I�ɈႤ�̂ł���B �l�b�g��ɂ��锜��ȗʂ̏���p���āA����߂ĕ֗����X�s�[�f�B�[�ɁA�I�Ȋ������ł��Ă��܂��B �����ɁA�l�X���Ǘ����Ă����v���Z�X��ǂݎ�邱�Ƃ͗e�Ղ��낤�B ���āA���y���Ȃ����̂悤�Ȍ��݂̎Љ�ɂ����Ă����Ě������̂��B ���̓����̈���A���ʂƃX�s�[�h�ɂ���ƁA�l�͌���B �܂��A����͌��݂ɂ����Ă��ł����ʂ��������f�B�A�ł���B ���̂��Ƃ́A�����PC�Ȃǂɕۑ������Ƃ��̃t�@�C���e�ʂ̑傫�����炷�łɕ����邱�Ƃ����A�o�ꂷ����̂������A�����M���A���y�������ɗ��݁A�K�v�Ƃ���Ε������ǂ�ǂ�o�ꂷ��B �������A�����̏����鑬���ɂ��Ă������߁A�l�X�͌܊��������邱�ƂɂȂ낤�B ����Ɣ��ɁA�A�[�g�̊ӏ܂́A���Ȃ莩�R�ɂ��̍�i�ɑΛ����鎞�Ԃ����Ȍ��肷�邱�Ƃ��ł��āA���������̍�i���̂͐��ꗬ���I�ȏ��}�V���K���A�˂����Ȃ��B �����ɂ͈�̍�i�������݂����A���̍�i���牽����ǂݎ�鎩���̑ԓx����ł́A�����ȑ��݂��炽���̃S�~�ɂ܂Ō��Ȃ����Ƃ��\�ł���B ���y�͂����炭�A���̂��傤�ǐ^�̍������ɗ����Ă���B ������O�̘b������A���y�͒��o�ɂ���Đ��藧���Ă���B ���擯�l�Ɉ��̑��x�Ń��Y�����A�����f�B�[���A�̎����E�����ꂼ����Ƃ��Ĕ����Ă��邪�A���ׂĂ͎���ʂ��ē͂�����B ����������ʂ����Ȃ��̂��B �����āA���̏��̌��@�߂悤�ƁA���g���F�Â��������悤�Ƃ���B ���傤�Ǐ����̓ǎ҂��A�o��l���╗�i�̒��Ɏv���`���悤�ɁB ���̓K�x�ȑn�������A���y�̑�햡�̈�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂��B �����ɂ͑��̌���I�ȕt�����l������B ���ʂ������邾���ɁA���y�͑����̂��̂����v���Ȃ��̂��B �e�탁�f�B�A�ł́A��̐������ƂɁA���̃��b�Z�[�W�����D���≿�l����X�ɕ��f�������������A���ې����������̂قǁA���x�͎�̊������ӎ��I�ɑ傫���J���Ȃ���Ύ��̂�����Ȃ��Ă��܂��B �������A���y�͂���Ӗ��ŁA��������Ă��邾���ł����̂��B ������b�Z�[�W�����������y��i������B �ł��A�u���b�Z�[�W�͎����Ƃ͍���Ȃ�����ǁA�A�����W�͂����v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��ȒP�Ɍ����郁�f�B�A�����y�Ȃ̂��B �Ⴆ�A�u�X�g�[���[�͂��܈�����ǁA�摜�������Ԃ�������v�f�悾�Ƃ��A�u��i�̈Ӗ�����Ƃ���͂ǂ����ł��������ǁA���̂�����ȁu���w��i���Ƃ��A�u�ߑ��͋C�ɐH��Ȃ����ǁA���`�ɂ͐S��D����v�H�|�i�ȂǂƂ������b�ɂƂ�Ə�����Ȃ����Ƃ�����A���y�̓��ꐫ��������B ���ې��̍������y�����Ă���B ����ɂ��Ă��A���y�̏ꍇ�́u���������Ă��ċC�����������v�Ƃ������̈�_�����Ő��藧���Ă��܂��B �܂��A�X�s�[�h���Ƃ�������́A����ɂ����Ă͔��ɏd�v�ł���B ���ɁA�����̓���ɔ�ׂāA�|�s�����[���y�͍�i�P�ʂ̎��Ԃ��Z���B ����͑��Z�Ȍ���̓s�s�����҂ɂ͑傫�ȃ����b�g�ł���B �܂��A���o�ȊO�̊��o��K�v�Ƃ��Ȃ����߁A������Ԃɉ��y���������ނ��Ƃ͎��ɗe�Ղł���B �����d�ԂŃX�}�z�̉�ʂߑ�����͓̂���ꍇ�����낤���A���^�������y���̂ɂ́A���炩���߃C�A�t�H�����w�b�h�t�H�������Ă����āA�v���C�E�{�^�������������������̘b�ł��邵�A�Ǝ������Ȃ���ł��A����Ŏd�����Ȃ���ł��A���y���Ȃ��牽���̍�Ƃ����邱�Ƃ��܂��y�����B ���ɁA����͉����̎h������Ƀ|�C���g�̂��鎞��ł���B �W�F�b�g�R�[�X�^�[����]���邭�炢�ł͂��͂≽�̋�����������Ȃ��̂ŁA�X�^���f�B���O�E�R�[�X�^�[�ɂȂ�����A���A���ȋ����͌^��3�c������������Ԃ𑖂蔲������A�V�[�g���E���痬��鉹�y���Ȃ����ꂽ�肷��R�[�X�^�[�����X�ɓo�ꂷ��B �u�����ƁA�����Ɓv������̕W��ł���A�o�ώЉ���x���錴���͂��B �|�s�����[���y�͎��ہA���̃j�[�Y���������i����葱���Ă����B �G���L�E�M�^�[�̉���c�܂�����A�V���Z�T�C�U�[�ʼn��̉\�����L����������Ă������A�e��G�t�F�N�^�[�≹�����H�Ȃǂ̋Z�p�v�V�ɂ�鋻�������ݏo���Ă������A���̈���ŁA���ۂɂ́i���m���y�́j���y���_�I�ɂ͂��͂�t�����e�B�A�͏��ł��Ă����B �����f�B�[�Ƙa���̊W�͊J����������A�t���[�E�W���Y�⑦�����������ꂽ���y�ȂǂɎ����āA���̐�ɉ\����T����́A���m���y�̊�b�����̂��A�č\�z���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���܂ŗ��Ă���B ����������ɗ������Ƃ��ł����v���̈�����F��y��̊J���������̂����A����������Y���̒Nj��Ƃ����H���������B 2�r�[�g����32�r�[�g�܂ł̃��Y���ו����͂��̍ł��������₷����ł���B ����������ȊO�ɂ��A�u�n�l�����Y���v�A�������V���b�t���̂悤��4��������3��������悤�ȒP���Ȋ���Z�ł͂Ȃ��h�炬�̂��郊�Y���ݏo������A���̔��ɂ܂������Ԃ�Ȃ��@�B�I�Ȕ����t���[�Y�ɉ��������o������A�������������郌�Q�G�ɐV�������g�����o������A���Y�������ŋȂ��\�����Ă��܂��Ƃ���t�@���N��q�b�v�E�z�b�v���o�ꂵ���肵�Ă����B �V�������Y���͐V�����X�s�[�h������ɂ����炵�A�h����^�����B ���y�ɂ́A�e���݂₷���炪����Ȃ���A�l�X���C�}�W�l�C�e�B���ɂ����p������B �����ӂƎv����������SNS�ɂ�����Ȃ����Ƃ��Ԃ₭�y���Ƃ͕ʎ�́A�������l�ЂƂ�̒��ɔ��������蒾�������肷��悤�ɁA���Ղɑ��l�ƕ������������Ƃ̂ł��Ȃ��v���������炷�B ������������v���͏�����ǂ�ł��A�f������Ă��A���p��i���ӏ܂��Ă��N���邱�Ƃ����A���ʂƃX�s�[�h�Ƃ�����̑��ʂɂ���āA���y�̓n���f�B�[�Ȃ̂ɐ[�݂ƍL���̂���}�̑��蓾�Ă���B ���ꂱ��������Љ�ɂ܂����y����ՓI�Ȏx�����������Ă��闝�R�̈���Ǝv���̂ł���B 5��16���i�j ����t���̃C���^�r���[�W�u�������邽�߂ɖ����l�͖ڊo�߂�̂ł��v��ǂ�ŋC�Â������Ƃ�����B �ǎ҂͍�i�ɁA�ŏI�I�ɂ͎����ɂƂ��Ėʔ����������ǂ�������ɔ��������B ��������ۂ̂Ƃ���A�A�}�]���̃������[�Ȃǂ���l�炪���҂���̂́A�����܂ł��̃R�[�i�[�̑_���ǂ���A�ʔ����ǂ߂����ȍ�i���ǂ����̃��T�[�`�ł����āA�{�i�I�Ș_�]�ł͂Ȃ��B �ǎ҂͕s���葽���̐l�ԂȂ̂ŁA�ʔ����������ǂ����̊�͓��R�獷���ʂŁA�����łȂ���ΎЉ�I�ɕs���N�ɂ܂�Ȃ��B ���̂��̂̊�≿�l�ς��قȂ邩�炱���A�X�l�͂��ꂼ��ɈӖ������Ƃ����̂����݂̖���Љ�̑O��ł���B ����A�����̍�Ƃ͎��g�̎����Ǝ����w���ɁA��i�ݏo���B �����ƂƂ́A���ɌǓƂȐE�Ƃł���B �����̓����ɂ��鐢�E����l�ŋ��ݏo���A��l�Ō��������Ă䂭�B ���肬��̕��Ɏ�����ǂ����ނ��Ƃ��ł��Ȃ������܂łł���B �������A�ʂ̈Ӗ��ŏ����Ƃ͓ǎ҂Ƃ̋��ʊ�Ղ�M���邱�Ƃ̂ł��閲�z�Ƃł�����B �������@�艺���邾���@�艺���ĕ�������b���A�ǂ����̒N���ɓ`���A�������邱�Ƃ��ł���ƐM����Ȃ���A��ƂȂǓ��ꑱ�����͂��Ȃ����낤�B �������A����邱�Ƃ́A��Ǝ��g�̎肾���ɂ����̂ł͂Ȃ��B ����t���͂�����u�N���Ȃ���ɂ��Ė����݂邱�Ɓv���ƕ\�����Ă��邪�A�l���ȑO�����������Ă����Ƃ��ɁA�u���ꂪ�V����~���Ă��āA�����͂����M�L����@�B�̂悤���v�Ɗ����鎞�Ԃ����x�����@��Ɍb�܂ꂽ�B ����͂�����x�̂Ƃ���܂Ői�߂A���Ƃ͂���܂ŕ~���ꂽ���[���̉������������̐��i�͂ő���n�߂�B �������A����_�ł��������Ԃ��āA�ǂ���ɑ���悢�̂������肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��u�Ԃ�����������B �\�����Â�������v�s���Ă�������ŁA���Ƃʼn��x��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂����R�ł���B �ɂ�������炸�A���͂͐�������Ώ����قǎ��g���K�肵�A�u���̐揑�����ׂ����E�v�ւƂ����Ȃ��B �r�����珑���Ȃ��Ȃ�����i�Ƃ́A����܂łɕ��͉����ꂽ���E�̐�Ƀ��[�����~����Ă��Ȃ�����ł͂Ȃ��A���͎��̂����i�͂ƂȂ�M�������Ă��܂�����ł��Ă��܂����̂ł���B �Z�ҏW�uTV�s�[�v���v���璷�ҁu�˂��܂����N���j�N���v�\���邠����܂ŁA�l�͑���t���̍�i�����܂�]�����Ă��Ȃ������B ���ɂȂ�킩��B ����́A�A�}�]���E�������[�̂悤�ɍD���Ƃ����P���Șb�Ō����āA���قǖʔ����Ƃ͊������Ȃ��������炾�B �������A�����́u����t�������Ƃ����v�Ƃ����A����ȃX�e���^�C�v�Ȍ����ł��������ł��Ă��Ȃ������B ����t���͍��ł��i���𐋂��Ă���B �N��ƂƂ��ɋZ�p��~���A�l���`�ʂ�e�[�}�̐ݒ�ɑ��ʂ��������A�ȑO�ɂ͂Ȃ��������͂𑶕��ɔ������Ă���B ��i��P�i�Ƃ��Ď��o���Ė��킢�A�߂��߂����D�荇��Ȃ��Ɗ������肷��̂́A�ǎ҂Ƃ��Ă܂������������ڂ������낤�B �����A�R�[�X�����̈�i���������o���ĉ]�X��������A�S�̗̂���ő����ė����l�̈ӎu�������邱�Ƃ��ł���A�����ƐV�������o�̐��E�ւƉH�������Ƃ��ł���͂����B �����Ƃ͓ǎ҂������鑕�u�ł��Ȃ���A���Ԃ�J���͂�蔄�肷��T�����[�}���ł��Ȃ��B �܂�Ƃ���A����͍�Ƃ��ڊo�߂Ȃ���ɖ���������Ƃ���܂Ŏ������@�艺���A�V���炠�܂˂��~�蒍�����̂��������߂���i�Ȃ̂ł���B ���āA������ȍ��ɒu�������Ă݂悤�B �|�s�����[���y�̓��R�[�h��̔�����V�X�e�������グ���Ƃ�����A����̃p�g�����ł͂Ȃ��A�s���葽���̃��X�i�[�ɐ��Ŏx������V�X�e�����l�������B ����̃p�g�����Ƃ̏o��͉^�����v��ق��Ȃ����A���ʂɏ��A���f�B�A�ɏ��A�R�}�[�V�����Y���ɏ�������y�́A���L�͂̐l�X�̎��ɓ͂��悤�ɂȂ�A���ɉH�����\�������|�I�ɍL�������B ���̈���A���y�Ƃƃp�g�����͌����̐l�ԊW�Ō���Ă��邪�A���X�i�[�͂قƂ�NJy�Ȃ�ʂ��Ă������y�ƂƂ̐ړ_�������Ȃ��̂ŁA���E�͂�������ƍs����B ������A�~���[�W�V���������R�[�h��Ђ��A���������̐����c��������Ĕ������̂���悤�Ƃ���B ���y����A���ɘ^���ɂ͂�����������̂ŁA���̎�������ւ̐ӔC�ӎ����w�������ƂɂȂ邾�낤�B �������A��ƂƂ��Ă̐��_���̔������͕̂����������B ���傤�ǁA�������̐���������C�g�E�m���F���Ǝ����悤�Ȃ��̂ł���B ����邽�߂ɏ����ꂽ���̂́A�s���葽���̒��ł��ł��邾�������̐l�X�ɍD�]����悤�ȍH�v�ɖ����Ă���̂ŁA�������傫���Ȃ�\�����������A�u�D�����v�Ƃ����Ă����l�𑽐��y�o�����邱�Ƃ��ł��邾�낤�B �ł��A����̓��X�i�[�������邽�߂̑��u�ɂȂ肫���āA���Ԃ�J���͂�蔄�肵���T�����[�}���d�����琶�܂�Ă�����̂ŁA�ǂ����������u���i�v�ł���B �A���f�B�E�E�H�[�z����}���Z���E�f���V�����̓o���҂܂ł��Ȃ��A��ʐ��Y�̃|�b�v�E�J���`���[�ɃA�[�g�����o���Ƃ������z�͂��ꎩ�̑f���炵�����̂����A�����A�l��͂��������o�ϕ����̂����炷��̃l�I���T�C����������Ƃ������Ă����̂͊m�����B �������A����͕\���҂Ɗӏ҂́u�����v�̐܂荇�����n�_�̙��ߓI�ȋP���ł���A���o�����Ƃ��̂��̂ɉ��l���u����Ă���B ���̕ϓN���Ȃ����s�̂̂ЂƂɎv���������������N�E�H���e�B�[�����o�����肷��̂́A���X�i�[���́u�����v�ɂ����̂ł����āA�N���G�C�^�[���̎�ɂ͂Ȃ��B ���̂����Ƃ��A�\���҂͂܂������̕\�����������̂������Ă��Ȃ��ƂȂ�Ȃ��B ���̂��߂ɂ́A�����̒��ɂ�������ƍ������낵�Ă�����̂����ɂ߁A�������@�艺���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �����āA��x�`�𐮂����������̂������n�߂��M�𐄐i�͂Ƃ��āA���̐��E�̌��o�̂��߂ɃV���[�}���I�ȑ��݂ɂȂ�K�v������B �Z�p���g�ɂ��A�\���͂��g�傷�邱�Ƃ��ł���B ���ꂪ����邩����Ȃ����A�]������邩����Ȃ����́A�m���Ɉ��C���F���g���B ����ł��Ȃ��A�������l�Ԃ�������낤�Ƃ���ł��d�v�ȃ|�C���g�͂����ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���B �l�l�����ꂼ��̊��z�ō�i�𖡂키���ŁA�u���������v�Ǝv���l���ǂꂾ�����������邱�Ƃ��ł��邩�B ��������A�������ǂꂾ���[���������邩�A�ł���B ����t���͂��̃C���^�����[�W�Łu����������Ȃ���A�����͂��̕���̍ŏ��̓ǎ҂ł�����v�Ɣ������Ă���B �����Ƃ��Ǐ���������Ƃ��납��X�^�[�g����悤�ɁA�~���[�W�V���������y���Â蒮�����Ƃ��琶�܂�Ă���B ��������������͂≹�y���A�i���V�V�Y���������������Ƃ���ł��D��œǂ蒮�����肵�����Ǝv����Ƃ���ɒB����܂Ńu���b�V���E�A�b�v����Ƃ���ɁA��i�̎��͂��̑���������������B ���N��12���A�O��̓��L�ŁA���X�i�[��z�肵���ȍ��ɂ��čl���Ă������Ƃ����������B ����A�l�͂��̋C�����ɂ����Ɩ��m�ȗ��R�����o�����Ƃ��ł����B ��Ɛ������X�i�[�Ƃ��Ă̎����̐�ɁA������l�͕��͂������A�Ȃ�����Ă��������B �Q�O�P�Q�N �܂��V���ȃV���O���Ȃ̃��R�[�f�B���O�������Ă���B ���N9��������X�^�[�g���āA����͂���1�Ȃ����Ői�߂Ă���Ƃ��낾�B ����́A�O��i6��27���j�ɓ������������Ƃ��̂悤�ȋC���ɂ͂Ȃ��Ȃ��Ȃ�Ȃ������B �܂��A�����ɉƑ����ł��āA�ނ̐�������ς����B �����āA����ō�����x�[�X�ƂȂ�V�[�P���X�E�g���b�N���A���R�[�f�B���O�����ɃX�^�W�I�œǂݎ�ꂸ�B ����ɂ��̌���A�X�^�W�I�̗\���Ɏ��ɂ��������������A�ԉ��т����^�����ƂȂ����B �����ĂƂ��Ƃ��A�l���g�A���R�[�f�B���O�ɑ���ӗ~���������ቺ�B ���̌��������낢��ƍl�������˂Ȃ���A�d�����������������Əグ�Ę^���ɗՂޓ��X���������B �l�����̓v���ł͂Ȃ��̂ŁA�l���������y�I�ɍs���l�����Ƃ���ŁA���f��������悤�Ȑl���A�܂����݂��Ȃ����낤�B ����ł��l�����R�[�f�B���O�𑱂����̂́A�ЂƂ��ɍ��̎������ǂ��܂ł̂��Ƃ�����̂������͂������������炾�B �l�ɂ͂��łɒ������y�I�u�����N������B ����10�N�قǂ̊Ԃɉ��y�I�ȉ\����ǂ������Ă����Ȃ��ƁA����10�N�ɂ͂������炾���������Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ă��邩������Ȃ��B �������A����ȂƂ��ɂ͂���Ȃ�̉��y��������艉�t�����肷�邱�Ƃ��ł��邾�낤�B �����A�܂��_��ɕ������z���ł��鎞���ɂ��ꂾ���̗͂�{���Ă����Ȃ���A10�N��ɂ͊y�ȍ쐬�Ɋy���݂���o���邱�Ƃ��ł��Ȃ���������Ȃ��B ����ȏł肪�A�l��˂��������Ă����B �����āA����̃��R�[�f�B���O�ŁA�Ƃ��Ƃ��l���g���l���������o���������Ă�悤�ɂȂ����B ���R�[�f�B���O���e���[�����Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B ����ɂ������āA�������g���l���߂Ċ�����̂́A�����������ɗl�X�ȕ����Ɏ����Ă����̂��Ƃ������Ƃ��B ���R�[�f�B���O�̃X�^�[�g������A�l��͂��̋ȂɁu���������̍ō�����ɂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��v�Ƃ����A���l���猩��i����܂j���܂����������������B ������A���ɗ͂�����܂����Ă����B ���̌�A�l�����̓��R�[�f�B���O���e�ɖ���s�������悤�ɂȂ����B ���t�ւ̕s���A�����ւ̕s���A�~�b�N�X�ւ̕s���A�`�ɂȂ�Ȃ�������Ȃ��c�c�B ���ׂẮu���̋Ȃ𖼋Ȃɂ������v�Ƃ����v������̂��Ƃł���B ���̃v���b�V���[�́A�����ł��ӎ��ł��Ă����B �����A����𐳖ʓ˔j�ŏ��z���邱�Ƃ������ɂȂ������B �g���l������ꂽ�̂́A����Ƃ��̎��ꎩ���ɋC�Â����Ƃ��ł������炾�B ���j�b�g��HP�ɂ��f�����Ƃ���A�l��̗B��̃��b�g�[�́u���������������������̂��`�ɂ��邱�Ɓv�B �����ɂ͓�̈Ӗ������߂Ă���B ��́A�����������S�̒ꂩ��悢�Ǝv������̂ɂ́A�ǂ����̒N���ɂ��͂��\��������̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƁB �Z�ʂ�Z���X���l�����ɂ��قǔ�����Ă��Ȃ��ɂ��Ă��A�v���ƃA�}�`���A�ł͐�q�̂悤�ɗ��ꂪ�Ⴄ�B �l��̓v����ڎw������������Ƃ��ăA�}�`���A���������Ă���̂ł͂Ȃ��B �A�}�`���A�Ƃ��čD���Ȃ��Ƃ��D���Ȃ悤�ɕ\���ł��邱�Ƃ��������āA�Ȃ������ꂪ���ԂɊׂ�Ȃ��悤�ɊJ���ꂽ���̂ł�������ƍl���Ă���B �����ɂ�������ā\�\�܂�A���������̔��ӎ��̐[���Ƃ���Ɏ��L�����Ƃ������ā\�\�Ȃݏo�����Ƃ��ł���A�����ƒN���C�ɓ����Ă����l������͂����ƁA����Ȃӂ��Ɏv���̂��B ������́A���X�i�[��z�肵���ȍ�������ɂ́A�l��͏C�s������Ȃ��̂��Ƃ������Ƃł���B ���Ƃ����K�c���S�����C�J�R���́A�O�ꂵ�����X�i�[�ւ̈ӎ������������F���ŏ����Ă���~���[�W�V�����ł��邱�Ƃ͂悭�m���Ă��邱�Ƃ����A����͌K�c���u�����d�ʁE���v�ƕ]���ꂽ���Ƃ�A���[�~�����u���̕����Ɋ����邽�߂ɐl�̏W�܂�ꏊ�łЂƂ�A���e�i�菄�点�Ă���v�Ƃ����G�s�\�[�h��������Ă���B ���������������ƁA�v���[���̗͂Ƃ������ƂɂȂ�B �Ɩ��Ɋ���Ȃ��V���Ј��������Ȃ蔲�Q�̃v���[����A������ɂ́A�{�l�������̓V�˂ł��邱�Ƃ������ƂȂ�B �l�����͂������A����ȑ傻�ꂽ�l�Ԃł͌����ĂȂ��B �ł́A�V���Ј��͂ǂ������Ƃ��납�犈��̎���������������̂��B �l�Ȃ�̗���Ȃ��ӌ������A�����̓������ӎ����āA������t�����p����V�[���������邱�ƂȂ̂ł͂Ȃ����B ���Ƃ��A�Ί炪���߂Ȃ��l�Ȃ�A���̏Ί�Ŗ��h��z�葱����B �b������̂����Ȑl�Ȃ�A����̌��t�ɐ^���Ɏ����X�������Ęb�������o���P��������B �܂�A�����̃p�[�\�i���e�B�[�ɑ����āA�����̑��������߂邱�Ƃ���n�߂�Ƃ������Ƃ��B �l��̓��X�i�[���ӎ������u���ȁv����낤�Ƃ������A����Ȃ��Ƃ������ɂ�10�N�����B �����ǂݑւ���A�l��́u���ȁv�����Ȃ������A�}�`���A�I�Ȕ��w�����R�ɒǂ����߂邱�Ƃ��ł���B �����āA�l�炪���ݏo�����Ƃ��Ă�����̂��u���ȁv�������Ƃ��Ă��A����Ȋy�Ȃ����łȂ����̂ɂł��邩�ǂ����́A�l�炪�ǂꂾ���l�玩�g�Ɍ������������Ƃ��ł��Ă��邩����ł���B ����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ���A���R�[�f�B���O�͉����ɓ��낤�Ƃ��Ă���B 6��27���i�j ���N�ɓ����Ĉȗ��A���̉��y���L�ł͎��g�̃o���R�N�ł̉��y�����ĊJ�̗l�q�Ƃ��̎v����k�R�ɒԂ��Ă����B �u�͂܂����v�Ƃ����̂͂܂���������������Ԃ��w���̂��낤�B ���R�[�f�B���O�Ƃ����I��_���ċ|�������A���Ƃ͖�̂悤�ɁA�����Ђ�����܂�������ڎw���ĂЂ����鎩���������B ��x����������ԂɂȂ�ƁAiPod�őI�Ȃ����Ȃ̑唼�͎��g�̃��R�[�f�B���O�Ȃ̃��t�E�~�b�N�X���Ԃ��`�F�b�N��ƂƉ����̂ŁA����ȊO�̋Ȃ��@��ɒ[�ɏ��Ȃ��Ȃ�B ����͕��͂��������Ƃɂ��Ă����l�ŁA��̒�����i�����������Ă���Ԃɂ́A���̍�Ƃ̖{��ϋɓI�Ɏ�Ɏ�낤�Ƃ͂Ȃ��Ȃ��v���Ȃ��B �V���O��CD��2�Ȃ̃��R�[�f�B���O�����ȍ~�A�͂��������悤�ɂȂ�������A���X�i�[�Ƃ��Ă̎������Ăъ���o�����B ���̃V���O��2�Ȃ͑ł����݂��x�[�X�ɂ������̂ɂ��悤�Ƃڂ���C���[�W���Ă������Ƃ���A���炭�n�E�X��q�b�v�z�b�v���ӎ����Ē����悤�ɂȂ��Ă���B �t�@���N�͑�D�������A�y���Ɍ������f�B�X�R�E�~���[�W�b�N�炭�h�����Ă����l�ɂƂ��āA�G���N�g���j�b�N�̌n���ɂ��鉹�y�Ƃ�YMO���璆�c���X�^�J�Ɏ���e�N�m�E�|�b�v�ł������ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B ���g�̊w������A���ɂ���̂��p���������Ǝv���Ă����u���[���E�r�[�g�v���n�E�X�ɕϑԂ��Ă������̂ł���A�{���ɉ��y�Ƃ͒�̐[�����̂ł���Ɗ�����B �N���u���y�����Ǝv���Ȃ��l�ɂƂ��Đ����ȂƂ���A�G���N�g���j�b�N�E�~���[�W�b�N�ɂ́A�璷�ɉ߂���Ɗ������镔�����Ȃ��ł͂Ȃ����A�ǎ��ȃG�b�Z���X�ɕ�܂ꂽ�P���������y�W�������ł��邱�Ƃ��A�����͗����ł����C�����ł���B �����ł悤�₭�C�Â����̂́ADragon Ash���Ȃ������I�Ȑl�C���Ă����̂��Ƃ������ƁB ����ɂ��Ă���n�E�X��q�b�v�z�b�v�̐��Ȃ̒��ɒu���ƁA�ނ�̉��͔�є����Ĉ�ۓI�ŁA�X�^�C���b�V���ŁA���{�I�ȏ��C���悳�Ɉ��Ă���̂��A���܂��玨�ɐV�N�ɔ�э���ł����̂��B �ނ炪�������������b�N�ɑ����鑶�݂��Ƙb�����Ƃ����̂́A�{���ɂ悭������B �q�b�v�z�b�v�̒��ł̔ނ�̈ʒu�Â��Ƃ����̂͂܂��悭�m��Ȃ����A���b�N�Ƃ����W������������I�ȉ��������͂�݂Ȃ��玩�R�Ȍċz�Ő�����������������̂ɂȂ�Ƃ������Ƃ��A�ނ�̋Ȃ͊m���Ɍ���Ă���B ���b�N�I�ȃX�s�[�h���ƃq�b�v�z�b�v�I�ȍ\�����X�������O�Ƃ������ҋ��ʂ̖��͂̒n�_�ŗZ�����Ă���AKj�̃��H�[�J�����A�q�b�v�z�b�v�Ƃ��Ă̒j�������Ə����t�@���𖣗����郍�b�N�̎��Â��Ƃ̒��ԓ_�ɗ����Ă���B �����A�����ň̂����Ȃ��Ƃ����킹�Ă��炦��Ȃ�A���łɖl�͔ނ�̋Ȃ̑�������A�����O�����悤�Ɋ����Ă���B ����A���ꂾ���ł͂Ȃ��A�G���N�g�j�b�N�E�~���[�W�b�N�S�ʂɂ��̌X��������B ����͂����炭�A�փ��B�[�E���[�e�[�V�����ɂ��߂��������ł��Ȃ���A���������Ɉڂ�������ł��Ȃ��B �l�ɂƂ��ăN���u�E�~���[�W�b�N�ɑ����鉹�y�́A���Ƃ��ƖO���₷���X���������Ă���̂��B �u��v�ɔ�����^�����邱�Ƃɂ���ē��������ÎA���X�Ƒ����O���[���ŗx��邱�Ƃ��N���u�̑�햡�Ȃ̂��낤���A����𗠕Ԃ��A�r�[�g�𒆐S�ɁA�\���p�^�[���������Y���ӂ��ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł�����B �r�[�`�E�{�[�C�Y��r�[�g���Y�̑g�ȓI�ȓW�J�Ń��Y�����ǂ�ǂ�ω����Ă����앗�Ɋ���e���݁A�h������x�[�X��S�����Ă����l�ɂƂ��āA�N���u�E�~���[�W�b�N�ɋψ�ȃr�[�g���̗p����Ă���Ȃ�A�����ƃ��X�i�[���y���܂��Ă���鏬�Z���ق������A�����łȂ���A�����ƈ��|�I�Ȋy�ȂƂ��Ă̖��͂������Ăق����B �������܂Ŗl���g�������Ă������b�N��|�b�v�X�ɂ��A�����͂���ł����Ƃ����قǓo�ꂵ�Ă���̂�����ǂ��A���S�Ȕ����ɂȂ�Ȃ��悤�ȑO�q�̏��Z�������Ă�����A�Ȃ̃T�C�Y�����X�i�[��O�������Ȃ������ɂ܂Ƃ܂��Ă�����A���|�I�Ȗ��ȂɂȂ��Ă��Ă�������S��͂܂ꂽ�肵�Ă����B ���ꂪ�؋��ɁA�����N���u�E�~���[�W�b�N�̔��e�ɂ����Ă��APizzicato Five�ɂ͔P��ɉ��x���X�炳��Ă����B �ق�̏�������ꖂ������炢�̌��݂̂Ƃ���܂ł̈ӌ��ŋ��k�����A�G���N�g�j�b�N�E�~���[�W�b�N�̑����͉��y�ⓩ����^���Ă͂������̂́A���X�i�[�Ƃ��ĉ��y�����ɂ͖������̍�i�ł���悤�Ȉ�ۂ�@���Ȃ��ł���i���̊��z�ƂāA�����o�Ă��ׂĂ��Ђ�����Ԃ��Ă��܂���ߐ��̂��̂�������Ȃ�����ǁj�B �����A����͖l���g�����ׂ����������͂����莦���Ă���Ă���悤�ɂ������n�߂Ă���B �����A�l�͎����������������y�������ō�邽�߂Ɋ����𑱂��Ă����B ���炭�̊ԕ��S��ԂɂȂ��Ă�������ǁA���m�ȕ��j�������Ă����悤���B ���̃V���O��2�Ȃ͑S�ґł����݂ōs�������Ƃ����͈̂ȑO����\�z���Ă������Ƃ��B �����A���̃W�������ɂ͂܂��ǂ��Ղ�łȂ����A�V�������_�������Ă���͂��Ȃ̂�����A�����Ă���������Ȃ����B �����������������̂����̒��ɁA���邢�͂ЂƂ�̒�����ɃN���X����u�Ԃ����߂āB
5��17���i�j 4��20���i���j 3��11���i���j �Ƃ��Ƃ��o���R�N�ŏ��߂ă��R�[�f�B���O��̌������B ��͂�A�܂��͈�l�ŃX�^�W�I���肵�ẴX�^�[�g�ƂȂ����B �����āA�܂��h���������̃g���b�N���^���炩����Ƃ������@���A���͏��߂Ă̂��Ƃł���B ���{�Ń��R�[�f�B���O���Ă����Ƃ��ɂ́A�h�����{�x�[�X�{�M�^�[��3�s�[�X�̓����^�������Ă����B ���̕��@���ƁA�N����l�ł����s����Ƃ��ׂĂ�蒼���ɂȂ�̂Ŋ댯�x�͍������A���K�Ŋ��ꂽ�`�Ǝ����悤�ɘ^���ł���̂ŁA�\�����ԈႦ�邱�Ƃ��Ȃ��B �h���}�[�ɂƂ��āA������ԁA���邢�̓N���b�N�������̖��̏�Ԃ���A�O���[�����o���Ȃ���\����ǂ�������̂͑z���������V�Ȃ��Ƃł���B �����A����͑����Ƃ̗\�肪�Ȃ��Ȃ�����Ȃ����Ƃɉ����A���̑��������ォ�Ȃ葽�Z�ɂȂ肻���ȗ\��������̂ŁA�}���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B �K���A�ߍ��̓X�^�W�I�Ōl���K�������Ă����������ŁA�\����ǂ����Ƃ͂���قǓ�����Ƃł͂Ȃ��Ȃ��Ă����B �h�����e���Ƀ}�C�N�����Ă��A�o�X�h������T�E���h�E�`�F�b�N���n�܂�B ��Ƃ̓X���[�Y�ɐi�݁A���R�[�f�B���O�ɃL���[���o���ꂽ�B �S�̂ǂ����ɂ܂��p�ӂ̂ł��Ă��Ȃ��������c���Ă��邪�A����Ȃ��Ƃ͂������Ȃ��Ƃɂ͂��\���Ȃ��ɏW���͎n�܂�B ���������A�����̊��o���v���N�����A���܃r�[�g������Ȃ��������A�u���C�N�E�^�C�����Z�������悤�ȋC������A�����G���ȁA���͂ǂ�ȃt�B���E�C�������悤���A�v���悤�ȃt�B���E�C���ɂȂ�Ȃ������ȁA�����A�V���o�����O�����B �ŏ��ɗ��������Ǝ����Ɍ����������Ȃ���A�����Ȏv�����Q�̂悤�ɁA�����h�����E�u�[�X���삯����B ���x���^�蒼�����A�������ԂƎ����̗͗ʂ̒ǂ����Ă��Ȃ����Ƃ��l�����킹�A���Ȃ�K���ȂƂ���Ŏ��ł��Ƃɂ���B �����ł����Ȃ���A�������[�v�̉ʂĂɈ�����ʂ��c��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B �x�[�X�̘^���́A�Ȃ�ƃG���W�j�A�E�u�[�X�ōs��ꂽ�B �������ɂ��ꂾ�ƁA�v���C���[�̓x�b�h�t�H�����炵���Ԃ��̉����Ȃ��Ƃ������������邵�A�x�[�X�E�A���v�̑O�ɗ��Ă��Ă���}�C�N�ɗ]�v�ȉ����E�킹�Ȃ��čςށB �����A�o���̐x�[�X���G���W�j�A�̖ڂ̑O�Ŕ�I����̂́A���ɋC���������B ���������C�������܂��A�L���[���o�����Ɗ��S���������ߍ��ނ����Ȃ��B ���R�[�f�B���O�͉��𒉎��ɋL�^����B �����āA�Ȃ��ł����Ƃ��ɂ̓��X�i�[�̒N�����A���̉��������y����ł����B �����ɃG���W�j�A�̂��Ńx�[�X��e���ْ���A�h�������������Ă���Ԃ̊�����\���Ă͂Ȃ�Ȃ��B �Ђ�����A�ł��邾����S�ɉ���t�ŁA�r�[�g�����ށB 3���Ԃ̃��R�[�f�B���O�͂����Ƃ����ԂɏI������B �����ȂƂ���A�������̂��ł����Ƃ͎v��Ȃ��B �v���C���[�͏�Ɏ����̋Z�ʂ������炸�ɘr���Z�p�̌����ڎw�����̂Ȃ̂ŁA�ۑ����ꂽ�g���b�N�̃��A���ȋL�^�̂ǂ����ɕK��������Ƃ����s���������Ă��邪�A��قǂ̘b�̂悤�ɁA�ǂ����őË����Ȃ���Ȃ�܂��B �@�����A���ɂ����Ƃ����e�C�N���c�������̂��B ��������A���������ɉ����ł���̂����l���Ă������B �M�^�[�ƃ��H�[�J���A�R�[���X�͊���H�������A����ɉ������邩�B �L�[�{�[�h�����Ԃ��悤���A����Ƃ��{���S�����Ă݂悤���A�t��]�ɂ��Ă݂ăV���o���ł����Ԃ��悤���A�����s�b�`���������Ă݂悤���A���ʉ���}�����Ă݂悤���B �܂�����������苎�邱�Ƃ��A�݂�Ȃł������t�H���[�������A�ЂƂ̍�i�����̂��o���h���B �����o�[�����Ȃ��A�ЂƂ�ЂƂ肪�����̒S�������Ƃ��Ă��A���̕��@�_�͕ς��Ȃ��͂����B �����A�ł���Η��T�A�܂����R�[�f�B���O��i�߂悤�I 1��13 ���i���j �Q�O�P�P�N �v�[�P�b�g����߂��Ă���3���B ���܂��ɂ��̓��X�̉����������̒��ő����Ă��āA�ڂ��o�߂�ƃo���R�N�ɂ��鎩�����܂����܂����ݍ��߂Ȃ��ł���B �s��̖�A�d�C�������ăx�b�h�ɐg����������ƁA�l�X�ȕ�������������荞��ł���B �����͊F�A�\�����킹���悤�ɁA���Ɍ����ėD�����Ȃ��@�B�����B �N�[���[�̎��O�@�̒Ⴂ�X�肩��A�Ԃ̖h�Ƒ��u�̂������܂������т܂ŁB �����Ėl�͎v�������B �s��Ƃ����ꏊ�́A�����Ȃ��Ƃɖڂ��Ԃ��āA���W�ɂ��߂����āA�h�����h���Ɗ����Ȃ��悤�ɕ�炵�Ă����ꏊ���������Ƃ��B �������A�v�[�P�b�g�ɂ���ԁA�l�𑨂��ė����Ȃ������̂�Perfume��"Dream Fighter"�������B ������A�C�h���Ƃ͂����A�؋�����̃e�N�m�y�Ȃł���B ����ł��A"Dream Fighter"�͔]���ɂ��邮�邮�邮��ƁA��̓��̕��i�̂������ʂʼn�葱���Ă����B ��ɂ́A�^�������Ńo���R�N������g�Ƃ��āA���ꂩ��̎����������ǂ��Ȃ��Ă����̂�������Ȃ��s���肳���W���Ă����̂��낤�Ǝv���B �u���ʁv�̓��X�̒��ŖY��Ă����v����U��Ԃ�ɂ͂����Ă����̉̎��ł͂���B �����A���ꂾ������Ȃ��B �l�͓�������A�̎��������|�I�ɉ��ɍ��E�����l�Ԃł���B �ǂ�Ȃɂ悢�̎����������y�Ȃł��A���Ƃ��ėD��Ă��Ȃ���ǂ����Ă��D���ɂȂ�Ȃ��B �v�[�P�b�g�؍ݒ��A�Ȃ�"Dream Fighter"�Ȃ̂��ɂ��Ă͍l���Ȃ������B ������Nj���������A���邪�܂܂��e���̂��A�v�[�P�b�g��炵�ɂ͕K�v�Ȃ��Ƃ������B �J���~�邩������Ȃ�����o�C�N�ŏo������̂���߂Ă��܂��悤�Ȏv�l���@�ł́A�v�[�P�b�g�̉���m�邱�Ƃ��ł��Ȃ����낤���炾�B �������ăo���R�N�ɖ߂��Ă���ƁAPerfume���v�[�P�b�g�̎v���o�Ɠ����悤�ȁA���炫����鑶�݂ł��邱�ƂɋC�Â��B ���̎����G��͂܂������Ƃ����Ă����قLjႤ�B �v�[�P�b�g�̖��͂������ł��Ə����Ă����������Ȃ��̂łقƂ�ǂ͑��e�ɏ��邪�A�����܂ł��̂悳�̓i�`�������ʼn��₩�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B ����ɑ��āAPerfume�̓e�N�m�ł������ł͂Ȃ��A�A�C�h���Ƃ��Ă�10�N�I��́A�����グ��ꂽ���j�b�g�ł���B ����ΐl�H�I�ȉ��H�i�Ƃ��Ă̊������ꂽ��̏��i�ł���B �Ƃ��낪�A���̐l�H�I�ȃL�����A�������炷�R���r�l�[�V�����̈��肵�����������������A�܂��������ɂ��炫�炵�Ă���̂ł���B 8��1���ɂ����������A80�N�ゲ�납��A���{�̏����A�C�h���Ƃ������C���̓����[�^�H���ł���B �Ⴂ�̂Ɍ|�B�҂ł������͂���Řb�萫�͐s���Ȃ����A�A�}�`���A���ۂ����������X�����Ƃ������Ƃł�����B ����ɎႢ����A�H���]���Ȃǂ̂�蒼���������B �������ɂ��̕��@�͋ƊE�ɂƂ��Ă����X�i�[�ɂƂ��Ă��D�����������Ă���B �������̈���ŁA�l�����́u�̗w�ȁv�������Ă������ł�����̎G�H�I�Ȗ`���u����A����ɕ����Ȃ������̃A�C�h���{�l�̗͗ʂɐG���@��������Ă����B �A�C�h�������ɂƂ��ē~�̎��ゾ����90�N��ɂ͏������F���ς�������Ƃ����������A80�N��̑f�l�A�C�h���̋ɒv�ł��������j�����q�N���u���v���f���[�X�����H���N��AKB48�ł܂�����Ȋ��������݂Ƃ̊ԂɁA�����[�^�H���Ɋւ���傫�ȊJ���͂Ȃ��B Perfume�͂��̈Ӗ��ŁA�܂������قȂ�ʒu�Â��ɂ���A�C�h���ł��邱�Ƃ́A�݂Ȃ�����������̂Ƃ��肾�B �L���̃��[�J���E�A�C�h������o�����A�u���C�N�܂ł̒������ς݂��o�āA�ؑ��J�G���Ȃǃv���̑�����̏^������������ޏ������̂�����́A���炭�l�炪�Y��Ă����A�{���ɗ͂̂���A�C�h���Ƃ��Ă̂���ł���B �����炱���A�ޏ������̉̐��ɂ��Ă��_���X�ɂ��Ă��A�꒩��[�ɂ͓�����͂����Ȃ��[����������B �����āA���̂悤�ɂ��ău���C�N�������̂���������т��������Ă���B ���炫��̐��̂͂��ꂾ�B 3�l�̐L�т₩�Ȑ��⎈�̂ɂ́A�v�[�P�b�g�̗z���Ɠ���ῂ������A�v�[�P�b�g�̕��Ɠ����u�₩��������B �����āA�e�N�m�Ƃ����������������t�H�[�}�b�g���A�ޏ��������x���Ă���B ���ꂩ����l�̒��ŁA�v�[�P�b�g�ƕ�����Perfume���A�������Ƃ��ďo�Ă��邱�Ƃ��낤�B �v���o�ƌ��т������y�́A���܂ł����̋P��������Ȃ��B �P�P���P�P�� ���[�����C�_�[�Y�̊�����������~�����ꂽ�B �v�[�P�b�g�Ńo���R�N�ޔ��𑗂��Ă���11��11���B ���傤�ǃ^�C�Łu���[�C�E�N���g�[���v���j�����̂��Ƃł���B �����C�̌�������͑���ۂދP���Ŗl�������Ƃ炵�Ă����B ����Ȗ����̌���ɁA�ނ�̊�����~�̕�ɐG�ꂽ�̂������B ���łɌ����A�l�͓����ɁA�����X�g�[���[�̑傫�ȗv�f�ƂȂ��Ă��鑺��t���́u1Q84�v�̃n�[�h�E�J���@�[��ǂݕԂ��Ă����Ƃ���ł��������B ����͂��Ă����A�������R�m�c�A�ނ�͂��̌��̂��ƁA�C�̔ޕ��ւƌ��������Ƃ����̂��낤���B �l�͂��̃o���h�ɂ���܂łǂ�قǐS������A�l���������A�e������A���y�̑f���炵���ɐg�k��������ꂽ���Ƃ��낤���B ������ǂꂾ�����t�ɒ����Ă��A�����đ���邱�Ƃ͂Ȃ��B ����Ƃ��ɂ͕������߂����Ǝv���i�����o�[�̊F����ɂ���C�������������c�j�A����Ƃ��ɂ͋��t�̂悤�Ɍh���Ă������[�����C�_�[�Y�B �ނ�Əo�������Q�l���ォ��A�l�͖{�i�I�Ƀ|�b�v�E�~���[�W�b�N�Ƃ͐��Ă��藣���Ȃ�����������邱�ƂɂȂ����B ���ނƂ����ɂ͂܂��������A����̃\�������Ȃǂւ̎x�����ނ玩�g���Ăт����Ă���B ����ɁA����͉��U�錾�ł͂Ȃ��B �t�@���Ƃ����̂͂��܂ł��ǂ��܂ł��킪�܂܂Ȃ��̂��B �����邩����A�ނ炪���[�����C�_�[�Y�̈���ł��葱���Ăق����Ɗ���Ă����B �����A1986�N�́u�h���g�E�g���X�g�E�I�[�o�[�E�T�[�e�B�[�v����1991�N�́u�Ō�̔ӎ`�v�܂ł̒��������x�~���Ԓ��ɁA���R���ł������ꂽ���̂́A�����ɕ������Ă���̔ނ�̃o���h�����ɂ����A�l��͂��肪�Ƃ���������x�������Ƃ���Ȃ̂�������Ȃ��Ƃ��v���B �o���h�ɂ͂��ꂼ��̎������A�X�̎v�������ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ����Ƃ��R�̂悤�ɂ���B �܂��Ă�A���{�Œ��̃o���h���ƂȂ�ƁA�l�����ɂ͑z�������Ȃ��B �����߂��������Ƃ����v���́A��q��1986�N����̒��������x�~����A���������ނ�̋��ɒ��ɂ͂����肠�����̂ł͂Ȃ��낤���B ���肪�Ƃ��A���[�����C�_�[�Y�B ����������Ƃ��ꂪ�Ō�ɂȂ�̂�������Ȃ�����ǁA���悤�Ȃ�͂��ȂȂ����ɂ��܂莗����Ȃ��C������̂ŁB �P�O���P�U�� ������̉̐����J���I�P�E�{�b�N�X�����ς��ɍL�����Ă���B���Ȃ₩�ł��Ȃ���c�̑����ޏ��̂��̉̐����B �u������A�́A���܂���v�ׂ̉Ɯ����X�ɗ���O�ɘb���Ă��Ă��ꂽ�Ƃ���A����A����ȃ����F������Ȃ������B�Ȃɂ���A�J���I�P�Łu���A���̋ȁA���Ȃ��̔����Ă�CD�ɓ����Ă�Ȃ���v�Ƌ�����ꂽ"It's a Party"�́A���{�ɋA�������̂��ɒ������������i�R�R�E���[�j�̃��H�[�J���̍��������Ɏア�����܂������������̂�����B������̉̂́A���̋Ȃ������o���s�s�����̉₩�ȑ��ʂ����łȂ��A�����ɂ��̋����`���Ă����B �Ɯ��͍��Y�łł������߂Ă̗F�B�������B�t���[�E�y�[�p�[�̎�ނŒm�������𗊂�ɒH�蒅�����o�[�̊K���Œm�荇���A�l���w�O�̂ς��Ƃ��Ȃ��h�ō��𐘂��悤�Ƃ��Ă���̂�m��ƁA���e�̂���Ƃɏ����Ă��ꂽ�B����̎Ⴂ�j�ŁA���������Ђ܂ňႤ�ӎU�L���ˑR�̖K��҂��A�Ȃ����Ɯ��̗��e�͖ٔF���A�������ЂƂ^�����B���ꂩ�獂�Y�ɂ���Ԃ��イ�A�l�͔ޏ��̌g�ѓd�b�̃A�N�Z�T���[�ƂȂ��āA���̖T����قƂ�Ǘ���邱�Ƃ��Ȃ������B���݂��̃g�C���x�e�ƁA�T���������ȓd�b�̂��ƁA���炭�m�荇���ɉ���Ă���Ɣޏ��������c���ăJ�t�F������Ƃ��ȊO�́B �J���I�P�E�{�b�N�X�ɂ͎��ɑ����̖K��q�������B����́A���̓X�������ɔɐ����Ă������Ƃ����b�ł͂Ȃ��B�l��̂��镔���̔����A���Ȃ����ς����Ă�20�l�ȏ�̗��K�҂�����ւ�藧���ւ��J���Ă������̂��B����҂�1�ȉ̂��A����҂͌y�������b���ς܂��A�����Ă���҂͂��炭�N���ׂ̗ɋ���������ߍ����A�N��l�l��Ƃ��̌�̍s�����Ƃ��ɂ���҂͂��Ȃ������B�����ɓ����Ă���p�͂��ꂼ��Ɉ�����I�[����Z���Ă������A�o�Ă����Ƃ��ɂ͖����ƌ��܂����قǂɈ�l�Ȕw�������Ă����B�����āA���̒N�����j�������B����Ȃɂ��X�Ɋ猩�m�肪����ޏ������́A�l�̑z���ȏ�ɗV�ѐl�Ȃ̂�������Ȃ����A���Y�����قǑ傫���Ȃ��X�Ȃ̂�������Ȃ��B��p�ł͓��{�őz�������Ȃ���҂����̍L��ȃl�b�g���[�N���펯�ƂȂ��Ă���̂�������Ȃ��B���̃A�W�A���s�ɐ�������A�t���[�y�[�p�[��ނŊX�ł̃R�~���j�P�[�V�����̊g��ɕ@���̍r�������l�ɂ́A���ׂĂ����I���̐V�N�ȃA�W�A�̖������Ƃ����f��Ȃ������B 2011�N�̃o���R�N�B�^���̃j���[�X���肪�J��Ԃ����e���r�̃X�C�b�`���AiPod�������_���I�Ȃɂăv���C�E�{�^�����������l�̌ۖ����A"It's a Party"���k�킹���B�ڂ����ƁA���Â����@�I�ȃJ���I�P�E�{�b�N�X�ɉ������āA�}�C�N�������Ă����B�������A�l�ׂ̗ɂ͉Ɯ�������B���̂Ƃ��̂���߂����Ȃ��ށB���ׂ̍��������̉̐��́A��������ɂ܂������L���̒f�Ђ�\������̂ɂ͂҂����肾�����B�����ƁA�������͂���Ȏ��Ԃ�\�z���Ă����̂��낤�B �Ɯ������ƒm�荇���O�A��k�̃��C���E�n�E�X�Œm�荇����������̉Ƃɂ��A�l�͏�����Ă����B�ނ̕��͖^��s�̓����x�X���ŁA�ގ��g�����{�Ɍ�w���w�̌o��������B�x�O�̂�����肵�����j�b�g�̃}���V�����ɂ́A�ډf�����̓��������������Ă����B�t�߂̂��y�����ӂ�܂��Ă��������A�����ɍ��Y�ɓ�������o�X�ɏ��A���̗[���ɂ͉Ɯ������Ɣt�����������グ�Ă����B�Ⴍ�A���S�C�ȓ��X�B����͂܂��A�v�����݂̏��������_�o�Ȋ��Ԃł��������BNHK���炩�烍�[�h�V���[�ԑg�Ƀ`�����l����ւ��邭�炢�̋C�����ŁA�X�̗l�X�ȓ���ɈٖM�҂Ƃ��ēo�ꂵ���l�́A����܂ł̏����̗����v���C���[�̎莝���J�[�h�Ȃǂ��\���Ȃ��ɁA�s�ӂɃQ�[���ՂɃ`�b�v��u������₩���q�ł����Ȃ������B�����̕����ɂ͂��̂Ƃ��A���̏�ɂ��������̌��͂Ȃ����̂����A�������̌���ꂽ���Ƃ����͎��Ԃ�⿂������A�o�����o�����ƂŌ���Ƃ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B �Ό������ςɑ����邱�ƂȂ��A���g�̐S�̕����܂܂̍s�����N�������e�������邪�܂܂Ɏe��Ȃ��炻���͂��ƂȂ��������o���邱�Ƃ��ł������̐t�Ƃ����p���������������G�߂��A�l��ῂ���������B���̍�������������Ȍ�������܂ł����A���ƂȂ��Ă̓V���K�[�E�R�[�e�B���O����Ă���B�����A���̂ނ�݂Ȓ��˖Ґi�ɂ��Ԃꂽ�A�ނ�E�ޏ���̔w�����Ă����͂��̂������ȏd�݂́A���ɂȂ��Ď�̂Ђ�Ɋ�������悤�ɂȂ����B���傤�ǁA�����ŏ_�炩���A����������Ă���鐅�Ƃ������݂��A�ЂƂ��їʂ𑝂��ƈÂ��������d�݂ł�������̂�ۂ݂��݁A���̍^���̐��ʉ��ɂ��ׂĂ߂Ă��܂����Ƃ���悤�ɁB "It's a Party"�͖��c�ɂ������Ƀt�F�C�h�E�A�E�g���A��҂����̓ƒd��ł����̏I���������Ă����B�~���[�E�{�[���̃t�F�C�N�ȋP�����~�܂��Ă��܂����X���o��A�����ɂ͔��ݏd�Ȗ閾�������邾�낤�B�l�X�͉߂����������Ԃɏ����v����y������A���炾���d���Ɗ����Ă݂��肵�Ȃ���A���ꂼ��̌����ւƋA���Ă䂭���낤�B����ł��Ƃ��ǂ��A��̒��̒��ɂ��鎞�݂����ɋ���ł݂����Ȃ�B�u�������͖����Ȃ�Č��Ȃ��Ă������I�@�����A���̏u�Ԃ���I�v ���@�������̊����\�����ł��Ȃ����߁A�������ȕ\���ɂȂ��Ă��܂��B2���ڂ͂����ւ�ɂ̂Ԃ�ł��B 8��1���i�j
�Q�O10�N 12��4���i�y�j
�P1���P4���i���j
�Q�O�O�X�N �P�O���P�W���i���j
�P���P�S���i���j
�Q�O�O�W�N �Q���V���i�j
�Q�O�O�U�N �P�P���Q���i�j
�Q�O�O�T�N �T���R�O���i���j �Q�O�O�S�N �P�P���P�T��
�P�P���V�� �P�O���P�� �U���X�� �S���R�O�� �Q�O�O�R�N �P�Q���P�S���i���j |
���u�v���[���v�\���ɖ߂��@�@�@���g�b�v�E�y�[�W�ɖ߂�
| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||
