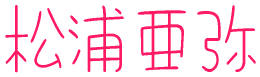
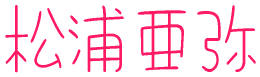
| 流行という装置は、季節の変わり目にかかる軽い熱風邪のようなものだから、治っていく過程には安静も体調管理も必要である。トーキョーが世界で最も面白かった90年代は終わり、「時は流れるのだからいたしかたない」という面持ちで2000年代もやってきた。少し疲れた世相には、明るく実直な若さのアイコンが必要だろう。 2000年から、私は生活の場をタイに移している。何をすることなくとも、そこに居るだけでシーンの様子が判ったり情報が伝わってくる日本からここは遠く、彼女の名も2001年紅白歌合戦のトップ・ステージに立つまでまったく覚えがなかった。しかし、僕はその地理的距離感によってブラウン管に彼女が現れてくる様をきわめて客観的に見ることができたとも言える。 今回の切り口のように「90年代」「2000年代」などと年を10年単位で区切ったとき、エポック・メイキングな潮流などというものは、実は各10年の半ば以降、本当に駆け込み慌てるようにできてくるケースが多い。それまでの前半戦は「白けた空気感」で単発的な音楽が様々に現れては消えてゆくといういつもの道を繰り返す。そして、そういった「この10年の潮流」をシーンが発見するまでの間を支える役目を大きく担うのがいわゆるアイドルである、と僕は考える。 そういう意味で、安室奈美恵はまさしく世紀末のディーヴァだったといってもいいように思う。沖縄から新鮮な魅力と並外れた表現力、それに折れてしまいそうな可憐さをスタートに90年代を走った彼女は、若くして最愛の人と結婚というこれまた素晴らしくトピカルな第1幕の幕引きを見せるが、それはたぶん、多くの視聴者にハッピー・エンディングを想起させなかったろう。それほどまでに結婚前の彼女の目からは生気が奪われ、スピードが上がったまま袋小路に入ってゆこうとする車のような悲壮感さえ漂わせていた。そうして、90年代は終わっていった。 松浦亜弥を前にしたとき、僕は毎回気づかされることがある。つんくプロデュース・シンクタンクの狙う「懐かしの王道アイドル路線」に乗せられているせいもあろうが、彼女はまったくアイドル以外の何物でもあり得ない。それが、例えば「この子にはぱっと見ただけで判る華がある」という以外に「カリスマ的なリーダーシップもある」とか「年齢のわりに清潔なセクシーさがある」とか「歌声が耳に残る」などといった付加価値が加算的にアイドル性を高めてゆくというのと正反対に、松浦亜弥はアイドルという一枚看板を取ってしまうとあとにあまり何も残らないゆえに、彼女がアイドルでしかあり得ないことを証明してしまうという減法的な方法論で成立しきっているところがすごい。臍を出してもまったく厭味にならないし、いつも明るい自分を演じていたとしても、そこにも何の影も残さない。 安室の後、歌謡界は「何もアイドルのリアル・ライフを 見続け、見届けなければならないわけではない。お茶の間の視聴者にとって眩しくて少年少女たちの憧れであればそれでいい」とつぶやいている。 |
 |
ALBUM
First Kiss
T・W・O
links of Aya Matsuura
Matsuura Aya Official Web Site
[[Ayaya-Style]]
松浦亜弥友の会
aya's cafe
my best song Love涙色
my best album First Kiss
my best lyrick 私のすごい方法
my best music 草原の人
my best arrange オシャレ
◆「プレーン・ジャパン」に戻る
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
