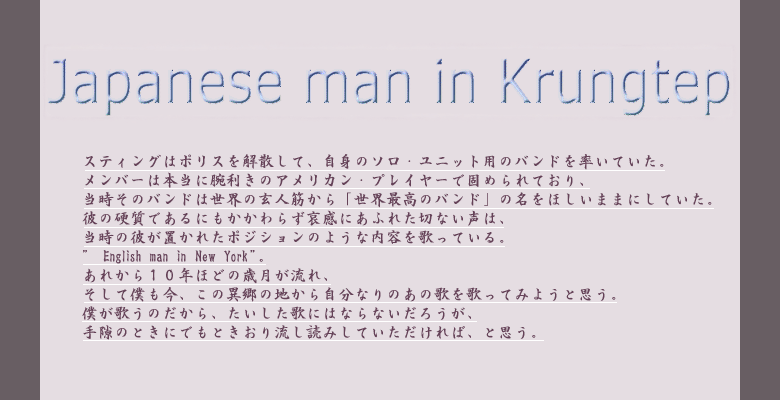
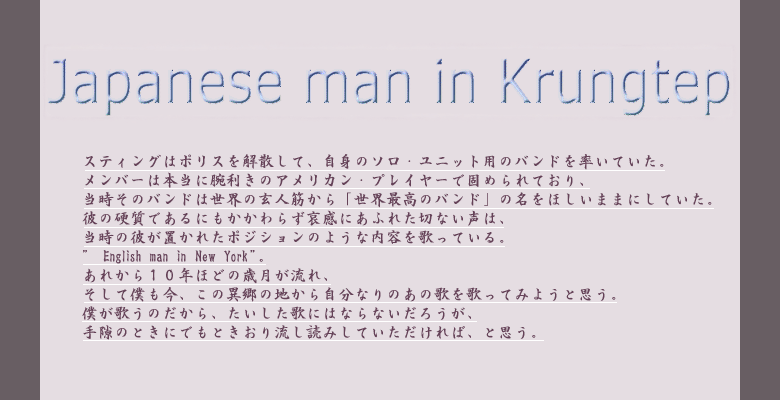
�Q�O�Q�O�N
| 10��2�� �^�C�ł�WHO�̃l�[�~���O"Covid 19"�ƌĂ�Ă���V�^�R���i�E�B���X�B ���E���̓s�s�Ɠ������A�o���R�N�ł��呛���ɂȂ����B �������A���̎����͑��������B 2020�N1��12���ɁA�������O�ŏ��̃R���i�����ҁi��������̒����l���s�ҁj���o���R�N�Ŕ�������A 1��22���ɂ͕������s����߂����^�C�l�̏������������B 1��31���A���̍��������ҁi�^�N�V�[�^�]��j���m�F���ꂽ�B ���̎����A�킸�������^�C�͒����ȊO�Ő��E��̊����Ґ����L�^�����B 2���ɂ�42�l�������̂ɁA3���ɂ�1651�l�ɂȂ�A�V���b�s���O�Z���^�[�Ɩ�LjȊO�͂قƂ�ǖ������A�����܂ŕ�����鎖�ԂƂȂ����B �����A�ό��Ƃɂ��Ȃ�ˑ����A����A�W�A�̃n�u�ł�����^�C�ł̊����g���s�v�c�Ɏv���l�Ԃ͂قƂ�Ǒ��݂��Ă��Ȃ������͂����B �����A5���ɂ�127�l�Ƒ啝�Ɍ����A6��13���̐V�K������0�ȗ��A101�����ꂪ�������B 9��21���ɂ͊C�O�n�q���̂Ȃ��^�C�lDJ�̊������o���R�N�ߍx��1�l�o�����A���̌�A�����܂ł܂��A��0�ł���B �M���n��ł̓R���i�E�B���X�̊����͂��݂��Ȃ�Ƃ����������������悤�����A�C���h��V���K�|�[���E�C���h�l�V�A�E�t�B���s���ȂǂŊg�債�Ă���ȏ�A�^�C�̗�̓��F�g�i���Ɠ��l�ɕ]������Ă�����ׂ����B �܂�������Ȗ͔͐��ɂȂ�Ƃ́c�B �V�^�R���i�E�B���X�ɂ��āA�����[�����Ƃ�������Ă����E�F�u�L�����������B �v�����������Ȃ��A�����g������܂�ɃX�s�[�f�B�[�����Ȃ���C�����E�B���X�������E��k��������A�Ƃ������e�������B �u�����Ɏ��Ă�ȁv �������A2011�N�̍^���������I ���̒n��ɂ͐r��Ȕߌ��������炵�����ǁA�h�g��ɂ���ăo���R�N�s���͊�����H���~�߂��^�������ł���B �o�σ_���[�W�ł͌��ݐ��E��4�ʂ̔j��͂����������A�^�C�Ƃ������͔ߑs�ȃ��[�h����������Ȃ��B ���̂Ƃ��l���w���Ƃ́A������蔗���Ă�����̂قNj��낵���Ƃ������Ƃ������B �k���Ⓦ�k���i�C�T�[���j�ł��傫�ȍ^����Q������ꂽ���A1�����قǂŐ��͉����ւƗ��ꋎ�����B �Ƃ��낪�A�o���R�N���܂ރ^�C�������͍L��ȕ���ł��邤���A���፷���ɂ߂ď��Ȃ��B ����������4km���炢�̂�����葫�ŁA�^���͂Ђ��Ђ��Ƃ���Ă���B �o���R�N�͂قڃ`���I�v�����[�͌��Ɉʒu���邽�߁A�S�[���̂悤�ȏꏊ�Ɉʒu����B ��������Ă���X�f�[���ǂ��\�����A�ǂ������ׂ��Ȃ̂��A�������X�������B ���ʁA�o���R�N�s���ɂ͐��͗��Ȃ��������A�o���R�N�ւ̕⋋�H���^���ŎՒf����Ă��邽�߁A�~�l�����E�H�[�^�[���͂��߁A���N�H�i���X����������A�s���傳�����B ��`�ł͂��łɍ^���̋������k���E���k���ւ̕ւ͂ǂ�����ȂŁA���s���Ԃ̐��i���Ƀ^�N�V�[�̐��j��������ƌ���A���{�l�w�Z���ꎞ�����ꂽ���ߑ����Ȑl���̓��{�l���ꎞ�A�����A������1�K�ɂ͍^����̃R���N���[�g�ł߂�y�X�̏���������Ă����B ���̎����̃o���R�N�́A�r�p���Ă����s�s�̏I�����������Ă���Ă���悤�������B �^�C�ݏZ�҂��R���i�����ɗ��������đΏ��ł����̂́A���������u�\�K�v�̑��݂�����������ł͂Ȃ��낤���B �^�C�̔��_�̂ЂƂ́A�ǂ����悤���Ȃ����ԂɂȂ����Ƃ��ɓ{��U�炷�l�����قǑ����Ȃ����Ƃ��ƌ��������B �������^���̉����~�ߋߗגn��̐l�X�̓{��̃j���[�X��A�R���i�����ł̃^�C�l�x�����{�l�R���i���ʔ����ȂǁA�{��̕��o�͌�����̂����ASNS�g�U�`�����ӎ��̌`���Ƃ��������ꂵ�����u����������ɁA�l���m��قƂ�ǂ̃^�C�l�͑ǂ��Ȃ��B �����ĖO����̂������X���������A�u�ߋ��v����̐��_�I�ȒE�o�����{�l��肤�܂��B �����͌l��`���Ȃ���Ƃ��Ǝv�����A����ɁA�^�C�l�͂����Ƃ����Ƃ��̈�v�c�������܂� �N�����}�X�N�����邵�A�X�ł̃`�F�b�N�C�����K�v�Ƃ�����邵�A�^���ň���������ɓ���Ȃ����Ƃɐ����r����q�͂��Ȃ��B ��������Ԃ̐��E�̒��ŁA���݃R���i�̐S�z������Ȃɂ����Ȃ��Ă������ɕ�点�Ă���w�i�ɂ́A����Ȃ��Ƃ�����悤�Ɍ�����B |
 |
�Q�O�P�W�N
 �^�C�ɏZ�ݎn�߂�����MBK�i�}�[�E�u���N���[���E�Z���^�[�j |
3��15�� �g�т̃c�C�L���X�A�v���ɂ́A��`�ł܂��ɏo�����悤�Ƃ��Ă���ؑ�����̐Î~�摜�ɂȂ����z�M��ʂ��f����Ă����B �����̂悤�ɐE��̊K���̃e���X�ʼn�������{��肾���Ȃ���u�����A�o���ł��ˁv�ƓۋC�ɏ������l�́A����12����ɂ̓J�^���Ɖ��𗧂ĂĂ܂������Ⴄ��ނ̐l�Ԃɕ^�ς��Ă����B �O���A�S��X�|�b�g�����^��ؑ�����ƂƂ��Ƀt�F���X�̔j��������蔲���A��Ђ̂������N���u�Ղ��M�ɕς�����X�n�Ō͂ꂽ���}�ݖ炵�Ă����B ���ǂ남�ǂ낵������ȏꏊ�ŁA���w���̍��ɂ��������u�`���v�̃t���b�V���o�b�N�ɐg��u���Ă����l�́A�������莞����ǂ����ɒu���Y�ꂽ�B ���J���͋x���̋��j���Ƀc�C�L���X�i�ȉ��L���X�ƕ\�L�j�́u���̑��C�O�v�^�O�Ɉ�l���������ؑ�����̔z�M���J�����Ƃ��납��B �����ꂽ���̕��i�̓o���R�N�̃V���b�s���O�Z���^�[MBK�i�}�[�E�u���N���[���E�Z���^�[�j�̂��́B �ނ͂����ōא�j���W���̃g�b�s���O���ꂽ�^�C�َq���ĐH�ׂĂ����B �������܁u�����Ƃ܂����ł���v�ƃR�����g���������ꂽ���A�������łɐ��\�o�[�c������q����Ɏ�n����Ă���B �Ă̒�A���̖��͔ނ̌����ɒ��炭�`�e����������a�����c�����悤�������B �L���X�̊C�O�^�O�́A���܂�u��������i�L���X�ł͏��߂ĖK�₵�������҂������Ăԁj�v���������ꂽ���Ȃ��z�M�҂ɁA�C�O�Ƃ͉��̊W���Ȃ����p����邱�Ƃ������A���ہA�C�O�^�O�͂قƂ�ǐl�C���Ȃ��悤���B �܂��A�L���X�ł͌Œ��ʂ̃��W�I�z�M�������A���ۖl������܂łق�̏����z�M���Ă������̂قƂ�ǂ̓��W�I�^���������A�ؑ�����̃��C�u�z�M�̓o���R�N�̊X�̏��߂Ă���Ă������s�҂̎��_��N�₩�ɉf���o���Ă����B �}�[�E�u���N���[���E�Z���^�[�͖l�̏��^�C���s�ł͂��߂ĖK�ꂽ�ꏊ�B �����āA�l�����̂̂���Ȃ��^�C�َq�Ɏ��L���Ĉً�Ԃɕ��荞�܂ꂽ�荇�ł���B �ނ̎p��20�N�O�̖l�Ɗ�d�ɂ��d�Ȃ�A��C�Ɍ������A�b�v�����B �z���[�f��ēł���ؑ�����̔z�M�ɂ͊y�������₩�ȃ��X�i�[�����i����z�M�ł����Ă������҂����X�i�[�ƌĂԁj����������B �����ɂ��l���悳�����ł��Ȃ���Ƃڂ������̖ؑ�����ɓ͂��R�����g�́A�ނ�l�X�ȕ��ʂ���u������v�Ȃ�����A�ǂ������Ɉ�ꂽ���̂��B �����̂Ƃ�����ؑ�����ɂ���A����ɂ��D�������Ă�����āA���ɑu�₩�Ȃ��敗�������v���������B ����Ȃ��^�C�����s�ɂ킭�킭�f���ؑ�����ƁA�Ƃ��ɉ�ʂɗ���Ă��郔�@�[�`�����E�^�C���s�����Ă��郊�X�i�[�����ɁA�l�͍݃^�C�҂Ƃ��Ăł��邾�����ɗ��R�����g�����悤�ƁA�v�킸���Ԃ�Y��ĉ�ʂɋz�����Ă����B 2����A����Ȃ��ߑO����̕ϑ��Ζ��ɐQ�s���̖ڂ�������A���Ƃ��d�����������l�́A�A���O���ł���͂��̖ؑ�����̔z�M���������܊J���Ă݂��B �ނ̓o���R�N�̒��S�n�T�C�A������A�S��X�|�b�g��K�₵�悤�Ƃ��Ă������A���łɑ����_�ɂȂ��Ă��邤���A�ړI�n���ڂ���Ƃ��Ă��ē��肵����Ȃ��͗l�ł���B �Ƃ肠�����y���C�����Łu�o�C�N�ł����肵�܂��傤���H�v�ƃR�����g���Ă݂��B �C�y�ɂ����������b���ł���̂��A�����^�C�̃X�^���_�[�h�ł���B 1���Ԃقǂ̂��A�l��̓Z���g�������[���h�ŗ����������B �^�C�V���N�̔��X�̑㖼���Ƃ�������W���g���v�\���̑O�ł̑҂����킹���������A�X�̑O�ɓ������Ă݂�Ɣނ͂��Ȃ����A�ނ̔z�M��ʏ�̏ꏊ�Ƃ͖��炩�ɈقȂ�ꏊ�ɖl�͂����B ���X�i�[�������l������l���A�p���������[���h�ɂ���̂��ƋC�𝆂B �u2���������肵��w�v�ƃ��X�i�[����R�����g������A�蓖���莟��^�C�l�ɐq�˂Ă݂�ƁA�����K�ɃW���g���v�\����2�����邱�Ƃ��킩���Ă������܂�����Ɍ��������B ���Ȃ݂ɁA�蓖���莟��ɐq�˂��̂́A�^�C�����ł̏퓅��i�ł���B �u�X�Ŗړ��Ă̏��i��������Ȃ��ēX������ɐq�˂Ă݂����A���i��u���Ă��Ȃ��Ƃ������ł���ƌ���ꂽ���̂����e�Ɍ�����v�悤�Ȃ��Ƃ͒��������Ƃł͂Ȃ��B �����āA����ȂƂ��̓X������͒p�����������ł����������ł��Ȃ��A�u�������Ă悩�����ˁI�v�Ɩ��邢�Ί�𑗂��Ă����B �ꎖ����������Ȓ��q�Ȃ̂ŁA�^�C�ł͐l�C��p����Ȃ̂��B �Z���g�������[���h�̒n�����ԏꂩ��2�P�c�Œn��ɏo����A�r�C�K�X���炯�̂͂��̑�ʂ�̕����A�����̂悤�ɑu�₩�Ɋ�������B �u����[�A�C�������������ˁ[�I�v �u�Ȃ�ŃA�W�A�Ńo�C�N�ɏ��l�������̂����������C�����܂��I�v �ЂƂ���傫���Ȃ����ؑ�����̐��́A�������U���Ă�����Ă����������Ƃ��ȁA�Ǝv�킹��M��ттĂ����B �y�b�u���[�ʂ�̓����ɓ���ݕ���������Ėl��͏��̃X�����ɏo���i�^�C���S�̐��H�e�̓X�����̊����������ɍ����j�B �^�C�ɂ͓��邾���Ŋ댯���Ƃ����ꏊ�����Ȃ��炸���邪�A���̕��͋C���@����{�[�_�[���C���͂Ȃ�ƂȂ����ŕ�����B �����̐l�����̖ڂ͗D�����B ���H�̏�ɂ��萻�̃g���b�R���o�Ă���̂ŁA�ݕ���Ԃ����炭������ʂ邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B ���݁A�S�����z���āA�Z���Ƃ��ڂ����^�C�l�����ɐ����|�����Ȃ牜�ւƕ���i�߂�B �ڂ������Ɩl�����Ƀr�[�������߂邨����������B �o�C�N�Ȃ̂łƂ��f�肵�āA�����ɂ��������o��Ƃ����b���Ă������ǁA�Ɛq�˂Ă݂���A�u�ȑO�͒r�ɂ������ǁA�߂��̂����ł��Q�肵�Ă�����Ē������ꂽ�v�Ƃ������b�ł���B �����������̂����A���b�g�E�}�b�J�T����K�˂��B �����S�O�������A���ɐ��l�������V�����ɗ�̂��Ƃ�q�˂�ƁA100�N�قǑO�ɂ͂��̎��ӂŕ���E��肪�s���Ă������A�݂�Ȃ����œ���ς̂ŗ�͏o�Ȃ��Ȃ����Ƃ����V�������b����яo�Ă����B �������A�[��5���ɕ܂��Ă����{�����킴�킴�J���A����������Ă��ꂽ���̒��Ŗl��͘b���Ă����̂������B ����������炩�ŋC�����ł��[���^�C�ɁA�l�͂���܂ł������x�����Ă���������Ƃ��낤�B �G�J�}�C�ʂ�ɂ��������l�C�̃N���u�u�T���e�B�J�v�́A2009�N1��1��0���߂��A�N�z�����C�����̉ЂŎ���65�l�E������200�l�̔�Q���o���āA�������̐Ղ̍X�n�͔����肪���Ă��Ȃ��B ����Ȃ��ƂɁA���̂Ƃ��X�e�[�W�ɗ����Ă����o���h�̖��O��The Burn�B �������A�o�Ό����Ɣ��\���ꂽ�z�[�����ł̉ԉ̑ł��グ�������̂́AThe Burn�̃��H�[�J���X�g�������Ƃ����^�����B �Ƃ��Ղ��ꂽ�G�J�}�C�ʂ肩��A�l��̓t�F���X�ɊJ�����j��ڂ�������A���������M�ɂȂ����n�𒆂قǂɐi�B ��ʗʂ̑����G�J�}�C�ʂ�Ƃ͋��ԂŊu�Ă�ꂽ�����Ȃ̂ɁA���͕K�v�ȏ�ɂЂ�����Ƃ��Ă���B ����ȏꏊ�ɗ����̂͂��̍��ȗ����낤�B ���̏ꏊ�́A���w���̍��u�閧��n�v��������L�����������ĂыN�����B �s��ɏZ�ލ��̎q�ǂ������́A����Ȏ��������̏ꏊ���ǂ��ɗp�ӂł���̂��낤���H �S�̒��H ����������ƃQ�[���̒��H �c����ƁA�ˑR�q�ǂ��̐��������A�l�����̉�b�͈�u�₽���Î�����B �U��Ԃ�ƃt�F���X�̌������Ɋی����̃G�J�}�C�ʂ�Ɏq�ǂ��̐l�e�͂Ȃ��B ���̏ꏊ�͎c��O�����n�ƃI�t�B�X�r���Ȃ̂ŁA����Ȃɂ͂�����Ƃ����q�ǂ��̐�����������̂͂����ɂ��s���R�ł���B �u����Ȋ���������̂ŏo�܂��傤�c�v �ؑ�����̐��������Ɋ����A�l��͐S���������ɒʂ�ւƖ߂����B �ؑ�������o�C�N�Ŏ��̖ړI�n�ɑ��������ƁA�Ƃ肠�����o�C�N�̂��Ŕz�M���J�����B ���X�i�[���A�l�̔z�M�ւ̔�э��݂��u���ꂼ�C���^���N�e�B�u�R���e���c�v�Ə����Ă���Ă����ԓ��ɁA�ؑ�����́u�z�M�̓R�����g������Ă��������̂̂��̂���Ȃ��ł���ˁB�o��������āv�Ƙb���Ă��ꂽ�B �F�A�Ƃ������t���ނ���ۂ��Əo���Ƃ��A���ɋ����M���Ȃ����B ������F�l�ƐH�������̂��A�Ăіؑ�����Ɖ�����B �ؑ�����͓��{�̃o���hThe Band Apart�̃o���R�N�E���C�������\���I������Ƃ���ŁA�^��{�^����������Ă��Ȃ��I�t���R���ԂɌ������������ȃv���C���F�[�g�b����яo���A�₪�ĊO�ɏo�Ă���ꂽ�����o�[���Љ�Ă��ꂽ�B ����Ȕނ��z�e���܂ő����āA�l�̖ؑ�����A�V�X�g�͏I������B �����̎d�����I��鍠�A�ނ͋�`�ŏo�����T���Ă���͂����B ������10���O�A�d�����I���ĂЂƂ�A�E��̊K���̃e���X�ł����̂悤�ɉ����ɉ������B �g�т̃c�C�L���X�A�v���ɂ́A��`�ł܂��ɏo�����悤�Ƃ��Ă���ؑ�����̐Î~�摜�ɂȂ��������z�M��ʂ��f����Ă����B ��������ł��Ȃ����A�����Ɂu�����A�o���ł��ˁv�ƓۋC�ɏ������B �������蒇�ǂ��ɂȂ������X�i�[�������玟�X�ƃR�����g���͂��B �u�����A�����I�v�u�܂��Ԃɍ����܂��v�u��`�܂Ŋ������ɂȂ��đ����Ă����ĕ����������v�u���������ăL�X�H�v�u���������������v�c����Ȍ��t���Z���Ԃ̂����ɕ��B ���܁A��`����26�L�����ꂽ�X���ɂ���l�ɁA�����ł��邾�낤���H �ؑ�����͂��łɎ�ו���������z���A�o���R���̗�ɕ���ł���B �������A�����̓^�C���B �Ⴆ�u�萔���v���u���ʋ��v�Ƃ������̂��ڂ��ڂ������Ȃ��Ƃ�����Ȃ��B �u�Ƃ肠������`�Ɍ������Ă݂܂��v �o�C�N�̃L�[�����肵�߂��l�́A�����A�R�����g��12����A�J�^���Ɖ��𗧂ĂĂ܂������Ⴄ��ނ̐l�Ԃɕ^�ς��Ă����B �r���̋������ɋC�����āA�����̔z�M���n�߂��B ����܂ŁA���X�i�[����������u�z�M���āv�Ƃ��������������B ����܂Ŗl�̓t�F�C�X�u�b�N�̃A�J�E���g�łԂ₫�Ɏ���������܂�Ƃ����z�M���������Ƃ͂��������A�ؑ�����ƃ��X�i�[���������߂Ă���̂͂������Ȃ��̂���Ȃ��͂����B �z�M�����Ăق����Ƃ������t�������������̂͂ƂĂ����������ǁA�l�ɂǂ�Ȃ��Ƃ��ł���̂��A�܂������C���[�W���Ȃ������B �����A���Ƃ肠�������|�P�b�g�Ɍg�т�˂�����ő���o���Ă݂�A�N���C�Â��Ă���邩������Ȃ��B �R�����g�ǂ݂͂ł��Ȃ����A���|�P�b�g�Ɍg�т���荞���x�ł͂܂Ƃ��ɕ��i���f��Ȃ���������Ȃ��B �ł��A�ؑ�����Ƃ̍ĉ�Ɍ����đ��郊�A���^�C�����|�[�g�́A���C���E�A�J�E���g�ł̏��߂Ă̂܂Ƃ��ȃ��C�u�z�M�ɂȂ肻���ȋC�������B �X�����i�v�[����`�ɂ�2�`3�x�o�C�N�ōs�������Ƃ����������A���C���Q�[�g�֏o�����������߂����Ă��܂����B U�^�[���������߂Ȃ�����̓��Ȃ̂ŁA���̐�ɂ���͂��̏��߂Ă̌o�H���J�邵���Ȃ��B �r���œ���u���Ă����Ƌ�`�̌�����ꏊ�֒H�蒅�����Ƃ���܂ł͂悩�����B ���A��`�~�n���ɓ������r�[�ɕ��s�҂��X�����Ƃ��Ȃ��Ȃ�A���𗊂�ɐi�ނق��Ȃ���ԂɁB �����āc�l�͋�`��ڂ̑O�ɂ��ĊԈ�������Ƀn���h������Ă��܂����B �C�������Ƃ��ɂ͂��łɁA�����t�����Ė߂�邭�炢�̋����ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���AU�^�[������ꏊ���܂������Ȃ��������H���Ђ����瑖��ق��Ȃ��B 10�L���ȏ㑖���ċ�`�~�n���o���Ƃ���Ńo�C�N���߂ėl�q�����Ă݂�ƁA�u�ؑ�����͂���������s�@�ɏ�荞�ށv�u�Ō��LINE�ŘA�������ł��v�Ƃ������X�i�[����̏������݂��������B ��������LINE�𑗂�A�u���߂Ėؑ�����̏���Ă����s�@�������邾���ł��v�Ǝ����̔z�M�ɏ�������ŁA���A��������ĕԂ����B �^�[�~�i���̔��Α��A�����H����]�ł������ȏꏊ�Ńo�C�N���~��āA���̊Ԃɂ����|�P�b�g�Ŏ~�܂��Ă������C���z�M���n�߂��B ���̂�����ɎՂ���̂̉����Ȃ����������炵���������A�������ʼnႪ�܂Ƃ����Ȃ��ꏊ���B ���X�i�[�̊F����Ɩؑ������������茩���邱�Ƃ��ł���B �o�C�N�ł͂قƂ�ǘb���ł��Ȃ������Ԃ�A�ؑ�����Ƃ̍ĉ���ʂ����Ȃ������Ԃ�A���X�i�[�̊F���i�ӊO�ɂ��j���ł��ꂽ�Ԃ�A�l�͑����ŏジ�������ŁA���߂Ă܂Ƃ��Ɂu�z�M�ҁv�ɂȂ����C�����ł���ׂ葱�����B �ؑ�����ɂ��Ă̘b���A�v���o�b���A�^�C�ɂ��Ă̘b���A�������ςɂȂ��Ď��X�ƃR�����g���͂����A�l�����̘b�͂ǂ����Ős����l�q�ȂǕЗ��Ȃ������B �₪�āA�ؑ�������悹�Ă���Ƃ��ڂ������������x������A�u�l��v�͈ꏏ�ɂ���ȋ@�e�Ɏ��U�����B �u�܂��ˁ[�v �����āA���̗]�C���݂�Ȃŕ������������B �g�т̓d�r��2���ɂȂ�܂ŁB ���̓�����Ƃ��ǂ��A�l�͓���ł̃��C���z�M������悤�ɂȂ�A���X�i�[����ɑ�����邱�Ƃɒ��q�Â��āA��l�Ńo���R�N�̐S��X�|�b�g�K��܂ł���悤�ɂȂ��Ă���i���ۂ̂Ƃ���A�����������̂̂��Ă���j�B �l�̔z�M�ɂ���������̃��X�i�[�����Ă����悤�ɂȂ��āA���N�Ƒ̂����ڂ邽�߂̂��܂̃E�H�[�L���O�ł����F����ɂ������Ă��������A���̂��̂�Y���C���F���g�ƂȂ����B �ؑ�����̒u���y�Y�c����Ȍ��t���]���ɉQ�����B �����A�l�͂ӂƎv�����������ƂɂЂƂ�G��łB �ނ��l�ɂ����Ǝ�n���Ă��ꂽ�̂́A���y�Y�Ƃ��Ă�������W���g���v�\���̃V���N���i��������Ȃ��B �ؑ�����͍�������̉f���l���B �ނ́A�f�����̂��̂Ƃ����p�����R�~���j�P�[�V�������ǂꂾ���f�G�Ȃ��̂Ȃ̂����A���t�ɒu�������邱�Ƃ̂ł��Ȃ��`�Ńo���R�N�Ɏc���Ă����Ă��ꂽ�̂������B �ނɒ��ڂ���Ȃ��Ƃ�`����A�����Ƃ��܂��{�P�ď��ɕς��Ă���邾�낤�B ���̌��t�̍s�Ԃ���A�܂��l�͂��������m�M����ɈႢ�Ȃ��B �ؑ�����̉f���Ƃ́A��i�Ƃ��Ċ����I�Ɍ����������R���e���c�ł͂Ȃ��A�₦�����͂�G�����čL�����Ă������Ƃ��邾���ɁA���܂ł������̂���A�l�����̐l�����̂��̂̂悤�ȕs��^�Ȃ��̂Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��B �����āA�ނ̉f������̈�o��l���ƂȂ邱�Ƃ��ł����l���܂��A���̖��̗͂��ƂȂ��āA���̊��ꂫ���Ă��܂����o���R�N��炵����̐���������ł��邱�Ƃ����������̂������B ���Ȃ݂ɁA�ؑ�����̃L���X�Ǝ���̃j�R���ł̃`�����l�����́u���m�K�^���v�ł���B |
|
 |
||
 |
||
 |
||
 |
| 2��16�� ���N�̃o�����^�C���f�[�A�v�����������܂����������m�炸�̐l���炠�܂�ɑf�G�ȃM�t�g��������B �v���[���g�̒��g�́AFacebook�ƁA����Ɋ֘A�Â����ꂽ�A�v���̈�ď�����ł���B ����A�W�A�𒆐S�ɂ������N�嗬�s���Ă���Bigo�Ƃ����z�M�A�v���ł̃��C�u�z�M�����̔��[�������B �^�C��œ��{�����������Ƃ��ǂ����C�u���l��Bigo�ł̎�Ȕz�M�R���e���c���������A���܁[�ɃQ�[���z�M���s���Ă����B ���Ȃ݂ɁA�l�͏��w���ȗ��A�e�g���X�������ĂقƂ�ǃQ�[�������邱�Ƃ͂Ȃ�������ł����A�X�}�z����ɓ���Ă��܂��ܖʔ������Ɏn�߂������̎���Q�[��������Ă݂���A�l�b�g��̉ˋ��������ƕ������Ă��Ă��A�Ȃ������Ă����Ȃ��Ȃ��āA�ӂƋC�Â�����5�`6�N�o���Ă����A����ȃQ�[���̔z�M��������ł� ���J���C�u�z�M�ł��̃Q�[�����v���C���Ă���Œ��A�X�}�z��SMS��Facebook����u�ʒ[�����烍�O�C�����������v�|�̊m�F���[��������A�Q�ĂđΏ����n�߂����A�����łɒx�������A�Ƃ�������ł���B �Z���Ԃ̂�����Facebook�Ɋ֘A�Â����ꂽ���̃Q�[����z�M�A�v�����������A�킸���Ȃ��炾���z�M�A�v���ւ̉ۋ������܂�A�����~�ς��Ă����Q�[���̃|�C���g�͂���������2���Ԃł݂�݂����ꑱ���Ă���B Bigo��facebook�̃Z�L�����e�B�[�Ǝ㐫�����Ԃ������N���������Ƃɂ͋^���]�n���Ȃ��B �����A�Z�L�����e�B�[���̓n�b�J�[�������ƂƂ̊Ԃł̃X�L������̂�����������������A��Q���y���ōς�ł��鍡�A�l�͂��̂��Ƃ��Ƃ₩�����������͂Ȃ��B ���́A�������Ĕ�Q�҂ɂȂ����ۂ̊e�Ђ̑Ή��̕��ɂ���B �܂��AFacebook�̓��[�U�[���璼�ڃ��[����d�b�ł̃T�|�[�g���s���Ă��Ȃ��̂����A�������Ă��炵�炭�͑Ώ��@�̌����ŏo�Ă���Facebook��FAQ�ɃA�N�Z�X���Č��o���y�[�W�ɓ��邱�Ƃ��ł��Ă��A���̏ڍׂ��N���b�N����ƃ��O�C�������߂����ʂɐ�ւ���Ă��܂��B �����������w���ɏ]���Đi��ł����ƁA�Z�L�����e�B�[�R�[�h��o�^���ꂽ���A�h��g�ѓd�b�ԍ��ɑ����ʂ��o�Ă���̂����A���R�Ȃ��������ƂɂƂ��Ă͐捏���m�Ȃ̂ŁA�������Ă����ɔނ�͂��̃Z�L�����e�B�[�R�[�h�����łɉ��x���\�����Ă��āA�l���Ώ����n�߂����_�ł̓Z�L�����e�B�[�R�[�h���͉�ʂɓ����Ă��u��莞�Ԃł̐��������p���Ă���̂ŗ��p�ł��܂���v�Ƃ������b�Z�[�W��������Ă��Ȃ��Ȃ��Ă���B 24���Ԍo�ƍē��͂��\�ɂȂ�悤�Ȃ̂����A�Ɛl�͂�������炩�̎���ŕs�\�ɂ��Ă���͗l�B �Ȃ���A�̗���ɂ��Ă���ȂɊm�M�������ď����邩�Ƃ����ƁA�l�͎�����3���O�ɂ�Facebook��������ꂽ���炾�B ���̂Ƃ��͏�����Ƃ��������������悤�Łi���Ԃ�Facebook���ɉۋ����[���ŁA�F���Ă���F�B��1����ł��邱�Ƃ�m�����̂����R���Ǝv����j�A�Z�L�����e�B�[�R�[�h�ɂ���ĉ������Ă����B ����Ȃɂ��Ƃ����₷���������A�Ώ��@�ɂ��܂�ɂ��s���������i�Ƃ�������������ƂɌ����ꂵ�Ă���Ƃ�����������jSNS���A�����I�ɖ{���o�^���`���Â��Ă���̂ŁA���ŕ��������Ƃ������ς�����Ԃ�Ƃ������A�D�ɂ͗����Ȃ��Ƃ������c�B �܂��ABigo��2�x�̔�Q�̗����Ɋւ���Ă��������Ƃ̉����ł���B �V���K�|�[�����̂��̃A�v���́A�������O�C���ł��Ȃ��Ƃ��������ւ̑Ώ�����{�I�ɕ��u����B ���[���ւ̕ԐM����Ȃ����A������ꂽ�A�J�E���g����Ă����̃A�N�V�������Ȃ��i���������{�^���������Ă��A���ꂪ�ǂ̂悤�ȓ��e�ɂ����̂���q�˂鍀�ڂ�����邱�Ƃ��Ȃ���A�u���M���܂����v�Ƃ������b�Z�[�W����\������邱�Ƃ��Ȃ��j�B �A�J�E���g�����Ԃ����Ƃɐ��������l�����l���m���Ă��邢�邪�A���̒N����Bigo�^�c�҂Ƃ̂Ȃ��肪�����ď��������߂邱�Ƃ��ł������߂Ɏ����ɑ������Ă���B ���ہA�����ᔽ�����Ă��Ȃ��̂ɁABigo�^�c�҂�m�l�ɂ����Ă��郆�[�U�[�Ƃ�����Ƃ�������̍s���Ⴂ�������������ŗ��p��~��H������l���A�l�͉��l���m���Ă�B �v����ɁA�g�т����E�������D��E���Ή��Ƃ������A�W�A�̌x�@��������͎҂Ȃǂ̑g�D�ƉZ��Ȃ̂ł���B �u�^�C�ݏZ�̐g�ɂ͌����ꂽ�\�}������䖝���₷�����낤�v�Ƃ��������ǎ҂̕��������邩������Ȃ����A���ی����ꂷ���ĖO���O�����Ă���̂ŁA�l�b�g�̒��ł܂ő����������͂Ȃ��Ƃ����̂��{���Ȃ̂ł�(�G�L�́M) �֗��Ȃ����ɁA���ꂪ�Ȃ��Ƃł��Ȃ����Ƃ��N�X���B���Ă���l�b�g���p�B �����A�v���C�o�V�[����K�̃Z�L�����e�B�[�́A�l�b�g�Z�p�̊v�V�Ɣėp���ɂ����Ԃ�Ȍ�������Ă���B �₪�ĖK���IOT�Љ���A�l�����͖{���Ɏe��Ă����̂��낤���H �Ƃ�Ԃ̌����A��s������A�p�X�|�[�g���A�d����̂قƂ�ǂ̂��Ƃ��A���ꂩ��͌g�ѓd�b������ɑ�����̂����Ɏ����ƂɂȂ�͂����B ����炪�����Ȃ����҂̎�ɗ����Ă��܂��\�����Ⴍ�͂Ȃ��댯�ɎN���ꂽ�܂܁A�u��������Q�ɑ����܂���悤�Ɂv�Ƃ������ׂ��F��̐������𗊂�ɕ�炷�����c����̓C�W�������Č��ʂӂ������N���X���C�g�̂���悤�ɂ������肾�B ���N�̃o�����^�C���̃M�t�g�́A���낢�l�����̓�������̌������Ă��ꂽ�A�����茘�����b�Z�[�W�������B |
 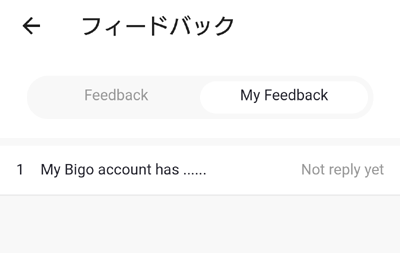 |
�Q�O�P�V�N
 |
11��10�� 2016�N10��13���A���[�}9���E�v�[�~�|���������������ꂽ�B �����č��N10��26���ɉΑ��̋V������s���A���������͗܂ƂƂ��ɕʂ��ɂ��B �v�[�~�|������������������ȐM���������N�ł��邱�Ƃ͂悭�m���Ă��邱�Ƃł���B �������A���̈̋Ƃ��ǂ̂悤�Ȃ��̂ł������̂����܂Ƃ߂ċL�����T�C�g�����邱�Ƃ͂߂����ɂȂ��B �����ŁA�����₩�Ȃ��炱���ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃɂ����B �E1973�N�F���̓��j�������ł̍��Ɗ�@���� �E1992�N�F�Í���5�������ł̈ꎞ���{�J���⍑�Ɗ�@���� �E2003�N�F�^�C�̃J���{�W�A��g�ٖ\������É� �E���W�I��ʂ��Ă̍ЊQ�~���i1962�N�̑䕗��Q�~���������L��)���玩�R�ЊQ��Ўҋ~��c�̐ݗ� �E�u�����m��o��(�Z�[�^�L�b�g�E�|�[�E�s�A���j�v�̒� �E���Ə��̒n�����@�ƁA���̏��n��̐B�Y���Ɓi���C�����E�v���W�F�N�g�j �E�T�C�A���E�Z�����g�ȂǍ��c���� �E�l�H�J�̌��� �E��nj��̎E�����֎~ �E�W���Y�ɂăr���{�[�h�E�`���[�g�Ƀ����N�C�� �E�A�W�A���Ƀ��b�g�ŏo�� �E70�N4�����ɓn��݈� �E���E�ō��̎��Y���^�C�������ێ� �E������ʂ��ă`���N���[���Ƃ̖��_���� |
| 2��8�� ���̂Ƃ���HP�ɕ��͂������@��߂����茸���Ă��܂����c�B �T�{���Ă���Ƃ�������܂łȂ��ǁB ����̒���SNS�̐Ȋ��ŁA���͂������~���E���M�������~���͂�����ŏ�������Ă���B �Z����M��SNS�ŁA�������̂͂�����ŁA�ƍl���Ă������A���́u�������́v������ɖl�̒��ŏ�������Ă䂩�Ȃ��B �g�V�̂����H ������A���������Ă��܂�����܂ł��ˁB �ł��A�����Ƌ�̓I�ł͂����肵�����R������B ����̓Y�o���A�����A�ł���B ����A�W�A�ِ̈��Ƃ������Ƃ��ɁA�o�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����i�������Ȃ������K���I�j�B ����́A���C���^���邱�Ƃ͂ł��邾�������邱�ƁA���B �^�C�ł͎d�����������Ƃ��Ă�������Ƃ������ԂɘA������肠���āA����ւ̕ς��ʎv���������Ȃ���A�����̐g�̌������ؖ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��i�d�b�����Ȃ��Ă��������̂̓o�C�N�̉^�]�����f��قɂ���Ƃ����炢�ł���j�B ���{�l�ǂ����Ȃ�u�ނ�݂ɕ��C���^���p��I�悳���邱�Ƃ̕����p���������v�u�����ɂ�����ɂ��p�[�\�i���Ȏ��Ԃ̗]�T���K�v���v�Ƃ������o���������낤���A�^�C�ł͏���������ł����Ƃ����قǂ��킢���q�Ԃ�̂��f�t�H���g�ŁA�u���Ȃ��̂��Ƃ��D�������炠�Ȃ��̍s���̂��ׂĂ��C�ɂ������ĐS�z�v�Ƃ����q�ǂ����ۂ������ŁA�j���͊Ď����ɒu�����B �܂��A�l�̍Ȃ̓^�C�l�ł͂Ȃ����A�K�v�ȏ�ɂ��܂�������ԓx��ޏ����g���D�܂Ȃ����Ƃő傢�ɏ������Ă���̂����A����ł��E���F�B�W����̉e���͂͐�傾���A���������^�C���C���i�Ȃ̏o���j�̓^�C���̐e�ʂł���B ���f�͋֕����B ����HP�ł̓^�C�̂��ƁE�A�W�A�̂��ƂȂǂɂ��Ă��ꂱ��ƒԂ��Ă����B ���ǁA�Ƃ��ɋx�����Ζ����ԑт����݂��ɈႤ�߂���̖l�����v�w�́A�O�H�ȊO�̖ړI�łǂ����ֈꏏ�ɏo�|����@��قƂ�ǂȂ��B �����Ȃ�ƁA���s���͂��߁A�V���b�s���O�E�Z���^�[�������U����A����I�ȃ^�C�̕��i�ɗn������łǂ����֏o�����邱�Ƃ��قƂ�ǂȂ��Ȃ��Ă��܂����B �ЂƂ�łǂ����֏o�������Ƃ��Ă��A�]�v�ȑF��������邽�߂ɂ��A�p�����ς߂������ƋA���B ����ɁA�o�C�N�������ƂƉ��y�����ɂ̂߂荞��ł��邱�Ƃ��A�܂Ƃ܂������͂��������Ԃ����߂Ă��邪�A��������͌����Ƃ�����x�̊W������B �o�C�N�����̂͂��������A��l��炵�̃������[���E�}���V��������̈����z�����l�����Ƃ��A�ꏊ���ǂ��ł���ړ������₷���悤�ɂƂ������R���炾�����B �o���R�N�ł̃o�C�N�ړ��͊댯���\�������邩��A�܂��̓o�C�N�ɏ���Ă��đ��v�Ȃ̂��ǂ������m���߂�Ӗ����������B �����Ă����o�C�N�������n�߂Ă݂�ƁA������ʋ@�ւ��قƂ�Ǘ��p���Ȃ��Ȃ�A�l�̃^�C�E���C�t�͂܂��܂��p�[�\�i���Ȋ��ɃV�t�g�����B �܂��A���y�����͌����Ƃ͂܂������ʌ��Ɍ����邪�A�u�X�^�W�I�ɏo�����Ă���v�Ƃ����Ȕ��́A�ȂɂƂĂ��������Ă��炢�₷���ƍߕ��ł���B �����J�[�h��p�����Ă�����̏o�Ȃ����ƂŁA�l�͂܂��܂����y�ɌX�|���Ă����B ����A�W�A�ł܂Ƃ��Ȑl�Â�����������Ƃ����̂́A�����̗\���l�̎��R�̗D�揇�ʂ�������Ƃ������Ƃł�����B �����́A�ٍ��ł̍L���ʂĂ��Ȃ��R�~���j�P�[�V�����̉\�������A����𒆐S�Ƃ���l�ԃT�[�N���̒��ł�����x�������Ă悢�Ƃ����S�[�E�T�C���̌��������ɂ������݂��Ȃ��B ���ǁA�l�͂�������ݍ����_�ŁA�܂Ƃ܂������͂�����������������I���ƂɂȂ�B �����āA��������ԏd�v�ȃ|�C���g�Ȃ̂����A����������Ƃ��������I���ƂŁA�l�͂��ЂƂ�l�ł͂Ȃ��Ȃ����B ���Ƃ���MK�łЂƂ�^�C�X�L��H���Ă������A����ꏏ�ɂ��Ă���鑊��i����͉Ƒ��łȂ��Ă��A�b������₿����Ƃ����m�荇���ł������j���̉\���̒�����T�����Ƃ��Ă����A���̏�M�̃G�l���M�[���l�ɕ��͂��������Ă����̂��Ǝv���B �L���Ӗ��ŌǓƂłȂ���A�Ӗ��̂��镶�͂��������Ƃ͂Ȃ��Ȃ��ɓ�����̂Ȃ̂��B �ƁA���߂̂������ɂ��Ή��Ȃ̂낯���A���̕��͂̈Ӗ�������̂Ȃ̂ł������B |
 |
�Q�O�P�U�N
 |
2��17�� �����u�W���p�j�[�Y�E�}���E�C���E�N�����e�[�v�v�́A�^�C�Ɠ��{�ł́u�F�B�ӎ��v�ɂ���2001�N�ɒԂ������͂���X�^�[�g�����B 15�N���o�����A������x���́u�F�B�v����n�܂��āA�l�ԊW�Ƃ����e�[�}�Ńo���R�N��炵�߂Ă݂悤�B �o���R�N�Ō����������y���j�b�g"Fractal"�̃����o�[A�͓��{�l�ƃ^�C�l�̗��e�����~�b�N�X�i�n�[�t�j�ŁA�ނ̉ƒ�߂�ƁA���{�ƃ^�C�̈ӎ����������Č����Ă���B �������ォ��A�ނ̉Ɓi���ƕ�炵�j�ɂ͉�����̉Ƒ����Ђ�����Ȃ��ɑ؍݂���悤�ɂȂ����B �u�K�˂�v�Ƃ������t��p���Ȃ������̂͂킴�ƂŁA��x����Ă������T�Ԉȏ�͔��܂��Ă����Ƃ��������F���Ȃ̂ł���B ���炩���߂ǂ�ȖʁX�����܂ő؍݂���̂��ȂǁA���{�l�Ƃ��Ă͓��R�K�v�Ƃ����C���t�H���[�V�������قƂ�ǂȂ���Ȃ��܂܁A���������Ƃ��ˑR����āA�؍ݒ���������Ƃǂ������W�ɂ���l�ԂȂ̂����Љ��Ȃ��܂܂ł���悤�ȃP�[�X�������B ����ɁA�ނ̕�e�͉Ƃ��邱�Ƃ������A�������ނɂ��d���⎄�p�����邩��A�ނ̉Ƃɂ͉�����̉Ƒ��������Ȃ����Ԃ������ɑ��݂��Ă���B ���͖l�̉ł������悤�Ȉӎ��ł���A�ޏ��̐e�ʂ��o���R�N�ɗ��邱�ƂɂȂ�ƁA�l�����̐��Ƃ������E���[���ł��邱�ƂȂǂ��\���Ȃ��ɏh���̕���ɂȂ��Ă��܂��A�d������A���Ă݂���N�������������ɂ���Ƃ������ԂɊׂ��Ă����肷��B �l�͎d�����^�����ł��邤���A�����E���[���ł͋M�d�i�̕⊮�ɂ�����̂ŁA���������P�[�X���Ȃ邾��������w�͂͂��Ă��邪�A����ł��s���̎��Ԃ�\�h���邱�Ƃ͓���B �^�C���ӂł́\�\�Ƃ������A�����炭���E�̑����̍��ł́A�Ƒ��E���l�Ƃ����P�ʂ����Ӗ��������ɂ߂đ傫���B ���Đl���s�҂ɂ₽��ƃJ�b�v�����ڗ��̂��A�����l�������W���d�����邱�Ƃ��A�悭�m��ꂽ�������낤�B �����Ă��̃^�C�ł́A15�N�O�ɂ������߂��悤�ɁA�F�B�ӎ��͒m�l�ɖт����������x�̑��݂ł���B ����̓��{�l�������Ă���F�B�Ƃ��������ӎ��̑����́A�Ƒ�������W�ɋz������Ă���B ���̓_�A���{�Љ�͐M�p�Љ�ƌ����Ă������ʂ��傫���B �ƂɖK�ꂽ�F�l����l�����Ɏc���Ă��A���̗F�l�͊�{�I�ɁA����ɃX�}�z��PC���J���Ē��g��`����������o�����J���Ă݂���͂��Ȃ��B �����������Ă������̂Ƃ���ɋA���Ă��闦�������B ��l�œ��������H�X�ŐȂɊ���u���ėp�𑫂��ɍs���Ă��A�߂��Ă����炻���ɂ����Ɗ����������g���g���đ҂��Ă���B 1970�N�キ�炢�܂ł̓��{���ƁA�ƂɎ{�������ɊO�o����ƒ�����������B �u�������Ƃ����ꂽ�瑊��͂ǂ��v�����낤�H�v�Ƃ�������̐��ʂ��Ǝv���Ă������낤�B ���������ꏊ�ł́A�F�B�����Ӌ`�͑傫���B �v�t���ɂ��鑽���̎�҂����͉ƒ����l�����A�F�l�W���瑽�����w��ł���Ɗ����Ă��邾�낤�B �������A����ȓ��{���O���[�o�������܂߁A�������ϗe��]�V�Ȃ�����Ă���悤�Ɍ�����B ���̌����̈�͂����炭�A�����N�̊��ω��ɂ���B �ŋ߂̗F�l�W�͔��Ɋɂ��B �ȑO�Ȃ�v���N���̖����ŁA���݂Ȃ�LINE��SNS�̌q����̐��Ōq���Ƃ߂��Ă���ꍇ�������B ����̃C�W���ɂ�LINE����O����邱�Ƃ��������ƂɁA����͂悭����Ă���B �����A�q�ǂ������̃R�~���j�P�[�V�����͂��N�X���ނ��Ă���͓̂��R�Ƃ����Γ��R�ł���B ���e�������̂����s���葽���̑�l�Ƃ̐ڐG���x������悤�ɋ��炳��A�w�Z�����̑��݈Ӌ`�ɗh�ꓮ���ĐM�p�������A�u����ꂽ�����N�v�����������M���ւ���r��������l�����Ԓf�Ȃ�����A�u�I�^�N�v�Ƃ����̍��ɂ������Ă�̂悤�ɋ�̓I�ȏꏊ�ɂ��ɂ��������ނ��Ƃ��Љ�I�ɗe�F����A�q�ǂ��̌�������l�̂�������|�I�ɏ����ĕۏႳ��Ă��錻����{�B �������瓱���o�����̂́A���l�Ƃ��a瀂̌o�������Ȃ��A��������邽�߂ɂ����ȉ\����������Ƃ��w�ю���Ă���q�ǂ��̎p�ł��낤�B 60�`70�N�O��̊w���^���������̓��_�E�c���̕p����ӌ��̈Ⴂ�̕��������̏ƁASEALDs�̎������u��̓I�ȖړI�������ł���Ίɂ��q�����Ă�����Ƃ���������̈Ⴂ�͖��m���B �������āA���{���l�Љ�̓����ɂȂ����Ƃ������邵�A�ƒ���ɂ��遁�q�ǂ������Ƃ����Ӗ��ŃO���[�o���������Ƃ�������i�C�O�ł̎q��Ă͉��X�ɂ��ĊÂ��j�B ���{�̗F�l�����́A�Ԃ̑��l���m�������ɂ��ĐM�p��������悤�ɂȂ邩����������A�M�d�Ŋm���ȕ��@�_���Ɗ�����B �Ƃ��낪�A���̓��{�ł͂��̍��ꂪ�傫���h���Ԃ��A������d����邽�߂̒P�ʂł���͂��̉Ƒ��̔�d���ȑO��蔖�炢�ł���B �������ɁA��ꂽ���炾�Ŏd������A�����ł̐e�ʂ��҂��Ă���悤�ȃ^�C�ł̐������y�ł͂Ȃ�����ǂ��A���̃V�X�e���Ɂu�e�ʂȂ���C���˂Ȃ��ɂ��������v�Ƃ����p���ɂ͋����l�b�g���[�N�������݂���B �܂��A���ٍ̈��̒n�Ŋm���ȗF�l�W�W�����ێ����Ă������߂ɂ́A���łȈӎu���K�v���B ���ꂪ���g�̐l�ԊW�ς�b���Ă��鑤�ʂ�����B �X�g���X�t���[��ڎw�����Ƃ���p���E��Ђ�l�ԊW�ɗ��ߎ���Ȃ����ȍm�芴�̋����l��`�E�l�Ԃ̗~�]�ɑ��ď_��ȐS�݂̍���ȂǁA���{�l���^�C�Љ��w�Ԃ��Ƃ͑����B �܂��A�^�C�l�ɂƂ��Ă��A�������≿�l�ς����L����Љ�̈��萫�E�Ƒ��Ɨ����ɕΏd���Ȃ��l�ԊW�E�i�����������b�g�[�Ƃ��镗���ȂǁA����������K���Ăق������Ƃ͎R�قǂ���B ���������̂ǂ�������A�}�C�i�X�ʂɂ����ĎႢ����𒆐S�ɋψꉻ�����l���������n�߂Ă���̂͂ǂ��������Ƃ��B �����炭�A�o�ώЉ�Ƃ������̂͂��������ψꉻ�ƃZ�b�g�ɂȂ������i�Ȃ̂ł��낤�B ���ꂪ�؋��ɁA���E���̐V���������͂ǂ�������悤�Ȃ̂���Ɩ��@���Ȋ�����Ă���B ���Ȑ������������ł͂Ȃ����A�l�炪���̎�����Ă������߂ɂ́A�l�͈�x�͑c�����o��ׂ��Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B �g�������đc���Ƒ؍ݍ��̃_�u���E�X�^���_�[�h���A���̍��ق����ł���ꂵ�肵�Ȃ���A�����̕d���ǂ��ɉ��낷�̂��Ɏv�������炷�A����ȓ��X����Ȃ̂ł͂���܂����B ���̓_�ň�A�^�C�����{�ɗD�悵�Ă���̂́A�^�C�Љ����ȑ����А����_��Ɏe��Ă��邱�Ƃ��B �����c�O�Ȃ̂́A�e��͂ł��Ă��w�т����Ȃ��B �����ł��A�w�т������e��͂��Ȃ����{�Ƃ͐����ł���B �����Ŏv������̂́A�u�w�Ȃ�����e���]�T���ł���v�A���邢�́u�e�ꂪ�ł��Ȃ�����s���Ŋw�ԁv�Ƃ������ƁB �������������̕����́A���������g�̌������u���ē���ɕ������Ԃ����Ă���B ���̂��Ƃ��������͂�����x��������Ǝ��o�����������ɗ��Ă���̂��ƁA�����v���ĂȂ�Ȃ��̂��B |
|
 |
�Q�O�P�S�N
| 9��14�� �����O����u��҂̘_���Ɏx�z���������{�Љ�v�ɂ��Ă��ꂱ��l���Ă���B ��҂���҂ł��邱�Ƃ�i���悤�Ƃ���A����_���܂���ɗ����Ƃ������Ȃ�B ��҂��~�ς���邽�߂ɂ́A�������������������W����Ă��邩�Ƃ��������ɗ����������Ă��炤�K�v�����邽�߁A��ɑi����K�v�����������炾�B �����\�Ŕɂ���A�K�R�I�ɂ��̎v�z�͎��Ȓ��S�I�ɌX���B ���������̓��{�Љ�̖�����ł����匹���̂ЂƂȂ̂ł͂Ȃ����H �������́u���҂̗��_�v�ł������悤�Ȃ��ƁB ���҂����Ђ�U�肩�����Ƃ��A�X�e�C�^�X����邽�߂����Ɏ��Ȓ��S�I�Ȏ��_����邱�Ƃ͉��X�ɂ��Ă���B ������A���{�l���C�O����^�����Љ�I�Ȑߓx�́u�ꉭ�����Y�K���v�ƌĂꂽ���オ���グ�����@�Ȃ̂��Ƃ��v���B ���҂ł���҂ł��Ȃ��l�X���s���s���̂�����x����ɔ[�߁A����ł��i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɣ����������𐢂ɖ₢�A�������Ƃ������̃t�B���^�[��ʂ��Ďv�l��~�����ɎЉ�̍\�����ƂȂ��Ă����ƌ�����B �������A����͐l�X�𒆎Y�K���ӎ��ɂƂǂ߂Ă͂����Ȃ������B �����ŁA��҂Ƌ��҂̍��قɂ��Č��Ă݂����B ���҂͋����ւ̃v���C�h�ƌ��͈ێ��̂��߂ɁA���҂Ƃ̘A�g�ւƔ��W���A�̖ʂ��l���邱�Ƃ��������A���(�̂ӂ������҂���)�́u�����͎���������́v���Ƃ����F������A�Ȃ�ӂ�\��Ȃ��Ȃ�X��������B ���̍\�}�̓^�C�Ō��Ƃ����قnj��Ă����B �܂�����ꎞ�I�ɌR���ƂȂ����^�C�ł́A�R�������ł͂Ȃ����Ȃ������e������܂����v���������A�Â����܂ŊJ���ȂǁA�_�����ɖ�N�ł���B �Η����Ă���^�N�V����h�́A�_���ɂ�T���������������ė^����ꂽ���̂��������吭�����ƌ��������B ���҂͂��̂�����D�����Ƃ���R�n�ɂ�������������K�v�����邽�߁A�A�g���������A�����L�[�v���邽�߂ɉ�������悢�̂����l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �������A���w�c�̂ǂ��炩�ɑ����閯�O�̑����́u�ǂ��炪�����������v�ɂ���Ď��g�̕[��A���̉��𐭎��I�ɊҌ����Ăق����Ƃ����|�C���g�ł������������悤�Ƃ��Ȃ��B �n���͂������ɔ��ɏd�v�Ȗ�肾���A���l�̘b�Ɏ����X���悤�Ƃ��Ȃ���Ȃ��́A�p���ĐS�܂ŕn���ɂ��邱�Ƃ��܂��������悤�Ƃ��Ȃ��B �b����{�ɖ߂����B �V�����Љ�l�ɂȂ�����҂������u�g���Ȃ��v�Ƃ����b���A�{���ɂǂ��ł������B �E��ɂ������Ă����d�b�Ɂu�ǂ���l�ł����H�v�Ƃ����ׂ��Ƃ�����u���l�ł����H�v�Ɛu�����Ƃ������b�����邪�A�����œd�b������M�����邾�������B ���́A���̎�҂������M�������Ă��邱�ƂȂ̂��B ���w���⒆�w���Ɂu��l�ɂȂ肽���H�v�q�˂�ƁA�u�Ȃ肽���Ȃ��v�Ƃ������������|�I�ŁA���R�́u�߂�ǂ�������������v�������B �܂��A�u��l�ɂȂ肽���v�Ɠ������w�����A���̗��R�ɂ́u���������R�Ɏg���邩��v�u�e�ɑ�������Ȃ��čςނ���v���قƂ�ǂł���B �����ɑ����I�Ȋ�]��l�ԊW�̊������߂�̂ł���A�ǂ��ɔނ�E�ޏ��炪��l�ɂȂ�K�v��������̂��낤���H �����Ȃ�Ύ��Ԃ������⍓����Ɏ��g���^�ы����Ă������o�����c��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B �u���������܂ꂽ�Ƃ�������{�͌o�ϓI�ɉ��~���Ă��āA�o�u����m���Ă��鐢��ƈႤ�͓̂�����O�v�Ƃ������ɂ܂��Ƃ��Șb����҂��畷���@��������B �Љ�㏸�u���������Ă���A���������̉e�����邱�ƂɊԈႢ�͂Ȃ��B �����A���̌��t���u��Ґ錾�v�ł����Ȃ��Ȃ�A�u�����g�v�Ƃ̍��͊J�����肾�B �o�u����ʉ߂����l�X�́A����ł��u���n�v�Ƃ����C���[�W�����������납�狳����Ă����B �J�l��m�ɂ�����肷����Ɛl�ԂƂ��Ă��������Ȃ邩��A�����ƃo�����X�����Ȃ����Ƃ������b�Z�[�W���Љ�狂�ݎ���Ă����B ���K�I�Ȗʂ�����߂��ڂŎЉ�߂���肾������A���ꂱ���^�C�ɈڏZ�������������B �����ł͉�Ђ��|�Y���Ă��A�u��x����Ă݂��������v�ƕ\����P�����ĕv�w�Ƃ��ǂ�����������悤�Ȑl�X�������ς�����B ���̎Љ��w�тƂ����̂͏��Ȃ��Ȃ��B �l���ŋ߂̎�ҎЉ�l�ɂ����Ĉ�Ԗ�肾�ƍl����̂́A�̂̂Ȃ������̎咣�ł���B �o���Ă���ȏ�A�������o�ĕ�����������������͓̂�����O�ŁA����͎d���̂ł��Ƃ͊W�Ȃ��i�X�L���͒P�Ɏ��Ԃɂ���Ē~�ς����Ƃ����̂���ȗ��R�j�A�E��ł̐l�ԊW�ɂ����Ă��V�l�����玩���ł͂Ȃ����͂����肵�z�����Ăق����Ƃ����A���̂悤�Ȍ����ł���B �������l�ԊW�ɔM���Ȃ�Ȃ��ނ�E�ޏ��炪����𐺍��Ɏ咣����킯�ł͂Ȃ����A�����̖��ɓ˂������邽�тɂ��̌��t�̗����畷�����Ă���̂́u�����v�ł���B �����������������X�L�����l�ԊW���A���ݏo���͎̂��g�̓w�͂ɂ����̂Ȃ̂��ƍl���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂́A�ǂ��������Ƃ��낤���B ���̗��R�̈�͕������Ă���B �ƒ낪�A�w�Z���A�Љ�ނ�E�ޏ�����Â₩�������炾�B ���̓��{�͎q�ǂ���P�Ȃ��҂Ƃ��������悤�Ƃ����A������ی��^���������Ă����u��艻���Ȃ��v�Ƃ����x���ɂ���ĕ������������Ă���B �Љ�l�ƂȂ��Ă��̎x�������g�őg�ݗ��Ă�ƌ����Ă��A�o���ǂ��납�����������z���Ȃ�����A������敪���ĕېg�ɑ���B �������Â₩���Ă����ʂ邢�W�Ƃ������̂������ɂقǂ��₷�����̂��Ƃ������Ƃ�m��Ȃ��B �����āA�������������̐Ǝ㐫��⊮���悤�Ə��ɖ�����悤�Ƃ���B �����ř��邱�Ƃ̂Ȃ���A�܂�����ɔނ�E�ޏ���́u�̂̂Ȃ������v�ς�������B �A���`�������邱�Ƃ͂�����ł��ł���B �����A���̉��������Ƃ�Љ�ɉ����t���āA�����Ȃ�̓w�͂����Ȃ��Ȃ�A���͌`��ς��ČJ��Ԃ���邾�����Ƃ������Ƃ��A�u��l�v�͂����Ɠ`���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B �����܂ł��Ȃ��A�u�ނ�E�ޏ���v�ɂ���ȎЉ��p�ӂ����͖̂l������l�ł���B ���{�Љ�o�ϓI�ɏ㏸���Ă��Ȃ����Ƃ��A���Ƃ�Љ�q�ǂ����҂ɏ\�S�Ȃ��̂�ۏ�ł��Ă��Ȃ����Ƃ��A�l��͎��̐���ɉ���`���Ă�����̂����A���낻��^���ɍl�������������B �p���n���ł��A�e�̊��҉ߏ�ł��A�v���C�o�V�[�̐N�Q�ł��A�]�v�Ȃ����b�ł��Ȃ��z���������āA�{���ɓ`�B���ׂ����Ƃ����I���Ď�n���Ă������ƁB �l������������̂ł͂Ȃ��A�����ōl������悤�ɂȂ��Ăق����Ƃ����肢��`�B���A���̐���ɓ`���Ă������ƁB ������A���̓��{�Љ�͂��܂�Ɍy���������Ă����܂ł���Ă����B �����ɂƂ��āA�͐����̌��_�Ȃ̂��B |
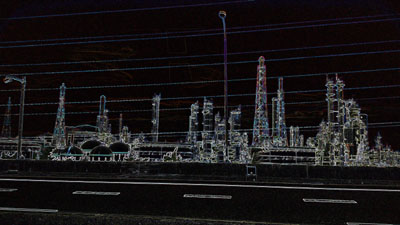 |
 |
1��27�� �܂���������Ȃ��A�����{�f���ɂ��ď����B 2�����قǑO�Ɂu�f���͂�������v�Ə������C�����ɋU��͂Ȃ����ǁA�݃^�C�҂ł���ȏ�A�����Ēʂ�Ȃ��f�����̃`�F�b�N��ʂ��āA��͂���{�̕Ƃ̋����������A��l�ł������̐l�Ԃ������������Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����C�����������Ȃ��Ă������炾�B �܂��A���{�ł̕��u�C�O�댯���v�Ɋׂ肪���ł��邱�ƁB �L���ȊC�O���s�K�C�h�u�b�N��ʂɂ������邱�Ƃ����A���{�Ƃ������͍���A�u�댯���Ƃ��������o���Ă���Ȃ���������A�s���̎��ԂɊ������܂ꂽ�̂͂��Ȃ��̂������v�Ƃ����ނ̃N���[�����ɓx�ɋ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ɂȂ�A�����Ɂu�댯���Ɛ����������̔����ʂ⎋�������オ��v�Ƃ��������̃Z�I���[�����܂��āA�傰���Ȋ댯����p���邱�Ƃ������Ȃ肷�����B �������ɂ��̂Ƃ���̃o���R�N���ӂł͔����������┭�C������������悤�ɂȂ������A����ȏ�ɁA����ǂ������W�J���҂��Ă���̂��S���\���s�\�ł���W�J�������Ă���A�l�͂����Łu�債�����Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ����ԓx�������������C�͂Ȃ��B �����A�����{��k�Ќ�̌������ɂ��͂�ꕔ�̐l���������ł����A��莋����Ă���閧�ی�@�ɂ��Ă��ӎ��̂Ȃ��������������{�̂�����߃��[�h�̕����A�l�ɂ͂���ۂǕ|���B �ɂ����̂�ɂ��Ɗ����邱�Ƃ͋��낵�����Ƃ����A�ɂ��͂��̂��̂�ɂ��Ƃ��v��Ȃ���������ۂǖ�肪�傫���̂ł͂Ȃ����B �ɂ����̂ɂ̓A���e�i�菄�点�A���ӂ����Ƃɂ���ď��Ȃ��Ƃ��h��Ԑ�����邱�Ƃ��ł���B ���������ňӎ��ł��Ȃ������ɐi�s���Ă���a�C�́A�C�������Ƃ��ɂ͂�����x��A�Ƃ������Ƃ������B ��ʎ��̎��Ґ��̎���5�{�Ƃ��Ȃ閈��90�l���̐l�X�����E���Ă�����{�̍�����肪�����悤�ɁA�l�̓�������Â��ɕ��H������S�̕a�̖������ǂ����ē��{�ł͂����Ɛ����Ɋ댯���Ƌ���Ȃ��̂��낤���B �f���Ŗ���90�l�̐l������ł�����A����͂��͂����ł���A���{�l�ȂǂƂ����ɋً}���߂ł���B �����ł��낤�ƍ��O�ł��낤�ƁA�l��͓����ł��邩����A�����̊댯�Ɨׂ荇�킹�ɐ����Ă���B ������ǂ��蔲���Ă����̂��ɔz�����Ȃ���A�����₩�ȍK������邱�Ƃ��܂��A�����E���O���킸�l�炪�ڎw���Ƃ��낾�B ����Ȃ�A���ܕ��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A�����{��k�Ѓj���[�X�Ŗ��ߐs�����ꂽ�ꎞ���̃e���r�ԑg�Ґ������l���̎����҂��m�C���[�[�Ɋ��������Ⴊ�����悤�ɁA�s�������悤�Ȍ������܂��U�炷���Ƃł͂Ȃ��͂����B ���̈ӌ��͈ꌩ�A��ɖl���L�����u���ƂȂ��Ă͌������Ɉꕔ�̐l���������ł��Ȃ��悤�ȓ��{�v�ւ̔ᔻ�Ɩ������Ă���悤�ɂƂ��邩������Ȃ����A��肪�S�̍��������ɐ����邱�ƂƁA������h�����ӎ���[�߂邱�Ƃ͂܂������ʖ��ł���B �����Ŏ��̘b��ւ̓����_���������B �V���̂悤�Ȋ����}�̂ł̎��ʂ̐����j���[�X�ł̕������Ԙg�����邱�Ƃ��A�l�b�g���ł͕��������₽��ɑ����ƌh��������Ԃɂ��邱�Ƃ����m�Ō����A���̔����{�f���Ɋւ�����_�̎w�E�́A���̃j���[�X�̒��ł͒f�ГI�ŁA�������قƂ�ǐG����Ă��Ȃ�����������B �f�ГI���Ƃ����_�́A���̖��ɊS�������Ă���l�X���j���[�X�E�\�[�X�𑝂₷���Ƃɂ���ĕ₢�A�X�ɑ���������悢�b�Ȃ̂ŁA�����ł͂��܂�G����邱�Ƃ̂Ȃ��b��������Ă݂����B ���ɂ͕Ɩ��łقǑ債�����Ƃ̂Ȃ��b����܂܂�Ă��邪�A�������Љ��̂��܂����̋L���̈Ӌ`�ł�����Ǝv���̂ŁA�������������������B �����āA����ȊO�̈Ӗ��ŁA�ǂ����Ă����������Ȃ���Ȃ��̂����l�@���Ă݂����B ���@UDD�i�e�^�N�V���h�j�̃f���ł͒��ږ\�͂��U�����悤�ȕ������̂�ꂽ���A����̔����{�f���i�ȍ~�A���̃f���̕M���哱�c�̂ł���PDRC�̖��̂�p����j��2008�N��PAD�f���͂�����x�̓����͂��s���͂��A�ł��邩����\�͂ɑi���Ȃ��f����W�J���Ă���BPDRC�̓f���s�i���Ɍ�ʐ����܂ōs���Ă���B�������A���{�̕ł͗��҂̍����C���[�W�ł��Ȃ��B ���@�����̌��Ђ��ۏႳ��A���O�ɂ������Ɏx������Ă���^�C�����ɂ����āA�^�N�V�����͂͂��̍\���ւ̑R���͂ł��鐫���������B�܂��A�R�̎w���ɂ͉����̈ӌ������f����Ă���A�^�C�x�@�̂悤�ɓ��t�̎w���œ����g�D�Ƃ͑S���ʕ��ƂȂ��Ă���B�܂��A������������܂ł̗����R�l����y�o����邱�Ƃ������A�R���̂��̂����ǂɂ����ă^�N�V���h�ƃ��C���@���W�ɂ���B�����������Ƃ���AUDD�ɂ͕����������Ȃ���Ȃ�Ȃ������݂���B����APDRC�ɂ͌R�≤������̃t�H���[�����҂ł���Ƃ����w�i������B ���@���{�ł͂ǂ��瑤�������ɏA���Ă��A���̌�̗����W���X���[�Y�ɃX�^�[�g�����邽�߁A�ł���ǂ��炩����Ɍ����ꂵ�����Ȃ��B�W�e�Ђ����l�ł��낤�B ���@�����{�^���w���҂����͖����`����ނ����A�I����ے肷���������ł��o���Ă���Ƃ����͐��������A�^�C���͂邩�Ɉ��肵�Ă���A�����I�Ɉ��肵�Ă���Ƃ������S���̂���V���K�|�[���͎�����}�ƍُ�Ԃō��̈���ƌo�ϓI���W��}���Ă����B�}���[�V�A������Ɏ��������݂���B�o�ϐ����Ɋւ��ẮA�ӌo������̑�p��p�N�E�`�����q�i�p�����j����̊؍��A�X�n���g����̃C���h�l�V�A�A�}���R�X����̃t�B���s���Ȃǂł́A���������̎�@�ň��̐��ʂ��グ�Ă���A�ߔN�ł͍ĕ]���̑ΏۂƂȂ�@��������B�܂��A�ŋ߂Ƃ݂ɓ��{�ł��]���̍����u�[�^���͈ӎ��I�ɔ�������Ԃ�ۂ��Ƃœ`�������⎩�R�����쎝���č������K���x�����߂�w�͂����ۓI�ɂ��F�߂��Ă���B�����`�����`�Ɩ{���Ɍ������̂��낤���H ���@�^�C�̍������[�ł͓��[�̂��߂̔��������Ȃ����҂�ɍs���Ă���A����ɑ���L���ґ��ɍ߂̈ӎ������Ȃ蔖���B�܂��A���O�i��ɔ_���𒆐S�Ƃ����n���j�̓R�����Z���X����玩�g�̒��ڂ̗��v�����Ă���鐭�}����ɍl���Ă���B ���@�^�C�����{���A�����J�̌�돂�ō��̂��ێ����Ă����ߑ�̗��j������A�����A�����J�̃v���[���X�͑����ɍ����B���̃A�����J�͖����`�Ɋւ��Đi���j�ς̂����Ől�ނ̌����_�ɂ�����ō��̃J�[�h�ł���Ƃ̎p�����^�����Ƃ��Ȃ��B�����EU�̑�\�I���������{�����l�ł���B���������`�̕���ɗ���������ɂ́A���������������邱�Ƃ������Ȃ���i���̎p���́A�h�~�m���_��ϐM���ĎЉ��`�Ƃ̓O��R����т����Ƃ�����펞��̎p���ƒʂ�����̂�����Ɗ�����B ���@UDD�̎x���w���^�C�k���E���k���i�C�T�[���j�ɂ��邱�Ƃ͂悭����Ă������A����̔����{�^���ɓ�������Ă���n���o�g�҂��암���瑽���o�Ă��邱�Ƃɂ��Ă̕����Ȃ��B�o���R�N�ȊO�ł͂���܂Ŕ�r�I�����Ă����n���ł���^�C�암�́A��������k����C�T�[���i���k�^�C�j�ɒD��ꂽ���Ȃ��Ƃ����w�i������B�������A�������v��L���Ă���Ƃ������Ƃ́A���{�Ƃ��Ă����������Ȃ����v�������Ă���Ƃ������Ƃł����邵�A����͖k���Ⓦ�k���̂悤�ȁu�_���ɍĕ��z�����߂���v�^���v�Ƃ����ڐV�����ēǎҎ̂悢�j���[�X�ł͂Ȃ����߁A�قƂ�ǖ�������Ă���B ���@�^�C�암�̓}���[�V�A�Ɛڂ��Ă���A�C�X�������k�������B2006�N�̃N�[�f�^�[�̍ہA�R�𗦂����\���e�B�E�u�������b�g�J���������X�����ł��������Ƃ��A�����������ԂƊ֘A���Ă���\��������B�A���n����h�����߂Ƀr���}�E�}���[�V�A���������Ă����C�M���X�ƃ��F�g�i���E���I�X�E�J���{�W�A���蒆�ɂ��Ă����t�����X�Ƃ̊ɏՍ��Ƃ��낤�Ƃ������Ƃł��L���ȃ^�C�́A���͊Ԃ̃p���[�E�o�����X�𗘗p���邱�Ƃɒ��������Ƃł���B ��͂�l��̓j���[�X����ʓI�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ������F�����Ă����������悢�B ���ɁA�����͂��ꂢ���Ƃ��������Ƃ������O�ɁA�݂��̐��͂��L�����邽�߂ɖژ_���������ē������̂ł����āA���̈ӎv�����������̂͂܂Ƃ��ȉ^�c���ł��Ȃ��y�U�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ͎����ł���B ���Ƃ����āA�l�b�g�L����Ђ��[����L�ۂ݂ɂ���̂��܂��A�\�[�X�Ƃ��Ċ댯���B �����A�������l�̏����Ă��邱�̕��͂����āA�ߓǂ݂��Ă�������������S���낤�B ���͂���Ԓf���Ȃ��A���̏��^�����܂����X�K���B ����ł��l��͎��������̐g����邽�߂ɁA�����Ȃ�̌�����ł����āA���ԂɑΏ����Ă����K�v������͂����B ���ꂪ�����炭����́u��v�Ȃ̂��B |
|
 |
�Q�O�P�R�N
| 12��3�� �����Ƀf���̂��Ƃ������̂��A�u�܂����v�Ƃ����C�����ǂ����ɂ���B 2006�N�̃N�[�f�^�[�i�^�N�V�����r�j 2008�N��PAD�f���i��`�E�{�Ȃǂ̐苒�j 2009�N��UDD�f���i�p�^���[�̃A�Z�A����c�̓P���j 2010�N��UDD�f���i�Z���g�����E���[���h�Ȃǂɕ��j �����ɁA2011�N�ɂ́A�����Ƃ͒��ڊW���Ȃ����̂́A�傫�ȍ^���������������B 2012�N�́A�v���Ԃ�Ɉ��肵��1�N���������A���̗��N�ɂ͂܂�����ȑ����ɂȂ��Ă���B �ȑO�̑���t����i�̎�l���Ȃ�A�ԈႢ�Ȃ����N�A�u�����v�ƙꂢ���ɈႢ�Ȃ��B ���̋C�����̒��ɂ́A�u�d���ɖ��f�������Ȃ��ł���v�Ƃ����o���R�N�����҂̖{��������B �����A������͂邩�����āA����͎��g�̋C�����������āc����A�����Ⴄ�A�S���o�ɂ������Ă���̂��B ���Ƃ��A�^�C�l�̗F�l�̉����A�@���r�������{�^���ɏo�����悤�Ƃ����Ƃ��A�F�l�́u����Ȃ�Ȃ��A�i���̃C�����b�N�������a�����邱�ƂɂȂ����Ƃ��́j�I���ɍs���Ȃ������́H�v�Ɛq�˂�ƁA�u�������̂�|���͓̂��R�v���Ɖ�����͕Ԃ��A���̒��ɂ͂܂������ނ̎���̓����͂Ȃ������ƁA����Șb��ނ̂��ߑ�������ɕ������B �F�l�̋C�����͂Ђǂ��悭������B ��������̉e��������̂��낤���A���̍��ł́u�P�v�Ɓu���v�̓_�������ς肵�Ă���A�u����́w���x�Ȃ̂ʼn����������Ƃ��Ă��������������Ȃ��v�Ƃ����ԓx�ƂȂ��ĕ\��₷���B ����ȂƂ��l�͌��܂��āA�q���̍��Ɍ���������̂̃e���r�ԑg���v���o���B �����{�������̌������̒��ɁA�����Ƃ����Ǝv�킹����̂�����B UDD�i�ԃV���c�����^�}�̃^�C�v���}�x���h�j�̃J�E���^�[�E�f�����̂قƂ�ǂ́A500�o�[�c���Ƃ�1000�o�[�c���Ƃ��̓����ړ��Ăœc�ɂ������Ă����A����̂悭�ۂݍ��߂Ă��Ȃ�����҂���ł͂Ȃ����A�Ƃ������̂��B ���̘b�͂��Ԃ�f�}�ł͂Ȃ��B ����܂łɂ������悤�Ȃ��Ƃ����풃�тɂ悤�ɂ���A�l�W�߂̂��߂̐l����W���A�l�̗F�l�̃^�C�l�����̂Ƃ���ɏo����Ă����̂��m���Ă���B �l�͋����ɂ��A2010�N5��23���̓��L�iUDD�f���ɂ��āj�ɁA�Ί�Ŏ��U��Ȃ���A�A���҂��ő���o�X�Ńo���R�N���o�Ă���UDD�Q���҂̃j���[�X�f���ɑ��Đ^���ɕ��𗧂ĂĂ������Ƃ��L�����B �����A���̏Ί�̗����ɂ́A�{���ɉ����Ȃ������̂��B �ނ�E�ޏ���́u�����ɂ��邾���œ����̂��炦�邨�������o�C�g��W�ɏW�܂����l�����v�ł����Ȃ������B �o�C�g�̘b�͓������m���Ă͂������A����ł�UDD�̐M�O�Ɋ�Â�����������l�������̂ł͂Ȃ����ƁA�ǂ����ł���Ȃӂ��Ɋ����Ă����B �ł��܂����������ł͂Ȃ��������Ƃ́A���̋A���o�X�̑�������U���Ă����l�X�̋����̂Ȃ��Ί炪�ؖ����Ă��܂����B �^�C�ł悭����E�͊��ɐZ���ꂽ�C�����ɂȂ����B �����A����ł����Ƃ͂����肵���̂́AUDD���W�Ԃ��閯���`�Ƃ͒P�Ȃ鑽�����̂��Ƃł����āA�����o�Ȕ_���̐l�X��M���邱�ƂɃX�|�b�g�Ă���̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��B �����A����ł͔����{���͂ǂ����Ƃ����ƁA����܂łɂ�PAD�i���V���c����UDD�c�̂����A���łɉ��U�j������Ă������Ƃ��J��Ԃ��āA�{�ōU�h����J��L���Ă���B �����̖ڕW�ł������^�N�V�����A���ɒ������鉶�͖@�̔p�ẮA�^�}���瑬�₩�ɍs��ꂽ���A�f���͐U��グ���������낷���ƂȂ��A�C�����b�N�����œ|���f���������{�^���ւƐ�ւ���Ă������B �v����ɁA�f�����͑I�����ʂőI�ꂽ�^�}���Ђ�����Ԃ����Ƃ����̂ł��邪�A�����2008�N��PAD�Ɠ��������B ���`�̂��߂Ȃ���͂��������ނ̂���ނȂ��ǂ��납�A�ϋɓI�ɖ��f�������āA���������ׂė^�}�ւ̃v���b�V���[�ɂ��悤�Ƃ������z�ł���B �Ƃ��낪����܂��A���̑I�����́A���[�ɃJ�l����T����Ă���̂ŁA���������s���Ȃ̂ł���B �������A�Ȃ����^�C�Ƃ������́A�[�̔��������e���Ď����܂낤�Ƃ��������ɂ͓����Ȃ��B ���̑���A���I�c���ȊO�́u�M���@�v�I�|�X�g��������ɐ݂��邱�Ƃ��APAD�͗v�������B �������Ȃ��Ɓu�^�C�̗ǐS�v�͂͂��炩�Ȃ��Ƃ����̂ł���B ���������C���͕�����C�����邪�A�ǂ݂̂������́A�J�l�ƌ��͂����܂�ɂ����ʂɖ��o�Ă���A�^�C��TV�h���}��������̍j�������Ȃ̂��B �����N�卑�ł���^�C�́A���ꂪ�����Ȃ�w�c�̍����ł����Ă��A�@�̉��ɂ���˂Ȃ�Ȃ��B �����`�]�X�̑O�ɁA�@�����Ƃł���˂Ȃ�܂��B ���̑b�ƂȂ�^�C�̌��@�́A1932�N�́u�V���������������́v�ȗ��A�X�����b�g�b����ɔ��z���ꂽ2007�N���@�ŁA����18�Ԗڂ̂��̂ƂȂ�B �A�����J�ɂ��f���𗧂ĂȂ����シ���ł����Ă�ꂽ1946�N���z�̌��@���Ŏ炵�Ă��鍑�̂��Ƃ��ǂ����Ǝv�����A���̘b�͒u���Ă����āA�Ȃ��������^�C�ʼn������������̂��Ƃ����A����܂����w�c�ւ̗��v�����j�������킾����Ȃ̂��B ����Ȍ��@�����@�����Ƃ̍����ł���ƁA�ǂ��̂��ꂪ�v���邾�낤���B �i�@���܂����Ȉʒu�ɂ���B �ǂ��]��ł����I���ł͈��|�I�ȕ[�c�����^�N�V���h�ɑ��āA�^�C�̌��@�ٔ����͗^�}���ጛ�Ƃ��ĉ�}��������A�I�����ʂ̖����錾��������ƁA�s���ւ̉�����J��Ԃ��Ă����B ���������A�������Ƃ������̂͂��̍��ł͌��O�����ł����Ȃ������A�W���b�W�̊�b�ł��錛�@�����̂悤�ȏ�ԂȂ̂ŁA�i�@�͂����܂Ŝ��ӓI�Ȉӎv����̏�ɂ����Ȃ蓾�Ȃ��B �����āA�����������c�̂��A�Ō�̗��݂Ƃ���̂͌��܂��č����ƌR�ł���B ���̕��Ƌ���A1992�N�̑��ʗ�������������@�̂Ƃ��ɂ͗��w�c�g�b�v�ւ̈ꊅ�Ŏ��Ԃ����E�����v�~�|�������ƁA2006�N�ɂ�����ꂽ�悤�ɁA�����Ɂu���s�v���݂���ƃN�[�f�^�[���N�����Ď��𐴎Z���Ă����^�C���R�B ���ǁA�N�����������̗͂����ŐM�O���т��ʂ����Ƃ��ł��Ȃ��B ����ς�ǂ����ǂ����߂Ă��A�ԉ��т����E�͂ɐZ��������Ȃ̂��B �����a���̃v���Z�X���A�Ă̒�A���������̗��v�D��ɐ�ւ��A���t��芴���������A���ӔC�ȓ������N����B ���̍��̃G�S�j�����͂�������B �ł��c�O�Ȃ���A�����������Ԃ͐��E���̃X�^���_�[�h�ł�����B |
 |
|
 |
 |
8��31�� ���ی����ɂ��āA�z��҂̋����Ƃ̊W����Ƀ}�C�i�X�ʂ��炲�Љ��L�����A�������̂ŁA����́A���ی����̂����Ƃ���ɂ��ď����Ă݂�Ƃ��悤�B �v�w�Ƃ��Ȃ�A�ǂ����Ă������܂��������Ȃ���ʂ͑����B �e�q���܁A�Z�팖�܂Ɠ������A�v�w���܂��܂��A����̂��Ƃ��悭�m���Ă��邩�炱���N����B �����Ƃǂ������Ă��邯��ǂ���Ȃ鑶�݂����炱���N����B ���肵�����ʂ̊�Ղ������āA�����ɂǂ����Ă�����Ȃ����l�ς̖��C�������邩��N����B �����𗠕Ԃ��A�����Ǝ��Ă͂��Ȃ��A���ʂ̊�Ղɏ������Ȃ��W�ł���A�߂����̂ǂ����̂����������܂͔������ɂ������낤�B �����A����ł͂��������A�Ƒ��W�͂��ɂȂ炴��Ȃ����A�v�w����l�ɂ��Ă��A���ʂ����y�䂪�Ȃ���Η����ɔ��W���Â炢�B �����A�����ō��ی����Ȃ̂ł���B ����Ɏ䂩��镔���Ɍl�I�ȑ������ւ���Ă���̂͑��肪�������{�l�ł����Ă��������Ƃ����A��������Փ˂̉Ύ�ɂȂ鎖������яo���Ă��Ă��A����Ǝ��������L���Ă���펯���̂��قȂ��Ă���ƁA���e�͈͂������ƍL����̂��B �v�w���܂̑����́A�ǂ���̌��������������������_�ƂȂ�B �������A����̏펯�������̏펯�ƈقȂ��Ă���ƂȂ�ƁA���������ǂ��炪�������̂��͐���ʖ��̒��ł���B �Ⴆ�A�l���ȑO�`�������Ƃ��A�Ȃ��Y��Ă����Ƃ���B ���ꂪ�厖�Ȃ��Ƃł���A�܂��͓{��������邪�A�����Ɠ`���邱�Ƃ��ł��Ă������A���t�̖�肪�����ɕ����яオ���Ă���B �l�ɂƂ��Ă��ȂɂƂ��Ă��^�C��͂��݂��̕��ł͂Ȃ�����A�b����ɂ��敷����ɂ���A���݂��Ɂu�`�B�������邱�Ƃ��܂��͑f���炵���Ƃ��悤�v�Ƃ�����{�����������āA���ꂪ�`�B�~�X�ƂȂ��Ă��d�����Ȃ��Ƌ����������������B �܂��A�l�̃P�[�X�͓��ꂩ������Ȃ����A����ł����g�ƕ��̈قȂ�z��҂Ƃ̊Ԃɂ͌���`�B�Ɋւ���p������g�ɂȂ邱�Ƃɂ��Ă͋O����ɂ���̂ł͂Ȃ��낤���B �������A�O��E�O�X��ƌ��y�����悤�ɁA����ɂ��掩�g�ɂ���A���ɕ�炷���Ԃ������Ȃ�ɂ�A���̎Љ�w�i���̂����������Ɗ����邱�Ƃ������Ă͂���B ���݂��ւ̗����Ɗ��ꂪ�[�܂邲�ƂɁA���ʔF�����`������Ă䂭�B �U�߂ɂ��扜����ɂ���A�u����v�Ƃ��������ł��ꂪ���̂��Ƃ��ʂ������悤�ȁu���^����v��������B ����ł��A����ɂǂ��܂ł̂��Ƃ����҂ł���̂��Ƃ���臒l���A�ٕ����̒��ň���Ă����l�ԓ��m�̊Ԃł͂ǂ����Ă������Ȃ邱�Ƃɕς��͂Ȃ��B ���{�l�ǂ����̕t�������́A����ւ̊��҂����邩�炱������x�������Z���Ȃ����ɃX�s�[�h�������̂����A����Ǝ��g�Ƃ̂�����Ƃ�������ɑ��Ă��_�o�ߕq�ɂȂ肪���ł���B ���̓_���ی����ł́A����ւ̊��҂͂��݂��̌X�̃p�[�\�i���e�B�[�Ɋ�Â��āA���҂��Ă��������Ƃ�����߂������悢�����Ƃɕ��ʂ���A�������҂ł��Ȃ������Ƀ��X�����悤�Ƃ��Ă܂Â��Ă��A�{��ł͂Ȃ�������ɗ��B �{��͂����܂ŃA�N�e�B���ȐS���Ȃ̂ŁA�t���X�g���[�V���������܂��Ă���܂��f���o���o���Ƃ��ė�������₷�����A���Ƃ����ǓƂȖ��͊��ɏP���邾���Ȃ̂ŁA�������s���J��Ԃ������Ȃ��Ȃ�Ƃ����A�Ȃ������̂������̂��킩��Ȃ�����ǁA�v�w�������~���Ȃ��̂ɂ�����ʂ�����̂��B �����A�u������߁v�Ƃ����Ƃ��낪�|�C���g�Ȃ̂��B �����A�����ȓǎ҂ɂ͂������@�������Ă��邾�낤���A���ی����ł́A���݂��̐S�������Ɨ����܂ŐS���I�ɂ����Ƌ߂��Ȃ�ʂ�����B �����I�ȏ펯����ՂƂ��Ȃ������ɁA���݂��ɑ���M�����A�l�������ɂ��闝�R�̂قڂ��ׂĂƌ����Ă��������炢�ł��邤���A�u������߁v�����݂��̊W�Ɍ����Ă��܂��Ǝ��Ԃ������Ȃ��B �����ɂ��l�͍��ی����̗��_������ł����o�����Ƃ���̂����A���ی����������l�Ԃ���������ƂȂ�ƁA���ʂ̖������Ƃ�����O�҂��������܂Ȃ����߂ɁA���ׂĂ͎����ɕԂ��Ă���B ���肪���������������̂��A����������ɏ�M�����ĂȂ��Ȃ����̂��A���ׂĂ͎������\�z���悤�Ƃ����W�̉��炩�̎��s�ɂ����A�����Ȃ��B ����ɉߓx�̊��҂��ł��Ȃ����������邩�炱���A������������₤�Ƃ����ӗ~���Ȃ���A���ی����̉ƒ�͈ێ��ł��Ȃ��B ���̈ӗ~���Ȃ��ɁA����ɂƂ��Ă������ɂƂ��Ă������Ƃ��������悤�Ƃ����̂ł���A����͍��ی����ł��ꓯ���ǂ����̌����ł���A�P�ɍs������̊W�ł����Ȃ��B �I�ǂɂ��Ă����w�т���A����Ȃ��������W�����ی����Ȃ̂ł���B �ł�����ȉ��N�ł��Ȃ��b�́A�����ł�߂Ă������Ƃɂ���B �^�C�ɒ�����炵�Ă�����{�l�́A��ɔN�ւ����܂�ɂ����B ������x�ȏ�̔N��ɒB���Ă��Ă��Ⴍ������̂́A�R���v���b�N�X�ł���ɂ��Ă��A�܂爫���C�����̂�����̂ł͂Ȃ��B �����A�Љ�I�ȐӖ�����������ăL���M���X�I�Ȑ����������Ă���ł���Ȃ�p�����������Ƃ��ƁA�l�͒��炭�����v���Ă����B �����A������͂��ƋC�Â����B �^�C�ŕ�炵�Ă���ƁA�ˑR���̑O�G����Ȃ��A�C�ɂ����߂Ă��Ȃ��������Ԃ��v���������Ȃ��}�]��������悤�Ȃł����Ƃɉ��x���o���킷�B �ł�����ȂƂ��w�����킦�Č��Ă���킯�ɂ͂����Ȃ��B ���Ԃ������J���A�Ȃ�Ƃ�����t��邾���̂��Ƃ���邵���Ȃ��B �u����͐��E���ǂ������ē������Ƃ��v�Ƃ��Ȃ��͂�������邩������Ȃ��B �u���ʂɑ���V�r�A���͓��{�̕������i�ゾ�v�Ƃ��l�����邩������Ȃ��B �������A�N�����Ă��鎖�Ԃ�}�]�����Ԃ肪�A�z����₷�郌���F���̂��̂���Ȃ̂ł���B �Ȃ̂��Ƃŗ�������Ă݂悤�B �E�^�C�ł̐g���ؖ��������Ȃ��܂܁A�l�͓������l�������Ȃ��������J���������Ă���ꏊ����E�o����̂���`���A���̌㐔�N�����܂����ƂɂȂ����B �E�Ȃ̐g���ؖ��擾�̂��߂ɁA�B���ɂ��̕��@��T�����邱�ƂɂȂ����B �E�悤�₭�g���ؖ���ꂽ�̂Ō�����I�����s���ƁA�\������o���R�N�̍^����@�Əd�Ȃ����B��I���̓�����l�̐E�ꂪ�������̕��ɓ���A�ĊJ�̖ړr�͗����Ȃ��܂܂������B �E�O���l�j���Ƃ̍������ւ����Ă��邽�߁A�`���͖��i�l�̍ȁj�̍����͂��A�l�̖��O�ł͂Ȃ��r���}�l�̖��O�ŏo���Ă��܂����i����͂̂��Ɍ���ł���Ɣ����j�B �E�Ȃ̎��Ƃ̂��鑺�̓y�n�����҂��ˑR����āA�y�n�J���̂��߂̋��������ނ���ʍ������i�̂��ɊJ���n�悪�����Ɉڂ������ߓ�ꂽ�j�B �E�Ȃ̎��Ƃ���u���������Z�ɓ��w����v�u�Ƃ�V�z����v�u�k�^�@���v�Ǝ������B�̒m�点������̂́A�����u�����������Ăق����v�Ƃ������˂ȘA���ł���B �E50��̋`���̂Ƃ���ɁA�������������璥���̒ʒB������Ă����B���̔N��ł̏펯�͂���Ȓ������߂̂��߁A�A�d���������ݐ��ȂǁA�l�X�ȉ������܂ƂƂ��ɔ�ь����Ă���B �����Ƃ���Ȋ����ł���B ����H�@����͍��ی����̔��_�ɂ��Ă̘b�ł͂Ȃ������̂��H �����݂͂������Ƃ��B �ł����������b�𑱂������Ăق����B ����Ȏ��Ԃ����Ƃ���J���Ă��������Ȃ��ƂȂ����Ƃ��A�l��͍ȂǂƂ��Ă����Ȃ��̂��B ���ԂɃX�s�[�f�B�[�ɁA�p���t���ɑΏ����Ȃ���A��̍Ղ�ƂȂ�����̂��Ƃ���z���ł��Ȃ��B �炪�Ⴍ������Ƃ������A���_�I�ɎႭ���葱���Ȃ���A�����c���Ă������Ƃ��ł��Ȃ��B �����A���ی����͎Ⴓ�̔錍�Ȃ̂��B ���肪�~�X�e���A�X�ȑ��݂ł������قǐS�䂩���X��������l�͑������낤�B �l�ɂƂ��čȂ̓~�X�e���A�X�`���������R�̑��݂ł���B �Ȃɂ���A�ޏ��͍��Z��ł���^�C�̍����ł��Ȃ����A�Ӌ���Ƃ̍���G�s�����]�ˎ���ɗႦ���r���}�̏��������̏o�g�ł���B �ޏ��̎��Ƃ̋߂��ɂ͐��E�I�ȃ��r�[�̍z�R������A���̃R�l����������������̌��l�^���������킹�Ă��Ȃ��l�ɂ͖K�₷��܂܂Ȃ�Ȃ��B �����ꂽ�^�C���X���b�v���������Ă����A�����̓o��l���Ƃ����Ă������悤�Ȑl�ԂȂ̂��B ����ł͂Ȃ��Ȃ�����ɖO���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B ���X�ɍ~�肩�������̉̕��ɂ��Ă��A�l��͖��͂Ȃ���Ȃ�Ƃ��z���Ă��������Ȃ��B ���̂��сA�l�͂܂������̒��Ɏc��Ⴓ�̎c���U��i���āA�����̗͂��ނ�݂ɐM���邵���Ȃ��B �����ΐl���͗��ɗႦ����B ���Ԃ�A���ی����͐l���ɒ����̗v�f���������ލs�ׂ��ƌ�����B �قƂ�ǐ�̗\���͂��Ȃ�����ǁA����ɂ���Ď������_��ɕϗe�����A����ł��ǂ����悤���Ȃ��ς��Ȃ�����������A���̂��ׂĂ������ɂƂ��ĕK�v�Ȃ��̂Ƒ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��ƁA���������Ȃ��B �l���ɗ��������������Ȃ��ɂ́A���ی����������̕���ł��邱�Ƃ����m�点�������B |
|
 |
||
 |
|
 |
||
 |
 |
2��8�� �Ȃ�2�����قNjA�Ȃ��Ă���B �����Ȃ肩�点�����b�ŋ��k�����A�����Ŏ����o�����ƂɂȂ����z�́A�l�̓��{�A�Ȃ����͂邩�ɍ��z�Ȃ̂ł���B �����Ȃ��Ă��܂��̂ɂ͂������̗��R������B ���Ƃ��A�^�C�����̒��^�L���b�N����Ȃ̗��ɋ߂����܂ł̈ړ��ɂ́A�n�C���[���g�p������肪�Ȃ��̂����ǁA���̎d���͂قƂ�njl�̓Ɛ��ԂƂȂ��Ă��邱�ƂƁA���ꂩ��A�r���ɂ����������Ȃ�҂��Ă���R�̌��⏊�ł��ꂼ��ɘd�G��v������邱�ƂƂŁA�����z�͌������̌����l�ɂȂ��Ă��܂��āA���̗]�n�͂܂������Ȃ��B �܂��A������͂邩�ɑ傫�Ȋz�������̂́A���e�ɓn��������A�e���E�m�l�ɔz�邨�y�Y�ɂ����邨���ł���B ����܂łƂ��ɕ�炵�Ă������Ō������Ƃ��Ȃ��n�͂��t���ғ����āA�����̂��炾���ۂ��Ɠ���قǂ̊��������������āA�����ȍȂ͋A�Ȃ��Ă������B ����́A�~�����}�[���R��n�C���[�^�]��ɂ��Ă̋�s�͂��Ă����āA�^�C���C���i�Ⓦ��A�W�A�̐l�X�j�Ƃ̌����̕��Y���̂ЂƂ߂邽�߁A�ȂƗ��e��e�ʁE�m�l�ɂǂ����Ă���Ȃ����̓������o��̂��A���ꂪ�l�̖ڂɂǂ̂悤�ɉf��A�ǂ���������Ă���̂��A���Љ�Ă݂悤�B �܂��A����A�W�A�̋��ʓ_�̂ЂƂɁA�Ɠ��Ȑe�q���J������B ���x�o�ϐ������ȑO�̓��{�ł�����ꂽ�͂��̘b�����A�q�̐e�ɑ���v��̔O�͐��ŁA�唼�̎q�̑�l�ɂȂ肽�����R�́u�傫���Ȃ��Đe�������Ă�����������v�ł���B �������{�ƈႤ�̂́A�e���g�̎q�ɑ���v���C�h�̎����悤�ŁA����A�W�A���������́u��l�v�̑����͎d����l���ɑ���v���ӎ������Ȃ̒��S�ɂ����邱�Ƃ͂Ȃ��A�����܂ŐA���⓮���̂悤�ɁA����̕����ւ̊��ӂȂ���������̂܂܂ɐ����Ă���B ��i�����̐l�Ԃ��猩��A����͌���Ȃ��A�}�`���A���Y���ɋ߂��������ł���B ���Ƃ��A�^�C���C���̐e�̑����́A�^�Ƃ��āu���ꂪ�q�̐����̂��߂ɂȂ�Ȃ����玶��v���Ƃ����A�����̊���̌����œ{��Ƃ����Ύ��ɂ���B ���𗎂����Ƃ��ĉĂ��܂����Ƃ���ƁA�q�����ӕs���ł��邱�Ƃ�A���Ƃ��Ȃ����߂̍H�v�����Ȃ��������Ƃ�����̂ł͂Ȃ��A���ꂪ�e�ɂƂ��đ�Ȃ��̂Ȃ̂ɉꂽ����{��Ƃ����悤�ȋ�ɁB �e�̎�������荹���������{�Ɣ�ׂ�A�Ȃ�Ƃ��C�y�Ȃ��Ƃ��ƁA�A�܂�����������������������邱�Ƃ��낤�B �������A���W�r��ɂ���n��ł́A���̉��l�͑����č����B �������ߍ��ނ��Ƃ��������K���̂悤�ɂ��������鍡�̓��{�l�ɂ́A��������g�̉��l�����ł����������������Ă��A�b�̎������Ⴄ�Ƃ͂�����B �܂��A�u���R���v�Ȃ���̂��A�����ɗ]�T�����邩�炱�����݂����郂���g���A���̘O�t�ł��낤�B ���������̃R�~���j�e�B�[�������Ȃׂĕn�������ł́A���g�̐������Ȃ���A���̗��v���Ƃ��ɋ�J���Ă����Ƒ��ɊҌ��������Ɗ肤�̂́A���R�Ȑ���s�����Ǝv���B �������A�e�������ɃA�}�`���A���Y���̌Ӎ��������Ă���߂�����̂͂ǂ����悤���Ȃ��������B ���Ƃ��r�㍑�̐l�����̘V���������A�q����̎x������������K�v�ł���Ƃ��Ă��B ���ɁA�����ɑ���ӎ��ɂ��āB ����܂œ���A�W�A�����Ŏ����̉ݕ������x�����̉��l�Ȃ������Ă������K�ւ̐M�p���ł���Ƃ��A��s���g�߂ɑ��݂��Ȃ����Ƃł���Ƃ��A�r���}�̏ꍇ�ɂ̓r���}���ɂ�闪�D�̉\�����������Ƃł���Ƃ��A����肪��������Ă��邱�Ƃ����������ł����̂�����ǁA�~���̈ӎ��������ɔ����B �������i���I�Ȋϓ_���猾���A����A�W�A�̑����̐l�X�ɂƂ��āA���K�͂���Ύg�����̂ł����āA�Ƃ̐V�z���x�܂ł̋��z�ł���A����͒��~�ł͂Ȃ������ɉƂ������x�z�̍������ւ�B �܂��A���������p���ł���ȏ�A�u�J�l�͂���Ƃ���ɂ͂��邵�A�Ȃ��Ƃ���ɂ͂Ȃ��v�Ƃ����l�����ɂȂ��Ă��܂��A�e�����݂ȓ����̌o�σ����F���ɂ���������A�N���̉��ɂ܂Ƃ܂����z���]���荞��ł���ƁA�ǂ��܂ł��ǂ�����̂�������Ȃ����炢�����e���܂ł��Q�����Ă��āA�����ȑ���łȂ�������́A�u���Ԃɉ_�U�������Ă��܂��B ���������ꍇ�ɋ������������Ɠ\�������u�P�`�v�Ƃ������b�e���́A�e���W�̍L����Ƃ͗����ɂ������������Љ���Ă���l�X�ɂƂ��ẮA���̔Z���ȃl�b�g���[�N����̗��E�ւ̏��Ȃ��Ӗ�����̂ŁA�u���͓V���̉�蕨�v�Ƃ������t���A���x�o�ϐ����Љ�Ƃ͂܂�������ϓ_�ł���ɈӖ���[�߂邱�ƂƂȂ�B ���Ȃ݂ɁA�~���Ɋւ��ăt�H���[����Ȃ�A�߂܂��邵���ϓ����鎩���̉ݕ����l��M�p�ł��Ȃ����Ƃ���A����A�W�A�ł͋��i�����ł͂Ȃ��M�����́u���v�̂��Ɓj�����߂�l�������B ���͐��E���ł����l�̕ϓ������قǑ傫���Ȃ��A���肵�����Y�ƂȂ�B �������A�A�N�Z�T���[�Ƃ��Đg�ɂ��邱�Ƃ��ł���̂ŁA�ꋓ�����Ȃ̂��B �����A�l�͂��́u���l�Ɍ����т炩���v���ƂɁA�����ɂ����{�l�炵���^�╄�������Ă���B �A�W�A�ł̓u�����h�i�Ȃǂ��Z���N�g����ꍇ�A���̃u�����h�̃��S���O�ʂɏo�Ă���悤�ȁA�����炳�܂Ȍ����т炩����z�肵�������������悤�Ƃ���X��������B �^�C�Ōg�ѓd�b��X�}�[�g�t�H���N����������l���������Ƃ��A�^�C�l���������l���ɂȂ肽���Ƃ����j���̃}�C�J�[�̏������`�F�b�N���悤�Ƃ��邱�Ƃ��A�܂����������S�����炫�Ă���B �����A�x�@�����Y�Ƃ̈�Ƃ̂��߂ɂ͔Ɛl�����ɑ��͂������Ă��A�n�R�l���������Ĕ��������i�𓐂܂��悤�Ȕ�Q�͂ɂ͏��ލ쐬�����邭�炢�̑Ή����������Ȃ��悤�Ȓn��ŁA�Ȃ��H�U�肪�����悤�Ȃ��Ԃ�������Ĕƍ߂̔�Q�Ҍ��ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�܂����������ɋꂵ�ށB ���ɁA�ȑO�������Ă����^�C�l�����́A�f�p�[�g�̐l�C�̂Ȃ��Ƃ���ōÖ��K�X�̂悤�Ȃ��̂�k������āA�l���v���[���g�����i�Ƃ������A������ꂽ�j���̃u���X���b�g�𓐂܂ꂽ���A�ޏ��͌x�@�ɓ͂��邱�Ƃ��炵�Ȃ������B �b�������E�������̂ł��̘b�͂��Ă����āA�Ƃ̐V�z�ɂ���A�o�C�N���w�����邱�Ƃɂ���A�����J�肪�ꂵ���Ȃ����甄�p����Ƃ����̂͋��Ɠ����ł���B ����Ȃ킯�ŁA���������Ƃ��ɖl���Ȃ̗��e�ɑ������i���{�ł����Ƃ���́j���[���́A�����ɂ͂�������Ȃ��Ȃ��Ă����������B �l�̂悤�ȁu�^�C�Ō��n�̗p����Ă�����{�l�v�͂��������Ƃ���Ŋ���H�����ƂɂȂ�B �Ȃ̋�����тł��A�����l�j����M���ɁA�u�������ƌ�����������Ƃ��������v�Ƃ�����͖����ɉɂ��Ȃ��Ƃ����B �����ʂ̗`�ɏ��Ύ��������̐������悭�Ȃ�Ƃ����e�̎v�����A�q�́u�e�Ɋy�������Ă��������v�Ƃ����肢�ƍ��v����Ƃ���ɁA�l�̂悤�ȁu���������Ƃ���l�����͂��Ă����āA�����̐l���̕���̑I���Ƃ��Ăӂ��킵���ꏊ��I�т����v�ƍl���ă^�C�ɂ���Ă������{�l�̔������]���荞��ł��Ă��A�Ȃ̋����̐l�X�ɂ��܂��J�e�S���C�Y���Ă��炤���Ƃ��ł��Ȃ��̂��B �����������W���������Ƃ������{�l�i���ۂ̂Ƃ���AGDP�ł͒����ɔ�����Ă���̂����j���z��҂ƂȂ��āA�o���R�N�ł͂ǂ����Ă�����������葊���ɂ悢��炵�����Ă��邪�A���������͂��قǑ傫���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�ƁA���Ƃ������Ԃ�����ꂽ�Ƃ��Ă��u����ς�ِl�Ȃȁv�Ǝv���Ă��炦�邠����Ŋւ̎R�Ȃ̂ł���B ��������{�l�������Ɏ��������̘V���A�q���ł����Ƃ��̂��߂̏�����A��a���������Ƃ��̂��߂̗p�ӂɏ[�Ă����~�����A���̎������ǂ̂悤�ȃX�g���X�⊋���̒����琶���Ă��Ă���̂��𗝉����Ă��炤�̂́A�Y�����̕ǂ��悶�o���ĉz����قǂɓ�V�Ȃ��Ƃ��ƌ��킴��Ȃ��B ���������v���́A�^�C�l������z��҂Ƃ����j����������Ă���ƁA�悭���ɂ���B �����A�ŋ߂ł����ω��������邪�A�~�����}�[���{�̂悤�ɂ���܂łԌ����ǂ����������Ă������̍����̌������ɁA�O���̏��������Ă������ɏZ�ސl�X�ɂƂ��Ă͂���ɗ���������A�~�����}�[���R�ɂ�邱��܂ł̐��X�̗��D��\�͂ɋꂵ��ł����l�X�ɂƂ��ẮA�Ȃ�����̂��ƂƂȂ�B ���݂��ɋ��ʂ̊ϔO���Ȃ��Ƃ���ł̘b�������̂��A���̎�̘b��̓����Ȃ̂����A����ł͂��܂ł����s�������ǂ邾���ł���B �ǂ����ɂ��݂��̗��������܂ꂻ���ȃ|�C���g�͂Ȃ����̂��B �����Ŏv���������̂́A�l�����ɂ͎q�݈�Ă�\�肪�Ȃ����Ƃ��B �^�C���C���Ɍ��炸�A�A�W�A�̑����̖����A�����Đ펞���܂ł̓��{�ł����A�q���e���x����V�X�e�����Ƃ��Ă���B �Ƃ��낪�A�l�����͎q���������������Ă��Ȃ��B �~�����}�[���{�͌��݁A�����������Ƒ����Вj���Ƃ̍������ւ��Ă���B ���{��^�C�ō����͂��o���ɂ��A���ނ������\���͍��̂Ƃ��낫��߂ĒႢ�B ���̏����Ŏq���a�������ꍇ�A1�N�ȓ��ɍ������܂߂����ނ�����Ȃ���A���{���ł͖l�̎q�Ƃ��Ă̔F�m���ꐶ���Ȃ��`�ɂȂ邱�Ƃ́A�����S���̓��{��g�قł��łɊm�F�����B �q��������\�肪�Ȃ���A��Ƒ��������₢�x����̂��A�A�W�A�������̃p�^�[���ł���B �������A�l��͍ȂƖl�̓�l�����̒��j�Ƒ����B ���̂܂܂ł����A�V��̎����͖l���������Ƃ����邵���Ȃ��B ���̂��Ƃ́A�l�炪��a���������Ƃ��ɂ����l�ł��낤�B �e���q����̑��������Ăɂ��Đ����Ă�����̂́A�q�������Ƒ��l�b�g���[�N����̉��b������\�肪���邩�A���邢�͎q������Ȏ����������Ă��邩�̂ǂ��炩�Ɏx�����邩��Ȃ̂��B �����A�����������g�̂��߂ɂȂ邱�Ƃł͂Ȃ��A�e�F�s���������Ƃ����C�����́A�{���ɔ������B ���Ƃ����Ă�肽���͎̂R�X�Ȃ̂����A���͓Ƃ�g�̍����玩�g�̐e�ɂ����A�قƂ�ǍF�s�Ȃǂł��Ă��Ȃ��l�ł���B ���āA�Ȃ��A�Ȃɂ������āA���e�̂��߂ɂ����������A�邱�Ƃ��A�e����m�l�����̂��߂ɕ�����Ȃ��قǂ̂��y�Y�������Ă��������Ƃ��A�������������R�ɂ��B ���E�ōł�������l�݈�ĂĂ��ꂽ�Ȃ̗��e�ɑ��銴�ӂ��A���̐l�̐l�i�`���ɑ���ȉe����^���Ă��ꂽ�����̐e���E�m�l�����ɑ���v�����A�Y�ꂸ�ɂ������B ����ǂ��A���K�̖��͂��܂�Ɍ����I�ɃV�r�A�ŁA���ӂ�v���Ƃ������R�Ƃ������_���E���y�����݉z���Ă��܂��B �Ȃ̉Ƒ������������������ł�����𐮂��邽�߂̎����Ȃ�A�ł��邩���苦�͂������B �����A�`����`�ꂽ���������ɂ��邩����́A�����̌����߂�悤�Ȏd���͂܂��������肻���ɂȂ��B �ł��A�����炱���l�͎v���B �V���A�X�ɂȂ肷����ȁB �`����`��ɂ��Ă��A�Ȃɂ��Ă��A�l�̕�e�ɂ��Ă��A�������Ƃ������ƌ����B �����͖����̕��������A�ƁB �����A���ꂱ�����^�C���C�ɂ����{�ɂ��^�C�ɂ����ʂ��ė���Ă��鐶���̒m�b�Ȃ̂��B �R�̂悤�Ȃ��y�Y������ċA�Ȃ���Ȃ̎p�Ɂu�͂͂́v�Ə��Ȃ���A�d���ו������̂���`�����ƁB ���̑�g���������A�A�W�A�̒m�b�Ȃ̂��ƁA�l�͍ŋ߂悤�₭�C�Â��n�߂��B |
|
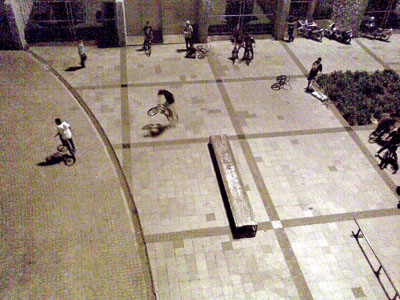 |
�Q�O�P�Q�N
|
  |
�Q�O�P�P�N
  |
�P�O���Q�R�� �������ՂɁA�l�̓h���C�Ȑl�Ԃ������B ����Ȑl�Ԃ��ƌ��������܂ł��B �������ɂ�����������Ȃ��B �ЂƂ�ЂƂ�̌��т����������ׂĂł����āA�`�Ƃ��Ă̎��ɂ͂قƂ�nj`����I�ȈӖ����������Ȃ��Ɗ����Ă������Ƃ͎������B ����҂Ɩl�́A2�N�O�Ɍ������Ă��Ă����������͂Ȃ������B ���݂������݂��������K�v�Ƃ��Ă��邱�Ƃ́A�A�N�Z���߂ΎԂ��i�ނ��ƂƓ������炢�����������B ���ꂪ�����������̂悤�Ȃ��̂łȂ����Ƃ��B �����A�l�����ɂ͔閧���������i2011�N8��24���̓��������Q�Ƃ��������j�B ���݂��ɂƂ��Ĉٍ��̎�s�o���R�N�łӂ��肪������Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɂ́A�ǂꂾ���C��z���Ă��z��߂��ł͂Ȃ��B �������āA�X�̏������̂悤�ɑ�����߁A�@����M���Ȃ���l��͕�炵�Ă����B �ˑR�Ƃ��Č����͖����̂悤�ɉ����ɂ��������A��̓I�ȃS�[���E�e�[�v�Ɏ����`�����グ�n�߂��B �^�C�ł̑؍����~�肽��A�l�����͂����ɋ������邱�Ƃ����߂Ă����B 8��21���A�҂��ɑ҂��ł���Ă����g���������l�����́A�����܂ł̓����ŒZ�����œ˂��������B �����ɁA�^���������s�C���ɂ������Ƃ������x�ł���Ă����B ��̐X�ʼn����d�����Ȃ������悤�ȋC�����ŁA�l�����́A�\�肵�Ă��������Ȕ�I���̊J�Â��ǂ�����̂��A�������̘b��œ���������B �ł��A�ǂ����̂Ƃ���ŁA���̓��������łɂ�����x�p�ӂ��Ă����悤�ȋC������B ���肬��܂ŔY�݁A�l�����͂�����������l�����ɂȂ����Ƃ��Ă��A��I�������s���邱�ƂƂɌ��߂��B �l�����͏[���ȋq�ϐ��������ĕ����̑I��������ɂ͑҂��ł���߂��Ă������A���͂̏Ɉ���I�ɘM��邱�Ƃɔ��Ă������B �����炱�������ɔ�I�����ς܂��邱�Ƃ��ł������Ƃ͈�i�ƁA����A��i�O�i�Ɗ��S�[�����̂�����B �Ȃɂ��A���̑����̒��ŏo�Ȃ��Ă��ꂽ�l�����ɁA�ǂ����Ă��o�Ȃł��Ȃ������l�����ɁA�l�������������Ă��ꂽ�l�����ɁA�S���炠�肪�Ƃ��ƌ��������B �����āA�݂Ȃ���ɂƂ��āA���̔�I�����s���ȋ�C�ɕ�܂ꂽ�o���R�N�̒��ň�̂ق̖��邢�j���[�X�ɂȂ��Ă����K�����B �������Ղɂǂ�ȃh���}������̂��A�l�͂����炭�܂��������m�������B �Ƒ��E�e�ʂ⓯���E�F�l�����ɂǂ�Ȃ�����������A�ǂ�ȓ����������̂��A�l���������͒m���Ă����B �u�����������ł����ˁv�ƁA�����I���������ƁA���Ȃ��������̕��ɐ��������Ă��炢�A�u�����v�ƕԎ����������Ƃ��������B �������A�����Ȃ��Ƃ������A���̏�ł́u�������̂��ȁv�Ɗ��������Ƃ��A1�N���Ă����L���̖��ɕ�܂�Ă���B ����Ӗ��Ŗl�́A�������Ղɂ��܂�ɑ傫�Ȋ�������߉߂��Ă���̂�������Ȃ����A1�N�����ĉ���ł��܂����Ƃ��������A���Ƃ͌���Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv�������Ă����B ����ł̓j���[�X�Ɠ����ł͂Ȃ����B �[���ȏ��ɑ��āA�l��͂ǂ�ȂɏՌ����Ă��A���̕����������Ă��炭����ƁA���̃j���[�X�ɂ����ڂ������Ȃ��Ȃ�B �������āA�h���������D�悵�āA�s�s�����҂̓{�u�X���[�����藎���Ă������Ƃ��A�s���ǂƌ`�����̊����ւƂ܂�������ɑ���ʂ��Ă䂭�B �����A�l�͎������������邱�ƂɂȂ��Ă悤�₭�A���߂ċC�Â��̂��B �l���g�������ɏd�ǂ������̂��ƁB �l�ɂ͂��ꂼ��̃h���}������B ����ĕ���������e�͂��ꂼ��ɂ��邾�낤���A�{���ɏd�v�ȁA�E�F�b�g�ł��Ăʂ�����̂���ۓ����������镨���́A���t���ǂꂾ���A�˂悤�Ƃ��A�����҂ɂ����������������Ƃ͂ł���܂��B �����炱���A���������A�Q��҂̂ЂƂ�ЂƂ肪�X�ɏj�����蓉�肷��̂��B �������Ղ��@���s�ׂ̑��ʂ��������������邻�̈Ӗ����A�悤�₭�l�͗������邱�Ƃ��ł����B �S�[���͎��̃X�^�[�g���ƁA�悭������B ����͂܂�A�I���Ȃ��A�˂Ȃ̂��B �Ղ��I���Ύ��̉������܂�����Ă��邾�낤�B �l�����̃h���}�͏I���Ȃ��B �����A�l���������ꂼ��̃h���}���Ă���̂��Ƃ�������������Ȃ�������́B |
| �P�O���P�U�� ������̉̐����J���I�P�E�{�b�N�X�����ς��ɍL�����Ă���B���Ȃ₩�ł��Ȃ���c�̑����ޏ��̂��̉̐����B �u������A�́A���܂���v�ׂ̉Ɯ����X�ɗ���O�ɘb���Ă��Ă��ꂽ�Ƃ���A����A����ȃ����F������Ȃ������B�Ȃɂ���A�J���I�P�Łu���A���̋ȁA���Ȃ��̔����Ă�CD�ɓ����Ă�Ȃ���v�Ƌ�����ꂽ"It's a Party"�́A���{�ɋA�������̂��ɒ������������i�R�R�E���[�j�̃��H�[�J���̍��������Ɏア�����܂������������̂�����B������̉̂́A���̋Ȃ������o���s�s�����̉₩�ȑ��ʂ����łȂ��A�����ɂ��̋����`���Ă����B �Ɯ��͍��Y�łł������߂Ă̗F�B�������B�t���[�E�y�[�p�[�̎�ނŒm�������𗊂�ɒH�蒅�����o�[�̊K���Œm�荇���A�l���w�O�̂ς��Ƃ��Ȃ��h�ō��𐘂��悤�Ƃ��Ă���̂�m��ƁA���e�̂���Ƃɏ����Ă��ꂽ�B����̎Ⴂ�j�ŁA���������Ђ܂ňႤ�ӎU�L���ˑR�̖K��҂��A�Ȃ����Ɯ��̗��e�͖ٔF���A�������ЂƂ^�����B���ꂩ�獂�Y�ɂ���Ԃ��イ�A�l�͔ޏ��̌g�ѓd�b�̃A�N�Z�T���[�ƂȂ��āA���̖T����قƂ�Ǘ���邱�Ƃ��Ȃ������B���݂��̃g�C���x�e�ƁA�T���������ȓd�b�̂��ƁA���炭�m�荇���ɉ���Ă���Ɣޏ��������c���ăJ�t�F������Ƃ��ȊO�́B �J���I�P�E�{�b�N�X�ɂ͎��ɑ����̖K��q�������B����́A���̓X�������ɔɐ����Ă������Ƃ����b�ł͂Ȃ��B�l��̂��镔���̔����A���Ȃ����ς����Ă�20�l�ȏ�̗��K�҂�����ւ�藧���ւ��J���Ă������̂��B����҂�1�ȉ̂��A����҂͌y�������b���ς܂��A�����Ă���҂͂��炭�N���ׂ̗ɋ���������ߍ����A�N��l�l��Ƃ��̌�̍s�����Ƃ��ɂ���҂͂��Ȃ������B�����ɓ����Ă���p�͂��ꂼ��Ɉ�����I�[����Z���Ă������A�o�Ă����Ƃ��ɂ͖����ƌ��܂����قǂɈ�l�Ȕw�������Ă����B�����āA���̒N�����j�������B����Ȃɂ��X�Ɋ猩�m�肪����ޏ������́A�l�̑z���ȏ�ɗV�ѐl�Ȃ̂�������Ȃ����A���Y�����قǑ傫���Ȃ��X�Ȃ̂�������Ȃ��B��p�ł͓��{�őz�������Ȃ���҂����̍L��ȃl�b�g���[�N���펯�ƂȂ��Ă���̂�������Ȃ��B���̃A�W�A���s�ɐ�������A�t���[�y�[�p�[��ނŊX�ł̃R�~���j�P�[�V�����̊g��ɕ@���̍r�������l�ɂ́A���ׂĂ����I���̐V�N�ȃA�W�A�̖������Ƃ����f��Ȃ������B 2011�N�̃o���R�N�B�^���̃j���[�X���肪�J��Ԃ����e���r�̃X�C�b�`���AiPod�������_���I�Ȃɂăv���C�E�{�^�����������l�̌ۖ����A"It's a Party"���k�킹���B�ڂ����ƁA���Â����@�I�ȃJ���I�P�E�{�b�N�X�ɉ������āA�}�C�N�������Ă����B�������A�l�ׂ̗ɂ͉Ɯ�������B���̂Ƃ��̂���߂����Ȃ��ށB���ׂ̍��������̉̐��́A��������ɂ܂������L���̒f�Ђ�\������̂ɂ͂҂����肾�����B�����ƁA�������͂���Ȏ��Ԃ�\�z���Ă����̂��낤�B �Ɯ������ƒm�荇���O�A��k�̃��C���E�n�E�X�Œm�荇����������̉Ƃɂ��A�l�͏�����Ă����B�ނ̕��͖^��s�̓����x�X���ŁA�ގ��g�����{�Ɍ�w���w�̌o��������B�x�O�̂�����肵�����j�b�g�̃}���V�����ɂ́A�ډf�����̓��������������Ă����B�t�߂̂��y�����ӂ�܂��Ă��������A�����ɍ��Y�ɓ�������o�X�ɏ��A���̗[���ɂ͉Ɯ������Ɣt�����������グ�Ă����B�Ⴍ�A���S�C�ȓ��X�B����͂܂��A�v�����݂̏��������_�o�Ȋ��Ԃł��������BNHK���炩�烍�[�h�V���[�ԑg�Ƀ`�����l����ւ��邭�炢�̋C�����ŁA�X�̗l�X�ȓ���ɈٖM�҂Ƃ��ēo�ꂵ���l�́A����܂ł̏����̗����v���C���[�̎莝���J�[�h�Ȃǂ��\���Ȃ��ɁA�s�ӂɃQ�[���ՂɃ`�b�v��u������₩���q�ł����Ȃ������B�����̕����ɂ͂��̂Ƃ��A���̏�ɂ��������̌��͂Ȃ����̂����A�������̌���ꂽ���Ƃ����͎��Ԃ�⿂������A�o�����o�����ƂŌ���Ƃ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B �Ό������ςɑ����邱�ƂȂ��A���g�̐S�̕����܂܂̍s�����N�������e�������邪�܂܂Ɏe��Ȃ��炻���͂��ƂȂ��������o���邱�Ƃ��ł������̐t�Ƃ����p���������������G�߂��A�l��ῂ���������B���̍�������������Ȍ�������܂ł����A���ƂȂ��Ă̓V���K�[�E�R�[�e�B���O����Ă���B�����A���̂ނ�݂Ȓ��˖Ґi�ɂ��Ԃꂽ�A�ނ�E�ޏ���̔w�����Ă����͂��̂������ȏd�݂́A���ɂȂ��Ď�̂Ђ�Ɋ�������悤�ɂȂ����B���傤�ǁA�����ŏ_�炩���A����������Ă���鐅�Ƃ������݂��A�ЂƂ��їʂ𑝂��ƈÂ��������d�݂ł�������̂�ۂ݂��݁A���̍^���̐��ʉ��ɂ��ׂĂ߂Ă��܂����Ƃ���悤�ɁB "It's a Party"�͖��c�ɂ������Ƀt�F�C�h�E�A�E�g���A��҂����̓ƒd��ł����̏I���������Ă����B�~���[�E�{�[���̃t�F�C�N�ȋP�����~�܂��Ă��܂����X���o��A�����ɂ͔��ݏd�Ȗ閾�������邾�낤�B�l�X�͉߂����������Ԃɏ����v����y������A���炾���d���Ɗ����Ă݂��肵�Ȃ���A���ꂼ��̌����ւƋA���Ă䂭���낤�B����ł��Ƃ��ǂ��A��̒��̒��ɂ��鎞�݂����ɋ���ł݂����Ȃ�B�u�������͖����Ȃ�Č��Ȃ��Ă������I�@�����A���̏u�Ԃ���I�v ���@�������̊����\�����ł��Ȃ����߁A�������ȕ\���ɂȂ��Ă��܂��B2���ڂ͂����ւ�ɂ̂Ԃ�ł��B |
 |
            |
�W���Q�S�� 2�N�Ƃ����Ό����u�����Ƃ����Ԃ��v�Ƃ����l������A�u�Ђǂ������v�Ƃ����l�����邾�낤�B �܂��ɁA�l���g�ɂƂ��Ă�����2�N�Ԃ́A���ɂȂ��Ă݂�Βn���S�Ŏ��̉w�ɒ����܂ł̂悤�ȑ����������Ƃ��v���邪�A��3���O�܂ł́A�҂ĂǕ�点�nj���Ȃ��҂��l���Ђ�����҂�������悤�ȓ��X�ł��������Ƃ��܂��m���Ȃ��Ƃ������B �����A���N��8������́A����2�N�Ԃɑ���v���͂ЂƂ����ł��邱�Ƃ����͊ԈႢ���Ȃ��B �Ƃ��Ƃ�3���O�A�l�̗��l�̓^�C�ł̐����ۏ������������B �����܂ł̓��̂�́A�u�o���R�N�ɕ�炷���{�l�v�Ƃ�������Ӗ��ŗI���Ȑg���̖l�ɂ́A�z�����y�Ȃ��g��������������B 2009�N8��12���̖{���ɒԂ����Ƃ���A�l���ꐶ���Ƃ��ɂ������Ɗ���Ă��鏗���́A�o���R�N�ŕ�炵�Ă��邱��2�N�ԁA�g���̕ۏ�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B ���̌��ɂ��ẮA�����Ԃ��Ȃ邾�낤���A������x�̐�����v���邾�낤�B �ޏ��̏o�g�n�͈�ʂɂ̓r���}�́u�V�����B�v�ƌĂ�Ă���A�~�����}�[���{�Ƃ͓G�ΊW�ɂȂ��Ă���n��ł���B �ڍׂ͕ʍ��ɏ���Ƃ��āA���{�̕����ł́u�V�������v�ƏЉ��Ă��邱�̖����́A�^�C�����̎�v�����ł���^�C���E���I�X�l�����勤�a���̎�v�����ł��郉�I���Ɠ����o���������A��������쉺���Ă��ꂼ��̏ꏊ�ɒ�Z�����Ƃ���Ă���B �u�V�������v���������������̖����̂��Ƃ��u�^�C�v�i�^�C����\���u�^�C�v�Ƃ͔�������E���n��ł̒Ԃ�͂��ꂼ��قȂ�j�ƌĂ�ł��邱�Ƃ�����A���̋��ʐ��𗝉����Ă��������邾�낤�B �����A�^�C���E���I�������ꂼ��̒�Z���Ƃōő��������ƂȂ����̂Ƃ͈قȂ�A�u�V�������v���蒅�����r���}�́A�C�M���X����̓Ɨ���A�B�̎�����F�߂��Ȃ��炻�̖̂ɂ���A����2�ʂ̖����l��������Ȃ�����A�A�E���T���X�[�`�[�������߂Ă����悤�ȌR�����Ɛ��{�Ƃ̑Η���]�V�Ȃ�����Ă����B ���݂ł̓~�����}�[���{�̎x�z���y�Ȃ��n��͂قƂ�nj����Ȃ��Ȃ������A�ȑO�́u�V�������v�̂ق��A�J�������E�R�[�J�����E�����ȂǗl�X�ȏ��������������x�z���Ă���n�悪���y�̂������������ԂŁA���ꂪ�p���Ă��ꂼ��̕����̏o�g�҂̌ːЂ��Ȃ���Ԃ�A���ꂪ���Ńp�X�|�[�g�Ȃǂ��������ɊO���ɏo�邵���Ȃ��Ȃ��ē������Ƃ��������܂�Ă���B �ޏ��ƂƂ��ɐ����錈�ӂ��ł߂��l���܂��������ꂽ���Ƃ́A�ޏ������g�̒a������m�ȔN���m��Ȃ��������Ƃł���B �ޏ����킭�A�Ƒ��ɐq�˂Ă��m��Ȃ����낤���A���̐l�X�̏o���͂Ȃǂ������ɂ���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͗����ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B �u�����̓r���}�l�ł͂Ȃ��v���Ƃ����R���ƍl���Ă���u�V�������v�ƁA�����ɂ���ė����ɌŎ�����~�����}�[���{�Ƃ��a瀂̐[�����l����A���{���Ǘ�����ːЂ̂Ȃ����Ƃ͔[���̂����b�ł���B ���v���Ȃ������𑗂�ޏ��̑��̐l�X�ɂƂ��āA�L�O���Ƃ����T�O�͏@���I�Ȃ��́E�s���I�Ȃ��̂Ɍ�����悤���B ���āA�����Ȃ�Ƃ܂���ɓ�������Ă��܂��̂́A���Ƃ̖@������ɂ�����x�܂Ŏ@�������l�̕��ƂȂ�B ������F�߂Ă��炤�ɂ��A�ޏ��Ɠ��{�ɍs���ɂ��A�ːЂ̏����͍Œ�����ƂȂ��Ă���B �����A���ꂪ���݂��Ȃ��ƂȂ�ƁA���������ǂ���������̂��B ����A�����Ƒ傫�Ȗ��Ƃ��āA�ޏ����o���R�N�Ő������Ă����̂ɁA�Œ���̐g���ۏ�͂ǂ���������̂��B �x�@�ɐg���̒����߂�ꂽ��A�a�@�ŏ���ɂ͕K���g���ؖ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ������肷�邱�Ƃ��A�ǂ̂悤�ɃN���A��������̂��B ���̓����͂��ׂāA��Ɏ��g�̏����W�ɂ���ĉ����̎�����������Ƃ������@�ɋ��邵���Ȃ������B �ǂ����Ĕޏ��̕��͓����Ȃ��̂��H �����A�ޏ����g���������ƁA�g�����S�������댯������������ł���B �ޏ��̃^�C����2�N�Ԃ́A���H�����̜p�j����X�ŕ�炷�������̂悤�ɁA������߂ċC�z�������A�M���ł��邽������l�̐l�ԁ\�\�ޏ��̏f��Ɩl�ȊO�̐l�ԂƂ���Ƃ��ȊO�́A�����ď����ȃA�p�[�g�̕�������O�o���Ȃ��|�̝|����邱�ƂɏI�n�����B ���E�ł��L���́u�����v�p�X�|�[�g�������Ă�����{�l�̖l���T�[�`��S�����邱�Ƃ́A���̓_�ŗL�����B �����āA�ł����ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�{�[�g�E�s�[�v����ǂ��Ԃ������Ă̓��{�Ƃ͑ΏƓI�ɁA���̃^�C�������������Ɋ��e�ŁA����ɂ��Z�ʂ��������Ɓi�Ȃ��A���݂̓��{���{��2010�N9��28���ɁA�^�C�̃����E�L�����v�ɕ�炵�Ă����r���}����̓�������Ɏ���Ă���B�������A���{�@�ւ����n�ɕ����Ėʐڂ��s���u��O����Z�v�F��̓A�W�A���̎��݂ł��邱�Ƃ�t�L�������j�B ���ƊԓI�E�o�ϓI�Ȗ��C����̖����r�ˉ^��������オ�������Ƃ͂�����̂́A�^�C�ɒ�Z���Ă���l�X�A�Ⴆ�Β��،n�E�C���h�n�̐l�X�ɑ��Ėڗ����������Ɖ������悤�Ȕ��Q�́A����܂łɃ^�C�����ł͋N�����Ă��Ȃ������B �e���Œ��ߏグ��̂ł͂Ȃ��A�u�^�C���b���A�^�C�Ƃ������𗝉����悤�Ƃ��A�^�C�ŕ�炷�l�X���^�C�l�Ƒ����悤�v�Ƃ���^�C�����̗e�F�p���́A���g�ɂǂ������������̎c��ڂɂ�ῂ������邭�炢�Ɍ���P���Ă���B �X�^�[�g�͂�͂茵���������B ���{�ւ̋A�Ȏ��ɋ߂��̖�������O���Ȃɂ܂ŘA�����đŊJ�̕��@��T�������A���R�̂��Ƃ����ׂĐ��A�ɋA�����B ���{�Ɍ��炸�A�傫�ȋ@�\�ɂ͂��ׂ��炭�l�X�ȕ������p�ӂ���Ă���A���̒��ŋ@�\�I�ɐ��I�ȃP�[�X�E���[�N���s���Ă���B ���̃V�X�e���́A�l�����̕��������̂悤�ȁA�܂��ǂ��ɑ��k���Ăǂ̂悤�ȉ����̕��@������̂������������߂Ȃ��ɑ��ẮA�ꖇ��̂悤�ȗ₽�����������킹�Ă���B ���̕����Łu�K�v�ȏ��ޏ�A����̃P�[�X�͉�X�ɂ͈������˂�v�Ƃ������t�̗ތ^�ɂ͂ǂ�Ȍ���������̂���������Ă��炤���Ƃ��ł����Ƃ����A���Y�������������Ă������i�l�Ɠ��l�̖�������Ă�����̂����₩�Ȃ��Q�l�̂��߂ɋL���A���������������Ƌ@�ւɑ��k����Ȃ�A�݊O���{��g�ق����E�߂���B��g�ق͊�{�I�ɑ�������ł��邽�߁A���k���e�ɑ��đ����ʂւ̍L����������Ă���B�܂��A�֑��Ȃ���t�L����A�l���K�˂��Ƃ��ɑΉ����Ă����������݃����S�����{��g�ق̏����X�^�b�t�̑Ή��͍��ؒ��J�ŗE�C�Â���ꂽ�j�B ��\���Ƃ����P�[�X���l�������A���ۂɌːЂ����݂���̂��ǂ������m�F���邱�Ƃ��挈�ł������B �����������A���̒n��ɂ́u�V�������v�ɂ��Ɨ��^�����U�����Ă���A�~�����}�[���{�͊O���l�����̒n��̉��[���ɓ����Ĕ����{�I�Ȍ��������n�l���猩����������A���̔��ɊO���l����l���Ȃǂ̌[�������n�l�ɗ^�����肷�邱�Ƃւ̌x����I��ɂ��Ă��邽�߁A�����Γ����������s����B �܂��A�����łȂ��Ƃ��A�O���l�����R���s�Ƃ��ăP���g�D���i�`���C���g�[���j��艜�̒n��ɓ��ݍ��ނ��Ƃ͋ւ����Ă���̂ŁA���̏ꍇ�ɂ͐��l�̏��Ҏ҂̓��s���K�v�Ƃ���邪�A�ޏ��̌̋��̓^�C�����n�т���قlj����A�����܂ŒN���ɏo�����Ă��炤���Ƃ͋ɂ߂Ĕ��I���B ��������Δޏ��̐g���͕ۏႳ���̂��낤���A�������Ȃ�Ƃɂ����A���ЂƂȂ�ǂ���ɂ��Ă��ːЂ̖�肪���܂Ƃ��B �V����������@�Ƃ��ė��p���邱�ƂȂnjy���ȃA�C�f�A���Ƃ͕������Ă��Ȃ���A�q���ɂ�������Ƃ������Ƃ��l�������A���̃A�C�f�A�̓����S���̓��{��g�قŔے肳�ꂽ�B �F�m�ɕK�v�ȏ��ނ�������ԓ��ɑ���Ȃ��ꍇ�ɂ͎t�����Ȃ��Ƃ����ߌ������ۂɋN�����Ă���Ƃ����B ��͂肱���ł����͌ːЂ������B �������A�~�����}�[���{�͐l�g������肩��A���������ƊO���l�j���̌�����F�߂Ȃ������ł��o���Ă���B ���{��g�قɏЉ�Ă�������A�r���}�l�j���ƊO���l�����Ƃ̌����i�l�����Ƃ͐��ʂ��t�̃P�[�X�j�Ȃ�\���ł���Ƃ��������S���̍ٔ����ɏo�����Ă��A��O�Ŏ~�߂��u���ɓ����đ��k���Ă���v�ƌ���ꂽ���A�o�Ă����ނ̕Ԏ��́u�m�[�v�B �ł��邾���̂��Ƃ͂���Ă݂悤�ƁA���ʐ��āu�V�������v�̃p�X�|�[�g�擾�ɂ��Đq�˂悤�Ƃق��̒��ɂɕ����Ă��A�����̑O�Ŗl��ǂ��������Ƃ������Ȃ���q�̃r���}�R�l�Ɉ�u�e��˂�����ꂽ�悤�ȗL�l�ŁA�Ƃ�����܂��Ȃ��B �r���ɕ��Ă��肢�Ă����Ԃ��߂��Ă䂭�����Ȃ̂ŁA��w�w�Z��T���A�����Œʖ�҂Ƃ��ē��s���Ă��炦��l�ނ�T���Ƃ����Ă��l���o���A����������ĕ����n�߂��B ���ɂ̋߂��ɂ������r���}�l�o�c�̌�w�w�Z�̌o�c�҂̕��͓����A��э��݂œ����Ă������q���b�������B���Ȃ��������A���e�𗝉�����Ǝ���ɂ߂��ۂ��e�ȏΊ�ɑ��ς�肵�Ă����B ���{����b����ނ́A�u�����������Ȃ�A���{�l���o�c���Ă����w�w�Z��m���Ă��邩��A�����܂ňē����܂��傤�v�ƌ����Ă����B �����A�r���}�𗷍s�����l�Ȃ�ǂȂ����������̂��Ƃ��낤�Ǝv�����A�r���}�l���̂͐l�̂悢�A�����ʼn��₩�Ȑl�X���B �������A���ƂƂȂ�Ɠr�[�ɕ��L����B �l�͏W�c�ɂȂ����Ƃ��ɁA�����ł���Ƃ��Ƃ͂܂����������Ȃ������F�ʂ�g�ɓZ���n�߂�B �����߂̍\���Ƃ܂������ς�邱�Ƃ͂Ȃ��B �ނɏЉ�Ă���������{�l�̕��́A�r���}�l�̉�����ƌ����Ȃ����Ă����B �ނ����Ă��ꂽ�̂͂����g�̌����̃P�[�X�Ɠ������A�r���}���Őe�ʂ��}���Ď��������グ���̂��A�����p�X�|�[�g������ė��w���ڂŒ����Ȃǂ֏o�����A�����œ��{��g�قɂ��炩���ߏW�߂��K�v���ނ��o���ē��{���ł����Ђ�F�߂Ă��炤�Ƃ������̂��������A��������~���ɖl�������s�����邽�߂ɂ́A�ޏ��Ɉ�x���A������Ă��炤�K�v������B �����A���͂����܂ł̈ړ����ɕߔ�����Ȃ����Ƃ������ƁB �r���}���ŏ�������������Ɉ���������̂͊댯�ɂ܂�Ȃ����A���ꂪ�^�C�ł����Ă��A�~�����}�[���{�ɐg���n���ƂȂ��Ă��܂����Ƃ͈łł���B ���������ɑ���E�l�E���D�E�\�s�E�����J���Ȃǂ̕��₦�邱�Ƃ̂Ȃ��~�����}�[�ł̐g���S���́A���Ƃ��Ă������Ȃ�������Ȃ��B �l�����ɂƂ��Đ����̏�ł͂��邪��O���ł����Ȃ��Ƃ�������^�C�ł́A�O���l�̑؍���������ɘJ�������s���ł���Ƃ����Ƃ���܂ł͗����ɑ������������A����ȏ�̐i�W�͐}��Ȃ������B ������ł͘J���ǂɍs���Ă���ƌ����A�J���ǂł͏A�E���ʂ��ăR���^�N�g���Ă���ƌ����邪�A���̖{�l�͂܂��^�C���������x�܂ł��������ł��Ă��Ȃ���Ԃ������B �����̔ޏ��̏A�E����R�l���Ȃ��ɒT�����Ƃ́A�o�ϓI�ɕn�������ŕ�����������邱�Ƃɓ������B ����Ƃ��ɂ́A�^�C�Ƃ��̎��ӏ����̏����̌����Љ�Ɩ��ł��ꂽ�z�[���E�y�[�W�̃^�C�����̘A����ɓd�b�����Ă݂����Ƃ��������B �l���d�b�����T�C�g�ł͂Ȃ����A���̎�̃T�C�g�ŁA�ʂ̈Ӗ��ł̏��������ɂȂ��Ă���Ƃ������ǂŕ��ɂȂ����Ƃ��낪����Ƃ������Ƃ��A�����ň����������Ă������ɂ���Ēm���Ă����B ����ł��A�m�������ގv���������B �u�����̏Љ�ł͂Ȃ��A���łɌ�������������������̂ł����A���̑���Ƃ̌����̎菕�������Ă��炦�Ȃ��ł��傤���v�Ɠ����������₢�ɁA�d�b�̓��{�l�j���͖��邭���J�ȏ����̕Ԏ������ꂽ���A70���~�̎������K�v�ł���ƍ�����ꂽ�B ���̊z�̓^�C���n�̗p�҂ł���l�ɂƂ��āA���̃P�[�X�ł��������Ă��܂����瑼�̃P�[�X�ւ̃��g���C�܂łɂ͂���Ȃ�̊��Ԃ�p�ӂ��Ȃ��ƂȂ�Ȃ��\�������邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B �o����������Ă����̂́A������{�@�ւȂǂ̐��ʓ˔j���́A�l���̕����L�Ӌ`�炵�����Ƃ������B �o���R�N�œ����Ă���r���}�l���Љ�Ă�����āA���̐l��������ǂ�����ĘJ��������ɓ��ꂽ����q�˂�ƁA����̓I�ɖl�炪�ǂ̕������炱�̖����������������悢�̂��A�����ɕx�b�������邱�Ƃ����������B �������A���̕��@�ɂ͏�ɂ�����x�̊댯��`���o�傪�K�v�ł���B ���l�̒m�l���璉�����Ă����悤�ɁA�b�����l����̃^�����݂��Ȃ��Ƃ͌���Ȃ����炾�B �^�C�ɂ̓^�����݂ɕ����o��P�[�X������̂͗L���Șb�ł���B �؍��������Ȃ��҂ɑ��閧�������̑ΏۂɂȂ�̂��ǂ����͒m��Ȃ����A�\����D���ȃ^�C�l�Љ�Ō��߂����閧�����ȏ�A���ӂ�������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B ����ɁA���̓l�b�g�ŏ�����Ƃ����ԂɊg�U���鎞��ł�����A�l�����̂悤�ȏ����ȑ��݂��N���̂ǂ����ł̃l�^�Ƃ��ėL�p�Ȃ��̂��Ƃ͎v���Ȃ����A�p�S����ɉz�������Ƃ͂Ȃ����Ƃ����́A����܂�PC�̃X�N���[���ɉf���o����Ă������b�Z�[�W�������Ă���B �l�l�b�g���[�N���L���邱�Ƃ����̑��������ɋ߂������Ƃ������Ƃ͌����Ă����̂ɁA������v�����ēW�J���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����W�����}�ɓ�������Ȃ�����A�l�����͗��������Ĉ��S�ł���������Z���N�g���邱�ƂɓO����ق��Ȃ������B �����A�Â��j���[�X����ł��Ȃ��B �ő�̋t�]���͔ޏ���ID�̑��݂�k������ꂽ���Ƃł������B �ޏ��͏f��ƂƂ��Ƀu���[�J�[���x�����i�D�Ńo���R�N�ɏo�Ă����̂����A���̃u���[�J�[��A�r���ōl������x�@�E�R����̍S���ɔ����āA�r���ɗ�����邱�Ƃ̂ł����k�^�C�̐e�ʂɎ���������ID�J�[�h��a���Ă��邱�Ƃ����������̂��B �Ȃ������ɂ킽���Ă��̂��Ƃ���X�ɔ铽�������Ă����̂��Əf���ӂ߂邱�Ƃ͂��₷���B �������A������Â�A���̖Â̌����߂����{�l������Ƃ����āA�ނ�݂Ɏ��������̐������Ƃ��Ȃ蓾��g���ؖ����̂��肩�����₷�����l�Ɍ���Ă��܂���قǐ��_�I�ɗ]�T�̂��鐶���Ȃǂ���͂����Ȃ��������낤���Ƃ́A���A�҂Ƃ��Ă̕�炵�ɑ����ȃX�g���X������Ȃ�����ÂȂ���Ȃ�Ȃ������ޏ��̂��ɋ���l�ɂ́A�ɂ����炢�ɂ悭��������肾�B �f�ꂪ�^���������Ă��ꂽ�Ƃ������Ƃ́A�l���F�߂�ꂽ�Ƃ������Ƃł�����B ���������l�͂��̃v���C�h�����ɁA�k�^�C�̍����n��ɒ��߂��e�ʂ̉Ƃ܂ŋ삯���A��l�Ԃ��ID����邱�Ƃ��ł����B ���̒n��ւ̓��H�ɂ͌��⏊���������݂����Ă��邪�A�l�͊�p�X��Ԃł������B ���{�l�ł��邱�Ƃ̍K�^���ǂꂾ���̂��̂ł���̂�����������B �����Ď��ۂɁA���̃~�����}�[���{���s��ID�́A���̌�̊e��̏��ސ\���̗B�ꂩ�}���`�v���̗͂����邱�ƂƂȂ�B ����1�N�߂��̂��ɍĂіk�^�C��K�ꂽ�̂́A��͂�����W�̂��߂ł������B �u�V�����B�v�̓^�C�k���ƍ�����ڂ��Ă���A�k�^�C�ɂ́u�V�������v�ȊO�ɂ������̏�����������炵�Ă���B �ނ�E�ޏ��炪�����ł��Ă���̂́A�ǂ������ؖ���������Ă��邩��Ȃ̂��B ID��a�������Ƃ��̖k�^�C�K��ɂ���āA�ޏ���l�E�f��̑��݂��^�C�̓��ɈڏZ�����e�ʁE�m�l�̊ԂŊm�F����ĉ\�ɏ��A�ޏ���f��ւ̓d�b�A�����������ĂĂ���悤�ɂȂ����������ŁA�l���k�^�C�Ŕނ�E�ޏ���ɉ���Ęb�����Ƃ��ł���Ƃ����A�������̖�O�����������ȑO�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ������W���\�ɂȂ��Ă����B �����ŕ��������̂́A�ߗ����̐l�X�ɗ^������u���@�b�g�E�^�[���E�_�[�H�v�Ƃ���ID�̏d�v���ł���B �����W�̏����i�K���炱�̃J�[�h�̑��݂͒m���Ă������A�k�^�C�ł͂��ꂪ���Ȃ�e�Ղɐ\���ł��邱�Ƃ����������B ���Z�n�搧�����Ȃ����̂�����A���̐\���̂��߂ɂ��炭�g��������ƌ����Ă��ꂽ�ޏ��̒m�l�Ƒ����������B �����A�l�b�N�͂�͂�ړ����̐g���ؖ��������߂���P�[�X�B ����܂łɉ��x���܂����Ă����|�C���g�ł���B �������Ƃ��N�����̂ɁA�k�^�C�̓s�����悳�������Ƃ������Ƃɂ��A���͑����i�K�ŋC�Â��Ă͂����B �l�b�g�Ō������čŏ��ɏo�Ă����̂́A�k�^�C�Ŕޏ���{���Ƃ��Ď���Ă����^�C�l�ƒ�������Ď萔���Ǝӗ�����A�������k�^�C�œy�n��ޏ����`�ōw������ΐ������̐g���ؖ������o��Ƃ�����������炾�i�������A���̏ؖ����ł͖k�^�C���o�邱�Ƃ�������Ȃ����߁A�ޏ��ƕ�炷���߂ɂ͖l���g���k�^�C�ɐE��������K�v������j�B �����A�ړ����̃��X�N�͏�ɔO����������Ȃ������B �������A����Ɉ��S�Ȓm�l���o���������Ƃ͑傫�ȗ�݂ɂȂ������A�擾�Ɋւ�����̎葱���̗���ɂ��Ă��������i�B �����āA�����������ǂ̕��ʂ�ڎw���Ė͍�����悢�̂��A�S�[�����������邱�Ƃ��ł����̂͑傫�Ȏ��n�������B �܂��A���̖K��̌���k�Ƃ��āA�ޏ��ƖK���Ƃ̓d�b�̂���肩��A�����l�������ޏ��̌̋����������Ƃ�����A�n�C���[���c��ł���h���C���@�[���Љ��ƌ����Ă��ꂽ�e�ʂ������B ��q�����悤�ȓ�������������u�V�����B�v�ɖK�₨���āA���т������ď����ł��M���ł���^�]��̊m�ۂ͔��ɂ��肪�������Ƃł���B �o���R�N�ł͓��^�C�̃n�[�t�ł���m�l�̃T�|�[�g�āA�u�e���|�����[�E�p�X�|�[�g�v�Ȃ鑶�݂ɒH�蒅�����B �ނ̒m�l���Љ�Ă��ꂽ�f�Տ����c��ł���r���}�l�́A����ɂ��̃e���|�����[�E�p�X�|�[�g�������Ă���Ǝ҂̓d�b�ԍ��������Ă��ꂽ�B ���̃r���}�l�Ǝ҂́A�������g�����̃e���|�����[�E�p�X�|�[�g���擾���ă^�C�ɑ؍݂��Ă���ƁA�ւ炵���Ɍ����Ă��ꂽ�B �f�Տ��̎В�����ɂ��A�������N�Ń^�C�ƃr���}�̊Ԃŋ��肪�ł��āA�r���}����^�C�����ɗ���Ă����܂ܑ؍��������Ȃ��l�X�̂��߂ɁA�^�C�ƃr���}���O�ւ͏o���Ȃ����A�؍���^������ʃp�X�|�[�g�Ƃ��Ĕ��s����Ă���Ƃ����B �܂������l�����̃P�[�X�ɂ҂�����ł͂Ȃ����B �ޏ���l�̗F�l�E�m�l�����Ƒ��k�ɑ��k���d�ˁA�����ŏ����ɏo�悤�ƌ��߂��B �u�����v�Ə������̂ɂ́A2�̗��R������B �ЂƂ́A2011�N7���̃^�C���I�����߂Â��Ă��邱�Ƃ������B �O�N��UDD�f���̂悤�ȎS�����J��Ԃ���Ȃ��Ƃ�����Ȃ��B ���Ƃ������ƂɂȂ�A�R�̌���Ɉ��������闦�͐��{�ɒ��ˏオ�邾�낤�B �܂��A�I���ŏ�������̂�UDD�h�̃v�A�E�^�C�}�ł��낤���Ƃ́A�^�C���O���킸�قƂ�ǂ̐l�X���\�z�ł��Ă������AUDD�h�̐��_�I�x���ł���^�N�V�����͍ݐE���ɂ��s�˔j�I�Ȑ�������{�������A���̐l�C�̔錍�͎����̌o�ό���ɂ���������A�݃^�C�O���l�̔r�˂ɋ߂����I������Ȃ��Ƃ͌���Ȃ��B ���{�l�ɂƂ��Ă��A�ނ�����������Ƀ^�C�ɕ�炷���Ƃ����B�U�ʂ�͂��o�ʂŋ����Ȃ��̂ɉ��ς��ꂽ���Ƃ́A���̎����̍݃^�C�҂Ȃ炾������m���Ă���B ����ɁA���ۃv�A�E�^�C�}�͌���Ƃ��ă^�C�l�J���ҍŒ������300�o�[�c�ɁA�呲�ŒᏉ�C����3���o�[�c�ɂ܂ň�C�Ɉ����グ��Ɛ錾���Ă����B ����Ȃɋ}���ȋ��^�A�b�v���o���ꍇ�A��K�͂ȃ��X�g�����e�n�ŋN���蓾�邱�Ƃ͖ڂɌ����Ă���A�����Ȃ�ƍŒ�����ɐ����̂Ȃ��r���}�E���I�X�E�J���{�W�A����̏o�҂��J���҂Řd�����Ƃ����Ƃ����o���邱�Ƃ��e�Ղɑz�������ȏ�A�^�C�l�ٗp�g���m�ۂ��邽�ߖ@�I�ɊO���l�J���҂���ߏo���ɂ����錜�O���o�Ă���B �l�����͂��Ƃ��}���������悳�������B �����Ă����ЂƂ̗��R�́A���̃e���|�����[�E�p�X�|�[�g�\���̂��߂ɂ́A�ޏ����r���}�����܂ŏo������K�v�����������Ƃ��B �S���҂́u�s���̓����ŕ߂܂�悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��v�ƌ������A����A�W�A�̐l�X�������܂莆�����Ƃ��ȒP�ɔj��Ă��܂��̂��A�l�͂��܂�ɐ��������߂��Ă����B ����A���s�͋�����Ȃ��̂��B �������A�Ռ��ɓ��炸��ΌՎq���A�ł���B �l����Ђ��������Ă�����Ĕޏ��Ɠ��s���A���Ƃ̈ꕔ�n�I������邱�Ƃɂ����B ���ӂƖ��̎����ɑO��Q���Ȃ��Ŏw��̓����}�������A�l�����͓�������͂��̎Ԃ����������҂��āA�v���茨��������H������B ��������Ԃɂ͌q�����Ă����Ǝ҂̒S���҂̓d�b�ɁA�N���������Ȃ��Ȃ����̂��B ���̓������œd�b�����ł����ƁA���{�ł͌x�@�Ɍ����点�Ǝ���Ă��d���̂Ȃ����炢�̃��_�C�����������B ���̂��тɕ������ꂽ�Ăяo���̉��y�́A�l�炪���̐��̒��ōł����������Ȃ��ȂƂȂ����B ���̂̂��ނɂ��f�Տ��В��ɂ��A�����d�b���Ă��Ȃ���Ȃ����Ƃ��m���߂邾���̐������������B �ޏ��̗��_������ɂ��A�S�����˂肠������B �܂��A�l���s�p�ӂɁu�l���̈�匈��͖����v�Ȃǂ�BBS��c�C�b�^�[�Ȃǂɏ��������ƂŁA�s�p�ӂɎ��͂̐l�X�̐S�z�������Ă��܂��A���̌㉽�̕��ł����Ɏ��g�̎���i�߂錋�ʂƂȂ����B ���ꂩ��قǂȂ��A�~���̐_�l�͈ӊO�ȕ�������p�������Ă��ꂽ�B �l�������e���|�����[�E�p�X�|�[�g�\���ɓ����̂ƕ��s���āA���łɃ^�C�l�j���Ǝ��������ς܂��Ă����ޏ��̏f��̓o�b�g�E�^�[���E�_�[�H�̐\�����������n�߂Ă����B �f�ꂪ�o���R�N�ɂ��鐔���Ȃ��u�V�������v�̗F�l�Ƙb���Ă��钆�ł��̘b����b�̒��Ɏ��R�ɏo�Ă����̂ł��낤�B ���̗F�l���������o�b�g�E�^�[���E�_�[�H�̐\�����n�߂悤�Ƃ��Ă���Ƃ����b���A�ޏ������������B �����āA�l��͂������܂��̐K�n�ɔ�я�����B �f��̗F�l�̓s���ɂ���Đ\���Ɍ�����������]�O�]���A�҂����킹�ꏊ�⎞�Ԃ��牽�ЂƂ���Ă��炦�Ȃ����A�悤�₭�l���6���ɓ͂��o���o���A���̌�����яd�Ȃ�{�l�o�����̓��̕ύX�E�S���҂̐����̏��Ȃ��ƃA�o�E�g�����ɂ���₫�����������Ȃ�����A�Ƃ��Ƃ��ޏ��͏A�J���T�����߂̃^�C�؍��ƕa�@�ɒ��鋖����ɓ��ꂽ�B �s���������A�����͉�X�����߂Ă����o�b�g�E�^�[���E�_�[�H�ł͂Ȃ������B ����ɁA����Ƃ��ɏ�Ԃ����^�N�V�[�̉^�]��ɂ��A�o�b�g�E�^�[���E�_�[�H�������Ă����A�x�@�Ƀp�X�|�[�g�������邱�Ƃ��ł��Ȃ���ΐ�o�[�c�̔����������Ƃ��������B �������A�^�C�ł̑؍݂ɑ���ؖ����邱�Ƃ��ł��āA�l�����̑傫�ȁA�傫�ȑ����͓��ݏo�����Ƃ��ł����B �ޏ��͂悤�₭�z�̂�����ꏊ�ɏo�āA�����̈ӎv�ł��̃o���R�N��������Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B ���邢���œ��X�ƌg�ѓd�b�Ɍ������āu�V������v��b���ޏ��̔����Ƃ����p�ɁA���t�ɂȂ�Ȃ��z���̉Q�������������߂����ł���B �ޏ��ƕ�����2�N�Ԃ́A�ӂ���ł������߂��v���o�̐��ƁA�߂��������Ԃɑ�������͔���Ⴕ�Ă���B ���A�͖�̂��Ƃ��˂��i�݁A�o������2�N���O�̂��Ƃ������Ƃ͂ɂ킩�ɐM���������B ���̈���Ŗl�����͓f�����J��Ԃ������Ȃ����炢�����A�o���̌����Ȃ��g���l���ɐg��u���Ă����B �����A�o���R�N�̂ǐ^�ŃJ�����I���̂悤�ȕی�F��g�ɓZ�����Ƃ������A�����̐������I������̂��ƌ���k�킹����́A�ǂ�����Əd����������Ƃ��Ƃ��ߋ��Ƃ������̃A���o���ɂ��܂����܂ꂽ�B ���ɓ�������������Đ���Ԃɏo�������̒��́A���̗z����ῂ����A��̐������܂ł��Y��邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B �� ���T�C�g�̑��̃y�[�W�ł����l�ł����A�����I�ɂ͌R�������ł��邽�߁A�~�����}�[���{���ύX�����u�~�����}�[�v�Ƃ��������͋��̂̂܂܁u�r���}�v�ƕ\�L���Ă��܂��B�������A�����{�̂��Ƃ́u�~�����}�[���{�v�Ƃ��܂����B�܂��A�u�V�����v�̓r���}������̌ď̂̂��߁A�u�@�v�������\�L�Ƃ��܂����B�{���́u�V�������v���g���p���Ă���ď̂��g�������̂ł����A�{���ł��G�ꂽ�悤�Ɂu�V�������v�͎��������̌��t���u�^�C��v�ƌĂԂق��A�����������g���u�^�C�l�v�ƌĂсA���������̋��Z�����w����ʓI�Ȍ��t�������܂���̂ŁA�����ł̓^�C�����Ƃ̍���������邽�߂Ɋ����Ă��̕\�L���̗p���Ă��܂��B |
| �U���P�O�� �ߍ��A�����ɏ������e���ǂ�ǂ�d�����̂ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA����́A�^�C�̌g�ѓd�b�ł̃j���[�X�E���[���b�ł��ЂƂB �挎�������肩��A�ˑR�l�̌g�ѓd�b�Ƀ^�C��̃j���[�X�E���[�����͂��悤�ɂȂ����B���N�O�ɂ��܂���������������A���̂Ƃ��ɂ͍ŏI�I�Ƀ��[���z�M���~���Ă�������B �^�C��w�K�̂��߂ɂ͂����̂����A�������������ēǂ݂ɂ����B ����ׂ߂Ȃ��珬���ȃ^�C������ǂ��ƁA�V�ዾ�ɗ���N��ɂȂ����C���ɂȂ邱�Ɛ��������B �������ɁA�����\����傫�����邱�Ƃ��ł���̂����A��������ƍ��x�̓^�C��ȊO�ł̕����\�����傫�����Ėʓ|���B �������A���Ȃ̂́A���̎�̃j���[�X�E���[���A����ɐ��\������Ƃ������ƁB �܂��A�l�̐������ԑт͎d����A�ǂ����Ă���ɕ�B �j���[�X�E���[���͒�6������z�M���n�܂邪�A�A�Q�O�Ƀ��[���̎�M������������I�t�ɂ���̂�Y��Ă��܂��ƁA�����̌{�̂��ȂȂ���낵���A���̎��Ԃ���Ђ�����Ȃ��ɋN������邱�ƂɂȂ�B ����ɁA�E��ɂ���Ƃ��ɂ��}�i�[�Ƃ��Ď�M���������Ă��邽�߃o�C�u�ɂ��Ă��邪�A��������Ɠd�r�̏��Ղ��ُ�ɑ����B �d�����I����ă��[���E�`�F�b�N����ɂ��A�ЂƂ��f���[�g���J��Ԃ��̂����������B �ȑO�͐E��̃^�C�l�X�^�b�t�ɁA���̎�̃��[�����͂��Ȃ��悤�Ɏ�z���Ă�������B ����Ȃ̂ɁA�Y�ꂽ����ɂ܂�����Ă����Ƃ����킯���B ���̂Ƃ��Ɠ����悤�ɁA������^�C�l�X�^�b�t�ɗ��B �����āA7���ȓ��ɔz�M���X�g�b�v����Ƃ������[����������B �Ȃ̂ɁA���ꂩ��2�T�ԉ߂��Ă��A�j���[�X�E���[���͎~�܂�ǂ��납�A�z�M���������āA1��50�����͂������o�Ă����B ���������A�\������ł����Ȃ��ǂ��납�A�ȑO�z�M�X�g�b�v�������Ă��郁�[��������Ȃɂ��͂��Ƃ����̂́A���������ǂ������킯���낤�B �������A�������ł��Ȃ��B ���[��B �G���|���A���̌g�уV���b�v�Ȃ�����ł��邾�낤�ƃ^�C�l�X�^�b�t�ɕ����āA������ɏo���������A�����ł��E��̃^�C�l�X�^�b�t��������̂Ɠ������@�����������Ƃ��ł��Ȃ������B �܂��E��ŕʂ̃X�^�b�t�ɐq�˂Ă݂�ƁA�ʐM��Ђł���AIS�̃T�[���B�X�E�Z���^�[���Z���g�����E���[���h�ɂ���Ƃ����B ����ɐ�����A�����Ŏ葱�������āu3���ȓ��Ɏ~�܂�܂��v�Ƃ������t��������Ăق��Ƃ����B �������A�葱���������u�Ԃ���A�z�M�͂܂������~�܂����̂������I ������O�̂��Ƃ��A�Ђǂ��������B ���ɒS�����U�b�N���悤�₭���낹���C���B �����ŁA����l�������Ƃ��������B �ЂƂ́A�u���f�v�ɂ��āB �^�C�ł͌�����ʋ@�ւŌg�ѓd�b�ɂ�������ł���l���������A��ɂ͓��[��R���r�j�̑O�ȂǂŎ������Â���A��ʂ��ǂ�����Ă��鉹���悭���ɂ��B �A�p�[�g�̘L���ł͉��x�����x���傫�ȉ��łǂ����̕������h���h���h���h���m�b�N���鉹����������A�I�����߂����́A�����ł������ꂵ���A����△�v��Ɍ��Ă�ꂽ�d���Ȃǂŕ����ɂ��������ɍs�����j�ނǂł��������҂̗��ĊŔ�����ł����ƕ���ł���B �g�ѓd�b�ւ̃j���[�X�z�M�͐�`���[���ł��Ȃ��킯������A�^�C�l���炷��u�Ȃ��T�[���B�X�z�M�����f�Ȃ̂��H�v�Ǝ���Ђ˂��Ă��܂���������Ȃ��B �l�̌����Ƃ����ʂł́A���{�l�͍s���߂��Ă���Ƃ����������A��������X�ɂ͂��邾�낤�B �������A�Ⴆ�o���R�N�ɂ͍��ی�������ʂȂ��ƂƂ͍l���Ă��Ȃ��悤�Ȃӂ�������B �������̓R�X���|���^���Ȃ��̊X�̓������Ƃ������邪�A����ŁA�����������m�̌�����]�܂Ȃ��l�������̂��������B �����ɂ���̂́A���l�ւ̔z���̂�����Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �u�w���E�P�[�E�g�D�A�i�g����j�v�Ƃ����^�C������ɂ��邽�сA�ł͂Ȃ������������Ȃ݂Ȃ��̂��A�Ȃ����l����w�Ȃ��̂��A�Ɗ����Ă��܂��B �����ЂƂ́A����ς�^�C�͂��̂܂܂ł����̂�������Ȃ��Ƃ������ƁB ����͂����܂Ŗl�̂悤�ȍ݃^�C�O���l�̋Y�ꌾ�Ȃ̂����A�u�ߐH����ė�߂�m��v�ƌ�����Ƃ���A�o�ϔ��W�ƂƂ��ɐl���Ɋւ���l���������シ�邾�낤�B �ł́A�l���g�͕֗��ʼn��K�ŋߑ�I�ŁA���f�ȃj���[�X�z�M�Ȃnjg�я����҂̋��Ȃ��ɂ͓͂��͂��̂Ȃ��l���ӎ����������^�C�̏�����҂��]��ł���̂��낤���H �������A�����͔ۂ��B �u�C�O�œ����v�̂ł͂Ȃ��A�u�^�C�ŕ�炷�v�Ƃ������Ƃ������l���ăo���R�N�������n�߂��l�́A�N���e�B���f�[���i���b�h�E�u���j�̃L���b�v��������Ă����Ȃ����Ƃɕ��𗧂Ă�̂ł͂Ȃ��A������u�J���܂����v�ƃ��W�Ɏ����Ă����ă^�C�̔��݂����Ȃ���A�W�������ł����J���Ă��������A�V�����r�Ɏ��ւ��Ă��������ł���R�~���j�P�C�V�������y���ނ��ƂɈӋ`�������Ă����̂ł͂Ȃ��������B �����A���̎�̘b�ł́A�����l�̓����͓����Ƃ���ɋA���Ă���B �o�J�{���̃p�p�̖����ǂ���B �u����ł����̂��v |
 |
| �R���Q�U�� �@�܂��A�߂����ł����Ƃɂ��ď������ƂɂȂ��Ă��܂����B �@�����{��k�Ђ́A��㖢�]�L�̔ߌ��������炵���B���{�ϑ��j��ő�̒n�k�A�l�X�⌚���E�ԂȂǂ��ۓۂ݂����Ôg�A�������J��Ԃ��u�^���E�K�X���܂��U�炵���K�X�^���N�����A�����āA���̌�̐����҂��������|�Œ��ߏグ�Ă��錴�q�͔��d�����́B�N�����ڂ�w���A�Ȃ�Ƃ�����ɂ��Ė����ɂȂ���ׂĂ����������Ɗ肢�����A�ߎS�ȏł��邱�Ƃ́A�N���������Ă���B�e������̎x�����������A�܂��A���{�ŋN���������̐k�Ў����l�A�\���◪�D���������Ȃ����{�l�̌����������_�̍����ւ̏^���N�����Ă��邪�A���̐k�ЂŖS���Ȃ�ꂽ���X�A���̉Ƒ���e�މ��ҁA�Ɖ���E���ȂǗl�X�Ȃ��̂���������Ў҂ɂƂ��ẮA���̐S�̒ɂ݂��a�炮�̂͂��̂��ƂɂȂ�̂��B�����āA�c���ꂽ�e��̖��͂����������ɂȂ������x�̈����������̂��B���̎����ɔߊϓI�ɂȂ�߂���̂��悭�Ȃ����Ƃł���Ƃ͕������Ă���B�����A�܂������ƌ����������Ƃ���Ƃ��A�܂𗬂��A�������̕\��ɏd�ꂵ���e���������Ƃ�����Ēʂ邱�Ƃ͂ł��ʁB �@�ߌ��̃j���[�X���܂����E���삯�����Ă���Œ��A���{�ł̒n�k��������12���o�߂���3��24���A���x�̓r���}�i�~�����}�[�j�E���I�X�E�^�C�����t�߂Ń}�O�j�`���[�h6.8�̒n�k�����������i�ȉ��A3�������k�ЂƋL���j�B���̔����̉Ƒ��͂��̐k�Ђ̔�Q�ɑ������\��������B���Ƃւ̘A���͂܂��Ƃ�Ȃ��i4�����{�ɘA�������A�����ł��邱�Ƃ��m�F�ł��܂����B�������A���̒n��ł͓Ɨ������߂閯�����ƃ~�����}�[���{�R�Ƃ̌���Ԃɓ����Ă��܂��j�B �@10���ɂ͉_��ȁi�����j�ł��n�k�i�}�O�j�`���[�h5.8�j���N�����Ă���A25�l�̎��S�A300�l�ȏ�̕����҂��m�F����Ă���A24���̒n�k�Ɠ������f�w��ł̒n�k�����ł���B����̏��\�f�������Ȃ��B3�������k�Ђł͌��݁A����75�l�E������111�l�ȏ�Ƃ����j���[�X���`����Ă��Ă��邪�A�^�C���͂Ƃ������A�r���}���E���I�X���ł͍��Ƃ̊Ǘ��\�͂�C���t��������A�ڍׂ̊m�F�ɂ͑����̓������K�v�Ƃ���邾�낤�B�k���̂���r���}�ł͂��̎��ӂɏZ�ޖ����̑����ƃ~�����}�[���{�Ƃ̑Η������[���A���{���炿���Ƃ����m�F���Ȃ����̂��A���m�Ȑ��l��c������C������̂����^����B���{�ł̃j���[�X�ŐG����Ă���悤�ɁA�x�������{�̒~���ɉ�A��ЎҒn��ɓ͂��Ȃ��\���������B����Ɍ��y����A���̎��Ԃɕt������Ń~�����}�[���{���x�z�͂����߂悤�Ƃ��鋰�������B���䌒�i�������S���������{�f�����E��A�A�E���T���X�[�`�[���炭�H���Ă����~�����}�[���{�̈����͍������A��X���{�l�͂��̐��{�̔Ԃ��k���N�ɂ��Ă̂悤�ɂ͒m��Ȃ����낤�B�ɂ��ɂ݂�[���m�邱�Ƃ̂ł���ЊQ������A���̋@����^�����邱�Ƃ̂Ȃ��ЊQ������B�V�Ђ��l�ЂɌq����A�ߌ�������Ȃ�߂��݂݂����Ȃ��悤�F��ق��Ȃ��B �@��Ȃ�n�𗣂�ĕ�炷�ƁA���ۂ��̏ꏊ�ɂ���̂Ƃ͂܂�������A���L�����Ǝv���Ă��͂��Ȃ����ǂ������s��������邱�ƂɂȂ�B�����āA2006�N�N�[�f�^�[��2008�N�X�����i�v�[����`�����E2010�NUDD�f���ƁA�o���R�N�ő������N���邽�тɁu���v���v�ƈ��ۂ��C�����Ă��ꂽ�Ƒ��E�e�ʁE�F�l�����ɉ��߂Ċ��ӂ̔O���N���Ă����B����܂ŐS�z�����鑤�ɂ������Ă������́A�������S�z���鑤�̋C�������[���ɋ��߂Ȃ��Ƃ��낪���������ƂȂ��Ă���B�����āA�����������̂��A�������ł��邱�Ƃ���邵���Ȃ��B��_�W�H��k�Ђ�̌������g�Ƃ��āA�����v���B �@���̂��т̓����{��k�ЁE3�������k�Ђł��S���Ȃ�ɂȂ�ꂽ���X�A��Ђ��ꂽ���X�ɂ͐S��肨����ݐ\���グ�܂��B |
�Q�O�P�O�N
| �T���Q�R�� �@���{���p�ӂ��������o�X�ɏ���āA�\���N���[���ł��Ȃ������ɋA�ȋq���������Ԃ����B3�����瑱���Ă���UDD�ɂ��f���̏I���ɂ���āA�c�ɂɋA��l������Ȃ��Ă������̃j���[�X�ԑg�ł́A�e���r�J�������o�X�ԓ��ɏ�荞��ł��̑f����f���̂��ǂ����Ō������Ă���l�X�̕��͋C���ɂ��ݏo�Ă��邩�Ǝv���A�o�X�Ɍ������ĕ�������A���̃o�X�����Ԃ����肷��Ƃ��ɏΊ�Ŏ��U���Ă���l�X�̎p������ꂽ�B �@�v���Ԃ�ɁA�S�̉��̕�����A�{�肪���ݏグ�Ă����B �@����UDD�f���̔�Q�͑傫�������B2�����ȏ�ɋy���UDD�̐苒�n��ł͋@�\����~�����B��ɏ����Ɍg����Ă���l�X�͂܂������̂���グ��Ԃł������B���{���V�����łȂ��A�����̃W���[�i���X�g���]���ƂȂ����B������ʂ��~�߂��A�e���r�ǂ��P���Ēׂ��ꂽ�BATM�⏤�X�ł̋��D�����������Ŕ������A�ɂ߂��ɂ͂��������ɕ����������B���̖��ɁA���̏Ί�ł̋A���B����ȉ��\�ȏΊ炪���������ŗ���Ă��邱�ƂȂǁA�܂���ʂ��Ă����̂��B �@�^�C�ł͓s�s���ƒn���Ƃ̋���i���͑傫���B���̗��ʂɂ��Ă��܂������ʂ��Ⴄ�B�^�C�l���g�A�悭�u�^�C�ɂ͓�̍�������B�^�C�ƃo���R�N���v�ƌ��ɂ���B����̑����͂��̓�҂̑Ό��������Ƃ�������B�������A����Ȍ��t�����ɂ���l�X�����āA���̃^�C�����邱�Ƃ�]��ł͂���܂��B������n���o�g�҂�����Ƃ����āA���������̈����N�����������ւ̐ӔC�����������y�����Ƃ������؍����͂Ȃ��͂����B �@���ׂĂ̎Q���҂����D����ɉ��S�����킯�ł͂Ȃ��B�����ꕔ���Ƃ����Ă������B����ɁA�f���Q���҂ɂ͎��������̎��ӂ̂��Ƃ�������Ȃ��悤�ȁA���̎�̏����ɂ�����Ԃɂ͂Ȃ��Ă����͂�������A�����͈����Z���čl���Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�܂��A���D����ɂ������āA�Ɛl���߂܂����킯�ł��Ȃ��B���ׂĂ̔Ɛl��UDD�W�҂��ƌ��߂���̂͑��v���B�����A���Ƃ̔��[�͖��𐭎��I�����ɑi���邱�Ƃ̂ł��Ȃ��������Ƃɂ���B���������Ӗ��ł͔���Ȃ��ƂɁAPAD�����̃f���݂̍���Ɏ�����^�����̂��낤�Ǝv���B�������APAD�Ƃ̑傫�ȈႢ�́A���̍������͂�ǂ����悤���Ȃ��s����Ȃ܂Ȕ̏�ɂ�������Ă��炸�A����܂ł̈���͂����̍K�^�������̂��Ƃ��������悤�̂Ȃ���ۂ��c�������Ƃł���B���ۓI�ɂ��A���̍��̗����Ă�������������M���͂قڎ��Ă����Ƃ����Ă������낤�B���ꂪ�ǂ��������ʂ������̂��A�n������f���ɎQ�������l�X�͗����ł��Ă���̂��B���邢�́A����ɂ��Ă�����ƌ��������čl���悤�Ƃ������Ƃ��������̂��B������N�����Ă��邩��Ƃ����āA���ׂĖڐ�̃j���W���ɂ���Ă��������Ȃ��̂ł���A�ނ�E�ޏ���̌����u�����`�v�ȂǒB���ł���͂����Ȃ��ł͂Ȃ����B��q�́u�����̍K�^�v�������炵���̂͂��������N�Ȃ̂����A������x�l�������Ă��炢�����B����͂Ƃ���Ȃ������A�n���̐l�X�����߂Ă����A���̍��ŗB����l���Ƃ������C�̂������v�[�~�|�������Ȃ̂ł͂Ȃ����B���邢�́A���̉������z�Ȃ̂ł͂Ȃ����B����������x��Ȕ��z�������Ƃ��Ă��A�����āA���ꂪ�P�ӂ����ł͂Ȃ����̂ł������Ƃ��Ă��B �@�V�g�̔��݂����^�C�����ɁA���������ݏZ10�N�̈�l�̓��{�l������Ȑ����𐂂��̂͂���Ⴂ�ł��邱�Ƃ͗����ł��Ă���B������A���̕��͂͂����̋Y���ɂ����Ȃ��B�������A�^�C�l�����̍�������Ȃ������A���g���^�C�l�ł���ƌւ�����Ƃ��A�l���Ⴄ�p�x����ł͂��낤�����̍��������A���̈����S�ɂ�����Ƃ���ῂ����������Ă����B���ꂾ���ɁA�u�������Ă�����Ă���v�u���b�ɂȂ��Ă���v�Ƃ������ꂾ���ł͍ς܂Ȃ��Ƃ������������Ă���͂����B�n�k���N�����Ă����D��\�����N���Ȃ������o�g�Ƃ����l�̐l�Ԃ̈ӌ��Ƃ������̂������Ă����Ǝv���B �@���A������������̉J���~�����B�ǂ����Ă��̉J�����������O�ɍ~���Ă���Ȃ������̂��B���̒���ɂ��̌b�݂̉J���������Ȃ�A�����Ƃ��̃^�C������v�[�~�|�������̕s�v�c�ȗ͂��܂��Ƃ��₩�Ɍ��ꂽ���Ƃ��낤�B�����A21���I���}�������E�ɂ́A���̂悤�ȗނ̐_�b�͏I�������̂���A�ƌx�����Ă���悤�ɖl�ɂ͌�����B �@�����̃j���[�X�ł́A�o���R�N�s��������I�ɓ��H��{�݂̐��|����`���Ă���p����Ă����Bⴂ�X�|���W����ɉ��V���A���𗬂��ނ�E�ޏ���̎p�ɋ~��ꂽ�B���Â��_�ɕ���ꂽ�����������̃o���R�N�̉ߋ�������Ă���悤�ł������B |
 ���@���̉���4�������Ă���܂Ȃ��Z���g�����E���[���h�i5��22���j  ���@���̂��ł����L����l���炵���L�����������߂�v���g�D�[�i�[���i5��22���j  ���@�O�o�֎~����30���O�́A�l�̎p�̂Ȃ�20�����̃g�����[�i5��22���j |
 ���@���Ɍ����鍕���i���������̏��E5��19���j  ���@�������߂ɑ���l�X�ō��݂����Z�u���E�C���u���i5��19���j  ���@���̗����A�\�k�ɔ����V�����ŃK���X��������R���r�j��18�F00�ɕX�i5��20���j  ���@�l�ł������Ԃ��͂��̎��ԁA�g�����[�E�\�C15�͕��i5��20���j |
�T���Q�O�� �@���ȏL���o���R�N���A�Ƃ��Ƃ������̌��悤�ɂȂ��Ă��܂������B���ꂩ���X�̐����͂ǂ��Ȃ�̂��A2000�N�ɂ��̍��ŕ�炵�n�߂Ă��珉�߂āA���O�ދ���o���R�N������Ƃ����ň��̎��Ԃ���������l���ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��Ɗ������B����܂łɂ��o���R�N�́A2006�N�̌R���N�[�f�^�[�A2008�N��PAD�i�����`�s���A�������^�N�V���h�j�ɂ���X�����i�v�[�����ۋ�`�苒�ȂǁA���݂̓��{�ł͍l�����Ȃ��ǖʂ��}���Ă������A�����UDD�i���ƍٖ��哝�����EDAAD���^�N�V�������h�j�����́A����܂ł̂ǂ������l�������������Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��ْ������o��������B����ɂ́A���ۂ̎����҂̐�����Ԃ̒����ɉ����A����܂ł̎��������{�����̑������s�X�n�ł���o���R�N��������Ȍ��ꂾ�����̂ɑ��A����̓f�����s���S���Ɉڂ��Ă��āA�������A16���ɑ傫�ȏՓ˂̂������{���J�C�n�悩����{�l���Z��Ƃ��čŋߐl�C�̍����s�A�|���p�j�b�g�ʂ�i�X�N�����B�b�g�E�\�C24�j�̓�����܂ŋ͂���P�q�̂Ƃ���܂ŋ߂Â����Ƃ��������I�ȋ������o������B����ȏ����o���Ŏn�߂Ă���A5��19���ɂ�UDD��]�w7�������哊�~�������̂́A�c�}�g���\�k�ƂȂ����Z���g�����E���[���h�E�`�b�h�����Ȃǂɕ����Ă�����B���������̕Б��ŁA�^�C�Ƃ��������̂����̎�����[�ɂǂ��ω����Ă����̂��킩��Ȃ��Ƃ����A���ߖ����ւ̕s���̂ق����傫�������B �@����܂ł̃^�C�̓����̗���͕ʍ��ɏ���Ƃ��āA���̑����͓��{�̕ɂ�����悤�ɁA�K�������ł��鑤�ʂ������B�^�N�V�����̐������o�ϓI�Ɍ��サ�����ƂɃo���}�L������������āA����܂łɂȂ��_�����̌����ւ̈ӎ����萶���A��������̊�������L����ێ�w�Ƃ̑Η��ɂȂ��Ă���̂͊m���ȂƂ��낾�낤�B�����A���̐k���ƂȂ��Ă���^�N�V�������̂������܂Ń^�C����̏����҂��������Ƃ������ł���A�ނ𒆐S�Ƃ����V�����͂ƁA�������o�b�N�ɍT����ێ琨�͂Ƃ̑Η��Ɉ�ʎs�����������܂ꂽ�`�ɂȂ��Ă���Ƃ������ʂ����낤�B�n���̐l�X�̗��Q�����낤���A�V�����͂ɂ���f���̍őO���ɗ����Ă����l�ԂƂ��ė��p���Ă��镔�������Ă���̂��B �@����A�����͒��ق�����Ă���B�����͐����Ɋ֗^���Ȃ����Ƃɂ͂Ȃ��Ă��邪�A����܂Ń^�C�͍����̂܂��Ɂu�߂̈ꐺ�v�Ŏ��Ԃ̉�����}���Ă����B���̍\�}�͂���܂ŁA�悭�ł����o�����X���Ƃ��Ă����B�����v�����I����Đ�Ή������I�������^�C�ł́A���݂����[�}9�������_������܂ʼn����̕]���͉��������ł��������A���[�}9���͐����Ƃ�R�����������̊i�t���ɉ��̖��𗘗p���悤�Ƃ���̂��t��ɂƂ��Č��Ђ����߂����B����A�����͐����ɒ��ډ�����Ȃ��̂ŁA������r����ɖ����Ӗ�����������Ă���B�܂��A�����̓^�C�����E�̒��_�ɂ�����̂ŁA�u�l�q�����P�Ӂv�Ƃ����n�ʂ��m�ۂ����B�K�v�ȂƂ��ɂ͍ŏI�I�Ȍ��f�������A����ȍ������A�����́u�|�[�i���j�v�ƌĂԁB�����āA����܂łɂ��q�ׂĂ������A�^�C�ł͍��R�̓������̍Œ��_�ɂ���̂������ł���A����܂ł������̃N�[�f�^�[�����R�ɂ���ċN������Ă����Ƃ�������������B�l��`�ł���Ȃ���A�����̎咣����������Ղ��ɗ��ꂪ���ȍ������̃^�C�l�Љ�ɂ́A�������������Z�b�g���Ă���鑶�݂��K�v�������Ƃ������ł��悤�B���ꂪ�܂��������}9���Ȃ̂ł������B �@�������߂̈ꐺ���Ă���Ȃ����Ƃɂ́A82�Ƃ�������W���Ă���ƌ�����B�܂��A���̗���㍑�������т��ѐ����Ɉӌ����邱�Ƃ�����B�����A���̗����ɊW���Ă̂��Ƃ��Ǝv�����A�����̌��Ђ�����Ă���̂͂ǂ����m���Ȃ悤���B����܂ʼnp�m���ւ������[�}9�������ɁA���̐l�q�����P�ӂɊÂ������^�C�����́A�u���̉��l�͎������̂��Ƃ��ȑO�Ɠ��������̎��߂Ō�����Ă��������Ă�����̂��낤���H�v�Ƃ̋^��������n�߂Ă���ƕ����B�N��������Đ������o�����Ƃ��āA����ł����������܂�Ȃ������ꍇ�A�����͂ǂ��Ȃ��Ă����̂��B�������̐l�C�����܂�ɍ����āA�c���q�͂��̌�p�҂��閼����͓̂���B����ȏ��ŁAUDD�͖����`�Ƃ������𗧂Ăė^�}�⍑�R�ƑΛ����Ă���B �@�͂��܂��A1973�N��76�N�ɋN��������w�������A�����^�}�T�[�g��w�Ȃǂ̗T���w�̑�w�����������Ƃ��l����ƁA���݃^�C�ł��ꂼ��d�v�ȃ|�X�g�ɍݐЂ��Ă���̂��낤����A����̑����ɊW���Ă���\��������B�܂��A1992�N���X�`���_�[�����ސw�f���̎�d�҂Ƃ��đߕ߂��ꂽ�`�����������o���R�N�s�m���́APAD�̃��[�_�[�ł�����A�^�N�V���͔ނ��}��߂��p�����^���}�̋c�����������Ƃ�A�������s���f�����ɗ����Ă����v���e�B�[�v����@�c���i�h�D�A���E�v���e�B�[�v���c��\�j��UDD���x�������Ƃ������Ȃ��ꂽ���Ƃ�����A���̑����Ƃ̊֘A���͍��������B �@�ǂ�ȓ��������Ă��������A��ؓ�ł͂����Ȃ��w�i������B�����A�����炭���̂��тɏ����́u���e�v�Ƃ��ė��p����Ă����B���̎����͖Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ٔ����ɂ�锻����AUDD�̃g�b�v�Ɉʒu����͂��̃^�N�V���͊C�O�ɂ���A�������Ђǂ��Ȃ��Ă��瓦���Ă����Ƒ��ƃV���b�s���O���y����ł���Ƃ̕��������B�A�s�V�b�g���ɂ��Ă��A�R�Ƌ�����u����Ă����ɂ���A�w���w�����������킯�ł��Ȃ��A�������{�i������O���玡���ӔC���A�k�|���i�ߊ��ɔC���Ă��܂��Ă���A�j���[�X�ɂ�����2���͂������炭�܂������o�ꂵ�Ă��Ȃ��B����Ȓ��A�Ƒ��⓯�m���������菝����ꂽ�肵����A�ڂ̑O�ɑΛ������G�̎p�ɋC�����グ�邱�ƂŁA�����͑̂悭��������Ă����B�x�炳�ꂽ�����ɂ��ӔC�̈�[�͂���B�����A���̎�����m��@����^�C�́A���ɒn���Ŏ������邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�����B��]���������ɕt������ł��邱�Ƃ͖������낤�B �@�܂��A�ɂ��Ă��A��ł͂��邪�l���������邱�Ƃ����������B�j���[�X�͂�͂菤�i�ł��邩��A�������悢�����Ƃ����̂́A�ǂ��炩�Ƃ�����UDD������������邱�Ƃ��������낤�BUDD�̂قƂ�ǂ͎��������̐��������i����n���o�g�҂ŁA�^�N�V����������Ɍ����ɖڊo�߂��Ƃ����l�X�Ȃ̂ŁA������Љ�I��ҁ����`�̖����Ƃ����\�}�̌��h�����悩�����ɈႢ�Ȃ��B���̔��ɁA�����Ƃ����̂͂����ᔻ�̖�ʂɗ����������̂��B�������A�^�N�V���������^�C�����}���^�}�������Ƃ��ɂ͂������ނ�����l�ɂ�����x�������ꂽ���A�n���ւ̃o���}�L�����ɂ��ᔻ���������B���̃o���}�L�������Ă�UDD���N���O��\�Ƃ��ďЉ��ɋ߂������͂ǂ����Ǝ�����x���X�����B�����r���Ɋւ��Ă��A�����O�̔��ɑ���ېg�̂��߂ł���Ƃ͂����A�ł��邾��������ׂ��w�͂��}���Ă����BUDD���苒���Ă������[�`���v���\�������_���ӂł̍s���ɂ��Ă��A�������^�C�����Ă̔ɉ؊X�ł��邱�Ƃ�z�����āA�ł��邾�����̒n��ł̕���������Ă����i�U�������߂���Ă����̂́A���ӎ{�݂̃I�[�i�[�ł�������ւ̔z���ł�����Ƃ������R�����낤�j�B����ɂ�������炸�A����7�l�����~�������ƁA�\�k�Ɖ�����UDD�͂��������ɉ�����A�Z���g�����E���[���h�E�`�b�h�����ɓ����Ă�����n�S�ݓX���ɐ��O�͍ďo���ł��邩�ǂ����̐��ˍۂɒǂ����܂�Ă���B������@��UDD�̈�����\�����Ă���ɐ��_���X���Ǝv�����A����܂�UDD�������グ�C���������^�������̗�����}�ς������Ƃ�����A��邹�Ȃ��v���͂���ɕ��B �@�^�C�͐ߖڂ��}�����B��_�ϑ��𑱂����l�Ƃ��Ă̑f���Ȉӌ��ł���B���̑����⍡��̏ɂ���ẮA�݃^�C���{�l�̃^�C���E�������ɗ\�z����邪�A�ł��邩���肱�̈����̒n�̖����ɂ���s���������͂������Ǝv���B���̍e�������n�߂�14������A���܂��܂ȕϓ�������A���̂��тɏ��������E�����������J��Ԃ��Ȃ���A���̎v�����������Ă���B |
�Q�O�O�X�N
| �W���P�Q�� �@���������B �@�s�ӑł��̂悤�ɁA����͌��ꂽ�B�ȑO�̗��l�Ƃ̎v���o���������邱�̊X�ŁA�⛌�̃o�X�^�u����g���N�������߂ɁA�A�Ȃ������{�ŋ��Ɏ�Ăċ�߂��B�����āA�o���R�N�ɖ߂����l��20��܂ő����Ă������y�������ĊJ�����B���炭�Y��Ă����A�o���h�E�����o�[�ň�̊y�Ȃ�a���A�ǂ�������Ђ��ނ��ȋC�����B�݂�Ȃʼn����o����Ƃ������̃V���v���Ȏ��������Ŏ�Ɋ��������B5�A�x�ɕ��������I�X�ł́AiPod��������ʼn��t�̂ł��Ȃ����Ƃ������䂭�����Ă������B�ł��A���̗���Ŗl�͋C�Â��B�y�����ɂ��Ă��Ȃ��Ƃ��A�l�͉��ЂƂY��邱�ƂȂ�Ăł��Ȃ��ł���Ƃ������Ƃ��B �@�l�ȊO�̃o���h�E�����o�[�݂͂Ȗډ�20��B�V�����ޏ����ł���A�ق��ɂ͉�������Ȃ��ƁA���K���I��邽�ю��ɂ���B�����K����Ƃ������̂�����Ȃ�A������߂����͂��̖l�́A�����ɂ���قǂ܂łɉ��������߂�C���Ȃ���A���z��������Ƃ��ł��Ȃ��Ɗ����Ă����B�Ȃ̂ɁA�L���[�s�b�h�͂���Ȗl�Ɍ����Ă�������ȋ|���������B�����A���͂����ǂ����߂�҂ł͂Ȃ��A�Q�N���⎨�����̍Œ��ɂ���҂̔����������B�m�M�Ɂu���ɗ�����v�Ƃ����������蒅���Ă���悤�ɁB �@���̗��́A���{�ɂ��邾���ł͂����ƁA�l�ɂ��قƂ�Ǘ����������܂��܂ȏ�ǂ������Ă���B�Ђƌ��ł����A�ޏ��͂��̏o�g�ł���{������̐g���ؖ��������Ȃ��B�����Ȃ�A���_���̃^�C�ł��e����߂Đ����Ă䂭�ق��͂Ȃ��B�����ɂ͂قƂ�ǎd�����Ȃ��A�ޏ��ٍ͈��Ɏ����̂���b���Ĕ�т����B���̃u���[�J�[���x���ꂽ�`�Ńo���R�N�ɏo�Ă��āA�ޏ��͂ЂƂ���c���ꂽ�B���̓���A�W�A�ł悭���ɂ���X�g�[���[�ł͂���B�����A�x�����_���猎�߂ĂЂƂ�ŗ����Ă����ޏ��̗܂��A�l�͂��̊�ł����ƌ����B�����ɗ������A���C�Ɖ�����̂���܂̑O�ɁA�l�͂����ǂ�Ȋʼn߂����邱�Ƃ��ł��͂��Ȃ��B �@���m�b�̂͂��炭���ɕ�炷�l�Ԃ��A�l���^�����Ƃ�m��Ȃ��n��ɕ�炷�l�Ԃ����悷��B�����b�g���̗܂��A�ނ�E�ޏ���͌��Č��ʂӂ�����ĎD�т�ɑւ��Ă������Ƃ��낤���B �@�����^�C�́A���������l�X�̂��߂ɂ��킸���Ȃ����˂��J�������ł���B�Ɠ����ɁA���Ў�`�������������ƌ��킹��n�ł�����B���͂̑��������Ȃ��҂ɁA�\���̔��̌�����ɓn��@��͂قƂ�ǂȂ��B�����A�������Ă���Ԃɂ��A�h���}�ɂ��o�Ă��邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ȍs����̂Ȃ��߂��݂��Đ��Y����Ă䂭�B���Ƃ��@������Ă��������B���̗܂��B�����k����悤�ȋC�����ŁA�S�̒ꂩ�炻���v���B�����āA���͂������̂��߂����ɖl�͐����Ă���B �@�����������ї������B�썑�Ȃ̂ɖk���̌���������������ցB���E�͈����A�����[�g��������܂������͂��Ȃ��B�������A���ɃV���v���ŁA���������������̂Ȃ��^��������B�ޏ����l���A�����ЂƂ肶��Ȃ��B |
 |
�Q�O�O�W�N
 |
�P�P���Q�R�� �@�����N�O�ɕʂꂽ�ޏ�����A������I���ɏ��҂����Ȃ�āA���������Ƃ��Ȃ��B�ޏ��̗F�l����d�b�Řb�����ꂽ�Ƃ��́A�܂�������ȗU���Ɏ������̂��̂��o�����Ă����p�ȂǁA�z�������Ȃ������B���ɉ߂������S�N�Ԃ̋L�����������U�����ŏ����Ă��܂��͂����Ȃ��B �@�ɂ݂̖����ʂ܂܁A�ԑ�������Ĕޏ��̖�o���j������Ȃɍ������̂́A�l���ޏ��Ɋm���Ȗ����ւ̂��݂ǂ����^���Ă������Ȃ��������Ƃւ̍ߖłڂ��ƁA���ĕЎv���������m����̂������ɂǂ����Ă��o��ꂸ�ɋC�����̐��������邱�Ƃ��瓦���������ŁA�m���ǂ���T���Ă��������̐��ɂ��Ȃ����Ƃ��������ĔF�߂邱�Ƃ��ł��Ă��Ȃ��������̂��Ƃ������B �@�o���R�N���S������^�N�V�[�łP���Ԕ��قǁB�N�����b�N�E�V���c�̃��C�h�E�X�v���b�h�ɍ��킹������̃h�b�g�E�^�C��I��ŁA�t�H�[�}���Ȓ��ɗV�ѐS�����郍�[�t�@�[���V���[�Y�E���b�N������o���A�v���Ԃ�ɃR�[�f�B�l�C�g�Ƃ������t���ӎ����Ă����l�́A����������ꂪ�����ŁA���̋���������₩�������[�����������Ă����̂��m�F�����u�ԁA�u�����̓^�C�������v�Ƃ����E�͂ɂƂ���邱�ƂƂȂ�B �@��������ł��オ�����j�����X�e�[�W�̑O�Ŕ���U�藐�������ɂ��炾�����˂点�钆�A�ޏ��̗F�l�Ɩl�́A���Ƃ����낤�ɐV�w�̉Ƒ��̐ȂɈē����ꂽ�B�ޏ��̕�e�́u���̂��Ƃ�҂��Ă���I�@�x������Ȃ����I�v�B�菵���̎���A��������Ԃ�炾�B �@�e�[�u���̖ʁX�͂������̂��ƁA�ʂ肪����q�Ɏ��X�ƁA�ޏ��̕�e�́u������A���J���v�Ƃ������炩��Ɛ������A�l�͞B���ȃW���p�j�[�Y�E�X�}�C�����ׂȂ����⊾��@������B���Ƃ����낤�ɁA�V�Y�ɂ܂Ŗʒʂ������Ă����̂ŁA�������ł����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƌ^�����A�Ȃɒ����Ă���ޏ��̕�e���Ȃ���������Ɩl�̔w�����˂邻�̒ɂ݂ɁA�������茻���Ɍq���Ƃ߂��Ă���B �@����ɂ��Ă��A���z�I�Ȗ邾�����B�ޏ����ˑR�ʂ���o���ēd�b�����Ȃ��Ȃ��Ă���A�����������t�����������グ���낤�B�Ȃ̂ɁA�l�͂������̗���䂭�܂܂ɐg���䂾�˂邱�Ƃ����ł��Ȃ������B�^�C�Ȃ�ł͂̌������p�����ςɑf����B�����ޏ��́A�e�[�u����͂������ɂ���Ƃ͊������Ȃ����炢�����ɂ����B�f������Ă���悤�Ȃ��̊��o�́A�������̔ޏ��̕�e�̎w�ł��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �@�ӂƌ���ƁA�ޏ��̕�e�����܂��Ă���B������˂Ȃ̂��ȁA�ƒ��߂Ă�����A�u�����s���łˁc�v�Ƃۂ�B�u�e�[�u���ɖ߂��Ă��Ȃ��e�����A�݂�Ȃ������킢�����ŁA���Ă����Ȃ�����Ȃ��O���Ă��v�B���߂Ďv���B����Ȍ�����I���A�{���ɃA���Ȃ̂�!? �@�A��̃^�N�V�[�ɁA�Ȃ����V�w����荞�ށB���̃^�N�V�[�́A�ʂ̃^�N�V�[�����܂��ʂ�܂Ńs�X�g�����Ă�����I���̌_��Ԃ炵���B�ǂ���炻���܂Ō������Ă����悤���B����Ȃɍ������l�̂�����납��A�O����قǂɕ������ꂽ�͂��̐�������B�l�ɂƂ��āA���E�ł��������₷���^�C��B�̂ǂ̉��ɂ���オ���Ă���M�����̂�����B��ʂ�ɍ~�藧�ƁA�l�͂����Ȃ�ޏ��̃n�O�����B���Ԃ������Ȃ��悤�ɁA�ޏ��̍����|���|���ƌy���������Ȃ��炻���Ǝ�����Ƃ����ł��Ȃ���������ǁA���ꂽ��ɕ����ꂽ�����n�g�̂悤�ɁA���ߑ�����Q�����Ă����l�̋��̏����Ȃ�������A�ޏ����A�l���g���A���������Ƃ��ł����B �@�����A�����A��ї��āI |
| �T���P�� �@���I�X�̂��Ƃ������痣��Ȃ��B �@����܂ŁA�l�ɂƂ��ă��I�X�́u�Ȃ����Ȃ��v�ꏊ�������B �@�܂��A���̍��ɂ͊C�ݐ����Ȃ��B�����ň�����������A���Ƃ����Ă̂Ȃ��h���C�u�ɂł������肷��ƁA�������傭�͊C�ӂɏo�Ă��āu�����̖ړI�n�͂������v�Ɣ[�������肷��Ƃ��낪���邩��A���I�X�ɂ͂ǂ�������ŏI�ړI�n�ɂ��ǂ蒅���Ă��Ȃ��悤�ȋC�����m�炸�m�炸���܂�邱�ƂɂȂ�B �@����ɁA����܂Ŗl�̐G�ꂠ���Ă������I�X�l�����́A���̂قƂ�ǂ��������݂������B�����Ȕ}�̂Łu���I�X�l�͈�̈�����Ȃ����炷�l�X�v���ƌ`�e����Ă���A���ہA���g�̂��Ƃ��u�L�[�E�L�A�b�g�i���̂����j�v���Ǝ��F����l�����Ȃ葽���^�C�l����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���悤�ȁA�̂�т肵����ۂ������B�h�̌o�c�҂ɂ��Ă��A�W�����{�̉^�]��ɂ��Ă��A���̕\��牽����ǂݎ�邱�Ƃ�����l�����������B����̋N����\�ʂɏo���Ȃ����ƂŁA���m�l���炷��Ɠ��{�l�͂������ɂ����l�킾�Ƒ������邱�Ƃ����������A�l�̖ڂ��猩�����I�X�l�́A�\�ʂɏo���Ȃ��Ƃ��������A�S�ɔg���𗧂ĂȂ����Ƃ�M���Ƃ��Ă���悤�ɉf��B�l�Ƃ̏o������̑�햡�̂X�O�����Ɗ����Ă���l�ɂƂ��āA����͑傫�ȃf�����b�g�������B �@���I�X���������]�@�ƂȂ����̂́A���s�҂ɐl�C�̍����k���I�X��^�C����̃A�N�Z�X�̗ǂ��Ői���𐋂��钆�����I�X�ł͂Ȃ��A�K�C�h�u�b�N�ł������̏������색�I�X�ɑ����^���Ƃł���B���������́A�܂�Ȃ����R���ƈ�R����Ă��܂����������A�H���������B����H�ׂĂ����������̂��B�^�C�������D���ŁA���{�ł͂��鎞���A�����������Ăł��T�Ɉ�x�̓^�C�����X�ɕ����Ă����l�����܂�^�C�����ɐH�w������Ȃ��Ȃ����̂́A�h�����̂����������Ȃ��Ȃ��Ă������Ƃ����邪�A�Ö��E�h���E�_���Ȃǂ����܂��܂ɗ��܂����������@�Ɩ��������ɑ傫�Ȍ���������B���o�g�̖l�ɂƂ��ẮA�_�V�̂Ƃꂽ�����̌������ɑf�ނ̎��R�Ȗ��킢���L�����Ă��钲���������̈ݒ��Ɉ�Ԃ悭�����Ă���B����͂܂������A�색�I�X�ŐH�ׂ������������̂��B�ǂ̗������H�ǂ̓X���H�Ɛq�˂���܂ł��Ȃ��B�ǂ̓X�̂ǂ̗������A����������͂��ׂĂ����������̂��B �@���R�����ɋ߂��ꏊ�ɂ��邩��ɂ́A�싛�������H�ׂ����Ǝv���A��ɕ����t���[�e�B���O�E�X�^�C���̃��X�g�����ɓ������B�����ɂ͎v�킸�U��Ԃ��Ă��܂����炢���l�̃r�A�E�K�[���������B����A�W�A�ł̃r�A�E�K�[���́A���Ƃ����r�A���I��������r�A���I�̃��x�����v�����g�����A�₽��ƃ{�f�B�E���C�������������ߑ��𒅂Ă���A����������Ƌ��d��������A��q�̘b����ɂȂ����肵�Ĉ��w��U��܂��B�����āA���̔���グ���ޏ��ɃL�b�N�E�o�b�N�Ƃ��Ďx������Ƃ����i���ɂȂ��Ă���B������A�r�A�E�K�[���͒[��ȗe�p�ƛZ�蕨�ɁA����ŋC���傫���Ȃ����q����u�y�������Ԃ̕����O�v�����炤�悤�Ȋi�D�ɂȂ�B �@�H�����^��Ă��鍠�A�c�̗p�ɂ�������ꂽ�ׂ̃e�[�u���ɘV��j��������������s�Ƀr�[����������юn�߂��B�ނ�E�ޏ���́u�P�E�Q�E�R�E���t�I�v�Ƃ����|�����Ŋ��t���悤�A�Ɖ��x���݂�ȂɌĂъ|���Ă���B�u���x���v�Ƃ����̂́A���̂��тɒN���������o������A��������ꂽ��A�킴�ƃt���C���O�����肷�邩�炾�B���̊��t�́A�����悤�Ȓ��q�ŁA�H�������x���J��Ԃ��ꂽ�B���̂��сA�S���������オ���ăe�[�u�����͂�ł���B�|�����A�N���̘b�A���B�߂ł������Ƃ��������̂��낤���A����Ƃ��v���Ԃ�̊O�H�Ȃ̂��낤���B���̃e�[�u���ł́A�N�����������K�������������B �@���l�̃r�A�E�K�[���͋��d����`���Ă���B�����āA�肪�����ăr�[���E�T�[�o�[�̑O�ɗ����Ă���Ƃ��ɂ́A�q�̘b���Ȃ���T�܂������Ă���B�ق��̃e�[�u���q���܂߁A�N���ޏ��ɐF�ڂ��g�����肵�Ȃ��B�ޏ����q�ɗ����ڂ𑗂�����Ȃǂ��Ȃ��B�����ɂ́A�T�U�G�����ƓI�Ȃق̂ڂ̂Ƃ�����C���Ђ����痬��Ă����B �@�f�W�J���Ў�Ɉٍ��𗷂��āA�����̏��L����p�\�R�����g���Ă��̗L�l���z�[���E�y�[�W�ɃA�b�v����悤���ґ���A�����̃A�W�A�l���A�ށB���̋C�����́A���{�{���ł͑z������i���Љ�ł���o���R�N�ݏZ���{�l�̐��E�œ��X�𑗂�l�ɂ������ł��Ă������ł���B�������A���������B�Ȃ����̂˂���ł��邱�Ƃ����m�Ō����A��n���̌b�݂������鎠���L���ȐH���ɔ����^���Ȃ���A����Ȃɋ����̂Ȃ��K�����F�ŋ��L����悤�Ȏ��Ԃ��A�ߍ��̖l��͂������������낤���H �@���B�G���`�����ߍx�̑��A�o���E�N���Ɍ������s�b�N�A�b�v�ňꏏ�ɂȂ�������������́A�Ђ����牓��������ė���Ă䂭���i�߂Ă����B�C���h�V�i�푈���A���̌�̎Љ��`�����A�ߔN�̌o�ϊJ�������Ă������̊�̐�ɉ�������̂��A�l���܂˂����Ēǂ��Ă݂����A�������ނ����Ă�����̂�l�ɂ͌��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B����������̘A�ꍇ���炵���������A���x���s�b�N�A�b�v���Ԃ����āA���̋߂��ɂ���X�▯�ƂŃg�C������Ă���B�A���߂��̂��낤�B�������A15������܂��Ԃ��~�߂�悤�ȕp�x�ɂȂ��������ŁA��q�͂�����������ɂȂ��Ă䂭�B���̃X�g���[�g�����܂��ʔ����B����ƁA��������̓g�C���ɗ���������X�̑O�ŕʂ̃s�b�N�A�b�v�ɏ��悤�ɑ�����A�������������A���Ă��Ėl��Ɠ����s�b�N�A�b�v�ɍ������B�ǂ����A���l�ǂ����������悤���B �@�ǂ����A�l�͊O���l����̏��������Ă��郉�I�X�l�̎p�������Ă��Ȃ������悤���B�ȑO�A���A���V���ɑ؍݂����Ƃ��A�����̑傫�ȏ�����j��������炠����������W�܂��Ă��āA�݂�Ȃʼn^��ł���̂������������Ƃ��������B�N���傫�Ȑ����o�����肵�Ȃ����A���Č��ʂӂ������҂��Ȃ��B���@�����B�G���ł͋��̂Ȃ��������������B��̌��������ɂ������悤�ɓ��������Ă���B�ǂ��Ȃ��Ă���̂��Ɨ����~���Ă���ƁA���Ƃ������ė����l�X�����̂܂ܐ�ɓ����Č������݂܂ŕ����čs�����B�V�����Ⴋ���j�������Ă炢�Ȃ�����̂܂܂̎p�ŁA���I�X�ł͐l�X������������Ȃ����炵�Ă���B���ɋv���Ԃ�ɁA����������Ă��Ă�܂Ȃ����A���ꂪ�l�ɂƂ��Ẵ��I�X�B |
  |
�Q�O�O�V�N
 |
�P�Q���Q�� �@�H���u�ꍑ�v������������傫�ȗv�f�ƂȂ邱�Ƃ͂���܂łɌJ��Ԃ������Ă����B���{�l�͐��E�ł��������������_�̏��Ȃ��������Ǝv�����A�C�O�ݏZ�◯�w�E�������s�ȂǂŒ��炭���ɂ��Ȃ��������X�`�₲�тɑ̂���������Ƃ��A���������{�l�ł��邱�Ƃ������ӎ��ł��邾�낤�B �@����Ǝ����悤�Ȃ��̂ɁA�u���v������B���Ƀe���r�ԑg�ɂ͑傫�����̈Ⴂ���f���o�����B���Ƃ��A���{�̏��ɂ́u�ԁv�����ɏd�v������Ă���B�����t���[�Y��1�b���������̂ƒx�������̂ł́A��������U���Ȃ��Ȃ�\�����傫�������肷��B���̂��߁A���{�̖��˂�R���g�A�����o���G�e�B�[�ԑg�̑����͔N��ǂ��ăX�s�[�h�����グ�Ă���B�����āA���˂ɂ�����u�{�P�v�̂悤�ɁA����U�����S�l���͕s���Ȑ��i���̂�������l�����Ƃ����ݒ�ɂȂ��Ă���B�܂�A�����ɍ\���I�Ȃ̂����ǁA���������E�����悤�Ɍ�����l�Ԃ����͂������̐��E�Ɉ�������ł����p�^�[���Ȃ̂ł���B�����M-1�O�����v���ł̃`���[�g���A����t�b�g�{�[���A���[�A�i�قȂǂ�����Ƃ悭�킩�邾�낤�B�₷���E���悵��R���g55���̂��납�炱�������v�f�͓`���I�ɑ����Ă���B�܂��A�����H���݂܂�Ⓑ��G�a�A�Ђ낵�A�Â��͉Ö�B�v�Ȃǁu���邠��v�X�^�C���̂��������������݂���B���퐶���̂͂��܂ŋC�ɂ��Ƃ߂Ă��Ȃ���������ǁA�w�E�����Ɓu�m���ɂ���Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�u�m���ɂ���Ȑl�����Ȃ��v�Ƃ�����ނ̏��ł���B �@�A�����J���E�W���[�N�ɏ��Ȃ��o����������Ȃ�A���̉�������ɍl���Ă��炦��Ǝv���̂����A�^�C�ł̂����ԑg�͊�{�I�ɁA���炩�ɂ������Ȋi�D�������|�l�������x�^�ȏ�k����������A�n���Z���ł���������A����ɂ͓c�Ɏ҂��o�J�ɂ�����A�l�̐g�̏�̌��_���R�P�ɂ����肷��p�^�[���Ői��ł䂫�A�l�͂ǂ����Ă��s�u�̑O�Ŕ������C�����ɂȂ��Ă��܂��B�n���Z����_�W�����Ɋւ��Ă͔��ɌÏL���C���[�W�����܂Ƃ����A���ʓI�ȃl�^�ł͏����Ƃ�������Ȃ��C���ɂȂ�B���Ȃ������̍ł��傫�ȃ|�C���g�́A�l�̃^�C�ꗝ�����s�u�ԑg�̑��x�ɒǂ����Ă��Ȃ����Ƃł���͖̂����Ȃ̂����A���������������Ă��A�^�C��̗͂����܂����Ƃ���ŁA����ς�g�����ɒ[�ɒႢ�j�̓����n���Z���Ŏv����@���āA���j�����̂����łӂ��ƂԂ��Ƃ�������}�����肷�邱�Ƃ͂ł������ɂ��Ȃ��B �@�����A����̓^�C�l�ɂ��Ă悭�w�E����邱�ƂȂ̂����A�Ⴆ�Γc�Ɏ҂�g�̏�ɓ������_������Ă���҂����̔ԑg�����ăP���P�������肷��̂��B���̊��o�́A���ۓI�ɂ����Ă����ɒ�������ނ̂��̂ł͂Ȃ��낤���B���ʓI�Ȋ���́A���Ɏ�ĂĖ₤�ƁA�ӂ��͒N�̐S�ɂ����邾�낤�B���������̂܂܂ɕ\�����Ă��܂��A��̑����_��Ȏp���ł����������Ă��܂��Ƃ����\�}�͒ɉ����B����ɑ��āA���{�l�͔����I�Ȑl�����������X�s�[�h�ł܂������Ă�悤�Ȑ����������Ȃ��Ɠ��퐶�����痣��邱�Ƃ���ł����A�܂��́u���邠��v�Ƃ������ʔF����ʂ��Ă���Ƒ��l�ƂȂ��肠����悤�Ȃ����̐��E�ɐ����Ă���B���{�̂����͑����������x���ƃZ���X�����˔����Ă͂��邾�낤�B�������A�����Ǝ�̃R�~�b�g��͓s��̌ǓƂ��v�킹�鑤�ʂ�L���Ă���B��͂�A�o�σ��x�����l��j�Q����P�[�X�������ɂ�����̂ł͂Ȃ����낤���B |
| �U���P�P�� �@�l��݃^�C���{�l�͂����A�����������Z��ł���^�C�Ƃ������̃��A���e�B�[��Y��Đ����Ă���B����Ȃ��̂����A���������������͒�����炵�Ă��鍡�����݂����A�^�C�ɂ��邱�Ƃ����ŕ@�����r���钷�����s�҂Ƃ��ĉ߂����Ă������ׂȓ��X�̕��Ɉ��|�I�ɑ��݂���B����͎d���̂Ȃ����Ƃł͂��낤�B�������s�҂͍�����������������A���Ԃ�s���̑������Ȃ����Ƃ��������Ȃ̂�����A���������^�C�ɂ���̂Ȃ炻�̑����ɐG�ꂽ���Ɗ肤���A���炩�̌`�œ��{�ɂ������d����������ݏZ�҂̑����́A�ӎ�����{�̃`�����l���ɍ��킹�Ă����Ȃ��Ɓu�҂��v���Ƃ��ł��Ȃ��B�ǂ����悤���Ȃ������ӎ��̕ǂ��A����I�Ƀ^�C�l�̑��̐ӔC�Ƃ��ċ�s�����ڂ��Ă�肭�肵�Ă���B �@���̕Б��ŁA�l�̓^�C�Ƃ������ɂ����Ԃ�~���Ă���B��Ԃŋ߂��̍��ȂɂȂ����l���炨�َq���Ă�������������A����̖�����u���炭�Ԃ�ˁA���{�ɋA���Ă����́H�v�Ɣ��݂���������������B�d����ł͑Ӗ���[�Y�ɂ��炢�炵�Ă����͂����A�����ł͂���炪��g���A���_�I�ȗ]�T�Ɩ���ς��Ėl�̐S�ɟ��ݍ��ށB���q�������A�Ǝ����ł��v���B �@�ǂ�ȗ��ł������͗�߂�悤�ɁA���܂ł����̃^�C�̂��Ƃ��ł����悤�ɖ����Ɉ��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����A���������Ȃ����茋�������ւƌ��т��Ă䂭�ɂ�A�����҂̗��l�ǂ�����v�w�ǂ����łȂ���Η�������ł��Ȃ��W���������Ă���B���͂₻�̂Ƃ��ɂ́A�F�B�̒N���ɗ��̑��k������悤�ȏu���I�ŃI�[���E�I�A�E�i�b�V���O�Ȏ�C�̎���ł͂Ȃ��A���Ԃ�����������l����������������d�݂������Ă䂭�ق��Ȃ��B���̂����A�u�����A����I�v�ƌ��������ł�����V����e���r�̃����R����r�[�������]�����Ƃ���ɏo���Ă��炦����A�u���̎��Ȃ��ǁv�ƌ����邾���ł��ꂪ�����̃��[���̘b�ł������葧�q�E���̋���ɂ��Ă̘b��ł������肷�邱�Ƃ��u���ɗ����ł���悤�ȁA�M�d�Ŋi�ʂȊW�����₩�ɑ����Ă䂭���萫�����X���x���邱�ƂɂȂ邾�낤�B�l�͂��̒i�K�ɓ����Ă���Ƃ������ƂȂ̂��B �@�^�C�͒n��ł��荑�Ȃ̂ŁA�u�����A����v�ƌ����Ă݂��Ƃ���ʼn����o�Ă͂��Ȃ��B�����A�l�͂��̏ꏊ�ő��݂�������A�F�߂��A�ꕔ�ł͌���Ă�����B���ꂾ���ł�������Ȃ����A�Ǝ����������߂邪�A�t������ڂ��邲�Ƃ��A�l�͂܂����̎����ɓ���߂Ȃ��ł���B�����āA�Ȃ��݂����Ă��܂�Ȃ����Ƃ���Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ����v���Ă���B �@���l�łȂ��Ƒ��ƂȂ邱�ƁA���s�҂���݃^�C�҂ւƐg��]�����҂̃^�C�Ƃ̊W�́A����ȂƂ��낾�B |
 ���@�T�C�A���E�f�B�X�J���@���[�O���A�܂����r������BTS���݂�Ղ��i1998�N�j |
 |
�S���P�U�� �@�o���R�N�����ɖ߂��ĂR�N�ȏ�̔N��������A���̊Ԃɂ��A�ȑO��炵�Ă���������m��Ȃ��Ԃɉz���Ă����B�d���A��A����ŃC�T�[��������H�ׂĂ���Ɓu�����A�����͍��A�^�C�̓y�n�݂��߂ĕ�炵�Ă���v�Ǝv�������ŋ��������ς��ɂȂ������߂Ẵ^�C�E���C�t�̃X�^�[�g�ɔ�ׂāA���̂R�N���������Ȃ��߂��Ă������̂́A���R�̂��Ƃ��Ƃ�������܂ł��B �@�����A�������ăo���R�N�̓����A�p�[�g�ɂ����ƕ�炵�Ă���ƁA��_�ϑ������Ă���悤�ȁA������Ƃ����X��l�̈ڂ�ς�肪�����Ȃ�ɔN�\�̂悤�ɂȂ��Ă��āA����͂���ňӖ��������Ă���悤�ȋC������B���̊E�G�ɂ͓��{�l�����Ȃ葽���Z��ł��邪�A���݈��̉Ƒ��Ƃ��Ă��̊X�ɏZ�ޑ唼�̓��{�l�ɂƂ��ẮA�^�C�͐��N�̒ʉߓ_�ł����Ȃ������A�X�̓����Ȃ�ĂقƂ�Nj�����������Ȃ��B�܂��A�Q�O��܂ł̐l�ɂƂ��Ă͊X�̔M���ɐG���@��͑������A����͏u�������������̂ɂȂ肪�����B �@���̃^�C�Ƃ��������͂��߁A����A�W�A�ɂ͍��Ƃ̗��j�ł����㐢�Ɉ₳�ꂽ���������Ȃ��B���j�Ɋw�Ԃ����V�����g�ɂ��܂���邱�Ƃɒ�����������������������̂��낤���B���{�ł͍l�����Ȃ����炢�̃X�s�[�h�Ŏ��X�ƊX�̕��i���h��ւ����A���̏ꏊ�ɈȑO���������Ă����̂����v���o���Ȃ��ꏊ������������悤�ȃo���R�N�ŁA�N�������̋L�����Ƃǂ߂Ă����̂́A�����Ȃ��B �@���̃o���R�N�̐����ɁA���������݂����ȋL���̒��̂P�X�V�O�`�W�O�N��̓��{�̎p���d�Ȃ��Č�����B�N�����u���v���邱�Ƃɖ����ŁA�o�ϓI���W���K�N�F�̖�������Ă���Ă���悤�ȋC�����āA���s�ɕq���Ȏ�҂������̂ɐl�X�̃R�~���j�P�C�V�������܂������ȁA���������Ɛl�Ԑ��̂荇�������傤�ǂ������~�ɂȂ��Ă���{�̎����B���Ԃ�l�́A���̎����̒Ǒ̌����l�Ƃ��Đ����Ă݂邱�ƂɎ��g�̃o���R�N�����̉��l�������Ă���̂��Ǝv���B �@���ÓI�ɂȂ�̂͂��������N�z�ɂȂ��Ă���ł������Ƃ͎v���̂����A�u�M�u�E�~�[�E�`���R���[�g�v�̐�����{�ŕ��������Ă̕ĕ��́A���̓��{���ǂ����Ă���̂���z�����Ă݂�ƁA�����̂킪�܂܂Ŗl�͂����v���Ă��܂��B�u����Ȃɐ����}���Ȃ��Ă���������Ȃ����B����ȂɌ��コ������肪���ׂĂ���Ȃ�����Ȃ����v�B����Ȑ��́A�o�ϓI�Ɍb�܂ꂽ���̐l�Ԃ�������ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ����ނ�������B�����A�o�ϐL���̂̂��A�ǂ�ȋ�ǓƂ⋰�|��ޔp���K���̂���m���Ă���̂́A���ނ����ȂŐ��}�Ȍo�ϐ������I������X���������̖{����m���Ă���B�}�U�[�E�e���T���u�C���h�̕n���w����������Ȃ��ǓƁv���A�����J�Ɍ����̂͂Ȃ��������̂��B �@�l�͂����Ńo���R�N�̈ꕔ�̋L�^�W���A�����ŏ���ɒS�����Ă���B���݂������ĊO��������A�u�}�C�E�y�����C�v�ƌ݂������������l�Â������ʼn����Ȑl�ԊW��ۂ��Ă������̍��ŁA�l��Ɠ����߂����N���Ȃ����ǂ����A�ǂ������̕���_�ɂȂ�̂��A��_�ϑ��𑱂������B �@ |
�Q�O�O�U�N
| �X���Q�U�� �@�O��̍��ŃN�[�f�^�[�ɂ��ď������̂ŁA�x�݂𗘗p���Ă������̃|�C���g������Ă����B�����m�̂悤�ɂ��̃N�[�f�^�[�͖����v���ƂȂ�A���ې��_�ł́u�����`�̌�ށv���w�E���ꂽ���̂́A���݂Ɏ��邱�̂P�T�Ԃ����肵����ԂŐ��ڂ����A��������^�Ă���B���̗l�q�����Ă������Ƃ́A�^�C�ݏZ�҂Ƃ��ďd�v�Ȃ��Ƃł���Ɗ������B �@�T�i�[���E�L���[�E�w�[���E�`���[�g�i�������Z��j�w�ɂ́A�R�l�̂ق��Ɍx�@�����z������Ă����B�ʔ����̂́A�R�l�����ς�炸�L�O�B�e�ɉ����Ă���̂ɑ��A�x�@���̓J������������Ɛ��������ƁB�x�����B�e�ɉ����Ȃ������̂͂��܂��ܕs�@�����������炾�Ƃ��Ă��A���ې��_�ɉ����Ȉ�ۂ�^����R���̃C���[�W�͂����������Ӗ��ł��������Ă���̂�������Ȃ��B �@���b�g�E�v���P�I�i�G�������h���@�j�ŋC�Â����̂́A�^�C�Ŋi�ʂ̈������邱�̎��@�풓�̌R���́A���p���Ă��鐧���̐F�����������ƁB�X�ɂ��镁�ʂ̌R���͖��ʐF�����A�����̂���̓I���[�u�E�O���[���B�������`���ƁA���傤�nj��̎��Ԃ��������A���c���ɂȂ����ނ炪���������킹�čs�i���A�l�ߏ��Ɍ������Čh�炵�Ă����B������̕��������Ԃ�Ɓu�{���v�炵������B �@����L�O���́A�P�X�X�Q�N�̊��܂킵�������̌���B���̂Ƃ������������ɓM�ꂽ�`�������b�g���������艺�낷���߁A�X�`���_���R�����N�������A���̌�u�����ɂ͎��˂����܂Ȃ��v�Ɩ����������R�͂��̂܂ܐ����ɋ����葱���ĎɁB���̖���L�O���̎��͓͂��ɓ��ɑ����Ă䂭�f���Q���҂Ŗ��܂��Ă䂭���A�Ƃ��Ƃ��R�͐�Ԃ��܂ޔ��C���N�����A���������ƂȂ����Ƃ����B����̃P�[�X�������Q�܂Ȃ��悤�ɂƁA�N�����F���Ă���B���̖���L�O���͌�ʂ̗v���ł��A���݂̃^�C�����ɂ�����d�v���_���߂��ɐ�����������y�n�ł����邩��A��͂胉�C�t�����������j����������B�u����L�O���ƈꏏ�Ɏʐ^���v�Ɗ肤�ƁA�u��͎B��Ȃ��ł���v�Ɣw���������B�l��̗l�q���x���`�ɍ��|���Ă��邱�̕t�߂̊w�������Ȃ��璭�߂Ă���B �@�J�I�f�B���i�������j�̂������ɂ̓A�i���^�E�T�}�R���i������c�����j������B���̂����O�A�A���|�[�������̉��𑖂铹�ɂ͐�Ԃ��c�Ԃ��Ă������B�����̓^�C�ő�̃��R�[�h��ЃO���~�[���I�[���E�X�^�[�E��O�R���T�[�g���J���Ă����Ƃ��낾�B�����������́A�R�l���ԂƎʐ^���B�낤�Ƃ����s���E�ό��q�ő吷���ł���B��Ԃɗ�������Ȃ��悤�Ɉ͂�ꂽ�Q�[�g���A�R�l�͎q�����Ԃɏ�点�Ă����邵�A������������ƋC�y�ɋL�O�B�e�ɉ����Ă���B����ƁA�ނ�̌����Ԃ̏�ɉԂ������Ă���A�������Ԃ���ɂ��Ă���q������������B�R�l���������Ă���̂��m�F�ł������A�J������������ƂՂ��Ɗ�����炷�q������B���̏��w���ʂ̔N��Ǝv�������̎q�́A���炩�ɉԑ��Ƃ����Ă������炢�̉Ԃ������Ă��āA���̊Ԃɂ����Ȃ��Ȃ����Ǝv������A�����Ăǂ�������܂��Ԃ������Ă����B�����A�ޏ��͂����ʼnԂ��Ă���̂��B�l�͂܂���A���{�ł͂Ȃ��Ȃ����ڂɂ����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��u������́v���_�Ԍ����C�������B �@�����ɂ���R�l�ɂ́A�ʐ^�B�e�̋������߁A�V���b�^�[��������Ɓu�R�[�v�E�N���E�N���b�v�i���肪�Ƃ��j�v�Ɠ����y��������l�������B���ɑ��Ă̊��ӂȂ̂��낤�H�@���̎ʐ^�̈ꖇ�ꖇ���^�C���R�Ƃ����[�𓊂��Ă�����Ƃł��������ƂȂ̂��낤���H�@����A���Ԃ̓����͈Ⴄ�B�^�C�ł͂��܂葘�����Ȃ����A�t�B���s���ȂǂŁu�����B���Ă���I�v�Ƃ����ނ����N�������j�������B�e��u�T���L���[�I�v��A������悤�ɁA�����炭�ނ́u�B�e���Ă���Ă��肪�Ƃ��v�ƌ�肩���Ă��ꂽ�̂��낤�B�s������̂Ђ�����Ȃ��ɋ��߂���L�O�B�e�̉Q�̒��ŁA���m�����͏Ί�����߂��A�����̈�l��l�̒j�ɂ����Ԃ�Ƌ߂Â��Ă������炾�B�E���ɓO���邱�Ƃ��ł��Ă��Ȃ��Ƃ��������܂ł����A���Ȃ����ς����Ă��A�l���܂߂����ɏW�����쎟�n�����ɌR�͈ӎ��v���𐬌��������ƌ�����̂ł͂Ȃ����B �@ |
  |
 |
�X���Q�O�� �@���{�����X�ŐH�����Ă���Ɓu����A�R���ɂ��N�[�f�^�[���N�������炵���v�ƃ^�C�l�̓X�����畷�����B�������Ɍ����Ă݂�A�Ԃ̐������Ȃ��B�������A�ǂ̃^�C�l������A�[���_�͂܂�������яo���Ă��Ȃ������B�^�C�l�̒��ł͔�r�I�V���A�X�̕����𑨂���X�����������F�l����ł���A�d�b��������Ă��ŏ��͂܂������N�[�f�^�[���݂ł͂Ȃ��b�����b���n�܂�B2006�N�̖�A���{�ł����m�����l�X���呛�������Ă���ԁA�o���R�N�ł͂���Ȓ��q�������B �@�������l�ɂ��Ă��A���S�̂��Ƃɂ��Ă͍l�����B�������A�����߂��~����Ă���͂��̗����̊X�ł́A��ʗv���ŌR�l�����C�t�����\���Ă��邱�ƂƁA�����̌�ʏa���Ȃ����Ƃ������A�\�ʏ�͂قƂ�ǂ����Ƒ����ς�ʕ��i���L�����Ă��邾���B�������Ɏ����̂́A�O�r�𗧂ĂČR�l�ƌ�����L�O�ʐ^���B���Ă���^�C�l�������������ƁB�����Ⴆ�Γ��{�l������Ă���̂����������s�u���|�[�^�[�Ȃ�������A�u�ӔC���̖����ɂ��قǂ�����v�Ƃ܂������Ă��邱�Ɛ��������B �@�ȑO���̂������n��Ŗ\�����N�����Ƃ��ɂ������悤�Ȃ��Ƃ��v�����̂����A����̂����߂���ʂ��Ă���n���S�͒ʏ�ǂ���ɉ^�s�𑱂��Ă��āA�O�ʓI�ɂ͂܂��������̑���������̂�����Ȃ��B����Ȃ��̂Ȃ̂��B���{�ɂ͈��|�I�ȃX�s�[�h�̏�L�͂ƁA�u����̂��Ƃ��䂪���̂悤�ɍl����v�Ƃ����A�ѐӔC��������B����͖{�����炵�����̂̂͂��Ȃ̂����A�}�X�R�~�����̍l�������t��ɂƂ��āA�h���x���A�b�v�����Ŏ��������҂����Ƃ��Ă���̂ɂ܂�܂Ə悹���Ă��邱�Ƃ��A�����҂͎��o���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B �@�������A���Ƃ����ČR�l�Ƃ̋L�O�ʐ^���J�߂�ꂽ���̂ł���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�������A���Ȃ��Ƃ����̖l�́A����̃N�[�f�^�[�������_�ł͊��ł���l�Ԃ̈�l�ł��邱�Ƃ��m���Ă����Ă������������B����̓^�C�ɂ����Ă͍����ł͂Ȃ��u�O���l�v�ł���l�̌l�I���z�Ȃ̂����A�������N�̃^�C�́A�����ē��Ƀo���R�N�͐i�����v�𑁂��i�߂������C������B�O�^�}�ł���^�C�����}�A�����Ă��̃��[�_�[�ł���^�N�V�������͍��Ƃ̌o�ϔ��W�ƍ��������̈���Ɋ�^�������A���̖����̂��߂ɑ傫������]�����Ă������A��O�ӎ��̕ω��ɂ���Ċm���ɂ�����x�̐��_�I�Ȃ�Ƃ�������������B �@�l�̂悤�Ȑl�ԂɂƂ��āA�^�C�́u���{���Y��Ă������́v��ێ����Ă���Ƃ����_�Ŕ��ɋM�d�ȏꏊ�ł���B�i�Љ�ɓ����Ă�����߂ɂȂ낤�Ƃ���ȑO�́A�q�����q���炵�����Ȃ����Ă��܂��ȑO�́A�o�ϐ����̃X�g�b�v���u�ꉭ�����Y�K���v�ł��������芴�������\����������O�́A�����ւ̕s�������q���ޑO�́A�ߏ��Ƃ̕t�������〈�m��ʒN���ɂ��e�ł��铹���S�������Ă��܂��O�́A�܂��o�ϐ�������܂œ��{�������Ă�����ȏ��M����\�����A�^�C�Ƃ������͗��s�҂ɂ����킩��₷���`�ŕۂ��Ă����B����A���m�Ɍ����A���݂Ɏ���܂ň��|�I�ɗL���Ă���̂����A���̈ꕔ�����{�ł������Ȃ��Ă������悤�Ȋ��o�Ŏ���ꂽ�̂��B �@���ꂪ�^�C�ł͊O���l�ł���l�̊��z�Ƃ��Ă͕s�K�ȕ����𑽂��܂ނ��Ƃ��킩���Ă͂��Ă��A���{���Ƃ����߂����^�C�ɌJ��Ԃ��Ăق����Ȃ��Ɗ肤�̂́A�����̏�Ƃ��Ă��̍���I�������l�ɂ͓��R�̐���s���ł��邱�Ƃ𗹉����Ă������������B���̏�ŏ����̂����A���R�����\�����u���Ƃ̂��߁A�����̂��߂̌��N�ł���v�Ƃ������\���A�l�͊���������Ă���B�����炱���A�^�N�V�[�E�h���C���@�[���u�^�N�V���o�čs���A�ƍ����݂�Ȃ��v���Ă���B100�����v�Ƌ�������Ί���A�l���P�O�O���̎v���Ŏ~�߂�B�����ȂB�����}�����Ƃ����ׂĂ���Ȃ��B�����⍑�̖͂��i�ɒǐ����ċn�ߐs�����A�X�����𗧂��ނ����A�r���f�B���O�̔w����������Ƃ��ŏd�v�ۑ�Ȃ̂ł͂Ȃ��B���ׂĂ̐l��������͂�����Ȃ����Ƃ��̐S�Ȃ̂��B �@�u���ҁv�̗]�T���u��������ҁv�ւƍ������炨�C�y�ȃR�����g��f���Ă���̂ł͂Ȃ�����Ŗl�͂���B�u�N�[�f�^�[�v���l�p�l�ʂɃV���A�X�ɑ����ĒN�����y���ȍs�����T���A������l��l�̗ǎ��I���f�Ȃ���̂O���炪�U�肩���������ł�������A��Ђ�w�Z���}�ɋx�݂ɂȂ����̂ŗ��l��F�l�ƊX�ɔ������ɏo�����A�����ɂ����R�l�ƋL�O�ʐ^���B���ĒN���Ƃ̘b�̃^�l�ɂ��邭�炢���R�Ȉ�ʐl�ł��邱�Ƃ̂ق����A�ǂꂾ�������銈�͂ɂƂ��đ�Ȃ��ƂȂ̂��낤���B����ƂƂ��Ɏq����������́E������͂��Ȃ����Ă��錻���J���闠�ŁA�l����{�l�͂ǂꂾ���ɂ݂�Ȃ�����̋�_�Ō����Q�����Ƃ��J��Ԃ��C���ςނƂ����̂��낤���B �@�ɉ؊X�ɐݒu���ꂽ�R�l�̘A�����̂����O�ŁA�o���R�N���q�����̓q�b�v�z�b�v�E�_���X�̗��K�ɋ���ł����B�l�ɂ͂��ꂪ�A������ῂ����B |
| �V���W�� �@mixi�ɓ���悤�ɂȂ��Ĕ��N�قlj߂������A���{�ƊC�O�Ƃ̊W�������Ԃ�ς�����ȂƊ��S����B �@���{�ł�mixi���ǂ������e����������Ă���̂��悭�m��Ȃ��̂����A���{�l���m�̐ڐG���ɒ[�Ɍ����Ă���C�O�����ł́A����mixi���ʂ��������ɂ͏��Ȃ���ʂ��̂�����悤�Ɋ�����B�o���R�N�̍ݏZ���{�l�͓s�s�ʃ����L���O�̐��E��炵�����A����ł��炪�����Ƃ������s�ւ���������x�ɁA���{�l�ƒ�̑����X�N�����B�b�g�E�G�͋����B�f���E�u���O�r�炵�������Ă�����L�ƃR�~���j�e�B�[�̏��ʂ��āA�p�[�\�i�����Ȃ�ƂȂ��M���m�邱�Ƃ��ł��铽���̓��{�l�ƕ��ʂ��̂悢�l�Â��������ł���Ƃ������Ƃ̈Ӗ��́A�����傫���B �@�o���R�N���璭�߂����{�̂悳�̂������Ɂu�ق����肵�������v�Ɓu�M���ł��鐽�����v�Ƃ������̂�����B�����ɑ������Ă݂����H�ׂȂ���A�R�}�[�V�����ɓ���ƃe���r�ԑg�̊��z���q�ׂ����悤�ȁu�ق����肵���v�����₩�ȍK�����̓o���R�N�̌�������͉����A�F�l�E�m�l�E���m�荇��������̒N���̐^���łЂ������Ȉ�ʂɁu���̐l�Ƃ͂����Ȃ��Ƃ��b����v�Ƃ����m�M�ɋ�����邠�̏u�Ԃ��A�o���R�N�̔r�K�X�ɉ��݂������B �@��������A�ق����肵����C��M���ł��鐽������������@���^���Ȃ����炢�ɓ��X�A���{�ł͂��肦�Ȃ��悤�Ȓ��������ƁA�ǂ����悤���Ȃ����ƁA���܂�ɔn���������ƁA�܂𗬂����炢���邱�ƁA�N�����s�𗝂Ɋ����邱�ƁA�����Ė{���ɑ傫�Ȏ����Ȃǂ��A�o���R�N�����ɉQ�����Ă���Ƃ������Ƃł�����B �@�l�͂��̂悤�Ȓ��ɐg��u���ׂ����ă^�C�ɂ���ė����̂ł͂��邪�A��͂�^�C��炵�̍��A���{�ĂƖ��X�`���o�����킴�킴�^�C������I���ł��Ȃ����ƂƂ܂������������R�ŁA���́u�ق����芴�v�u�������v�����߂Ă��܂��͓̂��{�l�̐��ł͂Ȃ����Ǝv���B �@������mixi�ł���B���̃I�����W�̉�ʂ���u�ق����芴�v��u�������v���`����Ƃ��ɂ́A������Ƃ��������̂悤�Ȃ��̂������邱�Ƃ��炠��B �@�܂��Amixi�ɂ͎����̃g�b�v�E�y�[�W��ŎQ���R�~���j�e�B�[��\�����邱�Ƃɂ���āA��⋻�������J���Ă���B�����ȂƂ���A���{�l���Z��œ����l�ԂɂƂ��ĊC�O�����́A���{�̓c�ɕ�炵�ɏ������Đl�ڂ��C�ɂȂ��Ă��܂����ʂ�����̂����A���{�̖��h�����̂悤�Ɏ�⋻����ʂ��ē����́A�������O����N��ɂƂ���邱�ƂȂ��_�C���N�g�ɐS�̂��镔���܂ł������đ��l���m���Ȃ����Ă䂯��Ƃ����\���������邱�Ƃ́A�����h���ɂȂ�B����ɉ����āA��ɂ܂ł��̂����ɂȂ��Ă��������ɂ��C�Â����Ă��ꂽ�B �@mixi�̃R���Z�v�g�ɂ́A�C�O�ݏZ�҂��������Ă͂܂��Ă���C�����ĂȂ�Ȃ��B |
 |
�Q�O�O�S�N
 |
�V���P�P�� �@�����Ȃ��x���A�v���Ԃ�Ƀo���R�N�̒��S�X�A�T�C�A���w�ɍ~�藧�����B�l������ɋx���������A�����葁���p�����ς܂���B�E��p�̃p���c�͂ǂ̂�����ŒT�����A�Z�[��������Ă���̂͂ǂ����A�^�b�N�������Ă��Ȃ��^�C�v�̂��̂͂ǂ̓X�Ŕ����Ă��邩�A�����������Ƃɑ�̂̌��������Ă��܂����ƂɁA���̊X�Ŗl����炵����������l������B�b�c�����߂�ɂ��Ă��A�ǂ̃��[�x���A�ǂ������W���P�b�g�̂��̂ɂ͂��ꂪ�Ȃ��̂��\�z�ł���B�������A���l��������܂����C���X���������ɂ���Ȃɂ��������u�����ɕ����Ă��錩�m��ʒN���Ƃ̏o�������L�����Ă䂫�����ȗ\���v�����͌����ɐ@�������Ă��܂����B�l�̕����Ă���T�C�A���E�X�N�G�A�́A���̊Ԃɂ����{�̊X���݂Ɠ������A������ƌ����Ԃ����Ă������Ɂu���A���݂܂���v�Ƃ͌������ďo�Ă��ɂ������炢�ɐl�Ɛl�Ƃ������Ȃ��Ă���悤�Ɋ����Ă��܂��B�����A����̓o���R�N���ω����Ă���̂ł͂Ȃ��A�ق��ł��Ȃ��l���A���̊X�ɒ����Ȃ����Ƃ��������̂��Ƃ��B |
| �S���Q�X�� �@�N�����Ȃ������ɂ���ƁA�₵���ł��F�B���Ă蒷�d�b�����肷��̂����A����ׂ��Ă��邤���Ɉ�l�ɂȂ肽���Ȃ��Ă���B�����ǂ�������C���C�����Ă���B�����ᔻ�߂������Ƃ����ɂ���Ƃ��ɁA�����悤�̂Ȃ��ł��܂�ł��܂��B�y�������Ƃ�T�������Ƃ͎v���Ă���̂ɁA���̋C�ɂȂ�܂ł͂����Ԃ�ʓ|��������B�\�ߍ��Ƃ݂ɉ䖙�ɂȂ�������������̂́A�������g�ł悭�����Ă���B �@�܂�A�l�͍�������̂��B����͔F�߂Ȃ�������Ȃ��B���܂ł��Ⴂ�C��ۂ̂́A�N�����킸�Ƃ���Ȃ��Ƃ����A�����������Ƃ�������F���������Ă̏�ł̂��Ƃ��낤�B��X�������������A������薰�肽���̂ɖڂ��o�߂Ă��܂�����A���̂����ň݂��d���A�H�~��������߂�Ȃ������肷�邱�Ƃ��A�u�����͂܂��܂��Ⴂ�v�Ƃ����v�����݂����ł��̂��тɏ����Ă��܂��ẮA�������đ̂ɕ��S�������邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B �@�����A�����ƋC����Ȃ�̂��Ƃ������Ƃ��A�l�͂����ŋ߁A���g�������Ċ����Ă���B���̕��䂪�o���R�N�ł���̂́A�����������B���̊X�́A�T�k�b�N�ŃT�o�[�C�ł��邽�߂ɁA���ɂ͊ɖ��Ƃ��������g���ł����Ȃ��Ƃ������A�Ë����A���߂����Ă��̏ꂵ�̂��ł��悢����Ί���ׂĂ��邱�Ƃ���������ȏꏊ�����炾�B�s�s�ł���ȏ�A�o���R�N�ɂ����Ď�X�̟T�ς���������������R�ꗭ�܂�A��̂悤�ɂȂ��Ă���B����ł��A�l�X�͖����Ɏ������}�b�`�ɉ����邪���Ƃ��A���́u�^�C�̔��v���ׂ�B���ߖʂ����ĉ���̈֎q�ɍ����~�낵�Ă���ƁA�����������ɂ��͂���҂ɂȂ����C������B �@�����̂Ƃ�����������B�Ⴍ�͂��肽������ǁA���̎O�������E�ł͎��̗����N�����蒆�ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂�����A�R�킸�A���������A�̓����v�ɉ������u�����������v���������B���{�ŕ�炷�̂Ƃ͈Ⴂ�A�����ɂ͔͂ƂȂ��B�����K���Ď��g�̏��������߂Ă䂭�i���邢�́u���߂�������v�j�悤�Ȋ��͖w�ǂȂ��Ƃ����Ă����B�N���������̃t�����e�B�A�ɗ����Ă���B���e�ɂȂ邱�Ƃ������ł͂Ȃ��Ă������B�����A�M�����鎩�����Đ����Đ��������Ă䂭���Ƃ�Y��Ă͂����Ȃ��A�Ƃ����₩�Ɏ�������B |
 |
 |
�Q���Q�O�� �@�P�N���o���āA�^�C�֕����߂��Ă����B���g�őI���Ƃ͂����A���������Ȃ�Ώh���̂悤�Ȃ��̂����̒n�Ɋ�����ق��Ȃ��B�����ȑO�R�N���炵���A�p�[�g�ɖ߂��Ďn�߂��B�E��܂Ō��̂���ɖ߂����B�������A�����Ȃ��Ƃ����ĂƂ͈���Ă���B �@�V������̑؍ݎ��ɂQ�����قǎg���Ă����Â��A�p�[�g�̓Q�[�g�Ɉ͂��ĉ�̍�Ƃ��i��ł���A����Y��ȃC���^�[�i�V���i���E�X�N�[���ɂȂ�\�肾�B�����N�O�ɂ��a�s�r���J�ʂ��Ă��Ȃ��������̃o���R�N�ɁA���Ēn���S������B�J�I�j���I�E�}���A�����̖��͌g�т���ɂ�������イ���[���ɖ������A�j�F�B���X����`���ł��Ȃ��Ђ�����Ȃ��ɗV�тɗ���悤�ɂȂ����B���̃A�p�[�g�̊K���ɂ������~�j�}�[�g�͖��O���ς��A�����z�ȓX���̊�Ԃ������ƌo�c�҂��ւ�����悤���B���̂����A�Q�S���ԉc�Ƃŕ֗��ȃt�@�~���[�E�}�[�g���߂��ɃI�[�v�����Ă����B�����̒m�l���o���R�N�𗣂�A���̂����Ɍ��m��ʒN�������̊X�ŕ�炵�n�߂Ă���B �@�����������āA�l�͂���܂ł̂ǂ̂Ƃ����������������C�����ŁA�͂����҂��قƂ�ǂȂ��܂܃o���R�N�Z���̈���ƂȂ��Ă������Ă���B���̊X�ɕς��Ȃ����̂��ЂƂ��炢�����Ă���������Ȃ����Ƃ������炢�ɁB �@���{�𗣂�钼�O�ƃo���R�N��������ɂ��ꂼ��̈�ۂɂł����炢���ȂƎv���Ă����B�����A�������������ɂ͕K������Ȃ�̎�������āA����ȗI���Ȃ��Ƃ͌����Ă����Ȃ��Ȃ�B�ł��A����ł����̂��A�Ǝv���B�����������߂ɐ��܂�Ă����悤�Ȑl�����邯��ǁA�l�������c�������Ǝv���Ƃ��́A�����̒����牽�����ɂ��ݏo�Ă����Ƃ��ł����Ăق����Ǝ��g�Ŋ���Ă��邩�炾�B�����}�����̃o���R�N�̐^�������ŁA���߂Ď����̍D���ȕ��������Ƃ����炢�A�������Ƃ����ʎ����ł������B�d���ȊO�ɂ͂����ĊO�o�����������o�b�ƌ��������Ă悵�Ȃ����Ƃ��������閈�����́A���������o���R�N�ŔS�������������Ă��̐S�ɗ��܂���������`�������B �@���{�l�Ƃ����C���M�����[�ȗ��ꂩ��A���̃^�C�ł̐�����������x�X�^�[�g���A����ɂ��Ă䂯���т��A�ł������Y��Ȃ��ł������B |
�Q�O�O�R�N
| �P�O���U�� �@�l�̕����y�[�X���������ŁA���Ԃ��肻���ɂȂ��Ă��܂��B�ǂ��ɂ��Ă��������邳���B�r�C�K�X�ő������Â炢�B�N�����A�ݏZ���{�l�ł��������̂�т肵�Ă���B�����ł͎��R�ɘb���Ă��邱�Ƃ��A����ɂƂ��Ă͂悻�悻�����ĞB���ɉf��B���Ԃ������ĕ����������Ă����Ȃ��B���R�̂悤�ɁA�����B �\���ꂪ�N�Ԃ̓��{�������o����̃o���R�N�ɑ��銴�z�������B���炭�̊ԂɎ��R�Ɠ��{�l�R�Ƃ������̂�g�ɓZ���Ă��鎩���Ɍ˘f�����o���A�ꍏ���������̃^�C�̋�C�ɓ���݂����Əł����ŁA�茳�ɂ�����x�߂��Ă��Ă����A���{�l�I�ȍs���͂�Z���X�A�ӔC�ӎ�������A�^�C�̒��ʼn����V�������Ƃ�����Ă䂱���Ƃ��鎩���ɂ��傫�ȃ`�����X������̂ł͂Ȃ����Ɩ��₩�Ȋ��҂������Ă����B �@�m�l��ł̊Ԏ萶�������l��炵�ւƐ�ւ������c�l�ԂƂ������̂��×~�Ȃ��̂��B����قǓ��{�ɂ���ԂɃ^�C�����ɏł���A��������ɂ�������A���ꂾ���Ŗl�͍K�����낤��ƍ����������Ă����l�������̂ɁA���܂肩���Ă���l�̂��Ȃ��g�ѓd�b�̃f�B�X�v���C���������߂�悤�ɂȂ��Ă����B���ł��낤�ƂȂ��낤�ƁA���炭��E��֒ʂ��v�Ƃ����s�ׂ̂Ȃ��܂܂ɂЂƂ̊X�ŕ�炵�Ă���Ƃ��A���̂��Ƣ�����͂��̊X�ɂ��܂茋�т��Ă͂��Ȃ��v�ƂЂƂ艌�����ӂ������Ԃ�������B�ɂ��Ȃ���Ύ��R���ق����Ɗ肤���A�ɂ������Ǝ₵���Ɗ�����B�{���ɂ킪�܂܂��Ǝv���B �@�u���l�͂���̂����H��ƁA�悭���鎿����^�N�V�[�^�]�肪���������Ă����B�u���Ȃ��ƂЂƂ�őދ��Ȏ₵�������𑗂�Ȃ���Ȃ��B���ǁA�����炢���ł܂�ƂŌ��܂��āA�ʓ|�ŗ����������ɂȂ飂ƁA�ނ͌����B�����Ȃ���A���{�ł̓��X�̂��Ƃ��v���o���Ă����B���̍��ł́A�ʓ|�Ȃ��Ƃ��{���ɍ��̐܂�Ė��Ȃ��Ƃ��肾����A�������L�̂悤�ɂȂ��đދ��Ǝ₵���Ɋ���Ď��g��Ⴢ����邱�Ƃ��y�������B�ł��A��������ăo���R�N�ɂ���ƁA�l�ɂ͔ނ̌����Ƃ���Ƃ��낪�ƂĂ��g�߂Ɋ�����ꂽ�B���̊X�ł́A���L�������ƒN���̎w�ɓ͂��B�ł��A�͂����w����J��Ă�������ƈ��荇���A�������Ԃ����L���Ă䂱���Ƃ���o�傪�`�Â����Ȃ��B�����Ɋւ��Ă��l�ԊW�ɂ��Ă��l���ɑ��Ă��A���̍��͂����܂ŃA�}�`���A�Ȃ܂��Ԃ���������Ă䂭�B �@�^�C�̓c�ɂ���o�Ă�������m�l�ɁA��l��炵�̗��R���Ă݂�ƁA�ŏ��͢�ЂƂ肪�D���Ȃ�Ɠ����Ă������̂́A���Ԃ��o�Ɓu�O�Ɉꏏ�ɏZ��ł��������l�ɓ��݂��͂��炩�ꂽ�v�Ɛ����ȂƂ����b���Ă��ꂽ�B�N������q���肽���̂Ɍq����Ȃ������������Ă���B���������̂ɂ������Ȃ��d�b�������A�������Ă��Ăق����̂ɖ�Ȃ��d�b�������Ȃ�A�����ڂ���ƌǓƂȒ����A�o���R�N�͌J��Ԃ��B |
 |
�Q���Q�T�� �@���{�ɖ߂��Ă����B �@�ǂ����Ă��̓��{�ɢ�ꍑ��̃C���[�W���Ȃ��̂��A���ꂪ�߂����B�ǂ̍��̐l�X�ɂ����Ă���Ȃ�̎����ɑ��鈤��������͂����B�ł��A�����̒��ɂ͂��ꂪ�قƂ�ǂȂ��B�����悤�Ɋ����Ă�����{�l�������Ƒ������Ƃ��m���Ă���B���A�l�����͢������Ƃ������������Ђǂ������B����Ȃ碃��}�g�����v�Ƃł��u�������Ă݂Ă��������A����ƂĐ̌��̂悤�ȗ֊s�̂ڂ₯�����̂ŁA���܂�ɂ����A���e�B�[���Ȃ��B �@�A�����đ��X�̈ꎞ���A�l�͌y������������̂悤�ȏ�ԂɊׂ��Ă��܂����B���p���Ă����@����̕���p�����������A���܂�̓��{�ɑ����a���̂��߂ł��������B�v���Ԃ�ɉ�e�����F�l�ɂ����͂��̂��Ƃ�b�������A�ނ�̓����͊T�ˈ�l�Ɂu�����J���`���[�E�M���b�v�����邾�낤�B���ǁA���{�ł����ƕ�炵�Ă���݂�Ȃ��A���g�͈���Ă������悤�ɌǓƂɉՂ܂�A�s�тɒQ���Ă���B����ł����X�̂����₩�ȍK����T�����ƁA���ʂ����Ԃ��Ċy�����ɐ����Ă����Ƃ������̂������B�������������������B�l�����̊��o�͓��{���o��܂ł����ƕ����Â��Ă�������Ȃ����B �@���Ԃ�A�l�̘b�������܂��������̂��낤�Ǝv���B�ނ�͏��������F�ɃA�h���@�C�X�����ꂽ�̂��������A�l�͔Y�݂��Ƒ��k�������������킯�ł͂Ȃ������B���̃M���b�v�������Ė��܂�Ȃ����낤���Ƃ͂��Ƃ��画���Ă����B�����Ėl�͜��R�Ƃ��Ă��܂����B�v����ɁA�l�͗F�B�ɐ��_�̏����ɂȂ��Ă��炨���Ƃ͊��҂��Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃ����A�F�l�B�́u�l�͌X���ꂼ��ɌǓƂȓ����𑱂��Ă䂭�����Ȃ���Ɖ����������������Ƃ��납��b���|���Ă������炾�B�ނ炪�b���Ă��ꂽ���Ƃ͂��Ԃ��Ő^���Ȉӌ����B����͈ȑO�̎������l����Δ[���������B�������A�l���b�������������Ƃ͖c��܂��Ă����u���̘b�̋A���Ƃ��āA���{�ȊO�̐��E�̂ǂ��Ɂw�l�͌ǓƂȐ������Ȃ�x�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��ɂ���悤�ȍ�������Ƃ����̂��낤�v�Ƃ������ƂȂ̂������B�b�����s����H�邱�Ƃ͉������薾�炩�������̂ŁA�ނ炪�l�̂��Ƃ�^���Ɏ~�߂Ă��ꂽ���ƂɊ��ӂ����ݍ���ŁA�b��������邱�Ƃɂ����B�����������X���������B �@�͂��҂�������Ƃ����o���h�́A�����قƂ�ǔF�m����Ă��Ȃ��������{��ɂ�郍�b�N���ӗ~�I�Ɏ肪���A�P�X�V�R�N�̉��U���Ɂu����Ȃ�A�����J�A����Ȃ�j�b�|���v�Ƃ����Ȃ��c�����B���b�N�Ƃ������m�������C�[�X�g�E�G���h�����{�ɓ������A���̗m�M�ǂ���Ƃ����Ȃ��V�����n���ɏo�Ȃ���A�����̐��������ł͂����ɐ���������邱�Ƃ̂ł��Ȃ��Ȃ�����Ԃ��u����Ȃ�A�����J�A����Ȃ�j�b�|���v�ƕ\�������B�������ɂ������Ă��āA�l�������悤�Ɋ�����B���{�̂��̂����ƃ^�C�̂��̂����A��̎ړx�̒����E�Z����m���Ă��܂��Ƃ������Ƃ́A���[�g�s�A�Ȃ�đ��݂��Ȃ��Ƃ������Ƃ�F�����邱�Ƃ��B��炷���ƂƗ��s���邱�ƂƂ͌���I�ɈႤ�B�ǂ����̍��ɖ�����ꂽ�Ƃ��Ă��A��قǂ̑������Ȃ�����A�����͑�Q�̃^�C�ɂ����Ȃ蓾�Ȃ��B �@���������Ƃ��A���{���l��̒��Łu�ꍑ�v�R�Ƃ��Ă��Ȃ��̂��c�O�łȂ�Ȃ��B�ǂ����Ėl��͓��{�ł�����肱�����Â��d���āA�a�O���ɖ����A�����ׂ��ꂻ���ɂȂ��Ă���̂��B�u���I�ȂP�O��̏��N�A�����B�̊��������̎Љ�Ɋ��݂����Ƃ���̂́A�ނ��뎩�R�Ȃ̂ł͂Ȃ����B �@���ꂩ��l�́A�ł��邾�����{���������Ǝv���B���ƂƂ�������`�Ƃ��i�V���i���Y���Ƃ����������Ƃ��A�����������ƂƂ͂܂������W���Ȃ��B���̂͂Ȃ�����ǁA�L���Ȍ���������A�����ŁA�R�C�ɕx�݁A�l�G�ɍʂ��A���l�̐g�ɂȂ��ĕ������l���邱�Ƃ����ԂE�꓾�ӂȓ��{�Ƃ������̂��B �@���̃y�[�W�̎�|�ł���u�ً�����̖l�̉́v�͋A���������ƂŁA����ŏI���B�����A���ꂩ����l�̓^�C�Ƃ������A���e�B�[��Y��邱�Ƃ͂Ȃ����낤���A�ނ̒n�ɕ������Ƃ����Ȃ��炸���낤���낤�B���x�̓x�[�X�E�L�����v��ς����Ƃ��납��A�N���ďo��v����Ԃ��Ă䂫�����B�����̒����炾���ł͂Ȃ��A�^�C���o�R���Ă��̓��{�ɖl�ƌ��̌q�������������Ȃ���B |
�Q�O�O�Q�N
| �X���Q�O�� �@�����Ƃ��炦�ė����A�Ɖ]������Ɍ������J���ܓ���@���n�߂��B�����A���悻�莞�ɍ~�J������J�G�ɂ��ẮA���̂Ƃ��뒿�������炢�X�R�[���͂Ȃ������B�u����Ƃ��͉��ł��Ȃ������̂ɂȂ��v�ƁA���������Ƃ��N�������ɂ���t���[�Y�����̓��Ŕ�䍂��Ȃ���A������ɂȂ����X�́A�����̂��鑤�ł킴�Ƃ�������p�b�g�E�~�[�������E���A���~�b�g��H�ׂĂ����B�����A����u���������ɂȂ��Ă��嗱�̉J�͂Ƃǂ܂�Ƃ����m�炸�A�u�Ƃ̃V�����[�̐����A���ꂾ���o�Ă��ꂽ�炠�肪�����̂Ɂv�ƁA���߂ėׂ̌��Ɍ������ċ삯�o�����B���̌�����H�邾���ŁA�G�ꂽ�������ɒ�����B�^�C�l�����͎Ԃ��D�u�Ƌ����Ă䂭���A���I���Ƃ��m��ʉJ�h������Ă���B �@����Əo�Ă����X�N�����B�b�g�ʂ����������A���˂ɂȂ����w�ɂ̉��ł��A�����ɂ͉J����������ł����B������������Ȃ���B����łт���т���ɂȂ�������ʂ����Ȃ���A�Ƃɐ����������Ă������Ƃ��v���o���Đ�ł����Ă����Ƃ��A�ӂƓ��ォ��J�����������̂��������B�����āA�T�ɂ��ĎP�����������Ă���Ă��鏭���̎p��F�߂��B����́A�p�b�g�E�~�[���ɍ��𗎂�������O���J�H�j���I�E�}���A�������X�̖��������B �@�P�������Ă���Ă��Ă��A�ޏ��͏��Ă͂��Ȃ������B�^�C�͊m���ɔ��݂̍��ł͂���B�������A�d�ԂŐȂ�ւ���Ă����邱�Ƃł����{�����e�B�A�Ƃ�����U���ȑ�`�����̕K�v�ȓ��{�Ƃ͈���āA���Ƃ��o���R�N�ł����A�^�C�ɂ͐̂Ȃ���̌ݏ����_����������c���Ă���B�P�ӂ������Ƃ��ɁA�Ί�𐏔�������K�v�͂��܂�Ȃ��悤�Ɋ����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B������A�P�ӂ����������܂����Ȃ��B�S�ɂ��Ȃ������〉���������������ɂ͂Ȃ��B �@�u�J���Ђǂ��ł���B�P�����邩��A�ǂ����܂ő����Ă������v�Ɣޏ��͌����B����A���m�Ɍ����Ɓu�Ђǂ��J�ł��ˁB�P������܂�����A�ǂ����܂ł����肵�܂���v�Ƃ������A������Ƃ����h�ꂾ�����̂�������Ȃ��B�������A�r�W�l�X�R�Ƃ����E��łȂ�����A�^�C�ł͌h��Řb����Ă��A�����ɂ��O�҂̂悤�ɕ�������̂��B�^�C�l�����̕\��̏_�炩����ӂ�ӂ킵�������̂������낤���A�b����̈ʒu�������Ԃ�g�߂Ɋ�������̂��B���Ԃ�h��Ɋւ���ӎ��͎��ۂ����Ԃ�Ⴄ�̂��낤�B�����āA���s�҂��^�C�́u�q�g�v�Ɏ䂩��Ă��̒n���J��Ԃ��K���̂��A���̂������Ǝv���B�����Ȃ�̐���t�̃^�C�l�炵�������߂āA�l�́u����A���ΎԐ��ɏo�Ȃ��Ⴂ���Ȃ�����A�w�̊K�i������Ă�����B���肪�Ƃ��v�Ə��Ă݂����B �@�w�̓�����܂ŁA����p�̑傫�ȎP���A�ޏ��͎w�������Ėl�𑗂��Ă��ꂽ�B�K�i����肫�����Ƃ���Ō����낵�Ă݂�ƁA�����ޏ��͂�������J�H�j���I�E�}���A�����̖��̊�ɂȂ��Ă����B�P�̈ʒu�����܂߂ɕς��A�}���A������ג����A�J�H�j���I�������A�z�Ɋ����Ȃ���e�L�p�L�����Ă���B�u�����Ȃ�v�Ɛ��������Ă��������Ȃ�B �@�A��̃^�N�V�[�̒��ŁA�ӂƋC�������B�ޏ��́A�l�̏����̐l�ɂ������肾�����B |
 |
 |
�U���Q�R�� �@�������܂������Ȃ��B �@�u�����͋x�݂��Ȃ��v�ƌ����ƁA�^�C�l�����͂قڗ�O�Ȃ��u�i�[�E�\���E�T�[���i���킢�����Ɂj�v�Ɠ�����B����Ȃ�̃^�C��{�L���u�����[�����Ȃ��l�̂悤�ȓ��{�l�ɂ��킩��₷�������̌������q�ׂ�Ƃ���ƁA���ǂ��̌ꂪ�ł��`��肻���Œ[�I�Ȃ��̂ƂȂ邾�낤�B�����A����ł����Ă��u��ς��ˁv�Ƃ��u�撣��Ȃ�v�Ƃ͂������������Ƃ��Ȃ��B���{�ł́u���킢�����Ɂv�̈ꌾ�́A���Ԃ�ł���B�d���͎���I��������̂�����A���Ƃ��n�[�h�ł����Ă����̎d���ɏ]�����Ă��錻����u���킢�����v�Ȃ��̂��Ȃ߂Ă��܂��̂͐l�����������������ɂȂ��Ă��܂��B �@����Α����猩��ƁA�^�C�l�͐���s����^���̂߂��荇�킹��A�d���Ȃ����̎d�������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƒz�������B���̋C��䂦���Â���H�Ƃ��e�ՂɎ�ɓ������썑�ł́A�d���Ƃ������͎̂��c�ł��Ȃ��ƁA��͂肠���܂Ŏ��Ԃ̐蔄��ɂȂ��Ă��܂��̂��낤���B��ʓI�^�C�l�͓��{�l�I���_���猾���ƁA�o�C�g���o�Ŏd�������Ă���Ƃ����Ă��������낤�B �@�ł͂����莞�ɋA��A�����Ɓu�����͋x�ށv�Ƃ��Ƃ��ȒP�Ɍg�т����o���ނ�E�ޏ���͂��̓��������Ă���̂��c�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�S���Q���Ȃ���s�u�����Ĉ�����I���Ă��܂��̂ł���B����͌���̓��{�l���e�����u�i�C�^�[���ăr�[�����A�����ŐV�����A�S���Q�v�ł���̂Ƃ͍��{�I�ɈႤ�B�ނ�͗���ׂ������̎d���̂��߂ɐg�̂��x�߂�C���^�[�o�����ƒ�ɒu������Ȃ��̂ł����āA�����Ƃ����C����ɁA�Ԉ���Ă��u�����͋x�ށv�ȂǂƂ����d�b�������Ȃ����߂Ɏ��q���Ă���̂�����B �@���ƂȂ��Ă͂����Y�ꂩ���Ă��邪�A���s�҂��������͂���ς�l���^�C�̂��Ƃ���D���ŁA�����炱�����̌�ɂ��̒n��I��ŋ��Z����悤�ɂȂ����̂ɂ͈Ⴂ�Ȃ��B�����������A���R�̂��Ƃ��u������̂ƏZ�ނ̂Ƃ͈Ⴄ�v�Ƃ������{�I�Ȓ藝�́A�l�̃^�C�E���C�t�̔�����O�Ȃ��m�b�N�����B�̂̂悤�ɁA�^�C�̂��Ƃ����Ɉ����Ă������ƁA���ł��Ɋ肤�B�����A�|�����|��ɏI���A�����B����́A�l�����܂�ɂ����{�l�����炾�B �@�q�g�̓��m���l����Ƃ��A�K��������g�p���Ďv�l����B�܂�A������{��Ƃ�����{�l�́A���{���p���ă��m���l����B�{���̈Ӗ��ł́u���S�Ȗ|��v���ł��Ȃ��悤�ɁA�Ⴆ�u�i�[�E�\���E�T�[���v�́u���킢�����Ɂv�Ƃ͕K��������v����킯�ł͂Ȃ��B����Ӗ������ɂ����ẮA�u�i�[�E�\���E�T�[���v�͑��l�̎d�����Z������Ԃɑ���V��I���A�̂悤�ɂ��v���B�������A�������邽�߂̃C���[�W��̂����{��ɂ��ȏ�A�l�͂ǂ����Ă�������u���킢�����Ɂv�ƕ�������Ă��܂��B�������Ėl�́A���{��Ƃ������������Ƃ����������ǂ��������̂Ɋ����Ă��܂��B�����������̂悤�Ȃ��̂ł���B �@�C�O���Z�Ƃ́A��łł��Ă��Ȃ₩�Ȑ������ł��邩����������ł���B�����Ėl�͂��Ȃ₩�ɐ������т邽�߂ɁA�������Ȃ���s���D�Ȏp���N���āA���̂悤�ɕ��������B���ꂪ�����l�̌l�I�ȃ��n�r���ł��낤�Ɖ��߂��Ă��������Ă��܂�Ȃ��B�����A�C�O�����Ƃ������̌ǓƂɂ������l�̎p���N���ɂƂ��ă��A���ł�������A�l�͂�͂蕶�������Â��悤�Ǝv���B |
�Q�O�O�P�N
| �V���W�� �@�V���V���A�V�̐���͂���œ�̐������I�ȍĉ���J��L������ɁA�l�͂ЂƂ��]���������B �@�ނ̖���l�͒m��Ȃ��B�����A�E��̓�����ŃK�[�h�}��������Ă����ނ́A���́u�^�C�̔��v�ł������A�����Ă����Ƃ����A���ꂾ���Ƃ������ꂾ���̊W�������B�d��������������Ƃ��A�o�C�N�D���������ނ͂悭�E��̒��ԏ�ň��Ԃ����ꂱ��Ƃ�����܂킵�Ă����B�������A�^���͔ނ����̂܂܂̂����₩�ȍK���Ɍq���Ƃ߂Ă͂����Ȃ������B�{���ɁA���̉\�̂悤�ɁA�u����A�ނ̓o�C�N���̂Ŏ���v�Ǝ��ɂ����B �@�^�C�ł́A�A�W�A�̑����̍��ł́A�q�g��l�̖��͌y���B�ƒ�⌌�����܂l�ԊW�̐ӔC�̏d������A���̍��̐l�X�͎��R���B�ނ��A�Ђ傢���Ǝ����́u�C�m�`�v��S���ŕʂ̊X�Ɉڂ�Z��ł��܂����悤�ɂ���������B�ł��A����ł��A�l���c���ꂽ�҂́A���̕���ɃG���h���[�����o���āu�����v�Ƃ������̃G�s�\�[�h�̌����f���I��点�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����A���������]����u�������A���ԂƂƂ��ɐl�Ԃ͕�����{�炭�Y��Ă������̂��v�ƌ����������Ȃ���A����ł��̂ċ����Ă��܂����ƂȂǂł����ɁA�˒I�ɕЕt���Ďd�����Ă��������Ȃ��B�l���ɂ́u����v���u�����v������A���Ԃ�u�����v���u������v������̂��B �@�����������u�t�߁v�Ƃ����āA�������ɔ��|��V���o����炵����ĐV�N����Ԃ悤�ɁA�^�C�����́u�\���N���[���v�ƌĂ�A�S���P�R������P�T���܂ł̂R���Ԃ��A�ʂ肷����̐l�X�ǂ����A�h��ɐ������������Ă��j��������B�l�́A�^�C�ŏ��߂Ẵ\���N���[���ɁA���������c���Ă����d���������āA�E��ł�����Еt���Ă����B�\���N���[���̂������ɂ��d���ŋA�Ȃł��Ȃ������A�����K�[�h�}���������ނ͖l�̎d�������Ă��镔���ɁA�u����ȓ��Ɉ�l�ł���͎̂₵���ł��B�ꏏ�Ɉ��݂܂��傤�v�Ƃ���Ă��āA�l�͔ނ̏��߂链�̂̒m��Ȃ��������R�b�v�ɂ��Ԉ��݂��������ŁA�E��̃g�C���Œ��܂ŐQ�Ă����B �@�u�C�ɂ��Ȃ��ł������v�u�C�ɂ��Ȃ��ł������v�ƁA�����l�͊̂ɖ�����B�ł��A�ʖڂ��B�ǂ����悤���Ȃ��A�l���ɂ́u����v���u�����v������A���Ԃ�u�����v���u������v������̂��B |
 |
 |
�Q���P�Q�� �@�l���B����u���U�[�Y�̃J���@�[�Œm�����̂����A�I���W�i�������i�[�h��R�[�G���̎�ɂȂ�gBird on a wire�h�Ƃ����Ȃ�����B �@�l���B���X�̓A�����J�암�����Ă̑�s�s�ŁA�t�����`��J���r�A���̓��������ɋ����c�����j���[�E�I�[�����Y�����_�Ƃ���u���b�N��A�����J���Y�B���i�[�h��R�[�G���̓J�i�_���̕��Q�҂Ō͒W�ƕY���̎��l��~���[�W�V�����B������u���U�[�Y��u���b�h�i�Z��̌��j�����Ȃ₩�ɉ̂��l���B���X�ƁA�����܂Ōł��邱�Ƃɂ�����葭�����痣�ꂽ�Ƃ��납��̊ώ@�҂ł��낤�Ƃ���R�[�G���̉̐��������������C�����J��o���B �@Like a bird on a wire �@Like a drunk in the midnight choir �@I have try to be free �@Like a bird, free �@As a bird, free �@�����āA�l�͂���ς�ǂ����Ă��A���̂ǂ����悤���Ȃ����̂ǂ����悤���Ȃ����D���ł��Ă��܂��B |
| �P���P�S�� �@������ƈȑO�̂��ƂɂȂ邪�A�u�l�炪���ɏo�闝�R�v�Ƃ��������̉̂��������B�����ł́u�����܂ŗ�������l�ɂ��ӂ��K�����F���v�ƌ����Ȃ���h��Ă��܂��j�S�̊������̂��Ă����B�����āAMisia���hBelieve�h�ʼn̂����̂́A�����悤�ɉ����ɗ������l�������闧��ɗ������Ƃ��Ɂu���݂��������ݏo�����Ί炪���̉��E���̒��A��������́v�ƌ����鏗�̑�����̌��ӂ������B����ɂ��Ă��A����͂Ȃ�Ƃ����u���肾�낤�B��l�Ƃ��A���ɏo����l�{�l�ɂ͖{���̂Ƃ���������Ȃ��ł��邪�A�����ɏo��O�̗��l�Ɂu�N�͊��S�ɂ͂��Ⴂ�ł���̂��v���炢�̔�������q�ׂ��Ȃ��̂ɑ��āAMisia�͂̂�������h�h Believe�h�Ɖ̂��グ�A�u�����A���Ȃ��ɓ`���������Ƃ���v�Ƃ����t���[�Y�̂������ƁA�ł͉���`�������̂��Ƃ����ƁA�h�h wanna get you�h�Ƃ���̂ł���B �@�Ƃ���Ŗl�͗������̐l�ԂɂȂ��Ă��܂����B���������l���ЂƂ�����v���̂́A�u�l�炪���ɏo�闝�R�v�ł͂Ȃ��āA�u�l�炪�����ŕ�炷���R�v�̂ق����B����͂܂��A���ɏo�鑤�̐l�Ԃ����̗��_�ł͂Ȃ��A���̏ꏊ�ő����҂��Ƃ�I���ɂ�����邱�Ƃ��B���͂���Ӗ��ʼnf��Ɠ������B�G���h���[�����o������A�����܂ł̕�������������A�Ô��ȑ}���Ȃ𗬂��Ċ����̃t�B�i�[�������o���邱�Ƃ��ł���B�������A�����̏�Ƃ����͈̂Ⴄ�B�����ɂ͕s���D�ȓ���̘A�����ɖ��ɑ����Ă���B���ɏo�Ă���Ƃ��l�炪���ɂ��錾�t�́A�����Ă݂�Z���t�����A��������炷��ł���������ȁu�����������䎌�v�Ȃǂ��悤���̂Ȃ�A�]�v�ɒp�����������ʂ�҂��\���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ɛ��������ł���B���\�͂����I���B��Ȃ̂́A���ꂪ�I��������ƁA�������ǂ��ɋA��̂��ł���B �@Misia���h�h Believe�h�Ɖ̂��̂́A�u���Ȃ��͂����ɖ߂��Ă���ł��傤�v�Ƃ����Ӗ����B�ޏ��ɂƂ��Ắu�����v�Ƃ́u���v�ł���B�����A���Ƃ��Δޏ��̐M����悤�ɗ��l���A���Ă����Ƃ���ƁA���̂Ƃ��ɔނ��ڎw�����u�����v�́u�ޏ��i���j�v�����ł͂Ȃ��A�u�ޏ��i���j��ʂ��Č�����A�����̏Z�ނׂ��ꏊ�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���B����͒P�ɁA�ޏ����Z��ł���Ƃ��낪���������ďZ��ł�������ݐ[���ꏊ�ŁA�ޏ��͂����ɕ�炵�Ă���̂��A�Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���̂ł͂Ȃ��B���E���ɂ��܂��܂ȃ��A���e�B�[�����݂��Ă���̂��Ƃ������Ƃ�g�ɍ���ł��܂������_�ŁA���Ԃ�ނ͂������̔ނł͂Ȃ��̂��B������A���Ԃ�ނɂƂ��Ă͂���͋A���Ă����̂ł��߂��Ă����̂ł��Ȃ��A�I�����āA�O�ɐi��ł����ɂ���ė����̂��B�����Ă��̂Ƃ��A���l�̑��݂͔ނɂƂ��āA�����̗��l�ł͂Ȃ��A��������炷���߂̏ꏊ�Ƃ��đI���̒n���ے��I�Ɋ܂��݂ɂȂ��Ă���̂��낤�Ǝv���̂��B �@ �@���̂��Ƃ̍D�������߂�̂͐��̗��l�{�l���m���B�����A�o�čs���ꂽ���Ƃ��Ă͂���ς��邹�Ȃ��͓̂��R�B���R������ɂ���Ȃ��ɂ���A�u�l�炪���ɏo��v�̂͐g����ł͂���B�����������������̂��������ł͂Ȃ����B �@������A�悭������A�R�j�ɂ���Ȃ�B�R�Ő��������A���Ƃ���B �@�R�j�A�悭������A������ɂ���Ȃ�B���S�͎R�̓V�C��B |
 |
�P���P�Q��
�@���{�ɏZ��ł���ԁA�����ƁA�������������Ă����B
�@���{�Ƃ������́A�����ȈӖ��ŌX�l�ɑ����̂��̂�v������B�݂�ȂƋ������Ȃ��炤�܂�����Ă䂭��������Ë��A��̋�C�̓ǂݕ���b�B���Ȃ��ƁA���̐l�͂����������Ƃ��������Ă���n�c�J�l�Y�~�ɂȂ��Ă��܂����A���̂�������G�ł��Ƃ��낪�Ȃ��Ƃ����̕ǂ̉ԂɂȂ��Ă��܂��B�����Ŗ]��Ő��܂�Ă����킯�ł͂Ȃ��̂ɁA���{�͕K�v�ȏ�Ɂu�����邽�߂ɂ͑傫�ȏd�ׂ�w�����ĕ����Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂��v�Ƃ���Ƃ����قnjJ��Ԃ��B�����������{�̊�Ȃ��́A�t��Ɏ���āA���܂��̂��̏��ŗx���Ă����Ƃ͊y�ɂ�����̂����A���������̂͂����O���O���������B
�@���_�I�Ɏア�q�������āA���������q�������Ɂu�����Ă���Ƃ����A���̂��Ƃ����őf���炵���v�ƌ������̌��ŁA���ʂɕ�炷�q�������Ɂu������Ƃ����̂͐{�炭��ςȂ��ƂȂ̂��v�ƌ����Ă̂���オ�����������B
�@�������������ɁA�l�̓A�W�A���E�ŁA�u������Ƃ����̂́A�P�ɐ����Ă���Ƃ��������̂��ƂȂv�Ƌ����Ă�������悤�Ɏv���B�^�C��ł͐����邱�Ƃ́u�~�[�E�`�[�E�B�b�g�E���[�v�Ƃ����B�u�~�[�v�́u����v�A�u�`�[�E�C�b�g�v�́u���v�A�u���[�v�͌��ݐi�s�`�B�܂�A�������݂��đ����Ă���Ƃ����A�������ꂾ���̂��Ƃ�\���B�q�g��l��l�̖��͌y���B�����āA�������ʂ̐l���������ʂɓ��X�Ɛ������Ă���̂��f���炵��������ꂽ�B�����̐����̒��ŁA���{�l�̑����͂���������ڂ���Ɖ߂����Ă��܂��ƁA�u�����Ƃ��������ʂɂ����v�Ɗ�����B���A�^�C�ɂ���Ƃ���͂���ł܂��������̋^����N���Ă��Ȃ��B���ꂪ�l�Ԗ{���̐������ł͂Ȃ��̂��A�Ǝv���Ă����B
�@�������A�قƂ�ǂ̕����������ł���悤�ɁA���m�ɂ͈꒷��Z������B
�@�u���m�̂���ׂ��p�v���X�l�ɗv��������{�����́A���X�ł��镔���ł͂��������Ȃ����A�m���Ɍ���S�������炷�B�����āA���l�̐g�ɂȂ��ĕ������l���悤�Ƃ��鑊�Ύp�����`�����B���ʂ̐l�����ʂɐ����ĉ��̍��ق������Ȃ��Љ�́A���̓w�͂�F�߂Ȃ��Љ�ł�����B�l�l�����R�ɂ��ꂼ��̉��l�ςŐ����āA���l�Ɋ������A�����̂��Ƃ����l��������l��`�Љ�ɂȂ肪���ł���B
�@���̊X�ł͊猩�m��ɂȂ�����A�����u���̐l�͗F�B�v���ƌ����B����܂ł́u�ȒP�ɗF�B�Ȃ�Č����Ȃ�v�Ƃ悭���ɂ�����{�l�̔��z���D���ɂȂ�Ȃ������B�}�ȃX�R�[���ŋ}���ʼnJ�h��ɉ����̉��ɓ������Ƃ��ɁA���݂��ڂ�����������������A���ꂾ���ł��̐l�̂��Ƃ�F�B�Ƃ��������Ă�������Ȃ����A�Ƃ����Ǝv���Ă����B����ǂ��C�����ƁA���{�l�����F�����猩�āA�l�ɂ͗F�B�ƌĂׂ����Ȑl�Ԃ����̊X�ɂ͕Ў�ɂ����]�邭�炢�������Ȃ��B�����āA����͂悭�悭�ώ@���Ă݂�ƁA�^�C�l�����ɂ��������Ƃ������������B�ꏏ�ɕ������V�F�A���ďZ��ł��钇�Ԃɂ����A�ǂ����Ɋu����������Ă��āA�u���̐l�̂��Ƃ͂悭�킩��Ȃ��v�Ɖk�炷�̂����ɂ���@��͑����B
�@�l�͓��{�l�ł悩�����Ƃ��Â��v���B
�@���Ԃ�A�u������Ƃ������Ƃ́E�E�E�v�Ɩ₢�A�v���ł��邱�Ƃ����łɓ��X�Ƌ����������Ȃ̂��B
�@���{�Ƃ������������t���Ă������I�ȉ��l�ςɁu�����͂����v���v�ƈ�ȂԂĂ鎞�_�ŁA���̐l�ɂ͎v��������F�B������A�Ƃ������Ƃ��B
���Q�O�O�R�N�S���`�Q�O�O�S�N�P���A�����̕���͓��{-�C����I�I�T�J��
| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||
