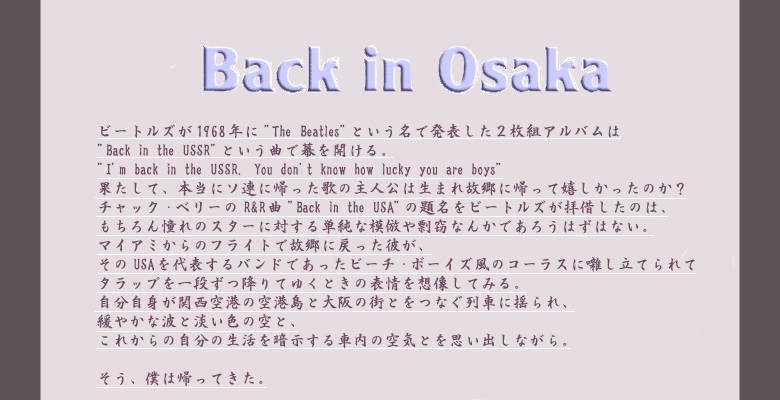
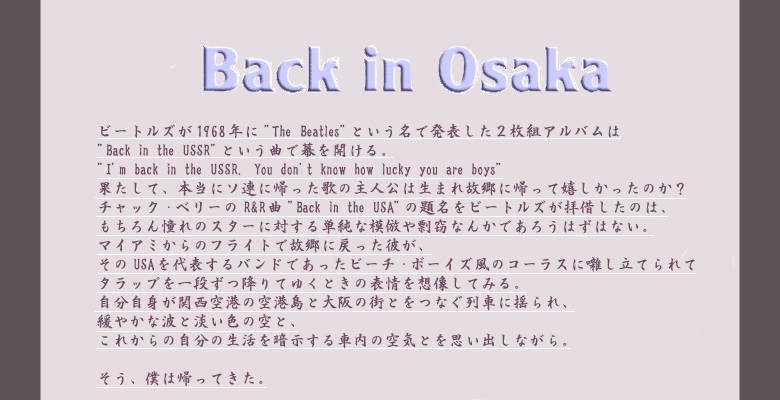
2004年
| 11月20日 以前、この項にモノを書いてからちょうど1年経った。タイに戻って9ヶ月でもある。日本の記憶も少々薄らいできた。そんな時ポツリと思い出したのが、日本の僕の部屋にある椅子のことだ。 部屋にいるとき、寝ている以外の時間の僕は必ずと言っていいほど椅子に座っていた。勉強机とセットの椅子なので、多くの時間は机に向かって何かしていた。タイにこうして住んでいる今、僕はまた前のように床に座り込んでいる。暑いタイでは冷えた陶器タイルの床が気持ちいいこともあるだろう。しかし、好んで床に座っている感覚はない。ただ、そこが定位置になっているだけのことだ。というのも、部屋の椅子は心から好きで座っていたからだ。 ちょうど「癒し」が1年前に書いたテーマだったが、日本の記憶が僕の部屋の椅子と結びついたとき、強く「癒し」の匂いを持って現れた。それはまさしく僕の「居場所」そのものだった。バンコク暮らしの中で、僕はもう本当に長い間、しっかりした椅子を買いたいと思ってきた。 ならば、なぜそれを買わないのか? 今の職場には、社長以外の個人机がない。そのとき空いているデスクを使って作業する。ちょっと不便ではあるが、そのことに強い不満はない。どこが僕の机だって、たいした問題じゃない。僕にとっては、職場のどこだって僕の居場所なんだ。そこに自分のにおいが染み込んだ場所になっている。 部屋だって同じことだ。今バンコクにいて、PCのキーをたたいているこの部屋は、僕という存在を固定する必要のない、タイの気だるい空気が満ち満ちた空間になっている。腰に負担をかけないためには買いたいが、自分の存在領域を護る牙城としての椅子は、今の僕には必要がない。 ただ、そんなことはべつにして、あの椅子のことが僕は、懐かしくてならない。共にPCや本と戯れ、音楽を聴いて空想のドラムをたたき、ビールを流し込んだ日々。自宅で静養を余儀なくされたときにも、あの椅子は静かに佇んでいた。 僕の大阪は、あの椅子という結び目の向こうに、今は少し薄らいできた。 |
 |
2003年
 |
11月19日 「癒し」という言葉が流行ることがもともと好きじゃなかった。 ストレスという言葉が確定してから、ここでいういわゆる「ストレス」に確固とした形と名称が与えられ、それによって誰もが「ストレス」を自分の中にも意識し始めた。そうして、「ストレス」と名づけたことで無意識下のものが明るみに出て、そのせいでストレス然としたものが何もかもひっくるめて「ストレス」と感ぜられるようになったため、名づけられる以前よりも数量的に増して意識に上ってくるようになったのではないか。「ストーカー」などもその好例だろう。以前は普通の恋愛の範疇だった「ふられてもあきらめの悪い異性」はいまや立派な「ストーカー」扱いである。それに、飼うつもりもないのに犬や猫を拾って家にとりあえず連れ帰った場合、決してしてはならないことは「名づける」ことだそうだ。自身が相手に固有の名を与えたところからその犬は他の犬ではなく自分だけの「ポチ」になったり「クロ」になったりする。 現在巷で使われているような「癒し」という言葉の濫用は、この社会がどうにも埒があかず行き場もない現状であることからの逃避であると認めてしまうことのように聞こえてしまう。なぜなら、今唱えられている癒しというのは受動的かつ一方的に快楽的に与えられる代物に聞こえるからだ。 今の職場の隣からは毎日、ラジオが聞こえてくる。朝から晩までAMをかけっ放しなので、否が応でもそのトークに耳がいってしまう。選挙戦、イラク派兵問題、児童誘拐、視聴率買収、自殺志願者カップルの家族殺害、株価低迷…。そのほとんどは一定年齢以上の日本人には常識的知識になっているニュースで、リスナーの世間話のネタとしても使え、また、一人で聞いているものにあれこれとものを考えさせるようになっている。自分のことや目先のことしか考えず日々を暮らす者は日本では蔑まれる傾向にあるから、これらを自身の毎日の延長線上に置き、その重苦しさをともに味わう。だが、画期的な解決方法などほとんど誰もが持ち合わせてはいない。だから、リスナーはせめて世間話にしてお互いの繋がり確認するのに利用する程度で、あとは重いものを「重い」と感じ続けることにしか行き場がない。それだったら逃げたい、癒されたいと思うのは誰しも当然のことではないか。 「デタッチよりコミット」を日本が真剣に考えなければならないという事実はずいぶん以前から叫ばれてきたが、何も功を奏していない。例えば、僕がこうして書いている内容を「これこそが逃げの姿勢、甘え、安っぽく癒しに走ろうとする姿勢、デタッチメントなんだ」と表する向きが強ければ、やっぱり日本は相変わらずだということになると思う。中途半端に世評を世間話に転換しながらラジオでのトークをさも自身の主張であるかのように他人に話そうとする曖昧さこそが問題なのだ。 癒しはたぶん、「癒し」という言葉を呪文のように唱えている間にはやってこない。意味内容を失った上っ面のコトバは必ず上滑りするものだし、ストレス発散にしかならないものはきっと「癒し」ではないはずだからだ。名前を与えて実体を追うのは虚しい。犬に名を与えると離れ難いものになるのは、そこにその犬があどけない目を上げて僕らを見上げる「実体」がまず最初にはっきりとあるからだ。 |
| 10月7日 語学は使ってこそ伸びるのであって、それは母国語にしても同じこと。日本語を忘れることは決してないだろうが、ちょっとした言い回しや表現力、話の筋道の立て方、ひいては着想の豊かさや鋭さまでもが、タイで暮らしているときよりも日本に戻ってからの方が一段と冴えていることは、自身でもなんとなく気づいたし、嬉しいご指摘のメールをいただいたりもした。しかしその一方で、身の回りの雑事や普段の生活の中で思い浮かべたことを書き散らすだけである程度まで読むに値する内容になるタイ生活と違って、日本では何を取り上げてどう切り込むのかに神経を尖らせる必要もあったし、書きたいことそのものが以前に比べて希薄になっていることも同時に自覚できた。 1年ほど以前、バンコク生活でのエッセイで、文がうまく綴れないと訴えたことがあった。異国で長くなると日本語の切れ味がそれなりに薄まってしまうのは致しかたないところだったが、こんなことをしていていいのだろうかと悶々とした。生活という名の緩慢な日々の反復、そこから来るうっすらとした疲弊。どうしても日本人であることを脱ぎ捨てはできないし、かといってタイ人の言い訳や嘘や怠惰さやご都合主義を何もかも認めてニコニコしてはいられなかった。その頃、僕にとって日本語で文章を書くことは一種のリハビリだった。そして、日本にいればおそらくもっと書籍も手にし、マスメディアをはじめとする様々な情報に敏感に感じ入り、友とああだこうだと肩寄せ語り合い、人の人としての微細な心の揺れに感応した自身を取り戻せるのではないかと夢想したりもした。旅と生活とは違うのだ。それが以前のバンコク生活末期の独り言だった。 ADSLの普及し始めたバンコクのネット・ショップである時、何気にHPの掲示板に書き込んだことを辿ってみた。日本で僕が書いてきたことは明確で、ちゃんとした主張を持っていて、頭で一度練られたあとがあった。バンコクに着いてからは、なんだかごまかしの定期報告のようなこと以外は、タイと日本の比較を泣き節で書き込むばかりだった。やっぱりタイではうまく文を書けないのかな、と思った。昨日のこと、一昨日のこと、驚いた話、笑った話、感心した話、いろいろあったはずじゃないか。…でも、なぜかネット・ショップの椅子に座って腕組みをしても、ひとつも思い出せない。いや、こんなはずじゃない、いっぱいいろんなことがあったはずじゃないか! 半年ほど離れていて忘れかけていたタイ暮らしの感覚を取り戻すまでに多少時間を要したが、その感覚はタイ語を話すことに違和感がなくなってきたと同時に手許に戻ってきた。言葉というのは人の思考方法や生活スタイルまでも決定してしまうのだから、タイのあの雰囲気を取り戻すのとタイ語に対する違和感を払拭してゆく過程とがぴったり重なるのはごく自然のことだろう。―だとすれば、僕が日本語という包丁を片手にネット・ショップでタイでのできごとを料理してやろうと思っても、それはよくよく考えてみると不自然なお話だった。タイで起こったできごとは、タイ語でこそ書きえる事象のはずだ。そう考え至ったとき、様々な発想の転換が訪れた。僕は日本人だから、日本語を捨て去ってしまうわけにはいかない。タイ語だってまだまだ駆け出しのところだ。小学一年生レヴェルにまで達しているかどうかも不安だ。だが、日本の読者を想定し、日本語で日本人に伝わりやすいようにということを至上目的にした文章では、おそらくタイを「観察」することはできても、「表現」することはできないのだ。 |
|
| 空港から日本の家に帰るときの電車でいつも見る光景。携帯メールと睨めっこしている若者、目が合うと眉根に皺を寄せてプイと横を向く女性たち、疲れきって寝ているところを物音で起こされて不機嫌なサラリーマン、時間を惜しんで本を読んだり英会話CDを聴いたりする人々。誰かと目が合ってしまうのが恐い。あれだけ泣き節で嘆いてみせた日本の姿が横たわっている。たしかに、僕はこの国にまたやがて慣れていくかもしれない。でも、この中のワン・オブ・ゼムになることをよしとすることで安心を求めることだけはやっぱりしたくない。 タイでは日本語による文がうまく書けなくなるから、心に澱(おり)のようなものが溜まってくる。それはしかし、僕にとっては本当に大切なものだ。重箱の隅を鋭利な視点からつついて書くエッセイなんかではない。僕が心から感じ、それを心に溜めているうちに自然と発酵熱を帯びた、きっちりとした「自身の思い」なのだ。だから、たぶん僕は日本でけったいな人を演じたいわけでもないし、住めば都を合言葉におかしな意味で「大人」になりたくなんかない。風が胸の風穴を吹き抜けるなら、僕はもうこれからあまりそれを隠すまい。無理に物分りのいい日本人を演じまい。タイでの日々を日本語や日本人意識が邪魔をするのならその逆、日本での毎日を自分の中にあるタイが侵すことだってある。澱が自分の中の真実を語るのなら、僕はそれを文字にしてゆこう。タイを知るものとして、日本への単一志向性だけではない新たな意識をもった日本語を考えながら。 日本に帰った実際のところ、僕はそんなに多くの人と会いたいとはもう思わなくなっていたし、情報過多であることが解っていても新聞やテレビに見入っている自分もいた。それが社会不安を掻き立てていることも気づいていたが、そうでもしない限りは、社会との結びつきのようなものを感じることができなかった。いつでも時事的な話題についてゆける用意をしておかないと不安になるのだ。それは、日本が本当にいろんな人と「知り合ってゆく」には、その一人一人の比重が重すぎるからだ。僕が本当に求めていたものは、微細な心の動きを感じあう結果、お互いがお互いを息苦しくするような関係ではもはやなかった。 言葉は言葉自体として機能してもいるし、美しい文章という様式美もある。が、僕は言葉元来の使い方である「伝達するための信号」という側面を意識したい。タイ語を話すとき、身振り手振り、体全体を使って知っている単語を並べ立て、何とか伝えようとするあの熱のようなものを忘れまい。そして、どこかで言ってきたことをもう一度ここで言おう。帰国はした。しかし、タイのリアリティーも知った僕には、これは本当のゴールではない。僕が本当に帰るところは、自分の胸の中の一番熱くて一番感じやすい部分だけにあるのだ。かっこつけて言えば、渡り鳥の家は、自分自身か、あるいは世界なのだ。 |
 |
 |
7月3日 「時が解決する」というのは、偉大な格言だと思う。確たる居場所を見つけたわけでも、自信を回復したわけでも、新しい目標を定めたわけでもないけれど、いつの間にか、日本の土地に足を踏ん張っているのだという実感が徐々に芽吹いていた。生活というのはそうしたものだ。こうして僕が言葉をかざして書き連ねるようなことよりは、もっと鈍くて緩慢で茫洋としていてとりとめがない。だから、「社会と折り合いをつける」とか何とか格好のいいことを口にしても、実際のところは食事から呼吸から、会話から接触から、気象からエアコンの効き具合から、生活のあらゆるところから「日本」は身体中にひたひたと浸透し、何の考えもなしに慣性の法則によって僕の日々をも大きな「日本」というステージに乗っけてしまう。 嫌な言い方をすれば、冷めない恋はない。いつまでもタイに後ろ髪を引かれ続ける自分もいるが、それは今タイの現実が自分から遠いところにあるからだ。タイから見た日本が遠く輝いていたのと同じこと。 しかし、日本が自分とは切ろうと思ったとしても切りようのない血縁の地であるのに対し、タイは世界のいろんな場所の中で、恣意的に自身が選び、そこに自分なりの因縁を感じている土地であることには変わりはない。 今度のタイ行きは、しばらく日本で暮らし、自身の中でのタイのリアリティーが変容し、日本的な価値基準をずいぶんと取り戻しての初めての入国となる。1年間ヴィザの期限も切れたし、タイの運転免許も切れた。日本を離れて暮らした経験を「国レヴェルで実家を出た」と捉えている僕は、今度は反対に、精神的なへその緒をちゃんとタイから切って「大人」になっているか。 |
| 6月5日 大阪弁でいう「けったいな人」。この言い回しは標準語に直すと「一風変わった人」ということなのだけれど、自他ともに対象をこき下ろすことでその対象への親しみがあることの表現になるという大阪ならではのニュアンスが元来強く含まれている。「あんた、あほやな」「俺、どないしょうもない(どうしようもない)男やねん」、こういったやり取りで茶化す方と茶化される方の両人が「そういうやり取りができるくらいに気安い者同士なんだ」とお互いの距離を近しいものに感ぜられるようになるわけだ。こうした関係性は「お笑い」の席巻とともに全国区的に日常化しているが、大阪では一般的な感覚よりずっときつい言葉で言い合うし、世代とか関係性を乗り越えて広く一般的にこの「こき下ろし」をやる。他地域の人々の場合には「あなたにそんなことを言われる筋合いではない」「私にだってプライドというものがある」となって然るべきところを、大阪人は「みんなが笑って過ごせるなら自分のことで笑ってくれればいい」「悪口を言うのは自分だから、なにか問題が起きたときは自分を悪く思ってくれればいい」「こんなことでムカッとするのは器が小さい」と考える場合が多い(ちなみに、先ほどから「大阪人」と断って「関西人」という表現をとっていないが、奈良・和歌山・滋賀と阪神間地域にはある程度大阪に似た感覚があるものの、京都・兵庫・三重にはほとんどこういう感覚がない)。 ところで、日本中が軒並み標準語化(中央集権化)へと突き進む中にあって、頑強な地方色をとどめる大阪も例外ではない。「けったいな人」という表現は「変わった人」にその座を明け渡すことが多くなっている。言葉が世を映す鏡であるなら、この二つの言葉のニュアンスの違いは大阪人的心理をも変容させているともいえるだろう。 タイ生活で得意になったものの一つに「妥協」と「諦念」というものがある。それぞれの生い立ちからしょってきた慣習や価値観やプライドや倫理観を超えて相互理解し合おうというのには自ずと限界がある。タイ人に「相手の気持ちに立ってモノを考えてくれ」と言ったところで、皮肉でも茶化しでもなく、馬耳東風という諺の生きた証明になってしまうのだ。反面、タイ人は相手を許し、認め、枝葉末節は忘れ去り、あの「タイの微笑」で寛容に包み込むことには非常に長けている。郷に入った一員として、僕もそれに倣ったわけだ。 日本に戻ってすぐに気づいたのは、「日本の常識」の分厚さだった。「こうあるべき」であったり「こうしないといけない」であったり「こうすることが常識」であって、つまり、あらゆる生活体系に帰順することが半ば経典化しているのだ。日本は無宗教の国、というのはウソだ。日本人のほとんどは教義に忠実な日本教の急進派だと言っていいだろう。そんな思いを深めている中で、大阪が「みんなが笑って過ごせること」に関して懐の広い地域であったことに救われた。なんだ、タイ人と一緒じゃないか! だからこそ気になる。どこの地域にもいる、一風変わった存在の人、「けったいな人」が「変わった人」に置き換わっていることが。「けったい」は異端でありながらも自分達とつながった地平で存在することを笑いながら確認する言葉だが、「変わっている」には排除と疎外の臭いが立ち込めている。日本が故なき暴力や暗く澱んだ欲望や妬みや憎悪に満ちてきていることは知っている。ただ、許容し妥協し認めることをやめた高度経済成長社会がこうした社会の翳の種をまいている部分は少なからずあるのではないか。「卵が先か鶏が先か」ではない。現にこういう文をネット上にアップしようという僕は、この日本教のハードな教義にアップアップしているからこそ文字を綴ってもいるのだから。 「けったいな人」、タイ帰りの、ちょっとまだどこかちぐはぐな僕は、当分そういう位置にいられればいいと思う。 |
 |
| 5月12日 懐かしい名前だなと思ってメールを開けようとしたら、そのお兄さんからのメールであることが題名に書かれていた。妙な胸騒ぎがする。 A君と出会ったのは、まだバンコクで求職活動をしていたときのことだった。僕はもともとは旅先で日本人旅行者とつるんだりするのがあまり好きではなかったから、バック・パッカーの吹き溜まりであるカオサンに足を向けることなどほとんどなかったが、その日はカオサンに宿を取っている知人に会わなければいけない用事があって、結局すっぽかしを喰らった。そのとき隣のテーブルにいた一人がA君だった。アロハを着た青年、バンダナを巻いた青年とともにA君はベースボール・キャップをかぶって皆と一緒にジュースを飲んでいた。誰もが一見してわかる駆け出しのパッカー候補生――彼らと僕は午後の強い日差しを避けて、そのレストランで額に浮く汗を拭くこともなく、捕りとめもないことを話した。 交換したアドレスに、A君はその後もメールをくれるようになった。その後バンコクで仕事を見つけた僕は、もはや旅ではない現実の生活拠点としてタイで暮らすようになり、あのとき僕の話に目を輝かせ初めて触れる世界諸国の放浪の夢にのぼせていたA君はインドやチベット、カナダなど各地を回り、僕なんかよりはるかに広範囲な旅を続けるようになった。そうして、いつのまにかお互いの連絡は途絶えた。彼は旅先で次々と新しい大切な出会いを重ねたのだろうし、僕はしだいに日常にがんじがらめになっていった。 4月の末、病気の療養とリハビリから立ち直った僕が日本で細々と働き始めた頃に、A君はタイで交通事故のために息を引き取ったという。彼が遺したアドレスに、僕の名が入っていたらしい。その数は多くはなさそうだった。ただ単に彼がメールのやり取りをその後あまり行わなくなっただけかもしれないが、ひょっとすると、僕の名前そのものが彼にとっては旅の出発点を思い起こさせる鍵となっていたのかもしれない。僕にもそういう記憶が、いくつかある。 知人の死を、こういうところに書くのはやめようかと思っていた。HPというのは誰もが閲覧できる公的な場なのだから、プライヴェートに関してはことさら神経を尖らせなくてはならない。だが、"Japanese Man in Khrungtep"を次のタイへの旅まで休み、実質をその大阪篇に移行するにあたって、僕は敢えて彼のことを書こうと思った。これは前欄にも書いたことだが、東南アジア諸国での人の命は軽くてあまりドラマティックじゃない。そして、旅人というのもまた軽くてよるべない存在だ。次々と新しい人や物や風景と出会い、その自身の自由を余すところなく謳歌できるのに、僕は比較的長い旅になったときには、必ず「この町は別に、僕を必要とはしていないのだ」というへんな疎外感を味わったりして、そのたび本当に身勝手なものだと自分に呆れた。ただ、旅人が自由や出会いの代償に安定や社会とのつながり、連帯感といったものを犠牲にするのはたしかだ。だから、僕は書き残すことにした。長期旅行に出る旅人なら誰もが覚悟していることとはいえ、旅先でのあっけなくひそやかな死が彼に訪れたことを、これからも忘れまい。 日本での生活は、昨日とわりによく似た今日を繰り返し、よどみなく「たぶん今日とよく似た明日」に向けて流れつづける。その安定した穏やかな日々の裏側に、また違うリアリティーがいくつも横たわっていることを、これからも忘れまい。 |
2003年3月以前、そして2004年2月以降、生活の舞台はタイのバンコク-イン・クルンテープへ
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
