

スナップ写真を眺めてその頃のことに思いを馳せるのは楽しいが、音楽を聴いて過ぎた日々を思うのは時にせつなすぎる。写真に写し撮られた思い出は、たとえチクリと胸に痛くても軽く笑って人に話せるが、音に込められた思い出は破裂した水道管のように、とめどなくあふれ、それがあまりにも個人的は思い入れだから、人には話しづらい。そんなときには曲の音楽性や意識の高さや作家のことなんてぜんぜん関係ない。思い出と別ちがたく結びついた曲は、その人だけにとってはただただ美しく、せつなく、楽しく、やさしい調べを持っている。
タイのアイドル歌手、ターターの歌う「オー…オイ」はひたすら元気でかわいい、ストレートで明るい曲だ。しかし、何度となく旅行中に耳にした僕にとっては、この曲は単なるヒット・ポップスでも消費音楽でもない。望郷の念にも似たタイへの狂おしいくらいの思いの何分の一かはこの曲が担っている。「オー…オイ」が入ったCDをかけるとき、僕はその向こうに幻のタイを見ているだろう。
帰国して彼女のCDやテープを探してみたが、簡単には見つからない。タイではどんな小さな店でも売っていた彼女のアルバムが、この情報大国の日本で見当たらないことが不思議だった。でも、日本でタイのアイドルのニーズがどれだけあるというのかを考えると、それはもっともなことなのだった。どうせタイの音楽に触れるのなら、もっとタイらしいエキゾチックなものを求めるのが一般的なはずだから。
けれども、CDやテープが見つからなかったからこそ、僕の思い出は「オー…オイ」に集約された。この曲が流れるあいだ、僕は初めてレコードを買った少年のときのように甘美なひとときに蒼くふるえる。
★1998年10月1日発行のフリーペーパー原稿より転載
| ブライオニー 「ヤー・クラップ・パイ」;「ブラック・ブライオニー」所収 |
 |
|
「懐かしい音」というものがある。たとえば、ゲート・ノイズのかかったスネアの音と薄っぺらな音響の広がりに80年代を感じるように。 ブライオニーのアルバムは1枚も持っていなかったけれど、コンピレーションを聴いた瞬間に判った。そして、同時に瞼の裏に浮かんだのは、タイによく見られる大きな体育館みたいなディスコのステージ。男女の歌手が学生時代を思わせるようなバンドと元気のいいダンサーを従え、ヒット・ソングを目いっぱいエンターテインメントしていた、当時のディスコでのステージの匂いが、この「ヤー・クラップ・パイ」にはふんだんに詰まっていた。お決まりのコード進行なのに、いや、だからこそだろうか、切ないメロディー・ラインに過ぎ去った時期のタイが交錯する。 タイに限らず東アジアの国々では、これでもかというくらいに典型的なバラードが量産されている。これは、ありきたりなコード進行やメロディー・ラインを超えた作品を、現時点では多くのリスナーが求めていないことや、制作・販売会社が商業主義を貫きすぎるきらいがあることもあるが、偉大なるマンネリズムが人の心を打つという単純な事実を示してもいる。 また、「ヤー・クラップ・パイ」で聞かれる音は、どれもベタベタ。お決まりの泣かせチョーキングのギター・ソロといい、グルーヴ感のないオン・タイムを目指したベースとドタッとしたドラミング。敢えて言えばイントロで左右にスイッチしたり、サビ前にコミカルにも思えるギミック的な音を配したキーボードが特色を打ち出しているが、エレピのオブリガートなどはまさしく泣かせのそれである。それなのに、この曲を貫く甘酸っぱさは、メロディーの良さとともに、やっぱりこの時代がかった何の変哲もなさなのだ。 昔撮った写真を見て当時に思いをはせることもある。写真はデータとしてさまざまな記憶を蘇らせてくれる。にもかかわらず、音楽を聴いて胸にこみ上げてくる懐かしさは、写真よりももっともっと、突き上げてくるような力を持っている。目で見るもののように外側からではなく、内側から湧き出てくる郷愁がある。音楽としてどうだという前に、ブライオニーは僕にとって、、そんなディーヴァの一人なのだ。 |
||
| フォー=モット 「ハイチャイ・ペン・トァー」;「フォー=モット」所収 |
 |
|
厚底サンダルがバンコクを席捲していた2000年。BTSが開通して、街には原色の明るさが満ちていた。ピチカート・ファイヴが「タクシーに乗って遊びに行こうよ」と歌ったその心理から一切のグレー色を抜き去って、BTSに乗って遊びに出かける少女の姿を捉えたのはniece!のジャケットだった。彼女らの舌足らずで不安定なヴォーカルをフレンチに仕立て上げることによってライト・メロウな世界を提出したDojo Cityだったが、その本体であるレーベルのベーカリーとともに失速したのは、インディー・レーベルの限界なのだろうか。 それから5年が過ぎ、エンドーフィンのように本格的な力量を有するバンドが登場したタイでは、RSプロモーションらしいお子様向けシュガー・コーティング路線にDojo Cityの流れを汲んだフォー=モットがデビュー。フォーは以前からカリスマ・モデルだったらしいが、相棒となったモットとの声質マッチングのよさはタイにしては珍しい。それでいて、少しハスキーがかったフォーの折れそうなので抱きとめてあげたくなるヴォーカルに対して、モットは中音域の音圧が豊かな、優しく癒しを感じる声であるというポジショニングもしっかりしている(モットの安定したヴォーカルはこのユニットの歌唱に大きな貢献をしている)。また、彼女らは純然としたアイドルであり、そのルックスが二人ともチャーミングでいて、なおかつ好対照なのことも人気に火をつける原因になったのだろう。これまでのどちらかというと寄せ集め的なタイのアイドル・ユニットとは一線を画しているところが、満を持しての人選を感じさせる。 例によって、あっぱれなまでのぶりっこ路線だが、タイのアイドルはこれでいいのだ。タイ人女性の話し声が異常に高いことも、かわいらしさを強調するためだという指摘もあるくらいである。どこまでもアマチュアで、限りなく甘く、そしてそれが世の中に受け入れられているあいだは、いくら時代が移り変わってもタイらしさを失っていないなということを確認できるから。いくら商業資本がインディーズから得た知恵を大量消費に応用したのだとしても、彼女らのハイチャイ(息)が新鮮なものだと感じられて、人々がその清楚に酔いしれる時代を、大切に守った方がいい。シンプルで覚えやすくて、気分をウキウキさせてくれる「ハイチャイ・ペン・トァー」は、懐かしさと新しさが絶妙にブレンドされた、今の日本には受け入れる土壌のなくなった、貴重な曲なんだ。 |
||
| コージー・コレクション 「タン・チャイ・ディアゥ」;「ラ・オン・フォン」所収 |
 |
|
2000年あたりからフレンチ・ポップスを彷彿とさせる曲が目立ったり、ピチカート・ファイヴに影響を受けたゾムキアットが活躍したり、小山田圭吾がタイでライヴをするようになったりと、バンコクのポップス・シーンはずいぶん渋谷系の香りを漂わせてきた。そしてある日、視聴用のヘッドフォンから流れてきたのは、カーディガンズ、いや、コージー・コレクションだった。 このユニットは、「影響を受けた」というのではなく、明らかにカーディガンズを変造している。どの曲がどの曲のアイデアを取り入れているのかがすべて言えてしまうような造りになっているのだ。思えば、日本のインディーズでも明確なカーディガンズの「カーニヴァル」を書き換えた曲を耳にしたことだし、このスウェーデンのバンドはよっぽど「自分もこういう曲を作りたい」と思わせる魔力を持っているのだろう。かくいう僕も、実はカーディガンズのコピーを少しやっていたことがある。 コージー・コレクションはこのアルバムで聴く限り、各々のプレイヤーの演奏力はさほど高くない。カーディガンズのメンバーのようなこまやかな芸もないし、よじれるようなアンサンブルの妙も聴けない。だが、ムードを演出することにかけてはすばらしいものがある。このタイにおいて明るくも暗くもないアンニュイなエッセンスというか、キッチュな毒のあるポップス・スタイルを前面に押し出して楽曲を完成しているのは特筆すべきことだ。自分の好きな音楽を表現する喜びが、このアルバムからは聞こえてくる。 |
||
| フライデー 「クラップ・マー」;「フライデー・エキスプレス・ライヴ」所収 |
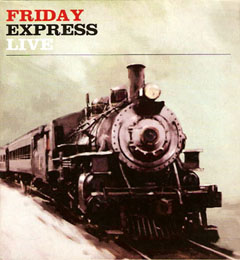 |
|
何気なくジャケ買いしたフライデーの「マジック・モーメント」を通じて知ったトライ・ブミラッタナーは、さまざまなミュージシャンに詞曲を提供したり、ソロや別ユニット活動を続けていたりして、なかなか僕らの前にフライデーとして姿を現してくれなかった。もともとインディーズ畑だからだろうか、彼のソロやユニットはどうも前衛というかオルタナティヴを目指す音作りがかえって邪魔になって、曲や彼の声のよさを削いでしまうことが多かった。DJサイアムで「フライデーの新譜は?」と尋ねて「ソロが出たよ」という声に一枚、二枚と買い求めて、家で「やっぱりこの路線か」とやきもきしていた。 久しぶりに訪ねた郊外の大型ショッピング・コンプレックス、シーコン・スクエアのCDショップ”cap”に何気なく立ち寄ってみると、インディーズ系列の品ぞろえがあって舌を巻いた。いよいよこんな時代になってきたんだ、と胸を躍らせる。そしてお決まりの文句、「フライデーの…」を出すと、「2枚組のコンサートCDがあるよ」! 店を巡るのもそこそこに、僕は急いでタクシーに自宅の住所を告げていた。 徹底的に切なく甘い彼の声に、僕はモンキーズのデイヴィー・ジョーンズをときどき重ねて聴く。コミカルなTVシリーズや、ビートルズの対抗馬として半ばでっち上げのようなオーディションでメンバーがかき集められた経緯や、アイドル的な位置づけから、このバンドの音楽的評価は長らく低かったが、珠玉の楽曲とともに、もう一人のヴォーカリスト、ミッキー・ドレンツとともに、少し疲れと寂しさを滲ませた歌声はもっと評価されていいと思っている。トライ・ブミラッタナーの歌声にはそうした要素が溢れんばかりに含まれている。 ここでは「クラップ・マー」を取り上げたが、ライヴ・アルバムだけあって、どの曲でもシンプルな演奏と観客の熱い声援バックに、彼のヴォーカルが堪能できる。 |
||
| エンドーフィン 「スィン・サム・カン」;「エンドーフィン」所収 |
 |
|
王菲の「夢中人」を聴いたら、誰だって虜になるだろう。その小型版のような風を、僕はこのエンドーフィンの「スィン・サム・カン」に感じた。風通しがよく透明な、それでいてグルーヴィーで浮揚感のあるバックに乗って、ヴォーカルは自由に空間を漂っている。歌のために生まれてきたといっても過言ではない王菲にまで達し得ないのは仕方ないとして、それでもエンドーフィンの女性ヴォーカリストの歌声はタイ人にしては桁外れに確かで安定したリズム感と表現力とがある。 ここ数年、バンコクのインディーズ・シーンが牽引車となって、タイ・ポップスはそのレヴェルを大きく変動させた。渋谷系のキッチュなコピーから始まった一連の動きは、ベーカリー・ミュージック → smallroom → アームチェアーの登場からエンドーフィンのブレイクで完全にオーヴァー・グラウンドなものへと認知が進んでいる。「スィン・サム・カン」にしても、U2の"I Still Having Found When I'm Looking For"を感じさせる空間をヴァッキング・トラックに見つけたりして、時の流れの速さを見せつけられるばかりだ。 |
||
| タクシー 「キットゥン・チャン・マイ・ミー・ウェラー・ティー・トー」;「フル・オプション」所収 |
 |
|
2000年を越えて以来、初めて1年くらいタイを留守にした期間に、スキンヘッドで顔を知っていた「タクシー」が大ブレイクしていた。それまでに、彼らの知名度は相当高かったと思うが、「キットゥン・チャン・マイ・ミー・ウェラー・ティー・トー」はいかにもこの年のベスト・オブ・ザ・イヤーに輝きそうな、エヴァーグリーンな熱さを、たしかに持っていた。 バンコク在住の友達が、久しぶりのタイで聴かせてくれたこの曲は、タイがまだ情熱的でいられる要素をたくさん持ち合わせていることを強く教えてくれた。1999年のバンコクを思い返すとき、「フアチャイ・クラダート」が自分にとってそのテーマ・ソングのように感じられることと同じように、誰かがタイで2003年を「キットゥン・チャン・マイ・ミー・ウェラー・ティー・トー」なしには思い出せないことがあるに違いない。 ハスキーがかったヴォーカルが高らかにシャウトする。バンドのバッキングとともに、その音はタクシーのラジオにもよく似合う。インディーズのセンスもいいけれど、タイはやっぱり、こうでなくちゃ! |
||
| エンドーフィン 「プアン・サニット」;「エンドーフィン」所収 |
 |
|
古いエレピとオルガンのイントロに続いて、情感を抑えて身を捩るようなヴォーカル。そして70年代あたりを思い起こさせる切ないサビへと縺れこむ。タクシーのラジオか、はたまた街中の店々のBGMか、「プアン・サニット」はいつの間にか記憶の片隅に、親しみやすく忘れがたいメロディーを忍びこませていた。 エンドーフィンの登場は、ちょっとしたタイのポピュラー・ミュージック界の事件だといってもいい。センスにせよテクニックにせよ、とにかくこのバンドは頭がひとつ抜きん出ている。タイのポップスには実に循環コードが多くてメロディー的にも飽和状態に近いのだが、圧倒的多数はこれを望んでいるので、売れるためには循環コードを基本に作曲しなくてはならない。一方で、インディーズの洗練はまったく侮れないくらいに進んでおり、こちらも無視できない。ヴォーカルの力量と演奏技術をバックに高いセンスのアレンジを施すことで曲を飽きさせないものにしている。それに、サビのメロディー作りのうまさはピカイチだ。 アームチェアーの登場はたしかにバンコクっ子のリスニング・センスを変えたとは思うが、エンドーフィンは完全に一般層にファンを広げた。無理せずに自分たちらしさを押し出した結果の、クオリティーの高さ。あのアルバムから聞こえてくる自然体がこれだけ普通のリスナーから支持され、知名度をほしいままにしているのは、決定打である気がする。 この曲を聴くと、やたらと何かが懐かしくなる。もちろんそこを狙った曲想を持っているからなのだが、それでもなお、バンドが新しい世界をクリエイトしてゆく熱気だとか、サイケ風味のまぶし方の爽やかさとか、日本で耳にしてもおかしくなかったメロディー・ラインとか、そういうすべてが僕をタイムマシンに乗せようとする。旋律だけではない。たしかに、かつて日本で、僕らはこういう種類の熱さを何度か経験したはずなのだ。 |
||
| サスィーカン 「ノー・サーイ・ロム」;「サスィーカン」所収 |
 |
|
RSプロモーションは他社に比してターゲット層の年齢が低い。だから凡百なお子様向けヒットが多くて耳に残らないことも多いのだが、逆に、こうした年齢層に対するアプローチは、多感な時期を過ごすその国のティーン・エイジャーたちが何を求めているのかをしっかりと浮き彫りにする。RSのそれは、今の日本が忘れた甘くて淡くて切なくてあまりにお伽の世界なシュガー・コーティング・ソング。タイがまだ忘れていない純粋な心と言い換えてもいいだろう。 恋人と過ごす一日の中で、テープやラジオから流れてくるサスィーカンの歌声に包まれる甘い時間が流れるのだろうタイのティーンズ・カップルがうらやましくも思える。僕はこの国で、エアコンの使える部屋でPCをいじったりできる自由を持っている代わりに、この部屋からは彼ら・彼女らの耳で聞く「ノー・サーイ・ロム」を感じて指で触れるところまで絶対に辿り着くことはできない。 「素直であることがどれだけ大切なことか」。彼女の無垢な歌声にそんな思いを巡らせたりする日本人という民族は…やっぱり思いっきり馬鹿だ。 |
||
| フライデー 「チュアモーン・トン・モーン」;「マジック・モーメント」所収 |
 |
|
病を患って入院する直前、サイアムで知人と落ち合い、DJサイアムへCDを見に行くことになった。以前からこの店ではインディーズを中心によくCDを買い求めていたが、彼女曰く、ここの店長は「このCD、どんな曲が入ってるの?」と訊くとその場で歌ってくれる「人間ジュークボックス」だそうだ。制服姿のワイルン(若者)たちでごった返す店内は忙しそうで、ジャケットに惹かれて求めようとしたいくつかのCDの曲は歌ってもらい損ねたが、彼女は「次こそ歌ってもらいたい」と意気込んでいた。タイが愛しくてたまらない彼女は、どんなときにも「タイの横顔」に触れたがっていることが、染み込んでくるように判った。 その後まもなく入院して帰国、自宅療養を経た僕は、あとから聞けば危ないところだったらしいが一命を取り留めた。それと入れ替わるように、彼女の持病の再発を知り、その冬、僕のメールにご家族から訃報が届いた。 それまでにも楽しい時間を過ごさせていただいたが、在タイ期間を経て僕より2年早く日本に帰国した彼女は、年齢こそ若かったけれども僕の「帰国の先輩」だった。母国で会うことはなかったが、彼女とのメールは、僕を包んで重く垂れ込める日本生活の一筋の陽光だった。筆まめな彼女からのメールがとうとう届かなくなってしまった頃に、僕は「あのときDJサイアムで買ったCDを、ベッドで聴いて少しでも元気になってくれたら」と、封書で送った。そのCD、"Magic Moment"を実際に彼女が耳にしてくれたかどうか、それは今ではもうわからない。 狂おしいくらいにタイを愛し、誠実に真っ直ぐに生きた彼女は、あれほど夢見たタイでの再スタートを迎えないまま天に召され、愛するというよりは離れられなくなってしまったタイを抱えながらこの街に戻ってのらくらと生きる僕はこの世に残った。どうしてそんな不公平があるのだろう、と僕は何度も天に問うた。答えを街角の片隅に見つけようと今日も目を凝らした。しかし、まだ見つけられない。 CDは今日も僕の家の安物ラジカセで、希望に満ち溢れた調べに部屋を満たしてくれた。羽ばたく鳥をあしらったCDジャケットのとおり、青い空が狭い部屋を遥か通り越して広がってゆく。希望の空は、けれどもその一方で、 "Because the sky is blue. It's makes me cry" (John Lenon) 「どうしてなんだ?」と、僕はもう一度、小声で問うてみる。 |
||
| プンプワン・ドゥワンチャン 「プア・バー・バー・ボー・ボー」;「チュット チュープ・コーン・チャーク」所収 |
 |
|
「タイの美空ひばり」だとかいう記述ばかりを先に目にした。ラジオでかかっている曲を、タクシーの運ちゃんが「これ、プンプワンだよ」と教えてくれた。どちらもきっかけとしては大切なことだったが、そんなことは今となってはどうでもいい。 CDウェアハウスのエンポリアム店で、店員のお兄ちゃんに「これどういうアルバムなんだろう?」と訊いてみた。「これはね、プンプワンのラスト・アルバム」。たしかに題名は「最期のキス」みたいな感じだ。僕は迷わずレジへ向かった。 家で初めて聴いたときのことを忘れはしない。プンプワンはある曲では童女になって手毬歌を歌っているようだったし、ある曲では天女のように羽根を広げて見せた。また、ある曲では亭主の馬鹿っぷりを下町のおばちゃんふうに嘆いてみせた。その曲、「プア・バー・バー・ボー・ボー」は下世話になりすぎないギリギリのところまで音程やリズムをわざと外し、歌を歌として成り立たせるための「自分もちょっと抜けた中年女」に成り代わる最大限の演出を見せる。そう、どの曲だってプンプワンは歌の主人公に取り憑かれたように歌っている。だが、それがあくまで根のところでは絶対的にプンプワンの素晴らしい歌唱そのものであるという…つまり、彼女がここで聴かせるものがいわゆる「本物の歌」なのだ。年齢も性別も、そして人間という性までも飛び出した彼女が31歳にして「生命」という枠までを飛び越えていってしまったのは返す返すも悔しい皮肉なお話だが、その一方で、「この領域にまで至ってしまったら仕方がないことだ」とどこかで納得してしまうのは、僕がロック畑から音楽を聞き始めた人間だからだろうか? |
||
| カラバオ 「メー・サーイ」;「ルアム・ヒット・カラバオ・クワーイトーン」所収 |
 |
|
プレーン・プア・チーウィットは「命のための歌」という意味だが、カラバオはこのジャンルの先駆者カラワンの意思を次ぐように、社会に虐げられてきた人々や生活に喘ぐ者、学生紛争の挫折を経験した者たちなど、社会の怒りを背負ってきた。サヌック(楽しいこと)でサバーイ(快適)なことが何よりも好きなタイ人だが、ビアハウスでプレーン・チーウィットの演奏を肴に飲みに集まるタイ人の姿は珍しくない。 カラバオが素晴らしいのは、メッセージ・フォークのスタイルを踏襲しながらもただただ怒りを歌声に込めてどなり散らしたり、内省に向かって七難しいことを述べ立てたりするのではなく、あくまで地に足のついた視点から歌を作り、それを自分達が自然だと思える形に昇華して歌にしていることである。 彼らの名曲「メー・サーイ」はピアノの静かなイントロで始まり、サビでぐっと盛り上がったりするものの、終始抑えた調子で声を美しく整えている。メー・サーイで生まれた少女が身体を売り、幾多の男が自分を通り抜けてしまった今では、麻薬のほかになにも彼女の心を癒すものはない、と彼らは歌う。彼らはここで怒りの代弁者を買って出ることはしない。ただ淡々と事実を歌う。少女がバンコクで身体を売るのは故郷メー・サーイの家族のためなのだが、その母の死を聞いて駆けつけても間に合うことはなかった、と歌は進む。むやみに吠え立てることなく、彼らは一人の架空の少女を水彩画のように描くが、それはタイ人なら誰もが知っている、どこにでもある事実である。 かつてボブ・ディランは「100のプロテスト・ソングよりも一つのラヴ・ソングの力が勝る」と気の効いたことを言ったが、100のプロテスト・ソングの中には聞き漏らしてはいけないものも、きっと、いや、間違いなくある。 |
||
| タナーントン 「フアチャイ・クラダート」;「クン・タナーントン」所収 |
 |
|
世紀末のバンコクは、いつもと変わらないバンコクだった。誰も「ノストラダムスの大予言」なんて信じちゃいなかったし、2000年やミレニアムのカウント・ダウン=お祭り騒ぎをしたそうなそぶりでいただけのことであった。僕もそう。ただやってきた今日を生きるだけ。ただそれだけ。 最近はバンコクでも中古CDを置き始めたので、ありがたく80Bくらいで買っている。かつては300Bだったのだから、新譜でも155Bでほとんど手に入る今は正規版CDリスナーとしてはいい時代だ。タイ人は旧譜を聴く習慣がほとんどないから、中古CDには掘り出し物もけっこうある。「あ、フアチャイ・クラダートだ!」 曲を流した瞬間、時間と空間が歪んだ。売れなかった下積み時代を経て、彼がポップスへと路線変更して一大ヒットを放った「フアチャイ・クラダート」。そういえば、あの頃の知り合いのタイ人は誰もがこの曲を好きだったな。あいつらはどうしているんだろう? あの頃住んでいた部屋には今、どんなふうになってるんだろうな。不器用にも感じてしまうこもり気味の彼のシャウトがフラッシュバックの連鎖を促す。そういえば、自由な時期だったな。誰もがその日を思うように生きているだけで、それ以上でも以下でもなかった。だから、あの頃の友達に電話しようと思っても、誰一人新しい番号を教えてくれなかったせいで「この電話番号は現在使われておりません…」ばっかりなんだけど。あ、そういえば僕自身も教えてなかったっけ。 そうだ。今の日本も100円均一ショップが増えて買い物は以前よりも概ね安くなってきた。でも、本当の意味で「暮らしやすい時代」なんだろうか? タイはタクシン政権に変わって経済や治安(※)をはじめ、安定成長を続けている。でも、それが望まれているタイの将来なのだろうか? タイ国民の願いが同歩調ならば仕方がないが、曖昧だからこそ人に優しくなれるのがタイ社会ではなかったか? 世紀末のバンコク―誰もが、もう少し自由だった。 ※記載したのはタイ南部のイスラム教徒過激派によるテロが頻発する以前のことです。ご了承ください。 |
||
| フローズンミュージックス -フューチャリング:メイ, オーイ, ビーヴァー 「エニイ・デイ」;「リムジン(クールヴォイス・コムVol.1)」所収 |
 |
|
おそらくはピチカート・ファイヴ・マニアのゾムキアットが在籍し、かつてはトライアンフス・キングダムやニース、Hなど素人っぽい女の子を起用して一大ムーヴメントを起こしたベーカリー・ミュージックが精神的な火付け役なのだろうと思うが、ここのところバンコクでのインディーズ・ブームはすごい。かつてタワー・レコードだった店舗で営業しているミュージック・ウェアハウスでも、視聴機のひとつがインディー・レーベルのCD専用にされているほどの加熱ぶりだ。 そして確実にそのグレードもかなりなところまできた。中でもとりわけ耳の残ったのがクールヴォイスのこのアルバムだった。7つのユニットが一堂に会したオムニバスで(まだバンドとしての名の通りよりもレーベル名先行なのだ)、ジャジーなトラックもあればエレ・ハード・ポップもあり、全体的にグルーヴィーなまとまり方。フローズンミュージックスの「エニイ・デイ」は印象的なメロディーの女性のスキャット・リフが反復される上を、クールな男性ヴォーカルの歌とライム(まあ、いうなればラップです)が交互に入り、90年代渋谷系的陶酔感で満ち満ちている。 少し気になるのが、この「渋谷系的」。もう日本ではその役目を終わったが、渋谷系の発想力はかなりずば抜けていた。2000年を越えた今も、それに代わるムーヴメントは兆しも見えそうにない。それは日本を黒く覆い続ける不況のヴェールと同じように、人々はその中で疲弊し、代わって癒し系とかシンプルなビート・バンド・アイドルが世の中を満たすようになってきた。通貨危機であろうと不況であろうと、バンコクは走ることをやめようとしない街。どうか、今の日本のように「癒し」などと言い出さないでほしい。これからも渋谷系的音楽を突き詰め乗り越え、過去の遺物となった「渋谷系」という言葉を人々に「バンコク系」と置き換えさせ、再認識させてほしい。 |
||
| トラヴェル・エージェンシー 「Narita / ナリタ」;「ターワル会社」所収 |
 |
|
外国人にとって、日本語はどういう風に聞こえているのだろう? その疑問はおそらく自分が日本語環境で育った純粋な日本語ネイティヴである限り永遠に解ることはない。 このアルバムの4曲目「ナリタ」では、リズム・トラックの乗ってタイ人のための日本語会話練習用CD(あるいはテープ)の音声が反復される。「バンコクの名物」「ええ」「ええ」「今日はトゥクトゥクに乗ってみませんか?」「そうですね」「あのー」「ああ、賑やかですね」「そうですね」「そうですね」…。これらの言葉が意味を失い、音声だけでタイ人リスナーに楽しまれる、そんなことが実際に起こっているのだろう。音としては抑揚が少なくベタっとした印象の日本語に慣れている我々には、イントネーションがしっかりした言葉を聞くと歌を歌っているように聞こえる場合が多い。全体的にクールな電子的トーンで包まれているこのアルバムに、日本語は無機質なユニークさを提供することに成功しただろうか? ちなみに、僕のベスト・テイクは1・2曲目の"Do you speak english?"と"Why ?"。 |
||
| パラポン 「フアン・ヤイ」;「ルワム・ヒット」所収 |
 |
|
1ヶ月ぶりのバンコク。懐かしさに変わるには短すぎる時間だ。だが時間の余裕があると、街はかつて僕も触れた旅人への横顔を見せてくれるようになっていた。そして、バンコクの日本料理店や居酒屋で流れる曲のほとんどはナツメロであるのが、この街で飯時に集う人々の年齢層を考えての選択であるように、僕の旅人化の第一歩もナツメロだった。 「フアン・ヤイ」はいつのまにかメロディーが頭にこびりついていた曲のひとつだった。意識してもいないから、日頃は思い出しもしなかった曲。でも、旅というのは誰かにとっては日常の断片に過ぎないシーンに鮮やかな感情の花を飾ることだと僕は思っている。そしてそのように、名も歌手も知らないこの曲が街角を歩く自身の胸に蘇ってきた。 タイ人はメロディーだけで歌ってみせても曲をわかってくれないことが多い。歌詞に重きがあるのは、「歌謡曲」と呼ばれていた頃の日本のヒット曲の受け入れられ方と似ている。頑張ってCDショップの店員さんに、BGMに負けじと歌って聞かせてもわからずじまい。しかし、その横でいた客の女の子が僕と店員さんの顔を見比べながら「フアン・ヤイ」を歌って、「この曲じゃないの?」と目で促した。僕は大きくかぶりを振る。「そう、それだよ」 「よく判ったね」と僕が息を弾ませると、彼女は携帯を取り出して着メロを聞かせた。紛れもない「フアン・ヤイ」だった。そう、着メロに歌詞はない。 経済規模というものが曲から歌詞をもぎ取って、言葉を置き去りにメロディーとリズムで突っ走ってゆくのなら、僕はその恩恵を受けたわけだが、一昔前のタイではTVでしか見たことのなかったようなチャーミングなその女の子の雰囲気は、なんだか日本のティーンエイジャーに似ていた。でも、そんなことにおかまいなしにCDの中のパラポンはタイの定石バラードをハスキーがかった声でひたすら甘く歌いつづけている。そんなパラポンを好きでいてくれたことを思うと、彼女がタイ人であることをしっかりと感じることができる、今は。 |
||
| バード&チンタラー・プンラーップ 「マー・タムマイ」;「チュット・ラップ・ケーク」」所収 |
 |
|
僕がアジアの旅を意識し始めたときにはもう名のあるアイドルだったバードことトンチャイ・メーックインタイは、40を過ぎた今でも超売れっ子アイドルである。移り気なタイ人の中でこの人気ぶりを維持するにはどういう努力があったのか、もはや僕のようなタイ・ポップス好きの端くれ中の端くれのような人間にはわかるすべもない。けれど、そんな僕でもバードがチンタラーとデュエットでモーラムを歌ったと聞いてなんだかがっくりしてしまった。日本では売れなくなったポップス・シンガーやアイドルが演歌転向を果たす例はいくつでもあった。結果として成功した人も数多くいる。ただ、もともとは通念的なロック・ファンだった僕は、彼ら・彼女らの生き残りをかけて路線転換することの意気込みや潔さに感じ入るよりも、芸能界にしがみつこうとする姿勢が透けて見えてしまうようで悲しかった。「バード、お前もか」と、僕は早合点したわけだ。 アルバムをお聞きになった方や、ちゃんとした情報をお持ちの方々はご存知のとおり、バードはモーラムやルークトゥンに転向したわけではない。それに何より僕が唸ったのは、この曲の軽やかな味の出し方である。 あくまで「聞く歌」「感じる歌」であるために歌の巧拙によって左右されることが多いルークトゥンと違って、モーラムは「踊るための歌」である。そのためには上手さが足を引っ張ることだってある。しかし、天性のリズム感を持ったバードはそのあたりをよく判って歌っている。もはやモーラムの第一人者となったチンタラーも、もともと軽みを出すことに長けた歌い手であるから、そのコンビネーションは抜群。しかも、なんだか「夢の二人がたまたま忘年会のカラオケでデュエットした!」的な感じがいかにもタイらしい風情を盛り上げている。へんに力まず練っていないところが素晴らしい。 タイのちょっと庶民的なディスコでは、それまで洋楽とかトランス・ミュージックを回していたにもかかわらず、閉店前30分くらいになるととたんにDJがモーラムをかけだして店内が嬌声に包まれながら、みんなタイ舞踊を踊りだすなんてことが少なくない。バードだってモーラムが好きなんだろう。酔っ払ってオヤジ、オババと一緒にこの曲で踊れるタイ人がうらやましかったりする。 |
||
| パーミー 「ヤーク・ロン・ダン・ダン」;「パーミー」所収 |
 |
|
バンコクにいても、CDショップにすら出かけないような生活が当たり前になっていた。市内の渋滞の激しさと職場の休日の少なさが、「もう家にいるか、近所でダラダラ過ごせば?」という悪魔の囁きにうんうん頷く自分を形づくってしまっていた。家にTVさえ持っていなかった僕から、バンコクの街としての動きや熱さが遠のいてゆくのは至極当然のこと。音楽のない生活が普通になっていた。 僕もどこかで迷惑をかけていたのだろうと思うが、隣に越してきた日本人女性は薄い壁のところを平気で大きな音でkiroroとかウルフルズを流して、眠れない僕をあざ笑っているようにすら感じられた。以前からあった大型レストランが毎晩ステージをやるようになった。警察署のすぐ脇にあるにもかかわらず、その音量のでかさは並ではなかった。はっきりいえば、音楽は僕の日常生活にとっては邪魔なもの、昔は好きだったというだけのものになり下がっていた。 パーミーが売れていることや、それとは別に名も歌手名も知らぬ曲が巷を席巻していることはなんとなく知っていた。そうこうしているうちに自分が日本に帰国することになって、職場と家の往復だけではない生活が手元に戻ってきた。買ってきたばかりのCDをヘッド・フォンでフル・ヴォリュームで聞いてみる。あ、この曲か! 忙しいバンコク生活の中でこの曲、「ヤーク・ロン・ダン・ダン」を知っていることが「僕は確かにタイで暮らしていたんだ」という確信を改めて握り締めさせてくれた。 束の間、僕はタイのことが好きで好きで、タイに恋愛していた頃の自分の思いと似たものを感じた。シンプルなロック・テイストのこの曲は、ともすれば湿っぽくなりがちな「タイを去る」「日本に帰る」という現実を賑やかでからっと明るいものにしてくれた。新しい門扉を開けるには、乾季の入り口である11月のタイは、絶好の日和だった.。 |
||
| アン 「スィーン・クーン・フア・チャイ」;「エクストラマインド」所収 |
 |
|
もともとアンは「×3」という、どちらかというとお子様向けユニットで元気な声を聞かせてくれていた。大型デパートを作ったなら映画館もボーリング場もカラオケも遊園地もプールも一緒にオープンさせてしまうオール・イン・ワンが大好きなタイ人セール戦略上では、それこそモー娘。やおニャン子に匹敵するような混成ユニットが好まれる。ルックス的にも力量的にもごった煮の素人っぽさを売り物にしたこの×3で、アンはハスキー・ヴォイスを活かして他の3人とは一線を画するプロ・ヴォーカルを披露していたのだった。 いつのまにか口ずさんで覚えてしまっていた歌、というのが最近のお気に入りのパターンだ。しかめつらして「このコード展開は」とか「アレンジが斬新で」などというロジックを振り回すのは二の次となった。要するに、ワーク・ソングというか、自身の生活の中でごく自然に口を突いて出る旋律が自分にとってリアルに感じられるようになったと、そういうことだ。いつのまにか「少しだけ大人になった自分を素直に歌う歌手」になっていたアンのこの曲は、そのようにしていつしか僕の掃除・洗濯時のハミング曲となっていた。 |
||
| ローソー 「パンティップ」;「レッド・アルバム」所収 |
 |
|
新しくできたばかりだったラチャダーピセーク通りのカールフールはかなりの賑わいを見せていた。視聴機の並ぶ一角は人が並んでいて、仕方なく辺りををうろうろしていると、聞きなれた声がひさしぶりにがなっていた。 ローソーはベストアルバムを発表後のオリジナル・アルバム「ロック・アンド・ロール」で燃え尽きたかのように見えた。演奏的にも相当な高み(失礼だが、あれは本当に本人達の演奏なのだろうか?)に達したあとの彼らの次作「ローソー・ランド」は掴み所のないふにゃけたアルバムだった。この頃から彼らは「国民的ロック・バンド」の形容をいただくことになるが、それと引き換えに芯のボケた、中庸なバンドになろうとしているように感じられた。 それまで300バーツだった新譜CDが、海賊版対抗のためにグラミー社とRSプロモーションでこぞって155バーツに値下げされた第一弾のアルバムが、このとき耳にしたローソーの「レッド・アルバム」だった。技術はとにかく、彼らに熱さが甦っていることがうれしかった。1曲目のシンプルなロックがそれを感じさせてくれた。 しかし、聞き進むにつれて?が増えてゆく。本当にそうなのか? そして、歌詞が耳に残ってくるようになって、ますますわけがわからなくなった。マーブンクローンとかサイアムスクエアとか、なんだか地名紹介ソングになっているぞ。それに、よく見ると曲名は「パンティップ」になっているではないか。何だこれは? 結局、この歌は「新しい恋人ができていろんなところにデートに行きたいのだが、パンティップだけはダメだ、あそこには前に付き合ってた人がいるから」みたいな筋書きで、彼らはそれをがなりたてていただけだったのだ。「国民的ロックバンド」ってなんだろう? ロックって、「国民」のものなのだろうか? ※ その後、この曲についての僕の誤解が判明した。「レッド・アルバム」はグラミー社がタイに多い海賊盤に対向してそれまでの半値近い155Bで音楽CDを発表することを決定してからの名誉ある第1段アルバム。ローソーはそれに呼応して、「昔の恋人=パンティップ・プラザ(違法コピーCD販売のメッカ)のところには、オレの書いた新しい曲は行かない」と宣言していたのだった。彼らのロック精神健在!とんだお恥ずかしいお話ですみません。 |
||
| トライアンフス・キングダム 「カン・ラ・カン」;「トゥワイス・TK」所収 |
 |
|
TKことトライアンフス・キングダムは「タイのパフィー」だとよく例えられたが、これには相当無理がある。というか、時期的に女性のコンビ・ユニットを日本で考えればたまたまパフィーだったという、ただそれだけのことではなかったかと勘ぐってしまう。TKはRCAあたりで学生やヤンエグ(超死語)あたりと、テキーラの一気飲み(タイ人はこれが大好き)でもしながらちょっと派手に踊っていそうな女の子二人のユニットで、玄人受けしないタイでもことさら素人っぽさを強調したウリで一世を風靡した。特に、かわいくデザインされた前歯の矯正金具をCDジャケットで披露して以来、日本人でもこれをつける在タイの女の子が増えたくらいだった。 タイでの生活が始まった。せっかくノートPCを日本で購入してきたので、パンティップ・プラザで買った100バーツのMP3のCD-Rを起動させたとき、マイクロソフト・メディア・プレイヤーの最新版でアンビエント映像を見ながら、初めて聞いたのがこの曲。TKはいつもらしくない大人びた溜め息調の雰囲気と、お馴染みの子供じみた舌足らずな声で、物憂げな男性コーラスとともにこのバラードを歌いこなしていた。静謐とした感じとメディア・プレイヤーの抽象動画はぴったり合っていて、ひとりの部屋で、僕は音の砂漠を彷徨った。買いたてのヘッドフォンを耳に押し当てて何度も何度も繰り返し聞いたため、この曲を聴くと自然に、僕はかつて住んでいたバンコクの自分の部屋を思い出す。そして、ヘッドフォンで聞くからにはいつもこの曲といるときはひとりだった。そういうひとりきりの日曜の、あてのない孤独がイントロを聞くだけでいつだって胸に広がる。 TKは空中分解してしまったけれど、そうなることがタイでは定番コースだ。刹那であることがわかるから、タイ・ポップはちょっと胸に痛い。 ※ 彼女たちの一人はTKの解散から数年後、まったく違ったことで世間を騒がせることとなった。覚醒剤の販売人として逮捕されたのだ。新聞の写真で見る彼女の姿は頬がこけて、言われなければ同一人物だとは思えなかった。刹那の夢が彼女の逃げ場を用意させたのか。さらに胸に痛くなってしまった。 |
||
| ニコル・テラウィット 「カ・ポ・ロ」;「カポロ・クラブ」所収 |
 |
|
ディスコ「スパークス」でニコルのライヴを始めて見て感心したのは、バックバンドの演奏の手堅さだった。音がグワングワンに回る地下ディスコでよくもあれだけタイトなプレイができるものだと感心したのを覚えている。 それとは対照的に、ニコルはティーンエイジャーのようだった。飛び跳ねながら舌足らずな声で観客に手を振りながらしきりに話しかけ、地についた愛くるしさを振りまいていた。「アルバムごとに若くなる」と皮肉半分に囁かれていた彼女だったが、英語圏で育ちタイ語がさほど得意ではない、半ば外タレ状態であるニコルは愛嬌のあるキャラクターにぴったりだった。僕がライヴに誘ったら最初は「アイドルなんて」と渋っていたフィリピン人の友達は、帰る頃にはすっかりニコル・ファンになっていた。 「カ・ポ・ロ」はそんな彼女のファースト・アルバムの1曲目を飾るとても弾けたナンバーだ。この曲のサビの部分の歌詞はほとんどが「ワー」とか「ハー」とか、いわゆるスキャットでできている。これも本当にニコルらしい曲だ。プロモーション・ヴィデオの中でも彼女はこの曲を歌いながら飛び跳ねている。 最近では「新作ごとに痩せ細ってゆく」ニコル。この頃の彼女の輝きは、今の姿をさらに痛々しいものに見せてしまう。遅咲きの彼女は、今後がつらいだろう。タイ人は老けるのがやけに早い。 |
||
| ルクラオ・アムラティシャー 「ルアック」;「リラックス」所収 |
 |
|
思いっきりタメの効いたドラムのタム回しで滑りだすイントロから、即座に、彼女が凡百の歌を歌おうとしているのではないことがわかる。エフェクトを抑えたエレキ・ギターとシンプルなベース・ライン。そして、彼女の、グレイ・トーン単色に見えながら、それとは気づかないくらいに薄く紅のさしたヴォーカル。彼女はあくまで地声で歌おうとしているから、曲が進むにつれてキーが高くなっていくのに対して、最後はヴォーカル・コントロールが行き届いていない。そこにこの落ち着きの中にもパンキッシュなものさえ感じる。 昨今のAОRブームも、彼女のような人を発掘してほしいと思う。本当の意味でのAОRが70年代のあだ花だったのだとしたら、今のタイはまさしく、その頃の先進国を敷衍しようとしているのだ。 |
||
| ナディア 「ウェルカム・スウィート・モーニング」 |
 |
|
| Mr.Zことゾムキアットが、鳴り物入りのプロデュースで世に問うたのがナディアの初ソロ・アルバム。彼は自身のアルバムで、ピチカート・ファイヴの「スゥイート・ソウル・レヴュー」を彼女のヴォーカルをフューチャーしてカヴァー済み。そのノウハウを詰め込んで、いっそう90’sトーキョー然としたプロデュースをぶつけてきた。 ただ、彼の書く曲はメロディー・ラインが単純で子供っぽいところが、クールなアレンジとマッチングのよくない部分があるように思う。ナディアのヴォーカルがウィスパー系な上に舌足らず気味なので、よりそう感じてしまう(その部分だけ取ると、これまたトーキョー的ではあるのだが)。今後、ここを活かしてフレンチ=渋谷系街道を進むか、それとも新境地を切り開くのかが楽しみだ。 |
||
| ジャンプ 「キャント・テイク・マイ・アイズ・オフ・ユー」;「JAMP」所収 |
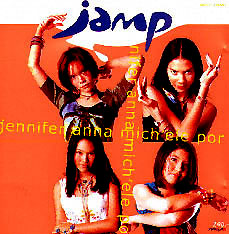 |
|
エカマイ通りに半年ほど店を開けていた、ラテン・バーみたいなのがあった。客の入りは全然だったし、肝心のラテン系の曲を演奏するバンドが下手だった。でも、サルサやパスタなど食べに、二三度は足を運んだのではないかと思う。そして、ここでもこの曲のコピーを何度も聴いた。フォー・シーズンズとしてではなくフランキー・ヴァリのソロとしてヒットした情熱的なこの曲は、たぶん世界中でこのようにコピーされているのだろう。そして、AメロとBメロ(サビ)をつなぐブリッジの個所にホーンがあるのが、この曲の構成的にいいところ。このバーのバンド演奏も、管があるから少し目新しく聞こえる。特にこのバンコクでは。 この曲のヴォーカリストとしての難しさは、声に任せてシャウトしたりせず、どうやって上品にあのキーの高いサビを歌いこなすかにかかってくる。日本とフィリピン、そして韓国の一部以外のアジア諸地域では、ブラック・ミュージックがヒットしない。だから、タイでもあちらこちらでこの曲を耳にするけれど、なんだか中途半端な印象で終わってしまう場合が多い。しかし、JAMPは端からソウルとかブラックとかおかまいなしに、徹底的なディスコ・チューンにしてしまっている。ヴォーカルだってそのままオクターブ上げたバッキングのため、女性が歌うにはキーが低くなっており、サビもAメロと同じようにベタっと歌ってしまっている。しかしそれがかえって痛快だ。ディスコ好きのタイ人の若者がこの曲をコピーするなら、そうした方法論が正しいと思う。そもそも、正統派ソウルを欧米人にまで聞かせてしまうという役割は、タイだけではなく日本も含めて、現地滞在のフィリピン・バンドが担っているのだ、どのみち。 |
||
| ニース 「kiss?」;「メルシー・メルシー」所収 |
 |
|
かつて「渋谷系」なるカテゴリーがあって、それはそれはかっこ悪いネーミングだし(完全なる死語の「渋カジ」とまったく同じ)、だいたいその所以が「渋谷のタワレコやHMV、WAVEで売れているモノ」だという時点でもう溜息をつくしかないのだが、その音楽性やパワーはすごかった。90年代はそのおかげで、トーキョーが世界で最も走っている都市だったと断言していい。 その意匠が、このタイで、こんな風に受け継がれているとは、意外だった。タイはどちらかというと「ナー・ラック(可愛い)」なものより、「スアイ(美しい)」ものが好まれる傾向が強いと思っていたからだ。しかし、思えばターターだってニコルだって、ナー・ラック系統のアイドルだ。 そしてもっと驚くのが、その音楽性だ。この路線を推し進めているのがニースも所属するDOJO CITY。素人っぽい、歌唱力のあまりない女の子に、地声に近い低いキーでメロディーを歌わせて身近さと等身大の可愛さ、それにある種の落ち着きあるムードを決定している。いわば、タイ流の似非・フランス。 「タクシーに乗って、遊びに行こうよ」と呼びかけていたピチカート・ファイヴのように、さあ、今日も、kiss?を聞いて出かけよう。 |
||
| ローソー 「ロック・アンド・ロール」;「ロック・アンド・ロール」所収 |
 |
|
「ひどく上手くなったな、コイツら!」シーロム通りにあったCDショップ「イマジン」の視聴機の前で、僕はヘッドフォンから流れてくるイントロを信じられない思いで聴いていた。 いまだに彼らがどうしてこのアルバムに限りここまでのことができたのかはよく解らない。打ち込みだったのかもしれないしスタジオ・ミュージシャンによる演奏だったのかもしれない(本当に彼らの演奏だったら、まことに失礼!)。とにかく後にも先にも、このアルバムでの彼らの演奏はパーフェクトだった。音の抜けはいいし、特筆すべきはベースとドラム。細かい技も光らせながら、しっかりグルーヴを作っている。ちょうどこのアルバムの前にベストが発売され、ヒットの多かった彼らはここで過去の清算をしつつ夜の機運を高め、このオリジナル・アルバムで押しも押されぬ「国民的ロック・バンド」の名を定着させた。それはちょうど、僕自身がタイに惹かれてやまなくなってゆく過程と重なって、個人的に興奮したりした。 余談だが、大ヒットした3曲目の「アイ・サン・ナー」はチャゲ&飛鳥の懐かしの一曲「終章(エピローグ)」とコード進行がまったく同じである(メロディーは違う)。無理にタイ・カラオケに連れて行かれて曲が歌えないあなたは、これでマイ・ペン・ライ??? |
||
| ニコル・テラウィット 「ドーク・マイ・ティー・タム・トック」;「ブッサバー・ナー・ペン」所収 |
 |
|
その頃僕は、バンコクに来て職を探していた。チャオプラヤー川を越えるととたんに家賃が安くなるので、日本人がほとんどいないトンブリー側のウォンウィエン・ヤイの近くにワン・ルームを借りて、仕事探しをオフにしたときには、暑い中を自転車でバンケーまで走ったり、ウォンウィエン・ヤイ駅から小1時間でマハーチャイまで電車にも乗って散歩に出たりしていた。 込み合う郵便局の列に並んで、いつもながら要領の悪い係員の仕事ぶりを眺めながら順番を待っていると、天井にセットされていたテレビから、彼女の舌足らずでころころした愛らしい声が聞こえてきた。それは彼女にとって、やっと巡ってきた遅いブレイクだった。まもなく街じゅうの書店に居並ぶ平積み雑誌の表紙を彼女は独占することになるが、丁寧な画像処理を済ませたCDジャケットや、ライティングを考え編集を重ねたヴィデオ・クリップとは違って、雑誌用のフォトは正直だった。ファンにすれば決して見たくなかった目尻のしわや肌のカサつきがそこにははっきりと写されていた。決して僕は意地悪であら捜しをしているのではない。僕は彼女のライヴに足を運ぶクチだし、今この作業を行っている最中のPCのデスクトップも彼女のスチールなのだから。 このマイナー調の曲を、からっとした小粋なアレンジで聞かせる彼女のクリップも、ファン・サーヴィスで、花が回転するように映されたシンプルなバックに彼女の顔がハレーション気味に大写しにされている。でも、いいのだ。彼女はセヴンの中でも徹底的に可愛くあろうとしていて、それが厭味ではないのだから。 ところで、人と汗と排ガスと使い古された油のにおいと垢抜けなさに満ちていたウォンウィエン・ヤイから見たニコルの笑顔は、とっても、眩しかった。 |
||
マイ・チャルンプラー 「ペー・チャイ」;「ペーン・トゥット」所収 |
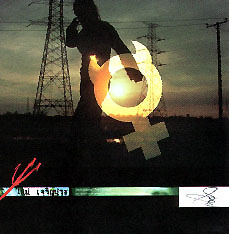 |
|
マイはもうタイのアイドル界では大御所。こうなってくると、古今東西どこででも見受けられるように、シンガーは保身に入る。イメージを固定して、そのイメージ戦略で生き延びようとする。残念ながら、最近のマーシャやナット・ミリア、クリスティーナ・アギラからはそんなムードが伝わってきて残念だ。マイだってロックっぽい曲調をモノにするセクシー系シンガーというイメージを打ち出して変わることはない。ただ、そういう彼女が、シンプルなロック・フレーヴァーのこの曲をヒットさせたのは嬉しい。 歌いだしの4小節でこの曲がタイ・ヒット・ポップスのスタンダードになるだろうことがわかるが、ヴォーカルのパンチという意味ではイマイチで、喉の奥にこもってつかえたような彼女の声が、かえってこの曲をレアなものにしている。例えば「ペー・チャイ」をリメイクしてニコルがカヴァーしているが、シンプルなメロディー・ラインと隙の多い音作り(この曲のテンポと志向性を考えると、音の壁で曲を埋めるのが難しい)に浮いてしまっている。 その人の弱さがリアリティーを生み出すとき、弱さは最大の武器になる(特に女性の場合は)。 |
||
| ザザ 「ノーン・マイ・ラップ」;「zaza」所収 |
 |
|
お子様向けアイドルは、アイドル本人の成長から、どうしてもやがては大人へのイメージ・チェンジを迫られる。タイの後発アイドル・プロモーターのRSプロモーションには、こうした低年齢層を狙ったアイドルの粗製濫造が次々と行われて、それまでグラミー社の独占だった音楽市場に殴り込みをかけた形になっていた。ZAZAはしかし、そうした「ちぎっては投げ、ちぎっては投げ」状態の場当たり的なプロモーション状態からスタートを切ったアイドルではなかった。その分、アルバムごとのアプローチもうまく後に続けることができるよう、年齢に無理のないイメージ戦略が丁寧に施されている。でも、こうした場合によくありがちなように、やっぱりファースト・アルバムが一番よかったりする。 ティーンエイジャーのアイドルが受けるのは、ただ単に最も多いファン層との年齢が近いところから来る親近感ばかりではない。その年齢には、その年齢にしか表現できないことというものがあるからだ。かつて大瀧詠一がファースト・ソロ・アルバムで「指切り」のヴォーカルをレコーディングしたとき、のちに何度トライしても、最初にテストのつもりで録ったテイクを凌ぐことができなかったというエピソードが残されているように、若さの無自覚がちらつかせる頼りない光を、「ノーン・マイ・ラップ」は部屋の中に充満させてくれる。 |
||
| ターター・ヤング 「コー・ターム・サック・ノーイ」;「アメイジング」「ターター・リミックス」所収 |
 |
|
僕はどだいユーロ・ビートとかいうへんてこな名前(そんなの、ヨーロッパのどこでどのように持て囃されている曲調だというのか? もう死語だが)のジャンルが好きじゃなかった。気持ちのよいステップを踏めるようにするため、「ディスコ・サウンド」と呼ばれたジャンルではBPM(曲の速度)がほとんど決まってしまっていて、さらにそこにぺかぺかのちゃちでバブル臭いデジタル・サウンドを乗せたユーロ・ビートなる代物には多少ウンザリしていた(事実、80年代のバブリーな日本ではそういう系列の音を好むディスコが多かった)。 旅行者としてタイに2ヶ月ほど触れたあと、帰国してからの僕はもぬけの殻のようになってしまった。心ここにあらずだと会う友人ごとにいわれたのはまったくの正解で、僕はもうはっきりとタイに恋していた。その「タイ」は一時期、具体的な顔を持った。ターターのそれである。全盛期を過ぎかけてはいたが、ターター旋風の後ではタイの町のディスコでは彼女の曲がハウス・バンドのレパートリーに入っていることが多かった。自分土産にと買ってきたCDをリプレイする毎日。「オー・…オイ」とともに僕をえぐったのは「コー・ターム・サック・ノーイ」だった。2ndアルバム「アメイジング」ではシンプルなバラードであったこの曲は、タイへの感傷を重ね合わせるのにもってこいだったからだ。 ところが、この曲のリミックス・ヴァージョンがこともあろうにあのユーロ・ビートだった。でも、恋している者にとって、そんなことはもうお構いなしだった。ただそこにターターの歌声とせつないメロディーがあれば。 かくして、僕のユーロ・ビート・アレルギーやディスコという装置への鼻白みは治っていた。 |
||
| モーメー 「クラ・ドゥック・クラ・ディック」;「フェイヴァリット・モーメー」所収 |
 |
|
そこは南タイ随一の街とはいえ、街角の何処に立ったとしても洗練や瀟洒という言葉を拾い集めることができないような.小さな街のディスコ。国境まで車で1時間だけあって、チャイニーズやマレーの姿も多い。なのに、ステージでは他のどのタイの街とも同じようにタイ・ヒット・ポップスのコピーの垂れ流し。軽薄なバックに乗せて軽薄な歌声と軽薄なダンス。真面目に聞いている者はいないだろうし、僕もそうだった。 が、旅を終えて帰国してしばらくすると、この曲の単純なリフが何時しか胸の奥のどこかでリピートしつづけているのに気づいた。そして1年後。今はなくなったバンコクのタワー・レコードで、この曲の旋律を店員に歌い聞かせてCDを探してもらった僕の姿がバンコクの一角にあった。 ※ タイは、こういう音・こういう底抜けの明るさのようなものを、もうすでにポップスの面では持てなくなってしまったようだ。やはり、歌は世につれる。 |
||
| ローソー 「アライ・コー・ヨーム」;「ザ・ベスト・オブ・ローソー」所収 |
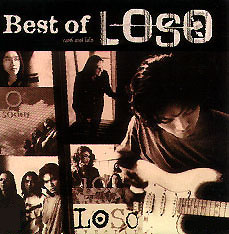 |
|
ミュージシャンがみるみる力量をつけてゆくのをアルバムごとに感じるのは、なんだか爽快だ。ローソーが会心の一作「ロックン・ロール」を発表したときには、僕も視聴機の前で思わず唸ってしまった。音圧やヴォーカルの迫力もさることながら、ドラムスがとにかく飛び級的に素晴らしくなっていた。タメの取り方やスピード感、ロールの使いまわし、タム回しのセンスや音の作り方など、一作前とでも比べものにならない進歩だった。 ただ、僕はいわゆる「芸術至上主義」型人間ではないので、どうしても思い入れのある曲、どうしようもなくそこに自分が過ごした時間とともにあった音に肩入れしてしまう。初めてのタイ旅行のときに知り合った女の子は、「この曲が好き」と、街のどこかからこの曲が聞こえてくるたびにそれにあわせて歌っていた。しかし、それがあまりに調子はずれで面食らった。彼女ももう今では結婚して、子供でもいるのではないかと思う。今でも彼女はローソーを聞いて、あの調子はずれな声を子守唄などにしているのだろうか。 |
||
| ターター・ヤング 「オー…オーイ」;「アミッター・ターター・ヤング」「ターター・リミックス」所収 |
 |
|
オリジナルはちょっとビート・ポップスっぽいバンド・サウンドで、懐かしのスターシップなんかも思わせる。「リミックス」はチャイニーズ・ヴァージョンで、イントロ・カウントからして「イー・アル・サン・スー」である。 どちらにせよ、この曲が成立するのは、ターターの声があるからこそ。彼女の声はタイ人らしからず固めで重心が低く、当時ミドル・ティーンだった彼女の青さをいい意味で感じさせるとともに、ダンス・チューンを歌ってみせても華やかでパンチの効いた声と背中合わせに、いつだってうっすらと翳が滲み出している。カレン・カーペンターのような闇ではない。しかしかといって10代の娘の怖気づきではない。だからこそ、男である僕にもその薄暗がりに親しみを覚えることができる。 ターターはビッグ・ネームが陥りやすいように、欧米デビューを狙ってタイ最大手のグラミー・レコードとの契約を更改しないまま沈黙していたが、2001年に復活劇を見せた。CDも売れたし、VCDに様子が収まっているコンサートの様子はほほえましくもあり、成長を見せつけてくれてもいる。でも、あのキンと張ったヴォーカル、しなやかなダンス、愛くるしくも大物を感じさせたまだあどけない笑顔−20歳の彼女は、かつて隠しようもなく輝いていた16歳だった彼女自身を超えることがまだできないでいる。 ※ ソニーと契約したターターはその世界的戦略に乗じて英詞のダンス・チューン"Sexy, Naughty, Bitch"と"I Believe"を特大ヒットさせ、見事にカムバックを果たした。これを期に日本でもアルバム発売、ツアーで来日、とかつてない注目を集めたことをご存知方も多いだろう。 しかし、あのヴァンプ的なムードは、正直ちょっとつらい。ダンス系のブラック・アメリカンを意識してのことかもしれないが、何もその役をターターがやることはなかったように思えて仕方がない。それとも、少女期のあまりに大きなブレイクによるイメージ・チェンジにはそれほどまでのインパクトが必要だったということか。いずれにせよ、両親から伝え聞く山本リンダの変貌ぶりのエピソードを思わせる一件ではある。 |
||
| カトーン 「チャックラヤーン」;「ルアット・ブアック」所収 |
 |
|
90年代の初めは、ワールド・ミュージック元年だった。その少し前に、僕は大阪にあった「ラングーン」というワールド・ミュージックの店で聞いたことのない国のアルバムをせっせと買ってきては、曲をピックアップしてカセット・テープを作り、「音楽の世界旅行」をするのが好きだった。目を閉じれば、インチキくさいイメージが広がる。物売り。寺院や教会。屋台。海。砂漠・・・。 カトーンのことは、「イープン・ユーンピー」で知った。当時、白いテーブルクロスに丸い赤皿の、明らかに日の丸とわかる上に盛られた、タイ国の形に切られた鯛の刺身を箸でつまんでいるジャケットはインパクトがあって話題を呼んだ。「日本はタイを喰い物にしようとしている」と。 続く「ルアット・ブアック」は「陽性血液」の意味で、つまりはHIVポジティヴのこと。リーダーのユットはもうバンドを離れていたが、これも強烈なテーマだった。けれど、その一方で彼等・彼女等の音や声はどこか農村の陽だまりを思わせるのどかさ、ゆったりした空気があった。だから、こんな重いテーマのアルバムに「チャックラヤーン(自転車)」などといった曲が入っていても違和感がなかった。ごていねいに、曲中にチリンチリンと自転車のベルの音まで挿入されている。それは、どれだけ重いテーマを扱ってもアジテートにはならないタイ人独特のたおやかさのなせるわざなのだろうか。 今ではその素朴な歌声を聞くこともない。カラワンのスラチャイやカラバオのように生き残ることもできなかった。それはでも、仕方がない。バンコクは生き急いで生き急いで、息せき切って突っ走っているのだから。 |
||
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
